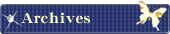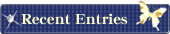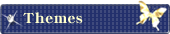創作mirage-儚い夢-25.黒い影

NYに戻ると、僕はまずアパートに向かった。
部屋の階でエレベーターの扉が開いた瞬間に、僕の部屋の扉に寄りかかっていた
あいつの姿が見えた。
ジョルジュ?
彼はもう随分長いことこうして僕を待っていたのだろう。
僕を見つけるなり睨みつけた彼の視線が僕の動向を執拗に追いかけていた。
僕はそんな彼に一瞥をくれたあと、その視線を無視して彼の横をすり抜け
沈黙のまま部屋の鍵穴にKEYを差し込んだ。
「お待ちしてました」 彼が満を持して言った。
「・・・・・・」
そして彼は努めて冷静を装い、落ち着いた口調で僕に尋ねた。
「あいつを・・何処へ?」
僕は依然として無言のまま、彼に部屋に入るよう目だけで促した。
彼も無言で僕の前を横切り、僕に勧められるまま先に部屋に入った。
「・・・・・・コーヒーは?・・いかがです?」
「いいえ・・結構です・・・」
「そう・・・僕は飲んでもいいかな・・・」
「どうぞ・・・」
決して僕から逸らさない彼の視線を背中に感じながら、僕はコーヒー豆を挽いていた。
「答えてもらえませんか?
わかっているでしょ?この数日、あなたの消息を探してました・・・
あなたの学校へも訪ねました・・・」
「学校?・・よく・・・わかりましたね・・・」
「必死ですから・・・」
彼はきっと、僕と対峙しながら自分の興奮を抑えようと、懸命に耐えていたのだろう。
鋭い眼光とは裏腹に丁寧な言葉遣いを使いながらも、僕への憎悪が握った拳に見て取れた。
「それは僕も同じだ・・・」≪必死だったさ・・君から逃れるのに≫
「あいつの親にはまだ
あなたのことは話していません」
「そう・・・」
「今はまだ・・・僕の都合で帰国が遅れていることになってる・・・
しかし・・・それももう限界だ・・・」
「・・・・・」
「あいつはまだ未成年です・・・
あいつの親がこのことを知ったら・・・」
「・・・・・」
「警察沙汰になりますよ・・・」
「それで?」
「一週間遅れると話してます・・・あと二日です・・・
あいつを・・・返してくれませんか・・・」
「返す?」
「ええ・・・」
「彼女は品物じゃない・・・彼女は彼女の意思で僕の元にいる・・・
それは君もわかっているはず」
「あいつはきっと、後悔します」
「後悔?」
「あいつは親に背いて平常心でいられる奴じゃない
自分の意思を貫き通せるほど大人でもない」
「彼女のことは“自分が一番知っている”・・・
そう言いたいわけだ」
「少なくともあなたよりは知っている!」
彼と僕は互いに睨み合った視線を譲れないまま、しばらくの間、沈黙に耐えていた。
「・・・・・・」
「・・・・・・」
その沈黙を彼の方が先に破った。
「それに・・あいつには夢があります・・・」
「・・・・・・」
「いつの日か・・・ホテリアーになるという夢が・・・
あなたはご存じないかもしれないが」
「・・・・・知ってます」
「そうですか・・・では・・
あいつが働きたいホテルもご存知だろうか・・・」
「・・・・・」
「私の父のホテルです・・・
小さい頃から、そこで・・・私と一緒に働くことが夢でした
いいえ・・・今でもまだその夢は捨てていないはず」
「・・・・・」
「僕は・・・あいつの夢を叶えるためなら
どんなことでもする・・どんなことでもできる・・
今までもそうしてきたし・・・それはこれからも変わらない
あなたはどうだろう・・・今、あいつの夢を知っているとおっしゃった
それなら・・あいつにそれを尋ねたことがありますか?
本当にやりたいことを聞いてやったことがありますか?
あいつは・・・
あいつはあなたの前で本心を語ってるんだろうか・・
語れてるんだろうか・・・
あなたは・・・あいつの真実を・・・
本当にわかってると言えますか・・・」
「・・・・・真実?・・・
今 彼女と僕の肌が触れ合う・・・それだけが真実だ・・・」
僕のその言葉に彼の眼光が力を増し唇が震えた。
「・・・・・・!」
「・・・・夢なんて・・・現実の元には儚いものだ・・・
彼女の幼い頃からの夢が例え・・・君と歩むことだったとしても
現実の彼女は今・・・僕と歩こうとしている・・・
その現実を・・・君は認められないのか
彼女のご両親にはいずれ、必ずお話をする・・・
ご両親とて・・それが彼女の幸せと思えば・・・」
「あいつの親はあなたを認めない!」
「・・・・・」
「あなたのような!・・」
彼は即座に、自分が間違ったことを言い掛けたというように言葉を詰まらせた。
僕は彼のそんな様子を冷たく見つめながら口を開いた。
「僕のような?・・・」
「・・・・・・」
僕は彼に対して口元だけで小さく笑って見せた。
「君は、何不自由なく育ったお坊ちゃんなんだな・・・
人を傷つけようと思うなら、もっと激しく罵倒しろ!
それでなければ、相手は君を甘く見るだけだ・・・
こんな時ははっきり・・・
“あなたのような・・親に捨てられた人間は彼女にはふさわしくない”・・・
そういうべきだ」
「・・・・・・」
「調べたんだろ?」
「・・・・・・」
「それで?」
「えっ?」
「それで・・・返さないと言ったら、どうなりますか?」
「・・・とにかく、あいつと話をさせてください」
「彼女が望まなかったら?」
「あいつの父親に全て話すまでです」
「ボス・・・遅かったな・・・時間に遅れるなんて
珍しいじゃないか・・・」
「すまない・・・野暮用が・・・」
「ま・・いい・・・早速始めよう・・・休暇中悪かったな・・・しかし・・
以前からお前が狙っていたホテル関連の重要な案件だ・・・
急いだ方がいいと思ってな・・・
知っていると思うが
あの業界は新参者は受け入れにくい
しかしだ・・・お前はどうも別格らしい・・・
最近M&A業界を賑わしてるヒーローだからな・・・
そのお前の力を見込んで、是非にと乗ってきた会社がある・・・
しかも、かなり大物だ・・・」
「何処だ」
「JAコーポレーション」
「JA?・・・そんなところに、入れるのか」
「ああ・・お前次第だ・・・今、そこが手掛けているM&Aがある
NYグランドホテルとカナダのプリンスヒルホテルとの合併だ」
「ああ・・知ってる・・・それを僕に?」
「ボ~ス・・それを成功させてみろ・・・どうなると思う?」
レオは意味ありげな目つきを僕に向けた。
「かなりの利益だ」
「利益なんてもんじゃない・・・今後の俺達の礎となること
間違いない・・・その代わり・・・」
「その代わり?」
「お前はこれを引き受けることで、どえらい相手を敵に回すことになる」
「どえらい相手?」
「お前も知らないわけじゃないだろう・・・
JAには、今まで遣えたジェームス・パーキンという男がいる・・・
奴の伯父が誰だか知ってるか・・・」
「マフィアのボス・・・パーキンと言えば知らない奴はいない」
「奴を敵に回すということはどういうことかわかるな・・・
しかしひとつだけ、奴らを敵に回さない手立てがある」
「何だ」
「奴の傘下に入る」
「僕にマフィアに加担しろと?」
「奴もたとえ相手が甥であったとしても仕事となれば話は別だ
ジェームスとお前では力の差は歴然
お前が手に入るなら、きっとお前を選ぶ」
「マフィアとは仕事はしない」
「そうだったな・・・それはお前のポリシーだ
それなら・・・」
「それなら?」
「弱みを見せるな」
「弱み?」
「守らなければならないものをそばに置くな・・・
そういうことだ」
「・・・・・・」
「あいつらのやり方・・・知ってるか・・・
攻撃したい人間がいるとする・・・その場合
直接その人間をやるのは最後の最後だ
まずはその人間の弱みに付け込む
その辺は俺達のやり方と変わらないよな・・
ただ俺達と歴然と違うのは・・・
あいつらがその相手に直接手を下すということだ」
「フッ・・・そんなこと・・・」
「今更・・か?当然・・知ってることだよな・・・
だが・・・敢えて言ってる
ボス・・・いや・・フランク・・・
お前に今・・・弱みはないか・・・」
「・・・・・・」
「ないか?・・・」
レオの僕を問いただす真剣な眼差しが、事情を深く尋ねるまでもなく
理解していると言っていた。
僕の弱み・・・それは・・・
ひとつだけ・・・
「・・・・・ある・・・・」
「なら・・・この仕事はやるな」
「どうして」
「どうして?・・・それはお前が一番・・・」
「この仕事を成功させたら・・・お前がさっき・・そう言った・・・
僕にとって大きなチャンス・・・僕達の仕事の礎となる・・・
そういうことだよな・・・」
「それはそうだ」
「なら・・・考えるまでもない・・・僕は必ず成功させる」
「しかし・・」
「守らなければならないものはひとつだけ・・・
それは僕が・・・命を懸けても守ってみせる
心配するな・・・
お前はとにかく、話を進めてくれ・・・」
「・・・・・いいのか・・・覚悟があるんだな」
僕はレオに向かって黙って頷いた。
守らなければならないものはこの世にひとつだけ・・・
ジニョン・・・彼女だけ・・・
そして・・・
彼女と生きるためにも僕は成功を急ぎたい・・・
誰もが認めざる得ない・・
僕という人間の歴史を作るため・・・
あいつの父親に全てを・・・
あなたのことを話します・・・
親父さんは頑固一徹な人間です
決して間違ったことを許さない
あなたは・・・あなた達は・・・
既に間違ったことを・・・したんです
間違ったこと?・・・
ジニョンとの愛が間違ったことというなら
この世の全てが間違ってる・・・
彼女のいない人生が・・・正しいというのなら・・・
僕は永遠に・・・間違った世界で生きる
それが・・・僕の選んだ道だ・・・
僕はレオとの話を終えた後、その場所からさして遠くない、three
hundred
rosesへと
歩いて向かった。
もうひとつブロックを曲がると店が見える・・・そう思った時だった。
《ソ・ジニョン・・・可愛い人だ・・・》
通りすがりに不意に、低くしゃがれた声が僕の耳に届き、僕は不気味なその声の主を
探して勢い振り返った。
ジニョン・・・今・・そう言ったのか
しかしその瞬間、ひとつの黒い影が直ぐのブロックから消えた。
僕は慌てて、走ってその影を追いかけブロックを曲がってみたがその影は忽然と
消えてしまっていた。
瞬時に胸が締め付けられるような恐怖が僕を襲い、ジニョンの元へと走らせた。
「 ジニョン! 」
丁度その時、店に入ろうとする彼女の姿が目に入って、慌てて声を掛けた。
「フラン・・あ・・いえ・・ドンヒョクssi・・・
驚いた・・私も今、着いたところよ・・
早かったのね・・・もう少し待つかと・・・」
僕を見つけたジニョンの満面の笑顔を前に、僕は大きく安堵のため息をつきながら、
彼女をきつく抱きしめた。
「どうしたの?ドンヒョクssi・・・苦しい・・わ」
「何でもない・・・」
「フ・・ラ・・ンク・・?」
「何でも・・・ない・・・
すごく・・・
・・・逢いたかっただけ・・・」