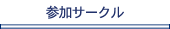【創作】女神の系譜(後編)
「・・おおきみ、おおきみ、・・ははうえ、母上、お疲れのようですが、目をお開けください・・」
突然の声に女帝は呼び戻された。
仕方なしに目を開ければ、葛城が覗き込んでいた。
「・・今のをお聞きになりましたか?・・吉報です、蘇我から火の手が上がったとのことです!」
『そが』から・・、と女帝は小声でくり返した。
なるほど、部屋の中はさっきまでとだいぶ様子が違うようだ。くすんだ顔をした男達の大半が外に出て行ったらしく、部屋の中はがらんとしている。内庭では、ばたばたと駆け回る兵士達の足音や興奮した声、馬のいななきも聞こえる。
ぶんぶん声はどうしたのだ、と思ったとたん、それはすぐ近くにかしこまっていた。
「鎌足、謹んで申し上げまする。蝦夷の動向はいまださだかではございませぬが、屋敷から出て行った気配もございませぬゆえ、恐らくは自害したものかと・・。」
そうか、あの、えみしが・・、と覚醒しきれない頭で、女帝はつぶやく。品の良い白髭の横顔が目に浮かぶ。優柔不断などと陰口をたたかれていたが、息子の入鹿とは異なり、書を好むおだやかな人物だったと思う。
が、葛城はそんなことは気にもとめない様子で、次なる一手を繰り出そうとしていた。
「早計に判断してはなりませんが、ここは、母上の、いえ、大王のお言葉が必要です。」
その言葉が終わるか終わらないかの内に、鎌足が大きくうなずくのが見えた。
「さようでございまする。いまだはっきりしない東漢直の動きを封じるためにも、ここは大王の詔がいただきとうございまする。」
女帝は、『みことのり』と小さくつぶやいたが、そのとたんになにか違和感のようなものを感じた。なにかおかしいような・・。
ぶんぶん声は話を進める。
「はい、詔の内容としましては、一同、混乱を収拾するため葛城皇子様の元に結集せよ、ということでよろしいかと存知まする。この鎌足、すでに原案は用意してございまする。」
ああ、やはり、そういうことか、と思った。体の中がざらざらしたものでいっぱいになる。
要するに、何も変わらないのだと女帝は思った。初めからずっと同じようにくりかえしてきたことなのである。きらびやかな衣装を身にまとい王冠をかぶっていても、彼女が自ら考え行動することなど何も求められていないのだ。
たとえば、厩戸皇子の子、山背大兄皇子(やましろのおおえのみこ)の上宮王家が襲撃されたときも、それから昨日の騒動も、である。コトが起こってから、実はかくかくしかじかなどと知らされる始末なのだ。目の前ですでに血が流れているというのに、である。
すべてがうっとうしくてたまらなかった。
女帝は立ち上がった。
「私は帰る。」
きっぱりと言ってのけると、胸がすっとした。ああ・・、と思った、ひどく意外だった。
葛城やら鎌足やら、周囲を取り巻いていた者たちがいっせいにこちらを見た。
一瞬の沈黙の後で、強い口調で言ったのは、やはり葛城だった。
「母上には、もうしばらくここにいていただきます!」
口元にうすら笑いを浮かべながら、鎌足がなだめにかかる。
「大王にはどちらへ行かれるとおっしゃるのですか?板葺宮は昨日のままの状態でございますれば・・・」
もごもごと、大極殿には死体がごろごろしたままだの、警備する兵もいないなどと続ける。
「そもそも大王ともあろうお方が、ご自分のお気持ちのままに、どこかへ行かれたりなさるものではございませぬ。大王のおわすところが宮でございますれば、民の混乱を招くものかと・・」
女帝は鎌足のしたり顔などには興味はなかった。そなたに大王の心得など説いてもらおとは思わぬとばかり、まっすぐ視線を向けたままで言った。
「ならば、退位する。」
今度は胸がすっとしただけではなかった。目の前が明るくなった。
周囲が息を呑むのがわかった。
「母上、本気でおっしゃっているのではないでしょうね。」
「このようなことを戯れに口にできようか。」
ふふ・・、と笑うと、葛城は小さくため息をついた。
「此度のことを事前にお知らせしなかったことで気分を害されておられるかもしれませんが、私はただ、コトが露見したときに母上を巻き添えにしたくないと思ったのです。ですから・・・・。」
そうか、それが、そなたなりの気遣いというものなのだなと、女帝は笑みを浮かべた。
昨日飛鳥寺に同行せよと求めた時点で、十分、巻き添えにしているではないかと思ったのだ。あの時点では、コトの成否は誰にもわからなかったのだから。それをはっきり口に出して言ってやるべきかと思ったが、やめておいた。そういうことは自分で気づくべきものだからである。
「もう、決めたのだ、私は大王をやめる。葛城、そなたが即位すればよい。」
「しかし、母上・・」
冷静沈着と評判の小作りな葛城の顔に、はっきりと戸惑いの色が浮かんだ。
「そうはまいりませぬ!」
突然鎌足が大声を上げた。
「今、宝女王(たからのひめみこ)様が退位されて皇子様が大王位につかれましたら、それこそ敵の思う壷、大王位がほしくて、入鹿めを屠ったと陰口をたたかれまする。」
なにを今さら・・、と女帝は高らかに笑った。
「ならば、何とでも画策すればよい。そなた、かまたりとか申したな、そのようなことは、得意であろう。私が退けば大王位に誰をつけるか、そなたなりにすでに考えていることがあろうが。たとえば、古人大兄皇子(※2ふるひとのおおえのみこ)あたりに即位の話をほのめかし、その出方を探るとか、たとえば、わが弟の軽(かる)を引っ張り出すとか・・・。」
もう一度にっこりと笑ってみせたが、鎌足は今度は返事をしなかった。ただ、細い目をいっそう細めて彼女を見た。いや、見つめていたのは、彼女ではなかったのかもしれない。その背後にいる誰かの気配を感じ取っていたのかも。
周囲は白けた雰囲気に包まれていた。十数年そばで仕えている女官長までがおろおろしている。
それが小気味良いというわけではなかった。ただ、このざらざら感を、彼女は少しでも早く脱ぎ捨てたかった。
「ともかくだわね・・」
と女王(ひめみこ)はさばさばと言ってのけた。
「私はこのうっとうしいものを脱ぎ捨てることにしたのよ。だから、あとはそなたたちの好きなようにやればいいわ。」
女官長を促し、じゃあ、私はこれで失礼するわと、女王は部屋の外に一歩足を踏み出した。
醜きことは嫌だ、もっと心のままに鮮やかに生きてみたい、女王は遠い空に目を向けて、そんなことをつぶやいていた。
※2、古人大兄皇子・・・田村大王の第一皇子。母は蘇我馬子の娘。蘇我本宗家は、この皇子を大王候補と考えていた。
【創作】女神の系譜(前編)
☆ヨンジュンさん、いえ、タムドク様が来日され、どきどきする土曜日をお迎えのことと思います。私も落ち着かない気持ちでいます。
そんなときに、彼とは関係ないお話をアップしようと思ったのは、私的な理由からです。昨夜、このパソコンが調子が悪くなり、これはダメかも・・、とひやりとさせられたのです。幸いにも朝になってどうにか復調しましたが、マイドキュメントに保存してある創作をどこかにアップしておかないと大変なことになるかもしれないと思い立ったからなのです。
ここにアップしますお話は、7世紀後半の古代日本が舞台になったものです。そう、あの大化改新のころのこと、主人公は時の女帝・皇極(宝女王:たからのひめみこ)です。このあとに続けて、女帝の息子・大海人皇子(おおあまのみこ)や、額田王らも登場させる予定ですが、今回はまだそこまでいたっていません。彼を想定できる人は出てきません。ごめんなさい。
あくまで緊急避難的なものでおもしろくないかもしれませんが、とりあえずこちらにおかせてください。
~~~~~~~~~~~~~~~
宝女王(たからのひめみこ)。敏達天皇の曾孫。初め、渡来系の王族・高向王(たかむくおう)の元に嫁すが、離別、田村大王(舒明天皇)の皇后となる。その死後、大王として即位(皇極天皇)。乙巳(いっし)の変(大化改新)の際に退位、実弟の軽皇子(孝徳天皇)に大王位を譲るが、その後、再び大王の位につく(斉明天皇)。
高向王(たかむくおう)との間に一子、漢皇子(あやのみこ)、田村大王との間に、葛城皇子(かつらぎのみこ)(中大兄皇子:天智天皇)、大海人皇子(天武天皇)、間人皇女(はしひとのひめみこ)(孝徳天皇皇后)がいる。
異説あり。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
飛鳥板蓋宮(いたぶきのみや)の大極殿で、権勢を極めていた蘇我入鹿(そがのいるか)が、葛城皇子、中臣鎌足らによって斃されたのは、皇極4(645)年のことだった。
後の世に言う、乙巳の変である。
その時、突然の襲撃者になすすべもなくうろたえた入鹿は、大王位にあった宝女王に助けを求めたと言う。事の次第を知らされていなかった女帝が、実の息子である葛城皇子を問いただしたところ、大王位を狙っていた入鹿の罪は明らかですと一言の元にはねつけられ、女帝はなすすべもなく退席したという。入鹿は殺害され、切り刻まれた無残な体は蘇我本宗家の前に放り出された。
葛城皇子らは、宝女王とその実弟、軽皇子(かるのみこ)を伴い、飛鳥寺へと移動した。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
「なんといっても義はわれらにござる。それゆえ、今も、葛城皇子様にお会いしたいと、阿倍内麻呂殿が西の部屋にてお待ちになっておられる。また、大伴長徳(おおとものながとこ)殿もまもなくこちらに駆けつけてこられると申しておられる・・・」
うなるような低い声が続いていた。ぶんぶんと虫が鳴いているようだと、宝女王は思った。
飛鳥寺の中庭に面した二十畳ほどの部屋には、押し黙った男達が十数人、いずれも武装を解かないまますわっていた。戦いの興奮も醒めて、一様に黒くくすんだ顔をしている。
その中には、息子、葛城皇子の小柄な姿もあった。ぶんぶん声に耳を傾けながらも、時折、神経質そうに眉根を寄せているのがわかる。綿密に計画して実行したのに、ここまで来てコトが思い通りに進んでいないと、いらいらしているのかもしれない。お若いのに頭脳明晰かつ沈着冷静でいらっしゃるなどと人は言うが、要するに、これはまだ子供なのだと女帝は弱々しい笑みを浮かべた。
そして、ぶんぶん声は、その右隣に陣取った男から発せられているのだった。
蛙を思わせるずんぐりとした身体、厚ぼったい一重まぶたの下から細い目をのぞかせて、どこぞの下級役人といった風情だ。ひとりくどくどと戦況報告なるものを行っている。
ぶんぶん声、名は何と申したか・・・、そう、かまたり、とか。
葛城によれば、三代前は百済の貴族だったということだった。百済貴族というのは真実ではないだろうが、そんなことはどうでもよかった。気に入らないのは、この声音だ。この粘り気のある語調とくどくどしさはなんだろう?耳に触れるだけで気分が悪くなるではないか。
前日起こった騒乱はすでに一区切りがついて、事態は次の段階に移ろうとしていた。
問題は、屋敷の前に放置された入鹿の無残な姿を目にして、その父、蘇我蝦夷(えみし)がどう動くかということだった。渡来系の東漢直(やまとのあやのあたい)一族という大軍団を擁している蘇我本宗家が、このまま黙って引き下がるとは思えなかった。
蘇我本宗家のある甘樫(あまかし)の丘は、飛鳥川の対岸にある。今のところそこはいつもと変わらない静けさを保っていたが、すでに目には見えない何かが漂っているように思えた。
そして、大豪族達が固唾をのんで推移を見守っているのは明らかだった。
「・・すでに東漢直にはわが手の者を忍び込ませてござる。蝦夷のヤツがあの蘇我のイヌどもを動かそうとするやもしれぬ。が、なんといっても、わがほうには大王がおられる、それゆえ・・・」
ぶんぶん声はまだ続いている。何げない顔をしているが、かまたりとやらは、騒動の後で疲れの見えてきた武将達の引き締めを図ろうとしているのかもしれない。まあ、それはどうでもよいが・・、と女帝は思った。
自分はここで何をしているのだろう。
さっきから、何かひどくたいせつなことを忘れているような気がしていた。それが何なのか、女帝にはおぼろげにわかっていたのだが、そこに目を向けるつもりはなかった。ほんのちょっとでもそれを見てしまったら、自ら手を差し伸べねばならなくなるからだ。
『いっしょに来ていただきます!』
前日、葛城が言うままに板葺宮をあとにしたが、なぜ行かねばならないのか、どこに行くのか、納得して従ったわけではなかった。だいたい、昼間起こったことさえも、事前にはまったく知らされていなかったのだから。
それでも息子の指示めいた言葉のままに宮をあとにしたのは、そこが黒いもので満ち満ちていると感じたからだ。
そこまで考えて、前日目で見、耳で聞き、心の奥底で感じ取ったモノの片鱗を思い出し、さすがに肌がぞわりとなった。
見てはならぬ!
女帝は目を閉じた。今は、身をかわさねばならなかった。
宝姫と呼ばれた頃から、醜いもの、不快なものは嫌いだった。
それから逃れるのは簡単だった。目を閉じ、遠く水の匂いのする場所に意識を飛ばしてしまえばよかった。それは、幼い頃から彼女が得意とするワザだった。
とりわけこんな朝はたやすい、・・こんな朝とは、ほとんど眠ることができなかった夜のあとは、ということだ。倒れそうな身体とさえざえとした頭脳、この微妙な組み合わせがよいのである。半分は覚醒し半分は眠っているような状態、・・周囲からはうつらうつらしていると見られる領域に、その身をおけばよいのである。
もしかしたら子供のころからそばで仕えていた女官長は気がつくかもしれないが、そんなことを、この場にいる葛城や他の男達にわざわざ話してきかせるような心配はまったくなかった。
逃れる場所は、たとえば、さらさらと流れる飛鳥川の川辺の湿った草の葉陰か、そうでなければ、寺の西門を出て百歩のところにある、雨をたっぷり吸った槻の木のはるか上方あたり・・。
そうだ、と女帝は笑みを浮かべた。雨の匂いの残るこんな日は、あの老いた大木の上がいい。茂った緑の葉の間に身を隠して、くだらない迷いごとに大騒ぎしている者たちを覗き見るのがいい。
目標がさだまれば、あとは容易なはずだった。
が、なぜかうまく行かなかった。
目を閉じた暗闇の先で待っていたのは、血しぶきをあげて、どうと倒れる男の姿だった。
すぐに後悔したが、すでに遅かった。
『それ』は、右手を伸ばしてこちらに救いを求める。恨みがましい二つの目、みるみる失われていく生の光、どうして、なぜだ?と問いかける苦悶にゆがむ口元・・。
私は少しも知らなかったのだ、少しばかり言い訳してみたけど、この世ならぬモノにそんなものが通用するとは思えなかった。
仕方がない・・、女帝は小さくため息をついた。
大臣だったこの男を、憎いと思っていたわけではなかった。かといって、好ましいと思ったことは一度もなかった。この男とのことをあれこれと噂する者がいることを女帝は知っていたが(その中には、葛城もいた!)、すべて無視することに決めていた。当然である、大王ともあろう者が、このような者を男として相手にするはずもない。
最初の夫と別れ、ひっそりと子を育てていた彼女を、先の大王の皇后に据え、その死後、大王として即位させたのは、蘇我蝦夷である。
『後継者争いを避けるため、・・誰の血も流れぬようにするためでございます、ここは、水を司る水拠姫(※1みずよりひめ)の流れを汲む女王(ひめみこ)様に大王となっていただき・・・』
などと言って引っ張り出したのだ。それを真に受けた自分も、ずいぶん未熟だったと思う。
蝦夷の後を継いだこの男にも、確かに世話になった。時には、苦手な「まつりごと」において、有用な助言をしてくれたこともあった。
だが、大王たる彼女をさしおいて、この男が政務をとりしきることが多かったのも事実だ。
『女王様には何もご心配召されませぬよう。万事は、この入鹿におまかせを・・・。』
わけのわからない「まつりごと」で心を煩わせることもなかったのは、この男の働きによるものだが、それが、葛城の言う『専横なるふるまい』になるのかもしれなかった。
そうだ、息子の言うように、この男は大王になりたかったのかもしれないと、女帝はじっとそれに目を当てた。大王の位などそれほど未練はなかったが、天孫の流れを汲む者でもない男に、それを譲るわけにはいかなかった。
そして、どちらにしても、この男が大王になるということは消えうせたのだと女帝は思った。
「いかにすべきかなどと言われても、私にはどうすることもできぬ。そなたの父蝦夷に尋ねてみよ。」
手負いの獣のようなその男に、女帝は静かに言い放った。
※1、水拠姫・・・息長水拠姫(おきながのみずよりひめ)のこと。第9代開化天皇の皇子の妃。琵琶湖の水神の娘で、息長氏の祖先のひとりとされる。息長氏は近江を拠点とした古代の有力豪族で、大和朝廷との婚姻を通じて力を伸ばした。神功皇后も息長氏の出として名高い。ここに登場する皇極、天智、天武ら、いずれも息長系の天皇である。
| [1] |