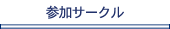【創作】女神の系譜(後編)
「・・おおきみ、おおきみ、・・ははうえ、母上、お疲れのようですが、目をお開けください・・」
突然の声に女帝は呼び戻された。
仕方なしに目を開ければ、葛城が覗き込んでいた。
「・・今のをお聞きになりましたか?・・吉報です、蘇我から火の手が上がったとのことです!」
『そが』から・・、と女帝は小声でくり返した。
なるほど、部屋の中はさっきまでとだいぶ様子が違うようだ。くすんだ顔をした男達の大半が外に出て行ったらしく、部屋の中はがらんとしている。内庭では、ばたばたと駆け回る兵士達の足音や興奮した声、馬のいななきも聞こえる。
ぶんぶん声はどうしたのだ、と思ったとたん、それはすぐ近くにかしこまっていた。
「鎌足、謹んで申し上げまする。蝦夷の動向はいまださだかではございませぬが、屋敷から出て行った気配もございませぬゆえ、恐らくは自害したものかと・・。」
そうか、あの、えみしが・・、と覚醒しきれない頭で、女帝はつぶやく。品の良い白髭の横顔が目に浮かぶ。優柔不断などと陰口をたたかれていたが、息子の入鹿とは異なり、書を好むおだやかな人物だったと思う。
が、葛城はそんなことは気にもとめない様子で、次なる一手を繰り出そうとしていた。
「早計に判断してはなりませんが、ここは、母上の、いえ、大王のお言葉が必要です。」
その言葉が終わるか終わらないかの内に、鎌足が大きくうなずくのが見えた。
「さようでございまする。いまだはっきりしない東漢直の動きを封じるためにも、ここは大王の詔がいただきとうございまする。」
女帝は、『みことのり』と小さくつぶやいたが、そのとたんになにか違和感のようなものを感じた。なにかおかしいような・・。
ぶんぶん声は話を進める。
「はい、詔の内容としましては、一同、混乱を収拾するため葛城皇子様の元に結集せよ、ということでよろしいかと存知まする。この鎌足、すでに原案は用意してございまする。」
ああ、やはり、そういうことか、と思った。体の中がざらざらしたものでいっぱいになる。
要するに、何も変わらないのだと女帝は思った。初めからずっと同じようにくりかえしてきたことなのである。きらびやかな衣装を身にまとい王冠をかぶっていても、彼女が自ら考え行動することなど何も求められていないのだ。
たとえば、厩戸皇子の子、山背大兄皇子(やましろのおおえのみこ)の上宮王家が襲撃されたときも、それから昨日の騒動も、である。コトが起こってから、実はかくかくしかじかなどと知らされる始末なのだ。目の前ですでに血が流れているというのに、である。
すべてがうっとうしくてたまらなかった。
女帝は立ち上がった。
「私は帰る。」
きっぱりと言ってのけると、胸がすっとした。ああ・・、と思った、ひどく意外だった。
葛城やら鎌足やら、周囲を取り巻いていた者たちがいっせいにこちらを見た。
一瞬の沈黙の後で、強い口調で言ったのは、やはり葛城だった。
「母上には、もうしばらくここにいていただきます!」
口元にうすら笑いを浮かべながら、鎌足がなだめにかかる。
「大王にはどちらへ行かれるとおっしゃるのですか?板葺宮は昨日のままの状態でございますれば・・・」
もごもごと、大極殿には死体がごろごろしたままだの、警備する兵もいないなどと続ける。
「そもそも大王ともあろうお方が、ご自分のお気持ちのままに、どこかへ行かれたりなさるものではございませぬ。大王のおわすところが宮でございますれば、民の混乱を招くものかと・・」
女帝は鎌足のしたり顔などには興味はなかった。そなたに大王の心得など説いてもらおとは思わぬとばかり、まっすぐ視線を向けたままで言った。
「ならば、退位する。」
今度は胸がすっとしただけではなかった。目の前が明るくなった。
周囲が息を呑むのがわかった。
「母上、本気でおっしゃっているのではないでしょうね。」
「このようなことを戯れに口にできようか。」
ふふ・・、と笑うと、葛城は小さくため息をついた。
「此度のことを事前にお知らせしなかったことで気分を害されておられるかもしれませんが、私はただ、コトが露見したときに母上を巻き添えにしたくないと思ったのです。ですから・・・・。」
そうか、それが、そなたなりの気遣いというものなのだなと、女帝は笑みを浮かべた。
昨日飛鳥寺に同行せよと求めた時点で、十分、巻き添えにしているではないかと思ったのだ。あの時点では、コトの成否は誰にもわからなかったのだから。それをはっきり口に出して言ってやるべきかと思ったが、やめておいた。そういうことは自分で気づくべきものだからである。
「もう、決めたのだ、私は大王をやめる。葛城、そなたが即位すればよい。」
「しかし、母上・・」
冷静沈着と評判の小作りな葛城の顔に、はっきりと戸惑いの色が浮かんだ。
「そうはまいりませぬ!」
突然鎌足が大声を上げた。
「今、宝女王(たからのひめみこ)様が退位されて皇子様が大王位につかれましたら、それこそ敵の思う壷、大王位がほしくて、入鹿めを屠ったと陰口をたたかれまする。」
なにを今さら・・、と女帝は高らかに笑った。
「ならば、何とでも画策すればよい。そなた、かまたりとか申したな、そのようなことは、得意であろう。私が退けば大王位に誰をつけるか、そなたなりにすでに考えていることがあろうが。たとえば、古人大兄皇子(※2ふるひとのおおえのみこ)あたりに即位の話をほのめかし、その出方を探るとか、たとえば、わが弟の軽(かる)を引っ張り出すとか・・・。」
もう一度にっこりと笑ってみせたが、鎌足は今度は返事をしなかった。ただ、細い目をいっそう細めて彼女を見た。いや、見つめていたのは、彼女ではなかったのかもしれない。その背後にいる誰かの気配を感じ取っていたのかも。
周囲は白けた雰囲気に包まれていた。十数年そばで仕えている女官長までがおろおろしている。
それが小気味良いというわけではなかった。ただ、このざらざら感を、彼女は少しでも早く脱ぎ捨てたかった。
「ともかくだわね・・」
と女王(ひめみこ)はさばさばと言ってのけた。
「私はこのうっとうしいものを脱ぎ捨てることにしたのよ。だから、あとはそなたたちの好きなようにやればいいわ。」
女官長を促し、じゃあ、私はこれで失礼するわと、女王は部屋の外に一歩足を踏み出した。
醜きことは嫌だ、もっと心のままに鮮やかに生きてみたい、女王は遠い空に目を向けて、そんなことをつぶやいていた。
※2、古人大兄皇子・・・田村大王の第一皇子。母は蘇我馬子の娘。蘇我本宗家は、この皇子を大王候補と考えていた。
【創作】女神の系譜(前編)
☆ヨンジュンさん、いえ、タムドク様が来日され、どきどきする土曜日をお迎えのことと思います。私も落ち着かない気持ちでいます。
そんなときに、彼とは関係ないお話をアップしようと思ったのは、私的な理由からです。昨夜、このパソコンが調子が悪くなり、これはダメかも・・、とひやりとさせられたのです。幸いにも朝になってどうにか復調しましたが、マイドキュメントに保存してある創作をどこかにアップしておかないと大変なことになるかもしれないと思い立ったからなのです。
ここにアップしますお話は、7世紀後半の古代日本が舞台になったものです。そう、あの大化改新のころのこと、主人公は時の女帝・皇極(宝女王:たからのひめみこ)です。このあとに続けて、女帝の息子・大海人皇子(おおあまのみこ)や、額田王らも登場させる予定ですが、今回はまだそこまでいたっていません。彼を想定できる人は出てきません。ごめんなさい。
あくまで緊急避難的なものでおもしろくないかもしれませんが、とりあえずこちらにおかせてください。
~~~~~~~~~~~~~~~
宝女王(たからのひめみこ)。敏達天皇の曾孫。初め、渡来系の王族・高向王(たかむくおう)の元に嫁すが、離別、田村大王(舒明天皇)の皇后となる。その死後、大王として即位(皇極天皇)。乙巳(いっし)の変(大化改新)の際に退位、実弟の軽皇子(孝徳天皇)に大王位を譲るが、その後、再び大王の位につく(斉明天皇)。
高向王(たかむくおう)との間に一子、漢皇子(あやのみこ)、田村大王との間に、葛城皇子(かつらぎのみこ)(中大兄皇子:天智天皇)、大海人皇子(天武天皇)、間人皇女(はしひとのひめみこ)(孝徳天皇皇后)がいる。
異説あり。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
飛鳥板蓋宮(いたぶきのみや)の大極殿で、権勢を極めていた蘇我入鹿(そがのいるか)が、葛城皇子、中臣鎌足らによって斃されたのは、皇極4(645)年のことだった。
後の世に言う、乙巳の変である。
その時、突然の襲撃者になすすべもなくうろたえた入鹿は、大王位にあった宝女王に助けを求めたと言う。事の次第を知らされていなかった女帝が、実の息子である葛城皇子を問いただしたところ、大王位を狙っていた入鹿の罪は明らかですと一言の元にはねつけられ、女帝はなすすべもなく退席したという。入鹿は殺害され、切り刻まれた無残な体は蘇我本宗家の前に放り出された。
葛城皇子らは、宝女王とその実弟、軽皇子(かるのみこ)を伴い、飛鳥寺へと移動した。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
「なんといっても義はわれらにござる。それゆえ、今も、葛城皇子様にお会いしたいと、阿倍内麻呂殿が西の部屋にてお待ちになっておられる。また、大伴長徳(おおとものながとこ)殿もまもなくこちらに駆けつけてこられると申しておられる・・・」
うなるような低い声が続いていた。ぶんぶんと虫が鳴いているようだと、宝女王は思った。
飛鳥寺の中庭に面した二十畳ほどの部屋には、押し黙った男達が十数人、いずれも武装を解かないまますわっていた。戦いの興奮も醒めて、一様に黒くくすんだ顔をしている。
その中には、息子、葛城皇子の小柄な姿もあった。ぶんぶん声に耳を傾けながらも、時折、神経質そうに眉根を寄せているのがわかる。綿密に計画して実行したのに、ここまで来てコトが思い通りに進んでいないと、いらいらしているのかもしれない。お若いのに頭脳明晰かつ沈着冷静でいらっしゃるなどと人は言うが、要するに、これはまだ子供なのだと女帝は弱々しい笑みを浮かべた。
そして、ぶんぶん声は、その右隣に陣取った男から発せられているのだった。
蛙を思わせるずんぐりとした身体、厚ぼったい一重まぶたの下から細い目をのぞかせて、どこぞの下級役人といった風情だ。ひとりくどくどと戦況報告なるものを行っている。
ぶんぶん声、名は何と申したか・・・、そう、かまたり、とか。
葛城によれば、三代前は百済の貴族だったということだった。百済貴族というのは真実ではないだろうが、そんなことはどうでもよかった。気に入らないのは、この声音だ。この粘り気のある語調とくどくどしさはなんだろう?耳に触れるだけで気分が悪くなるではないか。
前日起こった騒乱はすでに一区切りがついて、事態は次の段階に移ろうとしていた。
問題は、屋敷の前に放置された入鹿の無残な姿を目にして、その父、蘇我蝦夷(えみし)がどう動くかということだった。渡来系の東漢直(やまとのあやのあたい)一族という大軍団を擁している蘇我本宗家が、このまま黙って引き下がるとは思えなかった。
蘇我本宗家のある甘樫(あまかし)の丘は、飛鳥川の対岸にある。今のところそこはいつもと変わらない静けさを保っていたが、すでに目には見えない何かが漂っているように思えた。
そして、大豪族達が固唾をのんで推移を見守っているのは明らかだった。
「・・すでに東漢直にはわが手の者を忍び込ませてござる。蝦夷のヤツがあの蘇我のイヌどもを動かそうとするやもしれぬ。が、なんといっても、わがほうには大王がおられる、それゆえ・・・」
ぶんぶん声はまだ続いている。何げない顔をしているが、かまたりとやらは、騒動の後で疲れの見えてきた武将達の引き締めを図ろうとしているのかもしれない。まあ、それはどうでもよいが・・、と女帝は思った。
自分はここで何をしているのだろう。
さっきから、何かひどくたいせつなことを忘れているような気がしていた。それが何なのか、女帝にはおぼろげにわかっていたのだが、そこに目を向けるつもりはなかった。ほんのちょっとでもそれを見てしまったら、自ら手を差し伸べねばならなくなるからだ。
『いっしょに来ていただきます!』
前日、葛城が言うままに板葺宮をあとにしたが、なぜ行かねばならないのか、どこに行くのか、納得して従ったわけではなかった。だいたい、昼間起こったことさえも、事前にはまったく知らされていなかったのだから。
それでも息子の指示めいた言葉のままに宮をあとにしたのは、そこが黒いもので満ち満ちていると感じたからだ。
そこまで考えて、前日目で見、耳で聞き、心の奥底で感じ取ったモノの片鱗を思い出し、さすがに肌がぞわりとなった。
見てはならぬ!
女帝は目を閉じた。今は、身をかわさねばならなかった。
宝姫と呼ばれた頃から、醜いもの、不快なものは嫌いだった。
それから逃れるのは簡単だった。目を閉じ、遠く水の匂いのする場所に意識を飛ばしてしまえばよかった。それは、幼い頃から彼女が得意とするワザだった。
とりわけこんな朝はたやすい、・・こんな朝とは、ほとんど眠ることができなかった夜のあとは、ということだ。倒れそうな身体とさえざえとした頭脳、この微妙な組み合わせがよいのである。半分は覚醒し半分は眠っているような状態、・・周囲からはうつらうつらしていると見られる領域に、その身をおけばよいのである。
もしかしたら子供のころからそばで仕えていた女官長は気がつくかもしれないが、そんなことを、この場にいる葛城や他の男達にわざわざ話してきかせるような心配はまったくなかった。
逃れる場所は、たとえば、さらさらと流れる飛鳥川の川辺の湿った草の葉陰か、そうでなければ、寺の西門を出て百歩のところにある、雨をたっぷり吸った槻の木のはるか上方あたり・・。
そうだ、と女帝は笑みを浮かべた。雨の匂いの残るこんな日は、あの老いた大木の上がいい。茂った緑の葉の間に身を隠して、くだらない迷いごとに大騒ぎしている者たちを覗き見るのがいい。
目標がさだまれば、あとは容易なはずだった。
が、なぜかうまく行かなかった。
目を閉じた暗闇の先で待っていたのは、血しぶきをあげて、どうと倒れる男の姿だった。
すぐに後悔したが、すでに遅かった。
『それ』は、右手を伸ばしてこちらに救いを求める。恨みがましい二つの目、みるみる失われていく生の光、どうして、なぜだ?と問いかける苦悶にゆがむ口元・・。
私は少しも知らなかったのだ、少しばかり言い訳してみたけど、この世ならぬモノにそんなものが通用するとは思えなかった。
仕方がない・・、女帝は小さくため息をついた。
大臣だったこの男を、憎いと思っていたわけではなかった。かといって、好ましいと思ったことは一度もなかった。この男とのことをあれこれと噂する者がいることを女帝は知っていたが(その中には、葛城もいた!)、すべて無視することに決めていた。当然である、大王ともあろう者が、このような者を男として相手にするはずもない。
最初の夫と別れ、ひっそりと子を育てていた彼女を、先の大王の皇后に据え、その死後、大王として即位させたのは、蘇我蝦夷である。
『後継者争いを避けるため、・・誰の血も流れぬようにするためでございます、ここは、水を司る水拠姫(※1みずよりひめ)の流れを汲む女王(ひめみこ)様に大王となっていただき・・・』
などと言って引っ張り出したのだ。それを真に受けた自分も、ずいぶん未熟だったと思う。
蝦夷の後を継いだこの男にも、確かに世話になった。時には、苦手な「まつりごと」において、有用な助言をしてくれたこともあった。
だが、大王たる彼女をさしおいて、この男が政務をとりしきることが多かったのも事実だ。
『女王様には何もご心配召されませぬよう。万事は、この入鹿におまかせを・・・。』
わけのわからない「まつりごと」で心を煩わせることもなかったのは、この男の働きによるものだが、それが、葛城の言う『専横なるふるまい』になるのかもしれなかった。
そうだ、息子の言うように、この男は大王になりたかったのかもしれないと、女帝はじっとそれに目を当てた。大王の位などそれほど未練はなかったが、天孫の流れを汲む者でもない男に、それを譲るわけにはいかなかった。
そして、どちらにしても、この男が大王になるということは消えうせたのだと女帝は思った。
「いかにすべきかなどと言われても、私にはどうすることもできぬ。そなたの父蝦夷に尋ねてみよ。」
手負いの獣のようなその男に、女帝は静かに言い放った。
※1、水拠姫・・・息長水拠姫(おきながのみずよりひめ)のこと。第9代開化天皇の皇子の妃。琵琶湖の水神の娘で、息長氏の祖先のひとりとされる。息長氏は近江を拠点とした古代の有力豪族で、大和朝廷との婚姻を通じて力を伸ばした。神功皇后も息長氏の出として名高い。ここに登場する皇極、天智、天武ら、いずれも息長系の天皇である。
【創作】タムドクの復活~24話の後に(その2)
☆心痛むあまりに、『24話のあとに(その2)』の代わりに、こんなお話を書いてしまいました。いわば、自分の気持ちにけじめをつけるためのお話です。
はっきり言って、まだ不十分なところが多々あります。たぶん、手直しすることになると思います。
・・・たとえば、『パイレーツ・オブ・カリビアン』も、死んだと思われていた主人公の海賊さんを復活させましたよね。
となれば、愛するタムドクについても、こんな感じにしてしまってもいいんじゃないかと思うんです。
ご不快に思われた方、ごめんなさい、スルーしてくださいませ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
扉を開けると、ほのかな灯りの中に寝台の上に、その人がすわっているのが見えた。
「遅くなってごめん。おなかすいたんじゃない?」
声をかけると、かすかな笑みを浮かべる。
「アジクは寝たのか?」
「うん。
親子そろって、ほんとに手がかかるんだから。」
わざとそんなことを言ってみると、その人は恥ずかしそうな顔になった。
「すまない、俺のことを一番よくわかっているのは、やっぱりおまえだから。」
「あ・・、そんなつもりで言ったんじゃないの。
イングニムは、いばってていいんだからね。
スジニ、おれは空腹だ、もっと早く夕餉を運んで来い、とかさ・・。」
あはは・・、と笑ってみせたけど、やっぱりその人は、無精ひげにおおわれた端整な顔に、さびしそうな笑みを浮かべただけだった。
元気になるまでもうちょっとかな、
スジニは手に持った盆を寝台近くの座卓に乗せた。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
アブラム寺の決戦の日から二か月近くがたっていた。
あの日、黒朱雀に変身した姉のキハといっしょに眩い光の中にタムドクが消えていったとき、スジニはキハの子アジクを腕にかかえたまま、声の限りに叫んでいた。
イングニム~!と。
それを聞きつけたのか、まずクァンミ城主チョロが、次に斧を片手にチュムチが駆けつけてきたのだった。
すぐに何か大変なことが起こりつつあるのを見てとったふたりは、ためらう様子もなく、鮮烈な光の向こう側に飛び込んでいった。
ふたりが死んだように動かないひとつの身体を抱えて引き返してきたのは、それからしばらく経ってからのことだった。
『取り返して来たぞ!』
チュムチの焼け焦げた顔がにっと笑い、確かめるようにふり向いたスジニに、ちりちりになった長い髪を振り乱したままチョロが黙ってうなずいた。
そばに寄ってのぞいてみると、それは、鎧や胴着などあちこち焼けただれていたが、確かに彼だった。
いつものようにきれいな顔で、静かに眠っているように見えた。
『ほんとに、帰ってきてくれたんだよね?』
あとからあとから、ぽろぽろと涙がこぼれて仕方がなかった。
イングニムはただ眠っているだけだよね、すぐに目を覚ますよね、と。
本当は、「もうひとりの人」のことについても、どうしたのかとちゃんと聞きたかった。
でも、なぜかそれはとても聞いてはいけないことのような気がした。
そうでなくても、いつのまにか目を覚ましたアジクがわあわあと泣き喚いていたからだ。
スジニが姉のことを聞いたのは、あれから何日も経ってからのことだった。
尋ねてもいないのに、誰にともなくクァンミ城主チョロが、ぼそりと言ったのだった。
「結局、大神官はみつけられなかったんだ。」
やっぱり・・、とスジニは思った。
姉貴はイングニムをこっちの世界に追い返して、そうして、ひとりで逝ったんだ。
私はだいじょうぶ、と。
なぜなら、イングニムが姉貴のかなしみをひとりで引き受けようとしていたのがわかったからだ。
だって、イングニムのことをいちばんわかっていたのは、姉貴だったもの。
そして、イングニムだって・・。
だいたい、イングニムはやさしすぎるんだ。
だから、姉貴をひとりで逝かせられなくて、
だから、あのとき、天弓で射ることができなくて・・・。
もしかしたら、イングニムが天弓を破壊したのは、もっと別の理由があったのかもしれないと、スジニは思った。
でも、どっちにしても、姉貴は帰ってこない、それがすべてだ・・・。
こうして、やっとスジニは自分の中で区切りをつけたのだった。
そしてともかくも、タムドクは、生きて国内城に帰ってきたのだった。
火傷のあとはあちこちにあったが、不思議なことに致命傷となるようなものはひとつもなく、まさに奇跡だ、さすがチュシンの王だと人々は噂しあった。
本当のところ、それから何度か危険な状態になるときもあったのだ。
だが、そのたびに、生き残ったコムル村の人々や城内の人々の手厚い看護と、それからタムドク自身の驚異的な体力で、それを乗り越えたのだった。
とはいえ、タムドクが心に受けた衝撃はかなりなものがあったようだ。
横になって一日のほとんどをすごすという日々が、まだ続いていた。
以前の快活さは陰をひそめ、必要なこと以外は話す気になんかならないという顔でいる。
あのとき、なぜ、光の向こうに行こうとしたのか、そこで何があったのか、周囲の者たちは気遣って彼に尋ねようとしないし、彼も何も語ろうとしないままなのだ。
元通りに政務が取れるようになるまで、まだ時間がかかりそうな気配だった。
そんな中で、タムドクは、食事の世話やら着替えやら身の回りのことについては、何かにつけてスジニを側に呼びたがった。
スジニとしてもそれがうれしいのだが、どうしても他の用事で呼ばれてもすぐに駆けつけることができないこともある。
それに、キハの子アジクの母親代わりを務めなければならない。
チョロの目も気になる。
「おまえは忙しいのだから、ほかの女に頼めばいいだろう?」
スジニの男でもないのに、おせっかいにもそんなことを言ったりする。
普段はすごく口数の少ない男なのだが。
だが、それはまだいい、
クァンミ城主はまだ聞き分けがいいのだから。
問題は、ほかの女たちなのである。
「スジニはアジク様のことで手が離せないので、代わりに私が参りました、なんて言っても、全然だめなのよ。スジニの手が空いてからでいい、なんておっしゃるんだもの。」
ほんと、しょうがないイングニムだねなんてあきれたふりをしながら、スジニは胸がどきどきするのだった。
姉のことを思えば、そんなことさえうしろめたい気持ちになるのだけど。
その一方で、このごろになってだが、タムドクは師匠のヒョンゴを呼んで、長い時間ふたりだけで話し込んだりするようにもなった。
イングニム、なんだって?などと、周囲の者たちが期待に満ちた顔で尋ねると、ヒョンゴは、いつものように本気とも冗談ともつかない口調で答えるのだ。
「ああ~、
王が生きてここにおられるのは、まさに天の神のなせるワザというものだ、
とかなんとかいう話をしたんだ。
・・・王よ、あなたは光の中でご覧にならなかったか、
天の神が、おごそかに現れたのを。
そして、神はこうおっしゃったのではないか、
・・タムドク王よ、そなたはまだこちらに来てはならぬ。
下界でやるべきことがまだ残っているはずだ、なんてな。
あ~、つまり、人は生きて何をなすべきなのか、
まさにそういったことをだな、尊い神がお決めになっておられる、そういうことだな。」
そうかなと、その時スジニは思った。
もしそういうことをイングニムに言った人がいるとしたら、それは姉のキハじゃないかという気がしたからだ。
でも、とスジニは思い返す。
誰でもいいけど、そういうことをほんとにイングニムに言ってくれた人がいたのなら、あたしは、その人にこう言うよ、
ありがとうございます、
ほんとに、ありがとうございますって。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ともかく、生きて帰ってきてくれたんだから、
それに、このごろ、ちゃんとお粥も食べてくれるようになったんだから。
ほのかな灯りの中で、スジニは、タムドクが粥を口に運ぶのを見ていた。
「おいしい?イングニムが食べるんだからって、腕によりをかけて作ってもらったんだからね。」
「ああ、そうだな。
・・そういえば、昼間、アジクがここへ来たよ。」
「え?!
そうだったの?
知らなかった、いつのまに・・?」
勢い込んで聞くと、やわらかな笑みが返ってくる。
「手習いを見せてくれた。
お前が教えているのか?なかなかよい字を書いていたぞ。」
ああ、とスジニはうなずいた。
誰かに教えられたらしく、アジクはいつのまにか、イングニムと皆が呼んでいる人が、自分の父だということを知っていたのだった。
父上に見せるんだと言っては、一生懸命に、習いたての文字の練習をしたり、棒術の稽古に取り組んだりしている。
それはそれでいいのだが、油断していると部屋中墨だらけにしたり、額にコブを作ったりする。
なにしろ、ワンパクざかりなのだ。
しかたがないだろう、このタムドク王の血を受け継いでいるのだから。
スジニはそう思って、くすりと笑ってしまった。
「なんだ?」
「なんでもない。すごくいいことを思いついたんだ。」
スジニはそういって、またくすりと笑った。
このおだやかな日々が続いて、イングニムが元気になって、またみんなで楽しく笑えるときがくるといい。
姉貴もきっとそう思ってるよ、きっとさ・・・。
★読み返してみたら、あんまりな箇所がたくさんありましたので、あちこち修正しました。つくづくいやになりました。読んでくださった方に申し訳ないです。
タムトクの母⑥完~タシラカ
初めて会ったのは、百済王都攻めのときだった。
降伏するときの恭順の証として、百済王が差し出したものの中に、彼女がいたのだ。
『人質でございまする。』
『なかなか気の強い姫じゃ。
倭との交渉に使えまする。』
家臣たちの言葉に、タムトクは胸に強い痛みを感じた。
王位についてから4年、高句麗は北の強国としての名前をほしいままにしていた。
タムトクは戦場にいることが多く、城を留守にしている間に妃スジニを病で失っていた。
自分にかかわる女人はあまりいい星をもっていないと見える、そんな思いを心の片隅に抱いていたころのことだった。
目の前に引き出された異国の姫は、家臣たちの言葉通りの気丈さを見せた。
『私を利用して、百済や倭ににらみをきかそうとしても無駄というもの。
その時がきたら、自害して果ててご覧に入れます。』
荒くれた武将たちの前で臆することなく言い放った美貌の姫、タシラカ・・・。
思えば、最初に出会ったその瞬間から強く惹かれたのかもしれない。
だが、彼女は敵国の姫、人質だった。
うかつに手を出すことはできなかった。
なによりも、ほかの誰でもない、高句麗王タムトク自身が許すはずもなかった。
それなのに・・、と彼は思う。
批判的なサトの目をかいくぐり、なんだかんだと自分自身に言い訳しながら、
あっという間に、彼女を抱いてしまったのだった。
まったく、どうなっているのだ?!
これは、もしかしたら、私はあの契丹のブタ男と同じか?
私は下劣きわまりない男なのか!
タムトクはその問いを激しく否定したが、自分の中で始まってしまったものの正体を、最初からはっきりとらえていたわけではなかった。
ただひたすら、彼女をそばにおきたかっただけなのだ。
そうだ、やみくもに彼女が抱きたかったわけではない!
だから、抱こうとしたその前に、彼女に了解を求めたではないか!
そう思ってみたが、それもむなしかった。
出陣のときも、戦場にあるときも、彼女の顔が常に胸の中にあったのだから。
そう、彼女がほしかったのだ!
それは確かなのだ!
そうしてタムトクが引き出した答えは、きわめて明瞭だった。
私は、敵国の姫を愛しているのだ・・・。
こうなれば、彼女の心を確かめ、その上で『そばにおく』のにふさわしい処遇を与えればよかった。
頭の固い重臣たちは苦い顔をするだろうが、なに、処遇のことなど、簡単なことだ。
敵国の姫であろうが、なかろうが・・・。
タムトクはさっそく行動に移った。
一番の難敵はサトだと思っていた。
案の定、かつて契丹の城で、タムトクの中の荒れ狂う龍を押しとどめるために体を張ったサトは、冷たく言い放った。
『ですから、最初から申し上げているでしょう。
お気に召したのなら、おそばに召せばよいと・・・。』
相手に強いても、抱いてよいかと事前に了解をとりつけても、王の場合は同じことです、
要するに、妃にさえしなければなんでもいいんです、
そう、サトは言いたいのだ。
そなた、母上のことも、私のことも、よくわかっているくせに!
そう思いながら、タムトクはすべて知りつくしているサトに言った。
『私は王だ。自分にいちばんふさわしいと思う者を妻とする。
敵国の姫であろうがなかろうが、タシラカを妃にするのだ!』
サトは半分あきれ、家臣として心の底から心配しながらも、どうにかこうにか認めてくれた。
『側近としては反対ですが、友人としては心情的に理解できます。
まあ、惚れちまったものはしかたがないってことで・・・。』
それはタシラカを妃にするのにやぶさかではないと、そういうことだな?
そう手っ取り早く出した結論をぶつけると、サトはあわてふためいたが、もう遅かった。
ばかなヤツだ、サト。
側近としても、友人としても、同じことではないか。
サトはサトなのだから・・。
こうして、タムトクは、ともかくもサトを味方に引き込んだのだった。
こうなれば、彼女の気持ちを確かめ、あとは妃にしてしまえばいいと思っていた。
が、彼女はするりと彼の手から抜け出していった。
『妃になどなりたくはありません。
私はこのままでよいのです・・・。』
『ただの男と女としてお会いしたかった・・・。』
最初は、一風変わったところのある娘なのだと思った。
そのうちに、彼女の言っている意味がわかるような気がした。
しかし、高句麗王タムトクがただの男になるとは、非常に難しい問題だった。
そして、戦乱の中、タシラカは倭に帰って行った。
タムトクの子を腹に宿したまま・・・。
。。。。。。。。。。。。。。。
まったく、なんという女人なのだと、タムトクは腕の中で眠るタシラカを見た。
自分が迎えにこなければ、そのままでいいと、そう思っていたのか?
ひとりで息子を育てて、誰にも頼らずに生きていこうとでも・・・?
本当にそんなことを考えていたのか、タシラカ?
そっとつぶやいてみるが、彼女はかすかに身じろぎしただけだ。
そうはいくか!
なにしろ、そなたは、私が妃にすると決めた女人なのだからな、
それに、それに・・・・、ワタルは私の息子なのだからな!
タシラカ、愛しているのだからな!
愛・・・!
ずいぶん遠回りをして、ここまできたのだと思った。
だが、タシラカ、そもそも、そなたはどうなのだと、ふと思う。
そなたは、私を愛しているのか?
それは、裏を返せば、契丹の城で死んだ母への思いにもどることに、彼は気がついていた。
タシラカ、私はそなたに強いたのではないか?
私に抱かれよと、
私を愛せよと・・、そう強いたのではないだろうな?
初めから、そなたも私を愛していたのだろうな?
『虜囚の身ゆえ・・・』
そんな言葉を、彼女は口走ったことがあった。
だが、そんな気持ちで抱かれたのなら!
そう思うと、タムトクはたまらない気持ちになった。
胸の中に生まれた小さなわだかまりは、少しずつ大きくなっていくような気がしていた。
一度ちゃんと彼女に確かめればよいのだ、
そんなことはわかっていたのだが、ちょっと恐ろしいようにも思えるのだ・・。
それは、まったくこの男らしくないジレンマだった。
それに、それにだ、はっきり言って余裕がない。
夜毎彼女をその腕に抱けば、いよいよいとおしいのだ。
せっかくいっしょになれたというのに、そんな時間などないではないか!
しかし・・・、だ。
今夜こそ!
タムトクはそう心に決めた。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
「ひとつ、妙なことを聞いてもいいか?」
タムトクは照れくさそうな笑みを浮かべると、たずねた。
「そなた、私といっしょにいてしあわせか?」
「まあ、何をとつぜん・・?」
タシラカは輝くような笑みを見せる。
タムトクは思わず、目をそらす。
「私といっしょにいるのがいやなら、このまま倭に残っていてもよいぞ。」
「いやだなんて・・、そのように思ったことは一度もありません。
そばにいよ、そうおっしゃったのは、タムトク様ではありませんか!」
タシラカの長い髪が鼻をくすぐる。
むき出しの肩がいとおしい。
「そうだな・・・・」
そうひとりごとのようにつぶやいたものの、タムトクは彼女のあごに手を当てると、その瞳の中をのぞきこんだ。
「タシラカ、私はそなたを縛ったことがあったか?
籠の鳥のように、そなたの自由を奪ったか?
そなたに私を愛せと命じたか?」
「・・・ナカツヒコ様のことですの?
高句麗から帰るときに、ナカツヒコ様がタムトク様にそのようなことを言われたとか・・・。
あとで、何度もあの方から言われました。
腹に子がいながら、俺はなんてことを言っちまったんだって・・。」
タシラカがくすくす笑う。
そうだ、そんなこともあったとタムトクは思う。
だが、そんなことではない・・・。
タシラカ、そんなことではないのだ・・・・。
「私は確かめたいのだ。
この腕の中にいるそなたが、本当にしあわせなのかと・・・。」
胸に手をあてる。
やわらかな張りのあるふくらみは、7年前のものと少しも変わっていない。
「私は、しあわせですわ、・・・タムトク様。
あの、・・・ちょっとその手の動き、・・・止めてくださいませ。
お話ができませぬ・・・。
あ・・、タム・・トク・・さま・・。」
やはり、話はなかなか進まなかった・・・。
彼にとって、そして彼女にとっても、非常にたいせつなことに違いないのだが・・・。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
もう一度、最初から言いなおすことにした。
「そなたに言っておかねばならないことがある。
・・・ずっと以前のことだが、私は、北の異民族の王を憎んだことがあった。
それで、残忍なワザで、ヤツを殺害しようとしたのだ・・・。」
「・・・母上様のことなら、お聞きしたことがありますわ。
ずっと以前にジョフン殿から・・・。」
そうか・・、とタムトクは苦く笑う。
「そなた、私のことが恐ろしくはないか?
いや、そんなことよりも、私は、その異民族の下劣な王と同じだと思うか?
そなたは、無理に、私に・・・。」
「タムトク様!
あなたのことが恐ろしいだなんて!
あなたはそんな異民族の王様とは違います!
私は一度も、そんなふうに思ったことはなかったわ。
そんなに、おやさしいのに・・・。
・・・・タムトク様が私の手足を縛ろうとしていたら、
私は今こうしていませんわ。
ふつうの男と女として迎えにきてくださいなんて、わがままも言いませんでしたわ。
私、しあわせですわ、
タムトク様のお子を生んで、
こんなところにまで迎えに来ていただいて、
真剣なお顔で、タシラカ、いっしょに行こうっておっしゃっていただけて・・・。」
タシラカが、あたたかい腕でタムトクの肩を抱く。
すぐ目の前にある大きな瞳がうるんでいる。
「私ね、タムトク様が王様じゃなければって、何度も思いましたわ。
ふつうの男の人だったらなあって・・・。
私、王様じゃなくても、あなたを愛したと思いますわ。
そうだったらどんなによかったかって、何度も思いましたもの。
遠回りしなくても、もっと早くしあわせになれたのにって・・・。
タムトク様が心惹かれるようなお姿の方だから、
王様っていう身分の方だから、
私、好きになったわけじゃありません。
タムトク様だから、愛したんです。
王様でもしかたないか、
タムトク様だから許してやるかって・・。
母上様も、よくわかっていらっしゃると思いますわ。
きっとタムトク様のこと、りっぱな男の方になったなあって、
そう思っていらっしゃるわ。
私にはわかります、
あなたのことを愛していますもの。」
『龍』たるしるしを持って生まれたタムトク、
常ならざる人であるがゆえに、
天は、彼から母を奪い、代わりに、彼女を与えた。
タムトクの母⑤~復讐
☆失礼します。サークルの創作の続きです。
なぜかわかりませんが、あちらにアップしようとしたら、「禁止語句」とやらではねられてしまいました。何度も直したのですが、だめでした。
で、こちらでアップさせていただきます。この続きもこの後に入れます。
どうぞ、よろしくお願いします。
なお、ここまでがつらいお話です。次回のラストは、あま~い部分もでてきますヨン。
~~~~~~~~~~~~~
高句麗王の火のような思いが兵たちに乗り移ったのか、契丹の城は十日で落ちた。
父王の仇というだけならば、それほどの激しいものはなかったかもしれない。
だが、少年の日に刻み込まれた母への思いは、何年たってもくっきりとあざやかに消えることはなかった。
家臣の止めるのも聞かず、まだあちこち火の燃えている城内に先頭に立って乗り込んでいった高句麗王は、その人の痕跡を探した。
だが、わかっていた。
どんなに周囲を見渡しても、もはやその人の髪一筋残ってなどいないことを・・・。
タムトクは城の大広間らしき場所に立ちつくした。
珊瑚のかんざしを懐にしのばせたまま・・・。
じゅうたんは切り刻まれ、座卓や椅子は倒れたまま、そこここに、飛び散った血のりや泥だらけの足跡が見える。
思わず、ため息が出る。
そのとき、兵のひとりが思ってもみないことを伝えにきた。
「契丹王をとらえました!」
なに!
どこだ?
どこにいる!
激しい足取りでその後についていく。
そこは、城の中庭だった。
集められた10人ばかりの女たちの間に、後ろ手に縛られ老いさらばえた男の姿がひとつ・・・。
女人の衣装に身を包み、太った体を二つに折らんばかりに縮め、おびえた様子でその場にしゃがみこんでいる。
知らず知らずのうちに、タムトクは叫んでいた。
おのれ!
女たちのかまびすしい悲鳴が、中庭に響き渡る。
その声を聞いて、自分の中に、何か黒いものがむくむくと沸き起こるのを感じた。
すらりと腰の剣を抜く。
制止しようとした側近の腕をなぎはらい、駆け寄ろうとしたサトを突き飛ばす。
異民族の王の二つの目が恐怖に見開かれる。
腰をぬかしたらしく尻を地面につけたまま、こちらを仰ぎ見ている。
それにじっと目をあて、ひとこと、
「そいつに剣を渡してやれ!」
家臣たちの間に動揺が広がる。
その中からひとり、サトがつかつかと歩み寄ると、手に持った剣を、『そいつ』の前に置く。
だが、それは、『そいつ』をおびえさせるに十分なものだった。
置かれた剣など手に取ろうともしないまま、口をだらしなく開けたまま、首を小刻みに振る。
このような男が、母上に!
怒りがいっそう燃え上がる。
「戦え!
私は、高句麗王タムトク!
その方がもてあそんだ女の息子!」
ぎりぎりと歯を食いしばり、
剣をふりかざす。
「立て!
契丹王ならば、立って戦え!」
憤怒の声は限りなく低く、中庭の隅々まで響き渡る。
それは、龍のうなり声とも咆哮とも見紛うようなものだった。
女たちはもちろん、高句麗の男たちも、固唾を呑んで呆然と見る。
相手の口から、情けない悲鳴がもれたが、ためらう気持ちは微塵もなかった。
手に持ったそれを振り下ろすと、それは狙いすましたように相手の右腕に!
あざやかに血が飛び散る!
ぎゃあっという男の叫び声!
逃げ惑う、床の上をはいずりまわる音。
女たちの悲鳴。
ふん、一度で死ねると思うなよ!
今度は左だ!
もう一度、ふりおろす。
ぎゃあっ!
一度でとどめをさす気にはなれなかった。
少しずつ少しずつ、母上が味わった苦しみの、ほんの断片でもいい、
そのブタに味あわせてやるのだ!
家臣たちに新たな動揺が走ったのを、タムトクは心の片隅でとらえていた。
「寄るなよ!」
そちらに冷たい声をかける。
が、今や龍の化身とも見紛う主君と、血を流しながら這いずり回るおいぼれた契丹王に近寄るものはいなかった。
ただ遠巻きにしてながめている。
「そこへ、なおれ!
この卑怯者めが!」
そのとき、呪縛を解き放つような大声が・・・。
「タムトク様!」
声とともに、後ろから羽交い絞めにされる。
それが誰のものか、瞬時にわかった。
「サト!はなせ!
王の命だ!」
が、サトの力は思いのほか強かった。
「タムトク様!
もう、そのへんでよいでしょう。
相手は剣も持つ気力もないような男だ。
そのような下劣な男のために、自ら手をけがすことはありませぬ!
あとは、この私におまかせを!」
「ならぬ!
そなた、王の命にそむくつもりか!」
「どうか、お静まりを!
なにとぞ!」
「サト!はなさねば、そなたとて容赦はせぬ!」
「私のことならいかようにも、ご存分に!」
サトは、なおも強い調子で続ける。
「しかしながら・・、しかしながら、タムトク様!
そのようなお姿、王妃様が、・・・お母上が目にされたら、
なんと思われるでしょうか!」
急に力が抜ける。
ふところにしのばせた珊瑚のかんざしが熱くなったような気がして・・・。
「・・・・・」
「そのような下劣なこと、
王と呼ばれる方のなさることではない、
そう、悲しんでおられます。」
そうだろうか・・・。
タムトクは、手の中にあるものに、ぼんやりと目をやる。
そこに、血のしたたり落ちる剣があるのを・・。
それから、それをぽいとその場に投げ捨てると、
高句麗王タムトクは、足音高くその場を立ち去った。
珊瑚のかんざしを懐にしのばせたまま・・・。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
サトは、床の上に無造作に投げ出された王の剣に目をやった。
大きくひとつ深呼吸する。
そして、血塗られた剣をこの上なく貴重なもののように拾い上げると、瀕死の男を一瞥する。
「あとはまかせたぞ。」
高句麗王の側近第一号は、周囲を取り巻いた同僚たちに軽く言ってのける。
それから、心に深手を負ったままの王のあとを追った。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
「どうなのだ?」
声をひそめて、ジャン将軍は言った。
サトも小声で答える。
「おやすみになられました。
かなり強い酒をお持ちしましたゆえ・・。」
ふうむ・・、とジャン将軍はうなる。
「かなりこたえておられるようだな?
ま、無理もないか・・。
ひとつずつ、龍のしるしの扱いを学んでいっていただかねば・・・。」
はあ、とサトはうなずく。
「それに、契丹がわが高句麗の手に転げ込んできたことは大きい。」
「まあ、そうですね。」
「それにだ、もうひとつ得たものがある。
これで、王が敵の女に手を出さなくなるかもしれないってことだ!」
これには、サトが目をむいて、抗議する。
「あの方は、これまでも、女人におかしなふるまいをしたことはありません!」
ちっちっち・・・、と将軍は人差し指を横にふる。
「あま~い。
今まではそうかもしれないが、これからはわからん。
なにしろ、あの男ぶりだ。
たとえば、人質にとった敵国の姫が妙な気持ちを起こして、王に色目でも使ってだな~、
王もその気になって、つい手を出したりしてみろ!
あのご気性だ、先々、面倒なことになるかもしれない。」
「面倒なこと?」
いぶかしげに、サトがジャン将軍を見る。
「そうだよ~。
たとえばだな~、ちょっとした美貌に目がくらんでだな~、
敵との交渉に使わずに、
そばにおきたいとか、
妃のひとりに迎えたいとか・・・」
| [1] [2] |