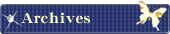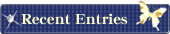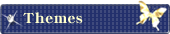mirageside-Reymond7 Hisname②

「マム!」
このベンチから見渡せるアパートの入り口に母の姿を見つけると、
僕は思わず立ち上がって叫んだ。
母は最初、僕の声に気がついて笑顔で手を振ってくれたがその笑顔が一瞬にして
硬い顔に変わり、そして次第に悲しそうな顔になった。
「レイ!いらっしゃい!」
僕は母に呼ばれるまま、その場を離れようとしたがその瞬間、誰かに強く
手首を掴まれ身動ができなかった。
振り向くと、さっきまで温和な顔で僕と話をしていたおじさんが怖い顔で
僕の手首を強く握っていた。
「離して・・・ください・・・母が呼んでます」
「あ・・・悪かったね・・・痛かったかい?・ごめんよ・・
レイモンド君、頼みがあるんだ
私は・・君のお母さんと少し・・・話がしたい・・・
君はその間ここで待っててもらえないだろうか」
正気を取り戻したかのように、おじさんは僕の手を離して、そう言った。
「・・・・」
そして・・僕を優しくベンチに腰掛させると、立ち尽くしたままの母のところへ
ゆっくりと進んでいった。
母とおじさんがしばらく話をしている間、僕はずっと不安な気持ちでふたりに
視線を送っていた。
おじさんの前で伏目がちに佇む母の姿はいつものように美しかったが、
その憂い顔は僕が知る母ではなかった。
しばらくして、母が僕を手招きしたので、僕は走って母の元へ向かった。
そして母は僕を傍らに抱くと静かに言った。
「レイ・・・この方はママの古くからのお知り合いなの・・・
今夜はこの方もお食事にお誘いしてもいいかしら」
「・・・・僕は・・・構わないよ」
母が食事の支度をしている間、キッチンの直ぐそばのテーブルで僕と話をしていた。
おじさんはとても優しく笑っていたけれど、時折、母のうしろ姿に視線を送る
おじさんの目が寂しそうに見えた。
それは・・・
僕の気のせいだっただろうか
母の得意料理がいつもより沢山テーブルに並べられて僕は上機嫌だった。
「マム!・・・今日は何だか、凄いね・・ご馳走ばかりだ」
「そうね・・沢山お食べなさい・・レイ」
「うん!・・」
僕がフォークを忙しく口に運びながら、母の料理を味わっている傍らで
母は伏目がちであまり開かない口元に静かにゆっくりとフォークの先を運んでいた。
おじさんはというと、そんな母を黙って見つめて目の前の皿に盛られた料理も
少しも形が崩れなかった。
「ふたりとも・・・食べないの?
美味しいよ・・おじさん・・これ、マムの得意料理なんだ
食べてごらん?」
「あ・・ああ・・ありがとう・・戴くよ・・・
本当だ・・美味しい・・・」
「おじさん・・・」
またおじさんが、泣いているのかと思った。
でも僕は今度は何も言わなかった。
決して楽しげとは言えない静かな会食が終わると母が僕に“勉強してきなさい”と
優しく言った。
まるで僕をその場から遠ざけようとしているようだった。
僕はふたりのことが気になりながらも、母の言う通りに二階に上がっていった。
「どうして・・・」
「・・・・」
「私のところからいなくなった?」
「・・・・」
「探してたんだよ」
「・・・・」
「何とか・・言いなさい」
「どうして?・・・」
「・・・・・」
「・・・私もお聞きしたかったわ・・・どうして!・・
どうして・・・嘘を?・・どうして・・
あなたはご自分のことを何もかも隠して・・」
「・・・・・」
「あなたが普通の方だったら・・・」
「普通・・・か・・・やはり私は普通じゃないんだね・・・
わかってるよ・・・
私も自分が嫌いだった・・私の血が嫌いだった
だから君と出逢った時・・思わず素性を隠したのかもしれない
しかし・・・
私が何者なのか・・・知ってしまったら君は
私を愛してくれただろうか・・・
私は君が一番嫌いな人種・・・そうだろ?
そのことは最初から分かってた・・・だから、言えなかった」
「それだけじゃないわ!・・何より、あなたには・・」
「・・妻との間には最初から愛は無かった」
「そんなこと!理由にならない!」
「理由にならない・・確かにそうだね・・・
でも、私は・・・君に嫌われたくなかった・・
君を愛してた・・心から愛してた・・・君に・・・
愛して欲しかった・・・だから・・嘘をついた」
「・・・・・もう・・いいんです」
「・・・・」
「私を・・・私達を放っておいていただけませんか」
「それはできない」
「なぜ?」
「私の子供を貧しい境遇には置けない」
「あなたの子供?私の子供だわ」
「わかっているだろ?今の君の力では、あの子にろくな教育も
受けさせられない・・
食べさせていくことだって・・・それでいいのか?」
「やはり・・あなたの仕業ですね・・昨日、仕事を失くしました」
「・・・・・」
「汚いわ・・あの子に・・そんなあなたの世界を見せたくない!」
「聞き分けのないことを言わないでくれ・・
君だってわかっているはずだよ・・君は・・・
だから・・僕の元へ・・あの子といっしょに・・・」
「あなたのお世話になんて・・・死んでも嫌」
「そんなに?・・私はどうしたらいい?!」
「何するの!止めて!」
「ママを泣かすな」
僕はふたりが物々しい会話をしているのを何故か震えながら聞いていた。
そして、ふたりの声が次第にエスカレートしていった時には既に僕は
母が寝室のベッドサイドの引き出しに忍び込ませていた拳銃を手にしていた。
イタリアは女と子供の二人暮らしには決して安全と言える国ではない。
母は護身用にと早くからそれを手に入れていたことを僕は知っていた。
「レイ・・何をしてるの!」
「ママを泣かしたら・・許さない」
その人が母の手を掴んで彼女の体を激しく壁に押し付けた瞬間、
僕はその人の背後に回り、彼の腰の位置にそれを付けた。
「レイ!・・止めなさい!」
母が僕のしていることに驚いて大きな声をあげたが、僕の目はその人を
鋭く睨んだまま、動かなかった。
「レイモンド・・・」
「馴れ馴れしく呼ぶな。僕を呼ぶな。」
この子は・・・
「ごめんよ・・・君のママを泣かせてしまったね・・・
そうだね・・私はおいとましよう・・・
どうか・・だから・・
その危ないものをママに返してくれないか・・・」
「レイ・・ママに頂戴・・お願い・・止めて・・」
母はそう言いながら僕に近づこうとしたが、それをその人は制した。
その人はしゃがみこんで僕の手に握られたその口を一旦自分の心臓の位置に
宛がうとこう言った。
「レイモンド・・・今君がこの引き金を引いたら
私はこの場で簡単に死んでしまう・・・
私は・・それでも構わない・・・本当に構わないよ・・・
しかし、君にそんなことはさせられないんだ・・・
君のママが悲しむことになるからね・・・」
そこまで話すとその人は銃口を下に向けさせ、話を続けた。
「今日は色々と驚かせて悪かったね・・・そして・・
君が大事に思っているお母さんを・・・泣かせて悪かった・・・
でも・・・君が大事に思っているのと同じくらい・・
私も彼女を大事に思っている・・・
君は賢い子だ・・・
もう・・わかるね・・・私が何者なのか・・・
私は彼女を愛してるんだ・・・
そして・・君のことも・・・愛している・・・
ふたりを幸せにしたくて・・私はここへ来た・・・」
僕は興奮と緊張で体全体が硬直していた。
その人は僕の手に握られたものから僕の指を一本一本外していった。
そして、やっと外されたものを後ろで涙を流して待っていた母に手渡した。
その人はその後に僕を力強く抱きしめて言った。
「レイ・・・たとえどんなに怒っても・・・武器は使うな・・・
武器を使わなければならないのは弱者だけだ・・・
本当に強いものは・・・武器など使わない・・・
使うのは頭脳だ・・・いいかい?レイ・・・
お前は本当に賢い子だ・・・強い子だ・・・
もっと・・もっと強くおなり・・・
お前なら・・・私ができなかったことも・・・きっとできる
レイ・・・
ママを守るために強い男におなり・・・」
「・・・・・」
お前は賢い子だ・・・
ママを守るために
・・・強い男におなり・・・
mirageside-Reymond6 Hisname①

「彼の名前は・・・レイモンド」
「レイモンド?・・・」
「はい・・・」
「いくつになる・・・」
「今年10歳になるとか・・・」
「10歳・・・彼女が私の前から消えて・・・
そんなに経ったのか・・・
それで・・・彼女は・・・」
「子供を手放すことを頑なに拒んでいます」
「・・・・・」
「如何なさいますか?・・・」
「私が行こう」
「では渡航の準備を・・直ちに」
「ん・・」
・・・マム?・・・
母が帰って来た物音に気がついて、僕はベッドを降り母がいるだろうリビングへと
向かった。
いつもなら、仕事から帰宅すると何を置いても真っ先に僕のベッドを覗きに
来るはずの母がなかなか現れなかったからだ。
僕がリビングへ入ると、母は頭を抱えたように椅子に腰掛けたまま、うずくまっていた。
「マム・・・どうしたの?頭が痛いの?」
「あ・・・いいえ・・・何でもないわレイ・・・
大丈夫よ・・・お夕飯はちゃんと食べた?」
「うん・・・食べたよ
ママの作ったラザニアはやっぱり一番美味いや」
「そう?・・レイ・・ありがとう
ごめんなさいね、いつもひとりでお食事させて・・」
「マム・・・僕は平気だよ・・
こうして夜にはママの顔が見れるもの・・
朝だって、ママのおはようのキス・・知ってるんだ
ただひどく眠くて、お返しができないけど・・
ごめんね」
「いいえ・・・お休みのキスができるまで
あなたは寝ないで待っていてくれるもの・・・
それだけで十分よ」
「マム・・・何だか元気がないね・・・
何かあったの?」
「いいえ・・・あなたが心配することは何もないわ
レイ・・・こっちへ来て?・・・キスしてくれる?」
僕はこの時、母が何を思い悩んでいるのか見当も付かなかった。
物心付いた時には僕達はいつもふたりきりだったせいかいつしか互いに心配掛けまいと
無理をするようになっていたと思う。
ふたりの生活の為に母は朝早くから、夜遅くまでふたつの仕事を掛け持ちしていた。
母は身を粉にして働いていたが、もっと小さかった頃の僕はひとりきりで待つ寂しさから、
母に駄々をこね困らせることもしばしばだった。
ある時、母はちょっと悲しそうな目をしながら、僕を思い切り抱きしめ、こう言った。
「レイ・・・ごめんなさい・・・
あなたにこんなに寂しい思いをさせる・・・
悪いママね・・・
でもね・・・
ママはあなたと一緒にいたかった・・・
それだけなのよ・・・
だから・・・あなたを・・・
許してね・・・レイ・・・許してね・・・」
いつの頃からか、“寂しい”という僕の言葉が母を一層悲しくさせていることに
気がついた僕はそれ以来母に“寂しい”と言ったことがない。
それが、どんな時にもいつも明るく僕に満面の笑顔をくれる母への僕のお返しだと
思っていたからだ。
そんな母がこの夜は何故か沈んだように悲しい目をしていた。
僕は自分が何か悪いことをしたんじゃないかと気が気ではなかった。
母が望むように左右の頬にキスをして、その首に抱きつくと、彼女の膝の上に
腰を下ろした。
「マム・・・僕・・もっといい子になるよ」
「レイ・・・あなたはとてもいい子だわ・・・
ママはあなただけがいれば幸せなの・・・
ママのそばを離れないでね・・・レイ・・・」
母はそう言うと僕を強く抱きしめた。
「マ・・ム・・・苦しいよ・・・」
「あ・・ごめんなさい・・・」
「マム・・・離れないよ・・・
僕はずっとママのそばにいる・・・」
「そうね・・・そうよね・・・」
「ああ・・そうだよ・・・
僕はねマム・・・早く大きくなりたい・・・
早く大人になりたい」
「そんなに急いで大人になることないわ・・レイ・・」
「駄目だよ・・・早く大人になって・・
お仕事をして・・お金をいっぱい稼いで・・
僕がママを守ってあげる」
「レイ・・・ありがとう」
「だからお願い・・・
そんなに悲しい顔をしないで・・マム・・」
「レイ・・・私の・・・レイ・・・
ごめんなさい・・・心配しないで・・・
大丈夫よ・・ママはあなたさえそばにいてくれれば
大丈夫・・・本当よ・・・」
「うん・・・マム・・・お仕事疲れたでしょ?
もう、遅いからおやすみ・・・
僕が本を読んであげようか?」
僕はわざと大人ぶって母の手を取った。
「まあ・・レイったら・・・
そうね・・・読んでもらおうかな・・・
ママはあなたの声が好きだわ」
「いいよ・・・おいで」
母は僕の掌に白い手を乗せて美しい笑顔を僕にくれた。
「ここです」
「こんなところに?」
「はい・・・朝は近くのパン屋で・・・
昼から夜に掛けてレストランで働いているようです
朝早く家を出て、夜は10時頃の帰宅の繰り返し
それでも、生活は楽ではないようです」
「その間・・子供は?」
「ひとりで待ってます・・・今の時間は丁度
学校が終わる頃・・・そろそろ帰ってくるかと・・・
・・・・あ・・あの子です・・・ボス」
「・・・・・」
僕が学校から帰ると、アパートの入り口に男の人がふたり立っていた。
僕の方をずっと見ているふたりの男に僕は少し怪訝そうな視線を送りながら、
入り口に向かった。
「君・・・」
「・・・・・」
「レイモンド・・君・・かな?」
「・・・・どうして僕の名前を知ってるの?
おじさん・・誰?・・ですか?」
「私は君のお母さんの知り合いで
アンドルフ・パーキンと言います」
「アンドルフ・パーキン?・・・聞いたことないけど」
「はは・・そうですか?・・・
私はよく君を知ってるが・・・」
「僕を?・・・どうして?」
「んー・・君が生まれた時・・・会ってるんだ」
「僕が生まれた時?・・・なら・・・
僕をよく知ってる・・・わけじゃないね」
「はは・・・そうだね・・・確かにそうだ」
「僕に用ですか?」
「少しお話してもいいかな・・・
お家に入れてもらっても?」
「駄目だよ・・・知らない人は入れられない
あなたが僕や母を知ってても
僕はあなたを知りません・・・」
「そうですか・・・そうですね・・・
当然だ・・・いや・・賢い子だ・・
じゃあ、そこの公園でお話しするだけは
どうだろう・・」
「誘拐しない?」
「ははは・・・誘拐か・・・
レイモンド君・・・実は君のお母さんに会いたい
お母さんは今日は何時ごろにお帰りかな?」
「今日は早く帰ってくるよ
一緒に夕飯を食べるんだ」
「そう・・・それじゃあ、それまで少し私に
お付き合いしていただけないかな・・・
あ・・・そこの公園の前に交番があるね
その前のベンチではどうだろう・・・
そこだと、ほら・・誘拐・・・できないだろ?」
「ふふ・・・いいよ」
その男は温和そうで、笑顔がとても似合う紳士だった。
どこか懐かしげなその声に僕は少し気を許していた。
「じゃあ、そこで待っててください
僕・・かばんを置いてきます」
「はい」
その人は僕がアパートの階段を上って行くのをまた目を細めて見送っていた。
「本当に・・・賢い子だ・・・
姿は私の小さい頃に良く似ている・・・
いや・・私よりもずっと大人びている
睨みつけた鋭い目はいっぱしの男だな」
「はい・・・成績は常にトップ・・・
子供ながらにかなり落ち着いたお子です」
「何としても・・・あの子が欲しい・・・」
「わかっています・・・
彼女が彼を手放さざる得ないように・・・
手を打っています」
「手荒なことはするなよ」
「もちろんです・・・あの方もボスにとっては
大切なお方ですから・・・」
僕は母に知らない人には決して付いていかないよう幼い頃から言い聞かされていた。
もちろん・・・そんなことは十分承知だった。いつもの僕なら、さっきみたいに
知らない人に声を掛けられても、相手などするはずがなかった。
それなのに・・・何故なんだろう・・・あの人はいいような気がした。
アンドルフ・パーキン・・・聞いたことのない名前
でも何故か・・・懐かしい声・・・懐かしい目・・・
誰かに似ている・・・誰に?
「お待たせしました」
「いいえ・・・じゃあ、ここへ腰掛けて・・・
何か飲むかい?」
「いいえ・・・いりません」
「どうして?学校から帰ったばかりで
おやつもまだでしょ?」
僕は正直、少しおなかもすいてたし、のども渇いていた。
僕のそんな本心を見透かしたようにその人はそう言った。
「いりません」
「そうか・・・私は飲みたいんだが・・・
でも、こんなところで大の大人が何も食べない
子供の横で飲み食いしてたら・・・恥ずかしいね・・・
君が一緒なら・・・
子供に付き合ってあげてるんだなって
あそこのおまわりさんも思ってくれそうだな・・・
そう思わないかい?」
「・・・・・・思・・う」
「じゃあ、いいよね」
そう言ってその人は、もうひとりの人に合図を送った。
しばらくして、目の前にあったハンバーガーショップから両手に袋を抱えて
その人が帰ってきた。
「さあ・・・どうぞ・・・召し上がれ」
「こんなに・・・食べられないよ」
「はは・・・そうだね・・・
でも、食べられるだけ食べておくれ」
「は・・い・・・いただきます」
僕はハンバーガーを口いっぱいに頬張って辺りを見渡した。
学校の友達がいないか、気になったからだ。
いつも友達が食べているお店のハンバーガーも僕は食べたことがない。
誘われるたび僕は必ずこう言った。
“僕はハンバーガーが嫌いなんだ”
食事はすべて母の手作りだったし、おやつには母が作ったクッキーが数枚
テーブルに置いてあって、ミルクと一緒にいただく。
母は決して言わないけれど、うちは無駄なお金を使うほど余裕のある家ではないことは
子供の僕でも分かっていた。
でも・・・美味しかった・・・
母の作る料理は美味しいけれど・・・
ラザニアもスパゲッティも・・・
少し甘すぎるシチューもすごく美味しいけれど
何も不満はないけれど・・・
食べてみたかったハンバーガーは・・・
本当に美味しかった・・・
「美味しいかい?・・・もっとお食べなさい」
「いいの?」
「あ・・ああ・・・いいよ」
「おじさん・・・どうしたの?」
「え?」
「泣いてる」
「いや・・・泣いてなどいないよ」
「だって・・涙・・・」
その人は、慌てたように目に手を当てて、零れ落ちそうになっていた涙を拭いとった。
「おじさんは食べないの?」
「私・・・は・・・そうだね・・・いた・・だこう・・・
・・・・・すまない・・・どうしたんだろう・・・
可笑しいね・・・何故・・だか
・・・のどを通って・・いかない・・・・・」
そう言うとその人は我慢していたものが堪えきれなくなったかのように、
嗚咽をあげながら下を向いて泣いていた。
僕は何故、その人が泣いているのか少しも理解ができなかったけれど、
声を押し殺すように泣いているその人が苦しそうに見えて、いつの間にか、
その人の背中をゆっくりとさすっていた。
何故だかわからないけれど・・・
僕がそうしなければならない・・・
・・・そう思ったんだ・・・
| [1] |