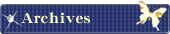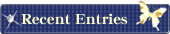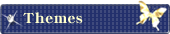創作mirage-儚い夢-9.彼女のコーヒー

僕は彼女とふたり・・・
並んでベッドに寝転がり、沈黙したまましばらく時間を忘れていた
きらめく星空を眺めながら・・・
こんな光景が・・・前にも何処かで存在していたような・・・
妙な想いに囚われていた
「 前にも・・・ 」
「前にもこんなことがあった気がしない?フランク・・・」
彼女が僕と同時に僕の気持ちのままを言葉にした。
僕は本当に驚いたけれど、その驚きを彼女に悟られないようぶっきらぼうに言った。
「気安く・・呼ぶな。」
そうやって僕は上手く言い表せない、今の不思議な感情を即座にごまかした。
「じゃあ、どう呼べば?Mr.フランク?あーfamily name?
そういえば、フランク・・・あなたのfamily
nameを聞いてなかった。ね、教えて?」
さっきまで僕の拒絶反応に確かに塞ぎ込んでいたはずの彼女が、急におしゃべりになった。
「君・・・うるさい。」 僕はそう言ったものの、本当はさほど、そう思ってはいなかった。
「あの!・・・私は君、じゃなくて・・・ジ・・ニョ・・ン・・・」
「あのね!僕と君は名前で呼び合うほど親しくもないし、きっと
これからも、そうはならない!」≪きっとそうはならない・・・≫
「どうして?」
「また・・どうして?・・・どうしても!」
いつの間にか僕たちは・・・
狭いベッドで隣り合わせに横になったまま、顔を突き合わせ言い合っていた。
「恋人がいるから?」
「・・・・そ、それもある・・・」
「そんなこと・・・関係ないと思うけど・・・あなたと私が親しくなることに・・・」
「関係なくはないだろ?それに僕はこれからもっと忙しくなるし、
余計なことを考えたり、振り回されたりしたくない・・・」
「何も考えることはないわ・・・私たちが親しくなることって・・・
何か考える必要があるの?」
「だから、子供なんだよ・・君は・・・
大人の世界では、人との付き合いも慎重にならざる得ないこともある」
「そうかしら」
「そんなだから・・君は危なっかしいって、言われるんだ
あーあの・・あいつ・・ジョルジュだっけ?彼も心配が絶えないね・・・
悪いけど僕は彼みたいに君のお守りをする気はない・・」
彼女が急に起き上がって僕を見下ろした。
「どうして、ここでオッパが出てくるの?・・・彼は関係ないわ
それに私は子供じゃないし・・お守りなんていらない。」
「そのお守り役が何日も現れなくて、パニック起こしたのは誰?」
彼女の興奮したような反論の後、僕はさらりと言った。
「あ・・あれは・・あの時は単に彼が心配だっただけよ!
私には自分の意思があるわ・・・その意思に!
自分に!いつも正直でありたい・・・
私の心が誰かを求めて・・・誰かに向かってる・・・
その自分の心を信じたい・・・それがあなたなの・・あなただって・・・」
「僕も?・・僕の気持ちも・・君に向かってると?・・・」
「・・・・・・」
僕も起き上がって今度は座ったまま僕たちは睨み合った。
「子供の癖に!・・・いや・・子供だから、だな・・・きっと・・・
自己中心的・うぬぼれ・我侭・図々しい・・・ハッ・・呆れるね、まったく。・・」
僕は彼女に嫌味混じりの言葉を容赦なく投げつけていた。
「いいわ・・・何とでも言って。」
彼女の目が“今度は傷つかないわ”というように僕を強く睨んだ。
「・・・・・・」
「私は!・・・あなたが・・好きです。」
そして彼女は僕の目を真直ぐに見据えて、ゆっくり言葉をつなげた。
「勝手にしろ!」
僕は彼女のあまりに真剣なまなざしを真直ぐに見られなくて、情けないことに
彼女から目を逸らしてしまった。
「勝手にしていいの?」 彼女がまた得意の輝くような笑顔を僕に向けた。
「でも、今日は泊めないよ!」 僕は大きく溜息をついてみせた。
彼女はそれでもにっこり微笑んで頷いた。「わかってます・・・でも・・・」
「・・・・・・・」
「また来てもいい?・・ほら・・星・・見たいし・・」 そう言いながら彼女は天窓を指差した。
「星は外でも見れる。」
僕はそう言って、彼女から顔を逸らした。しかし僕のその言葉は簡単に無視された。
「お仕事の邪魔はしないわ・・・あの・・・恋・・人・・の邪魔もしない・・・」
「・・・・・・・」
邪魔をしない・・・
そう言ったはずなのに・・・彼女は結局毎日ここへ現れた。
学校が終わるとまっすぐにここにやって来て、僕が留守の時は、玄関ドアの前で
例外なく膝を抱えてうたた寝していた。
「君・・・暇なの?」
「何だか、足が勝手に向いちゃって・・」 僕の呆れ顔を前に彼女は決まってそう言いながら、
俯きがちに人差し指で自分の鼻筋を撫でた。
そして部屋に入るなり彼女がすることといったら、僕のベッドに寝転がってまず空を仰いで、
「今日は星が綺麗」「今日は曇ってるわね」などと、独り言を言っていた。
≪それは、ここへ来る前からわかってることだろ?≫
しかし空に星が輝いているか、いないかなど・・・
彼女にとってそんなことはさして問題のあることじゃないらしい。
“邪魔はしない”と言った自分の言葉を一応は守るかのように彼女は特に僕に
まとわりつくでもなく、自分の教科書を広げて勉強らしきことをしてみたり、
いつの間にかまた彼女の手によってベッド脇に移動されたミニコンポで、
僕のコレクションを聴きながら鼻歌を歌ったり、僕の本を書棚から勝手に取り出しては
「難しい」と文句を言いながら読む振りをしていることもあった。
とにかく彼女はただ・・・僕のそばでまどろんでいることを楽しんでいる・・そんな感じだった。
彼女が現れるようになって、三日目にもなると、僕の彼女への想いにも変化が現れた。
本当のところ、鬱陶しく思っていたいたはずの彼女が、そこにいることにさえ
疑問を持たなくなって来ていた。
いつしか彼女は僕のそばに当たり前のように存在しつつあった。
僕は特に彼女に構うでもなく、部屋にいる彼女を気にするでもなく、ただもくもくと
仕事をすることができていた。
フッと一息を付いてコーヒー片手に視線を上げると、彼女もまた僕の方に笑顔を向けていた。
僕はそんな彼女の笑顔に、自分がどんな顔で返せばいいものか、その一瞬だけが
何とも僕を戸惑わせる瞬間だった。
その度に僕は慌てて仕事に戻っていたが、何故か高鳴る自分の心臓の音が
時にキーボードを叩く速度の邪魔をしていることに気がついた。
彼女が僕の部屋を訪ねるようになって四日目・・・
僕は彼女がこの部屋で何をしようと何一つ口出しをしなくなっていた。
「フランクの入れるコーヒー美味しいわね。私も入れてみてもいい?」
「勝手にどうぞ・・・」
ただし、僕は他人が淹れたコーヒーは飲まない。それはここ何年も続いた習慣であり、
ソフィアはそれを暗黙の内に理解していた。
頑なだと言われればそれまでだが、微妙な香りを楽しみたい嗜好品に関しては、
他人に介入されることを僕は頑固として望んでいなかった。
しかし、それを自分から人に言ったことはない。
だから、彼女が自分で入れて、黙って僕の傍らに置いていったコーヒーにも
手をつけないまま放っておくつもりでいた。
ところが、傍らから漂う香りに誘われて僕は無意識にそれを手にしていた。
そしてその瞬間、僕は彼女のコーヒーを自分が入れたものと錯覚して口に運んでいた。
僕の入れたものと・・・同じ香り・・同じ味だった・・・
僕はカップに口をつけたまま、無言で驚きの表情を彼女に向けた。彼女もまた
無言で“ん?”という視線を返した。彼女には僕の表情の意味が理解できなかったからだ。
この時僕は・・・他人が入れてくれたコーヒーを初めて口に流し込んだ。
それがどういう意味を成すことなのか、僕は考えないように努力した。
彼女は自分で買ってくるサンドウィッチと自分で淹れたコーヒーを夕飯にして
2~3時間を僕の部屋で過ごすと例外なく寮の門限に間に合うように帰って行った。
そんな日々が五日間続いた。
そして・・・また僕は明日から二日間ここを留守にする。
「明日は・・・来ても無駄だよ・・・」 僕は彼女に言った。
彼女に断る理由などないと思いながら、つい、そう告げていた。
「どうして?」
この頃になると、僕は彼女の「どうして?」もさほど癇に障らなくなっていた。
「帰らないから。」 僕はぶっきらぼうにそう言った。
「ふ~ん・・・」
彼女が視線を落として寂しそうに頭を垂れたのを見て、僕は少しだけ胸がチクリと痛んだ。
「・・・学校に・・・行ってるんだ・・・」
彼女に自分のことを話すのはこれが初めてだった。
「学校?何処まで?」
「マサチューセッツ・・・」
「・・・いつ帰って来るの?」
「金曜日・・・」
「金曜日・・・何時頃?」
「わからない。でもかなり遅くなる・・・だから・・来るんじゃないよ。」 僕は念を押した。
「・・・・・・・」
彼女はそれっきり深くは聞かなかった。
しかしこの時僕は彼女の質問ひとつひとつに答えていた自分に驚いていた。
たったひと月前は、存在すら知らなかった彼女に・・・。
いったい・・何やってるんだ?
「君・・・毎日ここへ来てて・・・ちゃんと勉強してる?
学生の本分を忘れてないか?」 僕は項垂れていた彼女にそう聞いた。
「してるわ」 彼女は項垂れたままそう答えた。
「ホントか?アメリカの大学は入るのは簡単だけど、進級や
卒業は難しいんだよ・・・本当に大丈夫?」
「・・・たぶん。・・・あさってから試験だから・・復習もしてるし」
彼女はベッドに広げた教科書を指差して言った。
「貸して・・・」 僕は手を出して言った。
「えっ?」
「教科書」
僕は彼女の数冊の教科書を手に取り一通り捲ると、レポート用紙にペンを走らせ、
それを彼女に渡した。
「解いてみて」
「・・・・・・・」
「たぶん・・・問題はそんなもんだ・・・それが回答できたら試験は大丈夫」
彼女は不思議そうな顔をしながら、僕が渡した問題を解き始めた。
「んー難しいわ・・・」
「それくらいのものを難しがるようじゃ、理解が足りないな
とにかく、その問題が解けるようになるまで復習してごらん」
「あ・・は・・い・・・」
この数日間決して、彼女のそばには寄らなかった僕がいつの間にか、ベッドに
広げられた教科書を挟んで彼女と向き合っていた。
僕の教授にいつしか彼女も促されて、復習に取り組む彼女は真剣そのものだった。
一瞬、彼女のその真剣な面差しの先に見えた伏せたまつげに、ときめいた自分を発見して
・・・また・・・驚いた
本当に・・・
何をやってるんだろう・・・僕は・・・
木曜日
僕はいつものようにマサチューセッツへと向かい、その日の夜もほとんど
僕専用になっていた研究室に泊った。
いつものように、コーヒーを淹れて、カップを口に運びながら窓の外を眺めていた。
ふと夜の窓ガラスに映った自分の顔が少し緩んでいることに気がついて可笑しくなった。
まさか・・・
僕は自分の心に生まれた柔らかい何かを懸命に否定していた。
何故ならその時、僕の脳裏をよぎっていたのは彼女が淹れてくれたコーヒーの香りと、
彼女の輝くような笑顔だったからだ。
翌朝、ソフィアが研究室に訪ねて来た。
「おはよう・・・フランク・・・」
「おはよう・・・」
僕はいつものように彼女にキスをした。その直後、彼女がふと僕の顔を覗きこんだ。
「何?・・・」
「いいえ・・何でもないわ・・・」
彼女は先週の講義で僕が出した宿題のレポートを集めて持参していた。
「ここへ・・・置いておくわ・・・お願いします・・・」
「ん」
「・・・フランク・・・」
「ん?」
「今日一緒に・・・帰ろうかな・・・NY・・・」 ソフィアが突然そう言った。
「えっ?」
「冗談よ」 振り向いた僕の顔を見て、彼女は即座に「冗談」と言った。
僕は今・・・どんな顔をしたんだ?・・・ソフィア・・・
「構わないよ・・・一緒に行く?」 僕は平静を意識して彼女に言った。
「止めとくわ・・・」 彼女は即座に笑顔を添えて答えた。
「どうして?」
「どうして?・・・さあ、どうしてかしら・・・」
彼女は自分自身に問いかけるように呟いていた。
そんな彼女のうつむき加減の顔が少し寂しそうに見えたのは、僕の気のせいだっただろうか。
「・・・・・・」
僕はその後、彼女に何も言わなかった。
彼女もまた、何も言葉を続けず「じゃ、また来週ね」そう言って研究室を出て行った。
何が言いたい?・・・
今 僕はあなたに何を?
今日は・・・教えてくれないのか・・・ソフィア・・・
いつも僕の気持ちを誰よりも早く・・・
当の僕自身よりも正確に分析して僕に告げてくれた
そして僕はあなたのその言葉に・・・
黙って目を閉じ・・・手を引かれて生きてきたんだ
あなたの言葉は優しくて・・・時に厳しくて・・・
いつも僕を勇気付けることを忘れなかった
ソフィア・・・僕は今・・・何に揺れている?
どうして・・・何も言ってくれない?
それとも・・・何も言わなかったことが・・・あなたの言葉?
僕は今・・・僕の心は今・・・
何処にあるんだ?・・・ソフィア・・・
創作mirage-儚い夢-8.星降るベッド

この度の事故で、お怪我をなさった方方に
心からお見舞い申し上げます。
一日も早く心身共に回復なさることを祈ります。
皆さんが幸せなひとときを過ごせた、そんなお気持ちのまま
帰国できたなら、と本当に時間を戻して、何事も無かった状態にして
差し上げたい気持ちです。
そして神様にもうひとつ祈ります。
ヨンジュンさんの心をどうかお守り下さい。

いつものことながら、マサチューセッツで過ごす時間は瞬く間に過ぎていく。
週に二日だけ・・・ここでの時間は、僕が緊張を要する仕事から少しだけ解放されて、
損得なしに向き合えるわずかな人々とのわずかな時間。
今の僕にとってはもしかしたらこの場所が唯一の安らぐ場所なのかもしれない。
しかし僕は今そんな時間にさえ、決別を急ごうとしていた。
時々僕は考える・・・
自分が何のために生きているのだろうかと・・・
朝になって・・・
運よく目覚めさえしなければ・・・
この拭いきれない虚しさを味わうことすらないだろうに・・・
でも・・・そんな僕にも・・・朝は必ずやって来た
「帰るの?」 帰り支度をしていた僕を見て、ソフィアが言った。
「ああ」
「来週また、講義お願いしてもいいかしら」
「いいよ・・あなたの頼みなら断れないだろ?」
「そう。光栄だわ、先生」
「来週の初めは少し忙しいんだ」
暗に僕は、NYには来ないで欲しいと彼女に告げていた。
「わかったわ。私も研修に追われるだろうし」
彼女は間を置かずそう答えた。
「そう」
ソフィアとの会話はいつも短く終わる。
それは、それだけで彼女が僕の言葉の意味を瞬時に理解してくれるからだった。
「それじゃ・・また来週」 僕はソフィアの首を片手で引き寄せてキスをした。
「何してる。」
車を走らせNYに戻ると、そこに彼女がいた。
ソ・ジニョン・・・
冷え冷えとした僕の部屋のドアの前で、丸まるように膝を抱え眠り落ちていた。
声を掛けても一向に目を覚ます様子も無く、僕はほとほと呆れ返っていた。
君はいったい・・・何を考えてるんだ・・・
僕が彼女の履いていた靴を少しばかり乱暴に蹴飛ばすと、彼女はやっと目を覚まして
僕を見上げた。
「あっ・・・・お・・お帰りなさい・・・やっと・・・・」
彼女はよろめきながら急いで立ち上がると、僕に向かって苦笑いを浮かべた。
「・・・逢えた」
「やっとって・・まさか・・昨日もここにいたんじゃないよね」
彼女は苦笑いをして、それを認めた。
「あのね。言ったはずだろ!」
「あ、わかってます・・・あんなところで待ち伏せなんかするな!
でしょ?」
彼女は少し眠たげだった顔を満面の笑顔に変えてそう言った。
僕はというと、彼女の腹立たしいほどに輝く笑顔を黙って冷たく睨んでいた。
「だから・・・しなかったわ・・・だって・・ほら・・
ここ・・・・・覚えちゃった・・し・・・」
苦虫つぶしたような僕の前で、彼女は何のてらいもなく、またにっこりと微笑んだ。
「僕に近づくなとも言った。」 僕は無表情に抑揚無くそう言った。
「それは・・・・その・・聞こえなかった」
僕から目を逸らしながら小声で言い訳めいた言い方をする彼女を、
僕は更に睨みつけた。
「うそつけ。」
彼女は知らないふりを装い視線を上にゆらりと逸らせた。
「それに今、何時だと思ってる?子供がうろつける時間か?また・・」
「明日は学校お休みだから・・・」
「だからって・・」
「昨日は2時間位しか待ってる時間無くて・・・結局あなたにも・・逢えなかったし・・・
でも、明日お休みだから、今日は逢えるまで待ってようかなって・・・」
「で・・いつからここに?」
「あ・・んー・・・3時から?・・・」
「5時間も?・・・君ね・・・」
余りに呆れてしまって、その後の言葉が繋げなかった。
「あの!」 突然彼女が声を張り上げた。
「何!」
「寒いです・・・」
彼女が「早く開けろ」と言わんばかりに部屋のドアに視線を流した。
僕は呆れたようなため息を彼女の前で深く強調しながら、ジーンズのポケットから
部屋のキーを取り出した。それでも彼女は僕の迷惑そうな反応をわざと
無視したかのように、鍵穴にキーを挿し込む僕の手だけを見ていた。
「君の図々しさには負けるよ・・いったい何のつもり?」
「何のつもりって・・・私は自分に正直なだけです」
「正直がいいことだと、パパやママから教えられた?」
「ええ。」 そう答えて彼女はまたにっこりと微笑んだ。
僕は彼女に対して、一言一言に皮肉を交じえ冷めた言い方を強調していたが、
彼女には一向にそれが通じている節はなかった。
「通じない振り?」
「何のことですか?」 彼女は僕にきょとんとした表情を返した。
≪それって天然なのか?≫
「・・・・何でもない。」 僕はわざとらしく大きな溜息を吐いて見せた。
僕は部屋に入るなりキッチンへと向かい、コーヒーメーカーに豆を入れて作動させた。
彼女はほんの少しだけ恐縮しているような顔をしながらも、しっかりと僕の後に
続いて部屋に入った。
「で、何の用?」 僕は彼女の顔も見ずにぶっきらぼうにそう言った。
「どちらにお出かけだったんですか?昨日はお泊り?」
彼女は僕の質問を無視して言った。
「質問してるのは僕だ。」
「今度から電話して来るようにします」
「電話番号・・誰が教えると言った?」
「・・・・・・・」 彼女が少しばかり不満げに口を尖らせた。
その表情はきっと彼女のくせなんだろうと思うと、可笑しくてならなかった。
そのあどけなさに僕は思わず噴出しそうになるのを堪え、彼女から顔を背けていた。
「コーヒー・・・飲んだら帰って・・」 僕は淡々と言った。
「あ・・フランク」≪フランク?馴れ馴れしいぞ≫「気安く呼ぶな」
「ねぇ、フランク・・」≪聞いてるのか?≫
「このベッド、こっちに移動した方がいいと思わない?」
彼女は僕の部屋のデッドスペースを指差して明るく、そう言った。
「・・・・・・」
「この前ね、そう思ったの・・・そう思ったら、どうしても早く伝えたくて」
「・・・・・・」
「早速、やってみない?」
にっこり笑ってそう言いながら、彼女はその場に置かれた椅子を動かし始めた。
「勝手なことをするな。」
「だって、こっちにベッドがあると、寝ながら星が見えるわ」
「そうしない理由がある」
「何故?」
「・・動線が悪くなる」
「だって、ここ、仕事部屋と言ってもベッドがあるということは
お仕事のお客様が見えることはないんでしょ?」
「・・・・・・」
「だったら、絶対こうするべきよ!ねっ!そうしましょ!」
彼女は口と一緒に素早く手も動かしていて、話し終わる頃には、その場所にあった
小さな椅子やテーブルが別の場所に移動されていた。
「フランク・・手を貸して・・頭の方・・」
さすがにベッドはひとりで動かせないらしく彼女はそう言いながら、シングルベッドの後ろに
手を掛けて僕に目で指示した。
そんな彼女を僕は何故か怒る気にもなれず、彼女のしたいように手を貸した。
「うん、これでいいわ・・・」
彼女は移動したベッドを前に腕組して満足げに微笑んだ。
「気が済んだ?」 僕は呆れ顔で彼女を見下ろした。
「フランク・・どうして、最初からこうしなかったの?」
その時僕は彼女にベランダに出るドアを指差した。
「あ・・・」
そして半分しか開けられなくなったドアを開けて見せた。
「あ・・・・・でも・・これって・・何とか人・・一人・・・
出れ・・そう?・・ね・・」
彼女が申し訳なさそうに僕を見上げながら自分の鼻筋を指で掻いていた。
その仕草もどうも、彼女が恥ずかしさを照れ隠しする時の癖らしい。
≪可愛い・・・≫
そう心の中で思ってしまった自分が急に可笑しくなって、声を立てて笑ってしまった。
彼女はベッドを動かしたことを呆れられたと思ったらしく、更に申し訳なさそうな顔をした。
「あの・・ごめんなさい・・・元に・・」
「いいよ・・これで・・・僕も本当はこうしたかった」
「本当に?」
「ああ」
彼女は僕のその言葉に、輝かんばかりの笑みを向けた。
僕は彼女が僕に向けてくれたその微笑が本当にまぶしくて、彼女をまっすぐに
見ていられないほどだった。
「コーヒー・・・どうぞ」
僕はなんとも中途半端な場所に移動されてしまったテーブルに、ひとつのカップを置いて、
それを彼女に勧めたが彼女は一向にコーヒーに手を付けようとはしなかった。
「どうしたの?寒かったんでしょ?体温まるよ」
「・・・・いらない」 彼女は俯いたまま言った。
「・・・・・・?」
「だって・・そのコーヒー飲んでしまったら・・・帰らなきゃいけないんでしょ?」
僕が手早く入れたコーヒーの理由に反発して彼女がそう言った。
僕はまた心の中で笑ってしまった。「いいから・・飲んで。」
僕が少しばかり強引に勧めると、彼女はしぶしぶカップに手を添えた。
「君・・・可笑しな子だね」
「・・・・・・」
「僕のベッドをあそこに移動したくて、あんな寒い中僕を待ってたわけ?」
「そうじゃないわ・・」
「だったら・・・何?」
「あなたに逢いたかったから」 彼女は率直にそう言った。
「ふ~ん・・・で、逢ってどうするの?」
「どうするって・・・
好きな人に逢いたいと思うのは自然なことでしょ?」
「僕を好きなの?」
「あなたが・・私の気持ちを恋だと言ったわ」
「僕が言った君の気持ち?・・・じゃあ、君がこうしてるのは僕のせいなんだ」
僕の言い方は彼女に対して、かなり意地悪だった。
「・・・そうじゃないけど」
「まだ世の中のこと何も知らない・・お嬢さん?僕はね・・・
君みたいなお嬢さんのお遊びに関わってる暇なんて無いんだ」
「お遊びって・・・そんな・・ひどいわ」
「とにかく。・・・もう一度言うよ・・・僕に・・近づくな。」
僕は彼女の鼻先に指が付かんばかりに近づけて、念を押すようにゆっくりと言った。
「どうして?」 しかし彼女は脅しのような僕の言い方に動じる様子は無かった。
「だから・・僕にはそんな暇が・・」
「どうして?」 彼女が僕に詰め寄るような目で「どうして」と繰り返し訴えた。
僕は少し彼女に圧倒されて後ずさっていた。
そして彼女の大きな瞳がみるみる涙で潤んで、彼女はそれを一生懸命落とさないように
堪えているようだった。
「ねぇ、どうして?・・・子供の・・私に・・・ちゃんとわかるように説明して・・・
あなたのことを想うと胸が苦しくなる・・・だから、あなたに逢いたくなる・・・
こうして・・そばにいたくなる・・あなたが私のことを・・・本当に嫌いなら・・・
仕方ないわ・・でも・・」
「でも?・・僕も・・君のことを好きだと?」≪冗談言うな≫
「・・・・・・」
「随分なうぬぼれ屋さんだね・・・君は僕の心がわかるの?」
僕は彼女の顔を呆れたように睨みつけた。
「そういうわけじゃないわ・・・でも・・・」
「また・・でも?」
「感じるの・・・」
「感じる?何を?・・・」
「わからない・・・」
「得意の・・わからない・・か・・・」
僕は彼女に向かって馬鹿にしたような薄笑いを浮かべた。
「・・・・・・・」
彼女はそんな僕に対して、睨み付けるような挑戦的な瞳を向けていた。
何なんだいったい!・・僕は君に・・・
そんな目で睨まれる筋合いは無い
「僕はね・・・ここで仕事もしてる・・・」
「知ってるわ、邪魔はしない」
「それに恋人だって訪ねてくる。迷惑だとは思わない?」
僕は彼女に止めを刺したつもりだった。
君に・・・意味もなく心を乱されるなんてごめんだ
頼むから僕に関わりあうな!
僕は心の中でそう叫んでいた。
彼女と出会ってからというもの何かが可笑しくなっていた自分に、今ここで
軌道修正を図りたかった。
「恋・・・人・・・」 彼女は確認するように呟いた。
僕が口にした「恋人」という響きを前に、彼女の落胆が目に見えた。
「そう、僕には恋人がいる。」 僕は自分で口にしておきながら、少し後悔していた。
肩を落とし視線を伏せた彼女の様子に、自分の胸がちくりと刺されたような痛みさえ覚えていた。
あ・・そんな顔・・・するな・・・
僕は彼女の視線から逃れるように背中を向け、彼女が移動してしまったベッドを見た。
「あ、そうだ・・星・・・せっかくベッド動かしたんだから・・・
寝転がって見てみな。」 そして僕はつい、そう言ってしまった。
「・・・・・・・」
「ほら・・・おいで」 僕は彼女に振り向き、その手をとってベッドに座らせた。
しかし彼女は下を向いたまま天空を仰ごうとはしなかった。
僕はそんな彼女をほったらかして、ベッドに寝転がってみせた。
「 あぁー・・・綺麗だ・・・何て綺麗なんだ
何でもっと早くこうしなかったんだろうな~」
彼女は僕の言葉に促されたようにちらりと天井に視線を向け、直ぐにまた下を向いた。
「・・・・・・・」
「寒くなると、星が際立って見える・・・だから・・・冬が好きなんだ」 僕はそう言った。
「あ・・・私も・・・」
彼女は僕の言葉に釣られるように答え、やっと僕に振り向いて目を輝かせた。
「そう?寒いの、強そうだしね」
「また・・皮肉ですか?」
「皮肉・・通じてるんだ」
「・・・・・・」
「褒めてるんだよ・・・あんなとこで5時間も座ってたら
普通は具合悪くなるよ」
「若いから」
「はは・・・君って・・本当に・・・」
「本当に?」
「いや、何でもない」
「言いかけるのはルール違反だわ・・・私って・・・
“可笑しい”・・そう言いたいんでしょ?」
「いや・・・」
「じゃあ、何?」
「何って・・・・んーわかりません。」
「あっ!私の真似した!」
彼女が寝転がっている僕の胸を叩いた。
「ウッ・・」 僕は彼女が叩いた胸を抱え込むように背を丸めた。
「あ・・ごめんなさい」
彼女がベッドに上がり、申し訳なさそうに僕の様子を覗き込んだ。
「嘘だよ」
「えー!」
あろうことかこうして僕は彼女を相手に戯れていた。
人と戯れることなど・・・
幼い頃の記憶にさえない
しかし彼女のあどけない仕草に、何故か遠く何処かで味わったことがある懐かしさを
垣間見て、僕の心は間違いなく和んでいた。
気分・・・少しは良くなったかい?
あまりにしょげている君を見ているのがちょっと辛かった
こんな気持ち・・・今までに一度も味わったことないや
自分の浴びせる言葉で他人が傷ついたところで気にしたことすら無い・・・
でも今僕の心は・・・君が・・僕のひと言に傷ついたことにひどく萎えてしまった・・・
それは・・・何なんだろう・・・
わからなかった。しかし僕の、色もなく、揺れるざわめきもない心の海に、確かに彼女が
小さな石を投げ入れたように波紋を広げていた。
僕はこの世に存在する全てに愛着がない
見るもの全てに・・・感動も無い・・・
たとえ・・・
世の中がたった今消え去ったとしても・・・
一分の悔いすら存在しない・・・
そう思っていた・・・
それなのに・・・
君のそのくったくのない笑顔に・・
僕の心が
戸惑いながらも頬ずりをしていた
今僕は・・・
君に何を見ているのだろう・・・
本当に・・・
・・・わからないんだ・・・
創作mirage-儚い夢-7.追いかける者

結局彼女は帰らなかった。
あろうことか、この僕が“泊まっていってもいい”と言ってしまったのだから、
笑ってしまう。
仕方ないという顔をして僕は彼女に向かって、ひとつしかないベッドを指差した。
しかし彼女は「私はここで」と小さなソファーに、遠慮がちに腰掛けた。
僕も彼女に対してそんな義理もないだろうと、敢えてしつこくは勧めなかった。
しかし夜中に何かしらの重苦しさに目が覚めると、いつの間にか彼女が
僕のベッドに潜り込んでいて、図々しくも僕の腕を枕代わりにしていた。
きっと眠くなった時、椅子に座っているのが疲れでもしたのだろう。
それにしても・・・
僕はすっかり呆れ果ててしまったが、それでも僕は彼女をベッドから追い払うことを
しなかった。
それよりも彼女の怖いもの知らず、というか、僕を甘く見ているというか、
僕はまたまた笑ってしまった。
彼女と会ってからというもの、僕はこうして何度笑っているだろう。
ともかく彼女のお陰で眠れなくなってしまった僕を他所に、彼女は僕の傍らで
ぐっすりと眠り込んでいた。
≪まったく・・・≫
見覚えのある彼女の寝顔がまた僕の目の前にあった。
その時僕はつい衝動に駆られて、彼女の顔に落ちた黒髪を指でかきあげた。
そして僕の鼻先に彼女の伏せた長いまつげが現れると、僕は吸い寄せられるように
そのまつげに唇を寄せた。
≪もう少しだけ・・・こうしていたい・・・≫
彼女に対して、疎ましく思う気持ちとは裏腹に、もうひとつの僕の心が
彼女がまだ目覚めないことを望んでいるようだった。
≪いや・・そんなはず・・あるものか≫
突然、彼女の無垢な寝顔が無性に腹立たしくなってきた僕は、彼女の首の下に
なってしまって少し血流が悪くなっていた自分の腕を、彼女の頭がガクンとシーツに
落ちるようにわざと乱暴に外すと、おもむろにベッドから降りた。
それでも彼女は一向に眠りから覚めることはなかった。
≪・・ったく・・・いったい何なんだ・・君は・・・≫
僕は彼女の代わりにソファーに腰掛け、意図も簡単に僕の心を掻き乱してしまった
彼女の寝顔を、その場所からただ黙って見つめていた。
「君・・・君・・」
夜明けを迎えて僕は彼女の肩をゆすったが、彼女はピクリともしなかった。
「君!・・・起きなさい!」
「・・・ん?・・・うん・・・もう少し・・・」 彼女は眠そうに寝返りを打った。
「始発の時間だよ、電車・・・学校あるんだろ?」
「あっ!・・・」
彼女は慌ててベッドから飛び起きると、まず、自分の置かれた状況を把握しようと、
周りを見渡して、それから最後に僕を見た。
「あ・・・泊めて・・もらった・・んでした・・よね・・」
彼女は頭の中の混乱をまとめるように言った。
僕は頷いた 「ベッドを貸した覚えはないけど」
「あ・・ごめんなさい・・ちょっとだけ・・横になったつもり・・だったのに
あの・・ごめんなさい!」 彼女はしどろもどろだった。
「いいから・・顔洗っておいで・・コーヒーくらいなら入れてあげる」
僕はシャワー室を指差しながら彼女にそう言った。
「あ、大丈夫です・・寮に一度戻りたいし・・・このまま失礼します・・・」
彼女は手荷物を慌しくまとめると、僕に急いで一礼してドアへと向かった。
「あ・・君!・・・」
慌てて帰ろうとする彼女の後姿に僕が思わず声を掛けると、彼女は勢いよく僕に
振り返った。
そして「あの!」と言った。
彼女の勢い余った表情に僕は少しばかり後ずさってしまった。「な・・何・・」
「あの・・“君”・・じゃなく・・・ジ・・ニョ・・ン・・です!」
彼女は僕に向かって、自分の名前を大きな口を開けて、区切って発音した。
「・・・・・・」
彼女は至って真顔だった。そしてそれだけを言うと、そのままバタバタと部屋を
出て行った。
「・・・・・・」
突然彼女がいなくなった部屋で僕はしばらくあっけにとられていた。
何・・なんだ?
嵐のように僕の前に現れて・・・
また嵐のように去っていった
僕は誰に向かうでもなく、玄関のドアを見つめたまま小さく笑った。
私はフランクのアパートを急いで出ると始発の電車に飛び乗り、一旦寮に戻った。
そしてシャワーを浴び着替えを済ませると、急いで寮と隣接している学校に向かった。
すると案の定、ジョルジュが正門で私を待ち構えていた。
彼を見つけて私は思わず顔を背けた。
「ジニョン!」
当然、彼の尋問を受けずにここを通り抜けることは不可能だということもわかっていた。
「お前!昨日何処行ってた!寮に何度も電話入れたんだぞ!
あそこは遅い時間は電話の取次ぎもしてくれないんだ
門限の9時に掛けた時もまだ帰ってなかったし
あろうことか、お前から友達のところに泊まるという
連絡が入ったって・・寮長から聞いたぞ!」
「おしゃべりね」 私はおしゃべりな寮長の顔を思い浮かべながら呟いた。
「おい!待て、ジニョン・・・いったい、どういうことだ!」
「その通りよ、友達のところに泊まったの。」
「友達って?誰だ。」
「誰でもいいじゃない・・オッパが知らない人!私だって・・
もうこっちへ来て2ヶ月は経ったのよ、泊めてくれる友達くらい出来たわ
何もかもオッパに報告しなきゃいけないの?」
「ああ・・駄目だね・・俺にはお前に責任がある。
おじさんと約束してるんだ・・お前を必ず守るってな。」
「もう!私のこと子供扱いしないで!」 私は思わず怒鳴っていた。
子供扱いしないで!
私は心の中でジョルジュじゃない誰かに対してそう叫んでいた。
「だから、誰のとこだと言ってるだろ?」 ジョルジュも引かなかった。
「オッパ!しつこい!」 自分の後ろめたさが、彼に対して強い反抗をみせた。
私は誰かに怒っていた。
そしてその誰かが自分の心を捉えて離さないことにも苛立っていた。
「ジニョン!」
結局ジニョンは昨夜、誰のところに泊ったのか決して言おうとはしなかった。
俺に言えない奴のとこか?・・・
昨日俺がどれほど心配したと思ってるんだ
その時、考えたくないことが俺の心を支配していた。一人の男の顔が脳裏を
過ぎって俺の不安を煽った。
まさかな・・・
俺は慌てて、信じたくない予感を頭から振り消した。
「フランク!おはよう!」
「Hi!ミル」
「フランク~久しぶり~会いたかった~」
「Hi・・サラ・・久しぶり」
「フランク!NYはもう慣れた?」
「やあ、スージー、まあまあさ」
「ねぇ、今度NYのお部屋に遊びに行ってもいい?」
「駄目。」
「冷たいのね・・相変わらず。」
僕は一週間ぶりのキャンパスを、生徒達が進む校舎とは反対の建物に向かって
急ぎ足で進んでいた。
そして自分専用の研究室のドアを開けると、そこには当然のように僕の到着を
待っている人がいた。
「やあ・・ソフィア・・モーニン・・」
「・・・・フランク君・・・君はここへ上がって来るまでに
いったい何人の女とキスを交わしたかしら?」
ソフィアが窓の外に視線を流しながらそう言って、僕を優しく睨んだ。
「見てたの?・・・でも・・・こんなキスはしなかった・・・」
僕は彼女が座っていた机に手を付いて、頭を斜めに屈めると、
彼女に挨拶以上のキスをした。
「・・・・・フランク」
「ん?」
「何かいいことでもあった?」
「別に?どうして?」
「ん~何となく・・・唇が優しい・・かな・・」
「そう?いつも優しいだろ?」
「そうね・・・」 ソフィアが何となく思わせぶりな笑みを浮かべた。
いいこと?・・・別に何もないさ・・・
「ところで・・・ご用とは?」
前日にソフィアから頼みたいことがあると聞かされていた。
「ええ、午前中に弁護シミュレーションを予定してるの・・・
そのインストラクションをあなたにお願いしたくて」
「そんなこと、教授に頼めば?」
「その教授があなたに依頼しろとおっしゃったの」
「ハッ・・・面倒なことは何でも僕に回す気だな」
「いいじゃない・・・たまには・・・」
大学院の課程もほぼ終了に近くなったこの頃には、僕は担当教授の助手まがいの
ことを引き受けるようになっていた。
「中には僕に教授されたくない奴だっているだろうに」
「それがそうでもないわ・・・
多くの生徒は、教授よりあなたの方が実力は上だと思ってる」
「あなたもそのひとり?」 僕は彼女の座った椅子を回転させて、僕に振り向かせた。
「ええ・・惚れ込んでるわ・・・先生・・・」
そして唇を彼女の首筋に這わせ、掌をスカートから伸びた白い足の膝頭から
次第に上に向かって進入させた。
「そんな暇ないんだよね・・・僕・・・」
そんな僕のお遊びにも彼女は一向に怯むことはない。表情のひとつも変えず
僕をあしらおうとする彼女の凛とした顔も・・・僕は好きだった。
「先生・・・電話・・・ですよ」 ソフィアが僕から顔を後ろへ引いて言った。
もう少しで彼女に届くところを無粋な誰かが邪魔をした。
僕はポケットから携帯電話を出して着信画面を見た。
レオナルド・パクからだった
僕は電話を耳と肩ではさみソフィアに目で合図をしながら手を差し出し、
小声で言った。
「 ・・・資料・・見せて
Hello・・やあ、レオ・・ああ、僕だ・・・届いた資料見てくれたか」
僕はレオからの電話を受けながら、ソフィアからの資料に目を通していた。
『ボス・・・この資料の中のどれをやるんだ?』
レオは僕から送られた資料を見ているようだった。
「All・・」 僕はひと言だけ言った。
『All?』 レオは僕の言葉を怪訝そうに繰り返した。
「Yes。」 僕は当然だと言わんばかりに言った。
『ここには期間が三ヶ月となってるが・・・』
「長過ぎるか?」
『おい、お前・・思ってたほど賢くないな・・・これだけの案件を
どうやって三ヶ月でこなすつもりだ』 レオの声は呆れ返っていた。
「それはお前が考えることじゃない。
お前は弁護士としての仕事をこなしてくれればいい
資料三枚目のリストにある会社の株の市場調査も頼めるか」
『あぁ、それは容易いが・・しかし・・』
「fifty-fifty・・だったよな・・・
三ヶ月でそれだけのことを僕がやってのけたら・・・
以後、僕の専任となる価値はないか?」 当然僕にはハッタリのつもりはない。
『価値?・・・・・・無いわけは・・ないな・・・』
レオが電話の向こうで少し考えて、そう言った。
今からの三ヶ月は僕のこの業界でのデビュー戦だ。「だったら・・見てろ」
僕はそれだけ言うと、レオからの電話を切った。
そして、それと同時にさっきソフィアに渡された資料を彼女に返した。
「赤で書き換えてるところ、至急直して・・・コピーを人数分用意して・・
一時間後に第3教室で・・・」 僕はソフィアに早口にそう言った。
「フランク・・・」
「ん?」
「あなたの頭の中・・・一度・・見せてくれない?
別の用件で会話しながら、よくこれだけのことを・・・」
ソフィアが僕に返された資料を一枚一枚捲りながら、溜息混じりにそう言った。
「いいよ・・・条件があるけど」
「何?」
「授業が終わったら・・・ひとり、そこに残ること。第三教室で・・」
「・・・・・?」
僕は澄ました顔で彼女の耳に唇を寄せた。「さっきの・・・続き・・・」
「バカ・・・」
僕は今、新しいものに向かって着実に進んでいた。
それが例え自分には見えない何かであっても・・・
僕は・・・ただ・・・
・・・追いかけるだけだ・・・
創作mirage-儚い夢-6.泣かないで

彼女の滑らかな黒髪にくちづけをして、僕はその額に自分の額を押し当てたまま
しばらく動かなかった。
≪いや・・・動けなかった・・・≫
僕たちはすぐそばにあった互いの熱い吐息の中に、まるで・・・
互いの存在そのものを確認しあってでもいるようだった。
僕たちは今・・・何処にいるんだろう・・・
何処に向かおうとしているんだろう・・・
「 私・・・もう震えていません・・・ 」
彼女が自分自身に言い聞かせているかのように小さな声で呟きながら
今僕との接点となっている額を僕からゆっくり離した。
「私・・子供でもありません。」 そして今度は僕をしっかり見つめてそう言った。
「だから?」 僕はその答えを知っていながら、敢えて確認するように聞いた。
「だから・・・あなたの・・・したいように・・・」 彼女は途切れ途切れながらも
精一杯に想いを僕に伝えようとしていた。
「僕のしたいように?」
「・・・・・・」
“あなたのしたいように”彼女はそう言ったきり、無言で僕を睨みつけていた。
君にとって・・・セックスという行為が・・・
相手をそんなにも睨み付けなければならないほど深刻な行為ならば・・・
そんなことを考えていると、急に可笑しくなって僕は声を立てて笑ってしまった。
彼女の眼が“何が可笑しいのか”と、また僕を睨みつけた。
すかさず僕は彼女のその固い視線から逃れてベッドを降りると、
自分の洗いざらしのシャツを手にとって彼女に差し出した。
「これ、着て」
「あの・・・私・・・」
彼女はたった今、自分が下したはずの決心を簡単に交わされてしまったようで、
拍子抜けしたような顔をしていた。
「何?」
「私・・と・・その・・・」
「セックス・・・したくないのか?」
彼女が僕に言おうとしていることを、代わりに僕が言葉にした。しかし彼女は
僕のその言葉に赤面して、また黙り込みうつむいた。
「したくない。」 僕は彼女に向かって無機質にそう言い放った。
僕の冷たい言葉にショックを受けたかのように彼女の表情は一瞬硬直し、
その時、自分の胸を押さえていたブランケットを落としてしまった。
わかっているかい?僕は君をからかっているわけじゃない
それなのに僕のひとことひとことに過剰に反応する君に
僕の方が困惑してしまう
日頃、他人の言動に一片の関心をも示さないこの僕が、彼女の一挙手一投足に
妙に囚われてしまっている。
僕はそんな自分に驚いていた。
「いいから、着て?送っていくから」
僕は煙草を一本シュガーケースから取り出しながら彼女に言った。
彼女はまだ黙り込んでいた。「どうしたの?」
「今からじゃ・・帰れないわ・・電車もないし・・寮は門が閉まってて入れない」
彼女は不満そうな顔をして、それでもしぶしぶシャツに腕を通していた。
そんな不満そうな顔をして・・・
本当はホッとしたんじゃないの?
僕は彼女に視線を送りながら、ため息混じりに心の中でまた笑っていた。
しかし本当は、彼女がさっき垣間見せた怯えたような眼を、この僕が見たくなかった
だけだった。この僕が彼女の肢体を解けなかっただけだった。
それが事実・・・ホッとしたのはきっと・・・
この僕の方なのかもしれない
彼女がのらりくらりとシャツを着ているそばで、僕は窓際の椅子に腰をかけ、
くわえた煙草に火をつけた。そして深く煙を吸い込み、大きなため息と一緒に
白い煙を外へと吐き出した。
さっきから僕の動きをただ目で追っているだけの彼女に、僕は無言で手招きをして
低い天井を指差した。
そこは立ち上がると頭が閊えそうなほどの高さで、この部屋のデッドスペースにも
なっていたが、天井には斜めに切り立った屋根を生かして大きな窓が設えてあり、
部屋の中から天空を仰ぎ見ることができる恰好の場所だった。
この場所が僕の一番のお気に入りだった。
彼女は腰をかがめて僕に近づくと隣に腰掛けて、僕をまね天井を見上げた。
「わぁ~綺麗・・・」
「だろ?ここは屋根裏だからね・・・部屋の中からでも夜空がよく見えるんだ」
「素敵だわ・・・あれは、きっと・・・カシオペア座ね・・・あれは・・・シリウス・・・
それから、あれは・・・」 無邪気に喜ぶ彼女の顔が更に幼さを増していた。
「星、詳しいんだね」 僕は驚いた表情を作って見せた。
「いいえ・・オッパが・・ジョルジュが凄く詳しいの・・小さいときから
私を相手によく解説してくれてたから」
「仲がいいんだ」 気のせいか僕は自分の心が少しだけ萎んだように感じた。
「ええ、家が隣同士で、家族同然でしたから」
「・・・・ねぇ・・・どうして・・・僕なの?」 僕は知りたかった。
「えっ?」
「あの日・・僕と君は偶然に出逢った。きっと、ただそれだけのことだったはずだ
それなのにどうして君はあの日、あんなにも・・・僕を信用できたの?
どうしてあの後・・あんな風に僕を必死に探した?
あんなことまでして・・・どうして・・
どうして、今君は・・・ここで・・こうしてるの?」
僕は本当に不思議で仕方なかった。
「・・・それは・・・わか・・」
「わかりません。・・だったね。」 僕が彼女の口真似を彼女の声に重ねたことに、
彼女は「くすっ」と笑って僕を見上げ、続けて言った。
「あなたの目が・・・とても澄んでいて・・・」
「それも・・聞いた・・・」 僕はまたも苦笑しながら彼女の邪魔をした。
「でも・・・それしか言いようがないわ・・・だって・・そうなんだから」
彼女はムッと口を尖らせながらそう言うと、小さな溜息をついた。
「君って・・・本当に危なっかしい子だね・・・」
僕は彼女のそんな幼いとしか言えない行いに思わず笑いを堪えながら言った。
「ジョルジュにもそう言われました・・・危ない奴だって。でも私・・
誰もかれもを信用するわけじゃないです・・・強いて言えば、
私は自分の勘を信じているだけ。」
彼女は姿勢を正して自信たっぷりにそう言った。
「勘?・・君・・いったいいくつ?」
「18・・」 さっきの自信が少しだけ小さくなった。
「18年生きて来て・・今までにいったい幾つの・・その勘とやらが当たった?
それにね、例え、今までの勘がすべて当たっていたとして・・・
今回は残念ながら・・・ひとつも当たってないよ」 僕は少し意地悪く言った。
「・・・・・・」
「僕は決していい人間じゃないし、君が言うような綺麗な目もしてない・・・多分ね
それに・・・世の中には君の思うような人間ばかりじゃないんだ・・・
君があの時無事だったことだって、運が良かったと思った方が利口だ」
「・・・・・・」
「・・・・・しかし・・・今日はもう遅いし・・君が言うように寮の門が
閉まってるんじゃ仕方ないね・・・仕方ないから泊まっていくといい・・・
でも言っておくけど・・・もうあんなところで待ち伏せしたりするんじゃないよ。
君はあそこの怖さを知らな過ぎる・・・それから・・・
二度と。・・・僕に近づくな。・・・わかった?」
僕は彼女の目を見て、言い聞かせるように静かに淡々と、そして最後の言葉は
かなり強調して言った。
僕の言葉に、彼女はただ大きな瞳で瞬きもせず僕を見つめ、無言だった。
「わかった?」 そんな彼女の顔を覗きこんで、僕は再度彼女の返事を強要した。
しかし返事は返って来なかった。
彼女は僕の言葉を聞いた後、寂しそうに目を伏せて黙ったままずっと自分の足元を
見つめていた。しんみりとうなだれたままの彼女を見ているだけで、僕は思わず
自分の言葉を撤回しそうになった。
そんな自分を奮い立たせるかのように、僕は勢い良く立ち上がりベランダに通じる
細いドアから外へ出ると、部屋の中の彼女に手招きをした。「出ておいで・・・」
彼女は僕に言われるままベランダに出て来た。
「見て・・・」 僕は下に広がる摩天楼を指して言った。
「綺麗・・・」 彼女は前方に広がるその夜景を眺めて呟きをもらした。
「綺麗?本当にそうだと思う?・・・
あの灯りの窓の奥では、男たちが金の取り分でもめて、
殺し合いをしてるかもしれないよ・・・
あの窓の奥では男が出した別れ話に女が泣き叫んでるかも・・・
あっちの灯りは子供が、母親が帰って来なくて眠れずに・・・
泣きながら母親を探してるのかも・・・
でも・・・遠くから見ている君には・・・ただ綺麗に見える・・・」
「あなたには・・・綺麗に見えないの?」
僕の言葉に対して、彼女は不思議そうな顔でそう言った。
「ただの景色だ。」 僕はそう答えた。
「あの灯りの窓の奥では・・・
仕事に成功した男たちが祝杯あげてるかも・・・
男と女が・・・愛し合った後・・・ふたりでワインを傾けてるかも・・・」
彼女はさっき僕が言った言葉を、ポジティブに解釈して、そう言った。
「愛し合う?それがどんなことかも知らないくせに。」
僕が茶化すように口を挟むと、彼女はまた得意の口を尖らせて見せて話を続けた。
「あそこの窓の向こうでは・・・
怖い夢を見た子供に母親が優しい声で絵本を読んで聞かせてるかも・・・」
「それは君の願望かな?」
「あなたは意地悪なのね」
「フッ・・どうしたら・・・そんな風に何でもいいように考えられる?」
「どうしたら・・・そんな風に悪く考えられる?」
今度は彼女が僕の目をまっすぐに見つめて僕の心に問うた。
その時の彼女の顔は決して18歳の子供ではなく、僕よりも遥かに大人に見えた。
「・・・・・・」
「人は確かにいい人ばかりじゃない・・・
そんなこと・・・子供の・・私にだってわかります・・・でも・・・」
彼女は僕に子ども扱いされてることに抵抗しているかのように、自分で《子供》を
強調して言った。
「君に!何がわかる」
僕は彼女の言葉の続きを強い口調で遮ってしまってから少し後悔した。
「・・・・君には・・・何も・・わからないよ・・・・」
僕は小さく呟きながら彼女から視線を天空へと移した。
「フランク・・・・」 彼女は僕をそう呼んだ。
「・・・・・・」
「フランク・・・・・泣かないで・・・」 彼女が突然僕の頬に掌を当ててそう言った。
僕は泣いてなどいなかった。なのに、彼女は何故か至って真剣に僕を慰めていた。
そして、僕の頬を優しく撫でて、僕の唇の端にそっとくちづけた。
僕が彼女の行為に驚いて彼女の方を振り向くと、彼女はまるで聖母のような
柔らかい微笑で僕を見つめていた。
その時僕はその微笑を真直ぐに見てはいられなかった。
僕が思わず彼女から顔を背けかけた時彼女は、もう一度、僕の唇に自分の唇を
静かに重ねた。
僕は決して泣いてなど・・・いなかった・・・
それなのに君は・・・
どうして・・・僕の心が・・・
・・・わかるんだ・・・
創作mirage-儚い夢-5.泥棒

「 見つけた! 」
背後からの大きな声に驚いて僕が振り返ると、サングラスを掛け、帽子を目深に
かぶった妖しい風体の奴が、僕に向かって走り迫るのが見えた。
≪何?・・僕?・・≫ 体の特徴からそれは女のようだった。
僕は何処かのいかれた女だろうと思い、それを無視して前進を続けていた。
「 待って! 」 その声はやはり僕に向かっていた。
そして必死に追いかけて来る女に、僕はつまらない面倒に巻き込まれるのを
避けようと、今度は少し急ぎ足で進んだ。
「 待って!・・・誰か!その人を捕まえて!
泥棒!その人泥棒です! 」 女が突然、群衆の中で甲高い声を上げた。
「な・・!」≪何!≫
僕は思い当たることこそ無かったが、咄嗟にそれから逃れるように走り出していた。
しかし人の通りが激しいこの時間帯に、思うように前に進めないでいた僕を、そこを
たまたま通り掛かった図体の大きいおせっかい野郎が、突然僕を羽交い絞めにして
僕の前進を食い止めた。
「 離せ! 」 僕は必死にもがいて、大男の太い腕から逃れようと試みたが、
奴の余りの馬鹿力を前に、僕の足掻きは徒労に終わった。
「泥棒って、こいつかい?お嬢さん・・」 大男は羽交い絞めにした僕をまるで
その女に差し出すかのように、大きな声を張り上げ、得意げに言った。
そして走って来た女はやっと僕に追いついて、息咳きりながら僕の目の前で
立ち止まった。
「はっ・・はっ・・あ、・・あり・・がとう・・・」
「ポリスマン・・呼ぶかい?」大男は言った。≪呼んでみろ、ただじゃ置かない≫
「 離せ!この野郎!・・君!どういうつもりだ!
僕が君の何を!何を盗んだと言うんだ! 」
少々の相手なら難なく倒せる自信があったはずの、さすがの僕もこんな大男に
突然羽交い絞めされたら簡単に身動きが取れるもんじゃない。
「いいえ・・大丈夫。・・離してあげてください・・私の・・勘違いでした・・」
まだ息が上がっていた彼女は言葉を切りながら、大男に言った。
「しかし」 大男はまたも力を加えた 「痛い!」僕は奴を睨み付けた。
「本当にごめんなさい・・私の勘違いなんです
お願い・・離してあげて・・」
大男は女の言葉にやっと僕の腕を離し、怪訝そうに首をかしげながら
渋々その場を立ち去った。
≪冗談じゃないぞ!≫ 僕は男を睨んだその目を彼女へと移した。
「 君ね!勘違いって! 」 僕は突然自由になった腕の調子を確認しながら、
彼女に憤慨して言った。
「勘違いじゃないわ」 彼女はそう言った。
「えっ?」
「勘違いじゃない・・・あなたは泥棒。」 今度ははっきりとした口調で重ねて言った。
「まだそんなことを!だったら言ってみろよ
僕がいつ・・君の何を盗んだ! 」 僕もいい加減頭に来ていた。
例え相手が女・子供であろうが、許せないこともある。僕はそう思いながら、
一歩彼女に詰め寄った。
その時、女は自分がつけていた帽子とサングラスを両の手で同時に取ると、
帽子の中からすべり落ちて来た長い黒髪を頭を軽く振って自分の肩に落とした。
「・・・君・・は・・」 あの時の・・・彼女だった。確か名前は・・・ジニョン?
・・・ソ・ジニョン・・・
「君は・・・あの時の・・・」 僕はしばし驚きで立ち尽くしていた。
「唇・・・」 彼女は小さな声で呟いた。
「えっ?」 僕は聞こえなかったので、聞き返すように言った。
「私の唇を・・・盗んだ。」 彼女は今度は少し声を張って言った。
ところが彼女は自分でそう言いながら、自分の言葉に赤面したかのように俯き黙った。
僕の目の前で、瞬時に真っ赤になってしまった彼女の頬はなかなか冷めては
くれないようだった。
「彼に聞いたの?」 僕はあの時のことを知っているだろう男のことを思い描いた。
「彼?・・・彼って・・・ジョルジュのこと?・・・
オッパ・・知ってたの?」 そしてまた彼女は更に赤くなった。
≪彼は言わなかったのか・・・≫「それじゃあ・・」≪どうして?≫
「あの時は夢だと思ってた・・・でも・・・夢にしては・・・あまりに。
その・・リアル・・すぎて・・・・・」 そう言ってまた、彼女は俯いた。
「寝た振りしてたってこと?」
「そうじゃないわ!・・・」 彼女は僕に向かって一度強く否定するとまた俯いて声を
弱めた。「・・・でも・・夢なのか、現実なのか・・わかってなかった・・」
「それで?」
「それでって?」
「泥棒・・なんだろ?」
「あれは・・・あなたが逃げるから」
「僕に文句を言いたくて、待ち伏せを?・・・しかもそんなかっこ・・・」
「そうじゃないわ・・・それにこれは・・・この前みたいな目に遭わないように・・
男の子みたいなかっこを・・・」
「ハッ・・・・余計目立つよ・・」 僕は吐き捨てるように言った。
「・・・・!」 彼女はやっと顔を上げてムッと口を尖らせた。
「僕を泥棒呼ばわりまでして・・何か言いたかったんでしょ?僕に」
「何って・・・・」
「じれったいな・・文句がないなら、行くよ。」
僕は彼女を置いてその場を立ち去ろうとした。
「待って!どうして!」 彼女があの時と同じように僕の袖を引いて僕を止めた。
「何!」
「どうしてあんなことを?」
「あんなこと?・・・どうして、君にキスしたかってこと?」
君は何度僕の前でうつむけば気が済むの?
君が僕に聞いてるんでしょ?・・・
「聞いてどうするの?・・・意味が必要?」
「必要・・って・・・」
「意味なんてそんなものあるかな・・・ああ・・強いて言えば・・・
僕が至って健康な男だということ?
腕の中で無防備に眠ってる女がいればキスもしたくなる・・・それじゃ駄目?」
「それだけ?」
「それだけって?」
「私に・・・私にその・・気持ち・・ありませんでしたか?」
「ないよ・・そんなもの・・・」
「本当に?」
「何が言いたいの?」
終始僕が突き放したように話していることに、彼女はしょんぼりとうなだれて
僕の前で小さく肩を落とした。
「どうして・・・」 今度は僕が彼女に訊ねた。
「どうして?・・こんなことを?そう言いたいですか?」
「ああ」≪聞きたい≫
「あれから毎日・・・あなたと出逢った時間にあそこに立ってました」
「毎日?・・・あれからって・・・ひと月は経つよ」 彼女の言葉に僕は本気で驚いた。
確かに彼女と出逢って数日は僕も彼女のことを気になっていたかもしれない。しかし、
最近は正直自分のことで精一杯で彼女と出逢ったことすら忘れかけていた。
「もうそんなに?・・・・フフ・・・気がつかなかった・・・」
彼女は自分の行動を振り返り宙を仰いで自嘲しているようだった。
「君・・頭可笑しいんじゃない?また危ない目に遭ったらどうするの?」
「だから、こんなかっこを・・」
彼女は手に持った帽子とサングラスを僕に持ち上げて小さく笑って見せた。
「そんなもの・・・役に立つわけないでしょ」
「立ったもの・・」 彼女が泣き出さんばかりの潤んだ目をしてそう言った。
「馬鹿じゃないの?」
僕は決してそう思っていない言い方で彼女を見つめそう言った。
彼女はただ黙って僕を見つめていた。
僕は彼女のその眼差しに、自分の心を覗かれているような気がして、
一瞬目を伏せた。
「英語・・・」 下を向いたまま僕は口を開いた。
「え?・・」
「上達したね・・・」 僕は顔を上げて、もう一度彼女と対峙して言った。
その時の彼女に向けた声が優しいトーンだったことに自分でも驚いた。
「あれからいっぱい・・勉強しました」 彼女も少し落ち着いた様子で答えた。
「あれから?」
「あの日・・・あなたの言葉が・・・よく聞き取れなかった・・・
今度、あなたと逢ったら・・・いっぱいお話ができるように・・そう思って・・・」
「何故?」
「わからないわ」
「わからない?」
「わからないの・・・あれからずっと・・・あなたのことが頭から離れなくて・・
あなたの声が頭の中から消えてくれなくて・・・
フランク・・・その名前だけが・・・私の胸を締め付けてた・・・」
彼女は僕の目を真直ぐに見つめてゆっくりと言葉をつなげた。
「それって・・・恋じゃない」 僕は他人事のようにそう言った。
それって・・・恋じゃない・・・
「恋?・・・恋・・・」
彼女は僕の言葉を自分で反芻し、それから納得したように頷いた。
「君・・彼いるでしょ?」
「彼?・・・ジョルジュのことですか?彼は・・・兄のような人です」
「少なくとも彼はそう思ってないようだけど」
あの時のあいつの鋭い目は到底忘れられるものじゃなかった。きっとあいつは
僕の彼女への行為に激しく怒っていたはずだ。≪そうか・・・≫
だから余計に話さなかったのかもしれない。彼にとっては間違いなく最悪な事実を。
彼女が僕を探していた。その事実は僕を驚かせたが、僕の中のもう一方で、
不思議とは思っていない自分がいた。しかし・・・
「悪いけど・・・僕は忙しいんだ・・・子供の戯れなんかに付き合ってられない」
僕は彼女に冷たくそう言った。
「子供じゃないわ!」 彼女はむきになって、僕に返した。
「僕にしたら、十分子供だ。」
「その子供相手にキスしたわ!」
「じゃあ、どうしろって言うんだ?僕にどうして欲しい!責任取れとでも?
ばかばかしい・・キスのひとつやふたつで大騒ぎ・・こんな風に待ち伏せして・・
やっぱり君は子供・・うっ」
彼女が突然僕に抱きつくなりキスをして、僕の矢継ぎ早の言葉を止めた。
≪な・・に?≫・・・簡単に・・・突き放そうと思えば突き放せた。
それなのに・・・
僕はそうしなかった。ついには・・・彼女の体を今度は僕が強く抱きしめて、
不器用なまでの彼女の幼いキスを、僕の激しいキスに変えていた。
そして彼女の固く閉じた唇を舌で強引に開かせ、彼女と呼吸をひとつにした。
僕はここが・・・道路の真ん中であることなど・・・忘れていた。
彼女を押し倒してしまいそうなほどの激しさが僕の体の芯をうずかせた。
あの日・・・彼女に意味もなく引き寄せられた感情が激流の如く蘇っていた。
まるでそれが引力であるかのように、僕は彼女の唇を激しく強く吸っていた。
彼女は僕の腕の中で次第に脱力し僕の支えなしでは立っていることさえ
ままならないようだった。
何故か狂おしいまでの情熱で僕の頭は爆発しそうだった。
≪駄目だ≫
僕は彼女の髪を乱暴に掴んでその引力に逆らうように、互いの唇を無理やり離した。
僕の目の前で彼女が熱いまなざしのまま放心していた。
そんなはずはない・・・
この僕が・・・誰かに心を囚われることなど・・・
あるはずがない・・・
ふいに僕は彼女の手を掴み、無言で歩き出した。
その手を乱暴に引きながら、僕は自分が彼女をどうしようとしているのかなど、
考えてはいなかった。
ただ僕の足は自然と自分のアパートへと向かっていた。
そんな僕の態度にも彼女は決して抵抗を見せなかった。
彼女はただ沈黙して歩く僕の顔を時折覗きながら、僕の歩調に合わせて
小走りに付いてきた。
アパートのエレベーターに乗り込んでからも、僕は終始黙っていた。
上昇する箱の中で壁にもたれかかった僕の隣で彼女もまた無言で正面のドアを
睨みつけていた。
エレベータが目的の階で止まってドアが開いた時、僕はしばらくその場を
動かなかった。
彼女もまた握られたふたりの手を見つめたまま、じっとしていた。
時間が来てドアが閉まりかけた時、僕はハッとしてドアの外へ出た。
「ここは?」 彼女がやっと聞いた。
しかし僕はその問いに答えもせず、鍵穴に鍵を差し込んだ。
そして部屋に入るなり僕は、彼女をたった今開けて閉めたドアに彼女を押し付けて
何の躊躇も無く彼女の服を剥ぎ取った。
彼女のブラウスのボタンがはじけて宙を舞い、胸に着けた小さな下着も
僕は引きちぎるようにして外した。
彼女の幼さの残る胸のふくらみが月明かりだけの部屋に一瞬浮き上がって消えた。
それは彼女が慌てて両手を交差してそれを隠してしまったからだった。
彼女は見るからに震えていた。
震えながら、黙って僕の目だけを見つめていた。
見るな・・・
そんな目で・・・見るな・・・
彼女の怯えた瞳から僕は結局逃れられなかった。僕の手は彼女の・・・
震えて硬く前で合わせたその腕を解かなかった。
僕は彼女から視線を逸らしてそばを離れるとそのままベッドに体を投げ出し、
黙って天井を見上げた。
彼女は僕の後を追うようにベッドに乗り込むと、むき出しになった自分の胸を
僕のブランケットで隠しながら僕の横に寄り添って座った。
「帰れ・・・」 僕は彼女と視線を合わせないまま言葉を投げつけた。
「帰らない・・・」 彼女は直ぐにそう言った。
「無理するな」
「無理じゃない」
「震えてる」
「・・・震えてなんか・・」
「僕はもう寝る。」
「ファーストキスだったの・・・」
「・・・・・・」
「夢を持ってた・・・ファーストキスは心から愛する人と・・・
子供の頃から・・・そう思ってた」
「・・・・・・だから?君の大切なファーストキスとやらを・・・
勝手に奪った僕が憎い?」
彼女は黙ってただ頭を大きく横に振った。
「だったら・・・何!」
「・・・・・凄く・・・不思議なの・・・嫌じゃなかった・・・
あなたで・・・嫌じゃなかった・・・」
「悪いけど・・・僕にとってはそんな深い意味はない」
「本当・・・に?」
「君・・僕のどんな答えを期待してるの?あれが・・・
僕が君をとても愛していて・・・だからそうした・・・そういう答え?
だとしたら勘違いもいいとこだ・・・
僕と君はあの時偶然に出会っただけ・・そうだろ?」
「本当に?」 いい加減僕は、彼女にイラついてきていた。
「いいか!さっきみたいに・・・男にあんなことをしたら! 」
思わず大声を出してしまった僕の目を彼女の萎縮したまなざしが彼女から逸らさせた。
僕の続けた言葉はトーンダウンしたように小声になった。
「・・・男は・・・こういうことをしたくなるんだ・・・
そんなこともわからないような子供が・・・」
「子供じゃないわ!」
「子供だよ!僕は子供は相手にしない。」
「・・・・・・・」
「ブラウス・・・そこにある僕のシャツ着て帰って・・・」
「あなたに・・・」
「・・・・・・・」
「あなたに・・・恋したんですね・・・私・・・」
「まるで・・他人事みたいだ・・」
「自分でも・・・わからなかった」
「だから?・・どうしたいの?」
「どうしたいって・・・わかりません・・・」
「わからない・・・そればっかりだ・・・」 僕は苦笑してしまった。
「わからないから!わからないの・・・あなたに逢ってから・・・
あなたと・・別れたあの瞬間から・・・
胸が潰れそうで・・・壊れそうで・・・
毎日・・毎日・・あなたのこと考えてた・・・
夢の中であなたが私にキスするの・・・そして息苦しくなって・・・
目が覚める・・・私の中に・・あなたの・・・あなたが・・・
起きてると・・あなたの顔が・・声が・・頭から離れてくれなくて・・・
ひとりでに涙が出てくる・・・苦しくて・・・
どうしていいか・・わからなかった・・・
今も・・・どうしていいか・・・わからない・・・
ただ・・あなたに逢いたくて・・・あなたの声が聞きたくて・・・
あなたを・・・ずっと・・ずっと・・ずっと・・待ってた・・・
それって可笑しいですか?
私・・・可笑しいですか?
私・・・いかれてますか?・・・私・・・私・・わた・・」
彼女の精一杯の告白が、頬を伝う幾筋もの涙が、決して彼女が子供ではなく、
女であることを僕に訴えた。
朧な月明かりがその涙を美しく輝やかせ僕の胸をうずかせた。
何故だ・・・何故・・君は・・・僕の前にいる?
どうして・・・僕は・・・こんなにも熱く・・・
君を・・・見ている?
いつの間にか・・・
僕はその白い頬に手を延ばし、指で彼女の涙を拭っていた。
「もういいよ・・・泣くな・・・」
僕は彼女の頭を優しく撫でて・・・
頭を支えるように引き寄せると、彼女の髪にそっとくちづけた。
彼女は・・・僕のくちづけになのか・・・
自分の僕への告白になのか・・・
僕の唇のその下で・・・いつまでもいつまでも震えていた。
君は・・・やっぱり・・・
・・・子供だよ・・・
| <前 | [1] ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] |