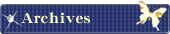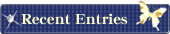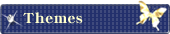創作mirage-儚い夢-4.うそつき

彼女の白くふくよかな胸のふくらみを掌で揉みしだきながら
僕は彼女を深く突き上げてめくるめく快楽の世界へと導く
僕の腕の中で・・・
理知的でいつもは落ち着き払った彼女が華麗に・・・しなやかに・・・
白い海に乱れ落ちていく
そして・・・
彼女と僕の頂点が重なり合った時、一瞬泣いたような顔を見せる
彼女のその憂い顔が好きだった
僕にとって女を抱くという行為に特別な意味はない
愛しているとか、いないとか・・そんな男と女の甘い執着も生まれることはない
しかし他の女を抱くよりも彼女を抱く方が僕は落ち着くことができた
それは何故なんだろう・・・
それは彼女が・・・
決して僕の心を求めないからと知ったのは・・・最近のことだ
17の夏・・・僕は・・・女の肌を初めて知った
ソフィア・ドイル・・・
彼女と初めて言葉を交わしたのは大学にスキップした年の翌年のことだった
彼女は僕よりも4つ上で、二学年先輩だった
僕はその頃自分の意思で養父母の元を離れ、奨学金のお陰で
学費の必要は無かったものの勉強以外の時間を生活のための
アルバイトに追われていた
僕はその頃、周りを見る余裕すら無くて、時に孤独に押しつぶされそうに
なったこともあった
まだ本当に子供だったんだ
ある時・・・
そんな僕をいつも誰かが見つめていることに気がついた
決して、近寄らず、遠くから熱い眼差しをくれる美しい人
いつもどこでも彼女の視線を感じることができた。
大学に入学して一年後、僕は更にスキップして、彼女と同じ講義を受けるように
なっていた。
ある日僕はわざと彼女の隣の席に座った。
いつも遠くから僕を見ていた彼女は突然僕が隣に座ったことに驚きを隠さなかった。
彼女は授業の間中、時折僕の横顔に視線を向けながらも僕を意識して無視した。
『僕に何か用ですか?』
『えっ?』
『ずっと、見てた。・・・僕を・・・』
『・・・・・・・・あなたに・・・キスしたくて・・・』
突然僕に声を掛けられた彼女は一瞬言葉に詰まっていた。そしてやっと口から
突いて出た言葉がそれだった。
彼女は自分のプライドを守ろうと毅然を装っていた。
僕はそんな彼女の様子を面白がっていた。
だから何も言わず、彼女にゆっくりと顔を近づけて当然のようにくちづけた。
授業が終わったばかりの騒然とした教室の中で、まだ多くの級友が取り巻く中で。
“僕がその時表情のひとつも変えなかった”と、後になってソフィアが不平を言った。
その後、気がつくと僕は彼女の手を強引に引いていた。
『ちょっと!何処行くの!』
『・・・・・・・・』
『止まりなさい!・・・フランク!』
『僕の名前・・・』
『あなたの名前?・・・』
『知ってるんだ・・・』
『・・・・・何処に行くの?』
『あなたの行きたいところ・・・』
『私の?・・・私の行きたいところへ?・・・それで・・・何するの?』
『あなたのしたいこと・・・』≪いや、僕のしたいこと≫
『あなたね・・・そんな回りくどい言い方しないで!』
『あなた・・・僕のこと、好きなんでしょ?この半年、ずっと僕を見てた』
『あなたも・・・私のこと好きなの?』
『いいえ』 僕は至って正直に言った。
『はっきり言うのね・・・』
『でも、好きになるかもしれない・・・』
『気になるの?・・・私のこと・・・』
『ええ』
≪嘘だった。好きになる?・・気になる?・・・
その感情がどういうものなのかが僕にはわからなかった≫
『だったら・・・いいわ・・・私の行きたいところで・・・
私のしたいこと・・・して・・・』
そして僕達は・・男と女になった。
学校でもいろんな意味で変わり者扱いを受けていた僕をいつも彼女だけは
一人前の男として、ひとりの人間として扱ってくれた。
その穏やかで慈愛に満ちた優しい視線の持ち主は僕の尖った心にいつしか
休息を与えてくれる存在になっていた。
僕はベッドの端に腰を掛けて、煙草をくわえるとジッポの音を鳴らした。
そして、その煙を深く吸い込みながら顎を少し上げると、唇の先から細く煙を
噴き出した。
僕の胸中にはその時何の感情も生まれていなかった。ただその白い煙が
立ち上る先を目で追っていただけだった。
彼女はしばしベッドにうつぶせたまま、鼓動が落ち着くのを待っているようだった。
それはいつものことだった。その間僕達は互いに声を掛けることも触れ合うこともない。
僕はゆっくりと一本の煙草を燻らせたあと、彼女を置き去りにして、
ひとりシャワー室へと向かった。
僕は・・・女の心を求めない
いや・・決して・・・誰の心も求めない
そして求められるのはなおのこと煩わしい
女は・・・
時に冷めきった体を・・・
黙って温めてくれる・・・それで良かった
人にまとわりつかれることが疎ましかった
抱くだけの女は他にもいた
そんな中で彼女が特別な存在だということは否定はしない
しかし、たとえ彼女であっても拭えないこの虚しさに・・・
僕はこうしていつも・・・喘いでいる
≪僕が本当に欲しいものは・・・いったい何なんだろう・・・≫
僕はシャワー室を出ると冷蔵庫からミネラル・ウォーターを取り出し
ゆっくりとのどを潤しながら、パソコンを起動させた。
そして数時間前に約束したレオナルド・パクへ送るべき資料を
メールに添付する作業を始めた。
その時ソフィアがやっとシャワー室へと消えていった。
「フランク・・・仕事の方はどう?」
ソフィアはシャワー室から部屋に戻った時には既にここへ来た時の服装に
身を包んでいた。
「ん・・・弁護士は確保した・・・
まずは小さな会社から手を付けていく・・・
もう着替えたの?」
僕は横目で彼女をちらりと見て、またPCに視線を戻した。
「そう・・・私も・・卒業後の進路を決めたわ・・・」
彼女は僕の質問に答えることなくそう言った。
「ん?・・」≪進路?≫
「弁護士になろうかと思って・・・」
「検事志望じゃなかったの?」
彼女は大学入学当初から、検事を志望していたと聞いていた。
「止めたわ・・・」
彼女は頭の後ろに両手を回して、長い髪を後頭部でくるりとまとめてた。
「僕のため?」 僕は一度キーボードから指を離し、彼女を見た。
「何故・・私があなたのために?」
彼女はそのまとめた髪を大きなピンで留めながら僕に視線を送った。
「ならいいや・・・」 僕はまた手元の作業を再開した。
「コーヒー飲む?」 彼女はキッチンに移動して言った。
「いや・・ミネでいい・・」 僕は手元のミネを持ち上げて見せた。
「そうだったわね・・・」
ソフィアは自分だけのために、慣れた手つきでコーヒー豆を挽いた。
「ね・・・卒業したらここへ来る?」
僕の視線は終始パソコンの画面を追いながら、言葉だけが彼女に向かっていた。
「ここへ?」 彼女は僕の言葉が不思議であるかのように首をかしげていた。
「ん・・」 僕は彼女との視線を交えないまま答えた。
「・・止めとくわ」 ほんの一拍を置いて、彼女は直ぐに答えた。
「そう・・・」 僕はただそう言った。
「・・・・・試したわね・・・フランク・・・」
「何を?」
「私の答えは・・正しかった?」 そう言って彼女は僕の顔を覗きこんだ。
「・・・・・来ればいいさ」
僕の向かいに立ちコーヒーカップを口に運んでいた彼女に
僕はやっと視線を向けながら言った。
「正しかったみたいね・・・・・」
そう言って彼女は僕を見透かしたように優しく睨んだ。
確かに・・・
あなたが決してそうしないことがわかるから言ったのかもしれない
女と暮らすなんて・・・考えたことも無い
もしも女がそれを望んだら・・・それで関係は終わりを告げる
ソフィアという女はそれを良く知っていた
「遅くなったね・・・どうする?」 僕はパソコンから離れて、ソフィアのそばに近づくと、
彼女が髪をまとめていたピンを抜き、その髪を彼女の肩に落とした。
彼女は僕のその行動を目で叱った。
「その方が素敵だ」
「帰るわ・・・勉強したいこと沢山ある・・・みんな今必死よ・・・
あなたみたいに余裕がある人間なんてあの学校にはいないわ」
女と朝を迎えない・・・
そんな僕を知っているのも・・・あなただ
きっと・・・
僕自身よりも・・・僕を知っていた
「余裕?僕には生活が懸かってるだけだ・・・学校で遊んでる暇が無いだけ」
「遊び・・ね・・・あなたにかかったら、研究材料も遊びだわね・・確かに・・」
「まあね」
僕はそう言って、片方の口角を上に上げた。
「ジニョン!」 ジョルジュが教室の後方から呼ぶ大きな声に私は振り向いた。
「俺はバイトに行かなきゃならんから、お前は早く寮に帰れ・・・
いいか、寄り道するんじゃないぞ。」
あの日以来、ジョルジュは自分と一緒で無い日は、必ずそう言って念を押した。
私は最後の授業のあと、ため息をつきながら教材を片付けていた。
≪授業の間中、私はいったい何回の溜息を吐いただろう≫
「わかってる・・オッパ、最近ちょっと心配し過ぎよ」 そう言いながら、
私はジョルジュを横目で睨んだ
「お前が心配させるようなことするからだろ?お前に
もしものことがあったら、俺はお前の親父に殺されるぞ」
「オーバーね」
「オーバーなもんか・・・もうあんなことするんじゃないぞ!
俺からたとえ連絡無かろうと、
一人であんなとこに来るんじゃない・・わかったか?」
「う・うん・・・」 ジニョンは口を尖らせながら、俯いた
「どうした?具合でも悪いか?」
「ううん・・どうして?」
「ため息ついてた」
「大丈夫」
「そうか・・じゃな・・行くぞ・・」
「うん・・じゃ、明日ね・・」
俺の脳裏にあの時のあの男の眼が焼きついて離れなかった。
俺を睨んだまま決して視線を逸らさなかったあの鋭い眼
俺はあの時・・・
奴の情熱的なまでのジニョンへのキスに圧倒されて息を呑んでしまった。
心に走った衝撃が俺の声を封じ込め、身動きできなくしていた。
あの瞬間、目眩がしたのは・・・決して熱があったわけじゃない。
ジニョンはあいつのあの激しいキスに本当に気がつかなかったのか?
しかし、あいつがあの男のことを意識したことには間違いない。
男が消えてしまった後、ジニョンは奴の話を一切しなくなった。
それが・・・
あの男を忘れていない・・・その証拠だ・・・
だから・・・
俺はジニョンにあの時のことを言わなかった・・・いや・・・
あの光景を・・・悪い夢だったと、思いたかったのはきっと・・
この俺の方だ。
忘れられなかった・・・
フランク・・・フランク・・・フランク・・・
私の頭の中にその名前だけが繰り返し巡っていた。
こんなこと・・・今までに経験の無いことだった。
10時間・・・彼といたたったの10時間
でも、ずっとずっと長く・・・一緒にいたような錯覚を覚えた。
無愛想で・・・
鋭いまなざしは少し怖い気さえした。
でも私はあの時・・・彼が一緒にいてくれることを即座に望んだ。
あんなこと・・・後で考えれば、決して私のやれたことじゃない
それなのに・・・
無意識に彼の袖を引いていた。
何がそうさせたのか・・・わからない・・・
あの日から・・・
私はジョルジュに・・・嘘をついている。
彼のことを何とも思っていないなら笑って話題にするはずなのに
ジョルジュに嘘をつくことなんて今まで一度も無かったのに。
「今度はいつ来る?」
「わからないわ・・・あさっては学校でしょ?」
「ああ・・でも向こうではこんなことしてる暇が無い・・・」
彼女の背後から、僕が肩に下ろした長いブロンドの髪を片方に寄せ、
彼女の白い首筋を露にすると、そこに唇を這わせながら僕は囁いた。
「ふふ・・校内に缶詰ですものね・・・」
そして腰に回した僕の手を彼女はそっと自分から外して、身支度を始めた。
「ねぇ・・僕をじらしてる?」
「じらす?・・あなたがそんな言葉・・使うの?」
「あなたにだけだ・・・」
「フランク・・・あなたには似合わない言葉ね・・・」
「どんな言葉なら似合う?・・・帰らないでって・・・言おうか?」
「じゃあ、言ってみて?・・・」
「か・・」
“言ってみて・・・”そう言ったはずのあなたの小指が僕の口が動くのを止めた。
「フランク・・・思っても無いことは言わない方がいいわ・・・」
「思ってないわけじゃない」
「預かった鍵・・・ここに置くわね」
「持ってればいいのに」
「鉢合わせはごめんだわ・・・」
「誰も来ないよ」
「・・・・・・・・・フランク・・・何かあった?」
「・・・どうして?」
「・・・・・何となく・・・」
「何が言いたいの」
「嘘はつかないで・・・」
「嘘?・・・あなたに嘘をついたことはない」
「・・・・・さっき・・・ベッドの中で・・言ったわ」
「何を?」
「愛してるって・・・」
「それが?・・・」
「ええ・・・それが」
・・・うそつき・・・
創作mirage-儚い夢-3.野望

フランク・・・
フランク・・・
彼が残した声の響きが私の耳にいつまでもこだました。
私はしばらくの間、静かに目を閉じて彼の声を繰り返し心に戻していた。
昨日逢ったばかりの・・・何も知らない・・・いいえ・・・
名前は・・・フランク・・・
私の心だけが、たった今彼が曲がって消えたその角を共に曲がり彼を追っていた。
でも・・・現実には・・・
そうする理由が・・・見つけられない・・・
私はその場に佇んだまま、本当に動くことができなかった。
何故?何故私はこんなに胸を締め付けられているの?
名前を知ったところで・・・
虚しいだけじゃない・・・
何故・・・聞いてしまったの・・・
“フランク”・・・
たったそれだけ・・・
それだけしか・・・残していってくれなかった・・・
たった・・・それだけ?・・・
私は自分でもわかるほどの大きなため息をひとつつくと、自分の気持ちに嗾けて
ジョルジュの部屋へと戻っていった。
部屋に戻ると、ジョルジュがベッドから下りて、窓際にもたれて佇んでいた。
フランクが壊してしまったドアをそっと戻しながら入って来た私を見つけて、
ジョルジュは少し怒ったような視線を向けた。
『名前も知らない奴だったんだ・・・』
ジョルジュは窓の外に一度視線を送り、そう言った。
『見てたの?だから・・・助けてもらったって、言ったでしょ?』
私は少しむくれたように言った。
『お前って・・・』
ジョルジュが視線を下げて、呆れたような冷たい笑みを浮かべた。
『お前って・・・本当に危ない奴だな』
『どういう意味?』 今度は本当に癪に障って言った。
『何でも無い!』 ジョルジュは私より遥かにムッとした様子だった。
彼の珍しくきつい口調に私は微かに動揺していた。
彼は窓際から離れると、私を無視して横を通り過ぎ、シンクの下から
工具箱のようなものを取り出すと無言でドアの蝶つがいを付け直し始めた。
『何怒ってるの?オッパ!あの人は・・・
私が怖い思いをした時、助けてくれたの!
私がここを見つけられないで迷ってた時、探してくれた!
私が・・オッパがどうなっているか不安でひとりで訪ねられなかった時
一緒に付いて来てくれた!
私が・・死んだようにしてるオッパをひとりで見てられなくて・・・
無理に引き止めたの!寒くて泣きそうな私を温めてくれた!
オッパなんて!私を心配させて・・・連絡くれなくて・・・
私を・・一人にしたくせに!・・不安にさせたくせに!』
私は何故だか無性に悲しくなって、悔しくなって・・・情けなかった。
ただ理由もなく、泣きながらジョルジュに当り散らすように叫んでいた。
『ジニョン・・・』
ジョルジュは私の癇癪に驚いて、手にしていた工具を放り投げて、私に走り寄った。
『オッパなんて!』 私はジョルジュの胸を激しく叩いた。
『ごめん・・・ごめん・・・泣くな・・・オッパが・・悪かったよ
心配させて・・・ごめん・・・』
ジョルジュは私をそっと包むように抱きしめて、私の興奮を鎮めようとしていた。
私は顔を両手で覆って、しばらく彼の腕の中で泣きじゃくっていた。
何故、こんなにも涙が出るの?
何故、こんなにも辛いの?
何故・・・何故・・・
私が泣いていたのは・・・ジョルジュのせいなんかじゃない・・・
だったら・・何のせい?・・・それは・・・あの人・・・
あの人がいなくなったせい・・・
私の体から・・・あの人の温もりが消えたせい・・・
でも・・・説明できないわ・・・こんな気持ち・・・
昨日初めて逢った人・・・そしてもう・・・
二度と逢えない人・・・こんな・・・
胸が今にも粉々に潰れるような・・・
こんな想いなんて・・・
自分でも・・・理解できないもの・・・
「ジニョン・・・」
ジニョン・・・最後に彼女が叫んだ名前が僕の頭から離れなかった。
別れる前の・・・あの潤んだ瞳が・・・忘れられなかった。
行きずりの・・・たかが・・・子供・・・
子供?・・・フッ・・・女・・・だった・・・
二度と出逢うことの無い・・・行きずりの女・・・
そう・・・もうきっと二度と逢うことは・・・無い
≪そうだ・・・≫
僕にはやらなければならないことが山ほどある。
学校にはもう形だけ行けばいい。
あとは僕がひとりで生きていくためにやらなければならないこと。
金・・・そう・・・金を稼がねば・・・
『大学院を出たら、何の仕事に就く?』
教授たちが卒業間近になった時、ごぞって僕に尋ねてきた。
『そのまま大学に残って自分の研究に加わらないか・・』
『教鞭をとらないか』と言ってくる教授もいた。
ある教授はこう言った。
『どうしてその才能を有効に使おうとしないんだ』
≪はっ・・余計なお世話だ≫
僕はその申し出のどれも断った。人の下で働くのはごめんだ。
うるさい餓鬼どもの相手をさせられることにもうんざりだった。
しかしひとつ問題があった。僕がここまで奨学金を得て就学を成し得たことだ。
そのため、学校に対していくらかの義理がある。
今はその義理を返すべく、学校に赴いていると言ってもいいくらいだった。
どちらにしても、僕は学校などの狭い世界に留まるつもりは毛頭ない。
僕の狙いは世界・・・
いつの日か・・・世界を牛耳る男になる・・・
僕はその手段としてひとつの仕事に目をつけていた。
“M&A・・・企業買収の狩人・・・”
一匹狼の僕には打って付けの仕事だ・・・
しかし、その世界には法的なルールはともかく、新参者を寄せ付けない空気が
そこら中はびこっていた。
≪だから・・・何だというんだ?≫
僕は僕のやり方で、成功を収めてみせる。そして必ずや・・・
≪その頂点に立つ≫
大学院へは週に二日行けばいいと決めていた僕は水曜日の夕方に
マサチューセッツへと向かい、金曜日の夜にNYに戻るスタイルを始めた。
僕に期待を掛けた教授たちをことごとく裏切った僕は、今では大学院でも
ちょっとした変わり者扱いだ。
NYでは住居兼事務所用に古びた中層アパートを借りていた。
そこにパソコンを5台備え付け、サーバー、FAX、電話、机がひとつにベッドがひとつ。
そして仕事用に高級スーツを2着、取り敢えず必要最低限のものだけを
身の回りに置いた。
そして学校に通う日以外の日をM&Aについての研究に費やした。
株の取引は朝の9:00から1時間のデイトレ中心で利ざやを稼ぎ
今後の軍資金にとそれを根気よく蓄えた。
そして・・・
この業界で生きていくためには幾つか乗り越えなければならないことがある。
そのためにどうしても必要なものが・・・もうひとつ。
優秀な弁護士だ・・・
僕は業界紙を読みあさり、この世界で一番実力のあるフリー弁護士を探した。
そして、ひとりの男に行きあたった。
レオナルド・パク・・・韓国系アメリカ人・・・
写真で見る限り、さえない30男だったが実力は自他共に認められていた。
≪さあ、彼とどう接触する・・・≫
僕にはこの業界に何一つ“伝”と呼べるものが存在しなかった。
だから、どんな小さなことでも、自分でひとつひとつ調べなければならない。
ようやくレオナルド・パクの行きつけの小さな酒場を探し当て、
初めて彼に接触できたのはあの変な女の子と出会った日の
一週間後だった。
僕はカウンターでちびちびとグラスを傾けていたレオナルド・パクに向かって
開口一番こう言った。
「いくらで・・・俺と仕事をしてくれる?」
「坊や・・・誰かと間違えてるか?」 男の第一声はこうだった。
「・・・レオナルド・パク・・・M&A専門弁護士・・・
その腕にかけては今、右に出るものはいない。
俺が探してるのは・・・そういう男だが・・・違ったか?」
僕は決して怯むことなく返した。
「はは・・・生意気だな・・・
いったい坊やとこの俺が・・・何の仕事をするんだ?」
「お前は・・・M&A専門弁護士じゃなかったのか?」
「言葉に気をつけろ・・・坊や」
「俺が雇うんだ・・・だから俺がボスだ。」
僕は彼に対して終始上から目線でものを言った。
「それで・・・いくらで仕事を?」 僕は再度言った。
「そうだな・・・fifty-fitty」
男はきっと、冗談半分で答えたのだろう、しかし僕は至って真面目に切り返した。
「・・・・・・・・これが今日、株で稼いだ半分だ」
僕はポケットから札を出して、そこから75ドルを抜くと男の前に置いた。
少し力を入れてしまったせいか、カウンターに置かれた彼のグラスが少し揺れて
音を立てた。
男は・・・目の前に置かれたよれよれの札をしばらく見つめた後、
僕の顔を見上げて軽く睨みつけた・・・そしてにやりと笑みを浮かべた。
「ひとつ・・・M&Aの仕事には金が掛かる・・・その資金は?」
男はさっきまでの含み笑いを、真剣な顔つきに変えてそう言った。
「そうだな・・・この小さな飲み屋を買収するくらいは・・・」
僕は多少はったりをきかせてそう答えた。
「ほう・・・若いのに・・・大したもんだな・・・
ひとつ・・・俺はもちろん、お前の専任はできない。
これでも売れっ子弁護士だ・・かなり、忙しいんでね。」
≪無論そうだろう。≫ もちろん、こちらとて、今は彼を専任弁護士として
雇うだけの地盤は持ち合わせていない。
「そのうち・・・俺だけの仕事をしてもらう。」
≪いずれは必ずそうしてみせる。≫
「生意気な・・餓鬼。・・・いや・・・ボス。」
男はクロコダイルの立派な名刺入れから、一枚の名刺を僕に差し出した。
「必要な時、ここへ連絡を。」 そして男は席を立って、僕に右手を差し伸べた。
僕より、遥かに小さい・・・
本当にさえないオヤジ・・・だが・・・
この男が・・・僕のこの世界での・・・今後の鍵を握る・・・
僕にはその確信があった。
これが僕とレオナルド・パクとの出会いだった。
「まあ、一杯どうだ・・・この75ドルで乾杯といこう」彼はそう言った。
僕は自分から仕掛けておきながら、ことの成り行きに正直呆然としていた。
本当は僕の申し出など、彼に一笑に付されるものと覚悟していた。
「どうした?」
「いや・・・」
あのレオナルド・パクが本当に僕の仕事をしてくれるのか?・・・
この・・・たったの・・・75ドルで?
「どうして・・・僕と仕事をしてくれる気になった?」
レオが注文してくれたカクテルで唇を湿らせながら僕は彼に尋ねた。
「どうした・・・さっきまで、あんなに強気だったじゃないか・・・ボス」
レオは僕を“ボス”と呼んだ。僕は急にそれが無性に恥ずかしくなった。
「フランクだ・・・」 僕はグラスをカウンターに戻しながら、俯きがちに言った。
「フランクか・・・仕事のときはボスと呼ぶ。
それがフリー弁護士としての俺の礼儀だ。 しかし今は・・・
フランクでいいか?」
「ああ」
「どうして?・・・そう聞いたか?・・・どうしてだろうな。
お前のその眼に惚れた。・・・そういうことかな」
「眼?」
「ああ、果てしない野望に満ちた鋭い眼。それでいて、言ったことを必ず
実現させるだろうと思わせる・・・賢い眼・・・そして・・・」
レオはそう言い掛けて、僕の顔をまじまじと見た。
「そして?」
「そして何より・・・鋭さの奥に見える・・・純粋な・・・
綺麗な眼だ。」
≪何処から、そんなに人を信用する心が生まれる?≫
≪あなたが・・・純粋な・・・綺麗な眼をしてるから・・・≫
一瞬、あの時のあの子の言葉と、そう言った時の彼女の笑顔が脳裏に蘇った。
そのことが僕を驚かせて、言葉を失わせた。
・・・私の名前はジニョン・・・
「どうした?フランク・・・」
レオが僕の背中を叩いて、僕はやっと現実に戻った。
「いや・・何でもない」
≪何故今・・・彼女?≫
一瞬僕の頭をよぎったあの日のあの子の屈託のない笑顔を
僕は自嘲しながら首を振ってかき消した。
「そうだ、早速見てもらいたい、資料があるんだ
帰ったら・・・このアドレスへ送ればいいか?」
そう言いながら、僕はさっき彼にもらった名刺を指で挟んで彼に示した。
「見てもらいたいもの?仕事か?」
「お前に仕事以外の話はない」 自分でも嫌な奴だと思った。
しかしレオは僕のその言葉に目を細めた。
「ああ・・構わん、送ってくれ」
僕は結局、レオへの分け前として渡した75ドル以上の酒を
彼の奢りで飲んだ。
彼もまた僕と機嫌よく酒を酌み交わし、「明日早いんだった」と
笑いながら千鳥足で帰って行った。
レオに渡した75ドルのせいでタクシー代すらなくなっていた僕は
アパートまでの10キロを、歩いて帰るしかなかった。
それでも僕が珍しく上機嫌だったのは・・・レオナルド・パクという優秀な弁護士を
得たことで、暗中模索状態が続いていた世界に突破口が開けた気がしていたからだろう。
≪いよいよだ・・・≫
いよいよ僕の未来を賭けたゲームが始まる。
≪駒は揃った・・・≫
あとは僕がスタートのフラッグを振り上げればいい。
僕の胸は希望と野望が入り混じった感情で高揚していた。
とうとう10キロの道を歩ききった時、アパート近くの鉄橋で少し足を止め、
欄干に寄りかかり、ポケットから煙草を出しくわえた。
そして火を点けてそれをゆっくりと吸い込み、宙を仰ぎながら白い煙を闇に放った。
その直後、その橋から見える自分の部屋に灯った明かりに気がついた。
僕は急いで吸っていた煙草を落とし火を踏み消すと、鉄橋を駆け降りた。
「フランク・・」
性急に鍵を開けて部屋に入った僕に、声の主が笑顔を向けた。
≪ソフィア・・・≫
僕は彼女に走って近寄ると、無言で彼女の手を掴み、乱暴に抱き寄せた。
そして、彼女の次の言葉を聞くより早く、微かに濡れたその唇を容赦なく塞いだ。
・・・遅かったじゃないか・・・
創作mirage-儚い夢-2.kiss

「彼・・・同郷の人なんです・・・幼馴染で・・・
年は二年先輩・・・NYの大学に留学して来たの・・・彼・・一年前・・
でもアルバイトに追われて・・そのせいで留年してしまって・・・
結局・・同級生に・・・今年留学した私と・・
私・・外国初めてだし・・彼だけが唯一の・・頼りなの・・・
それが3日前から連絡が取れなくなって・・急に・・
だからパニックになったみたい・・・私・・・
じっとしていられなくなって・・こうしてよく知りもしない町に・・
きっと大変なことになってた・・さっきあなたに会わなかったら・・
わかってます、無鉄砲なことだって・・それに
知らない・・あなたに・・・無理なお願いを・・ホント・・どうかしてますよね・・・
・・・・・あの・・・怒ってますか?」
彼女の英語は主語も述語もめちゃくちゃだった。
僕の腕の中でゆっくりと片言の英語で言葉を繋ぎながら、言い訳のように、
ことのいきさつを懸命に話していた。
そうして下から伺って僕の言葉を待っているようだった。
悪いけど・・・僕は君の身の上話など興味はない。
まして、ベッドで臥せっている彼の素性など知りたくもない。
そんなことなんて、どうでもいいことだよ。
僕は運の悪いことに、今日たまたま君に出会ってしまって
そして何の因果か、こうして見ず知らずの男が目を覚ますのを
君とひとつブランケットに、暖を取りながら待っている
そのことの必然性を説明など出来るはずもない
“怒ってるか”・・だって?
僕は君にいったい何を言えばいいんだい?
しかし、彼女は僕の言葉がどうしても欲しいらしい
“いいや・・・怒ってないよ”そう言って欲しいのか?
本気で“怒っている”そう言ったらどうするつもり?
君は結局、捨てられた子猫のような顔をして僕をここまで連れて来た
他人には例外なく無関心なこの僕をこの場に留め抜いた
それだけで・・・笑える・・・本当に笑える・・・
だから・・・そういう意味だけでも・・・
「怒ってない。」 ≪きっとそうだ≫
「本当に?」
「ああ」 僕は呆れた眼差しでじろりと彼女を見下ろした。
僕は「怒っていない」と怒ったような無愛想な答え方をしていたのに
それでも彼女は僕の言葉通りを受け取った。
「良かった・・・」 彼女はそう言ってホッとしたようにうつむいた。
「コーヒー飲んだら?冷めるよ」 僕は彼女の手の中で少し
冷めてしまったかもしれないコーヒーに視線を向けて言った。
「ええ・・・いただきます」 彼女は満面に笑顔を輝かせた。
彼女はコーヒー缶のタブレットを引き抜こうとしたが、手がかじかんでいるらしく
上手くできないでいた。
「貸して・・・」
僕は彼女から缶を受け取ると、タブレットを引き抜いて再度手渡した。
「優しいんですね」
「優しい?・・・僕と無縁の言葉だな・・・」
≪笑ってしまうな・・そんなこと誰にも言われたことがない≫
「・・・どうして?」
本当に驚いたというように、目を丸くして僕を見上げた彼女の顔に
僕は思わず吹いてしまった。
「どうしてって・・・」
そんな真顔で「どうして?」と言われても・・・どう答えればいい?
ただ、僕を知る人間は一人残らず、僕を優しいなどと表現する奴はいない。
それだけは確かだ・・・ただ、それを君に言ったところで何になる?
「何か可笑しいこと、言いましたか?・・私・・・」
僕が何も言わず、ただ声を殺すようにして笑っていると、彼女は
きょとんとした表情で首をかしげた。
「いや、失礼・・・そうじゃない・・・
それより、彼のタオルそろそろ換えてあげた方がいいんじゃない?」
僕は高いベッドに向かって顎をしゃくった。
「ほら!やっぱり優しいんだわ」 彼女は弾けるような笑顔で、
自分の考えが正しかったと言わんばかりに得意そうに言った。
その彼女の笑顔に僕の胸の奥が何か鋭い爪に鷲掴みされたようだった。
君は・・・なんて笑顔を向けるの?
こんな・・・僕に・・・
そして次の瞬間、不本意にも・・・
彼女の笑顔に僕自身の顔が自然とほころぶのを感じた。
その後も彼女は10分置き位に冷たい水でタオルを湿らせて
眠っている彼の額にそれを乗せてあげながら、優しく声を掛けていた。
『ジョルジュ・・大丈夫?苦しくない?
ずっとそばにいてあげるからね・・・』
彼は・・・ジョルジュというのか・・・
君は?・・・君の名前は?・・・
聞いて・・・ ・・・どうする・・・
当たり前だろうが、彼女は彼をとても心配していた。
彼のベッドがもう少し低い位置にあったなら、彼女はきっと
ベッドの脇にでも座って彼の傍らに付いていてあげただろう。
しかし、それは余りに高い位置に設えてあって、梯子を必要だったばかりに
彼女は彼の熱を冷ます為に、額に乗せてあげたタオルを換え終わると
僕の腕の中へ戻って来るしかなかった。
彼は・・・恋人?・・・きっとそうだろうね・・・
でも・・・聞かなかった・・・
僕は彼女が戻って来るとしっかりと包み込んで寒さから防いであげた。
そうすることで僕自身の防寒にもなったからであって、他に理由はなかった。
彼女はそのことに抵抗することもなく、むしろ僕に身を委ねてさえいた。
すっかり僕を信頼しきっているかのように・・・
今日初めて会ったんだよ僕は・・・
君の頭の中を覗いてみたいよ・・・
恐れを知らない?・・いや・・
まだ子供なんだね・・・君は・・・
「どうして・・・アメリカへ?・・・」 僕は彼女に初めて質問した。
彼を追って来た・・・そんなところだろうが・・・
「いつの日か・・・ホテルに勤めるのが夢なんです・・・
そのためにはしっかりとした語学を・・・
早い上達には生活に溶け込むのが一番だと・・・オッパが・・・
あ、いえ、そこにいる彼が・・・そう言ったんです・・・
父はかなり反対しましたけど、オッパが説得してくれて・・・
彼がそばにいるなら、と許してくれました・・・」
「信用あるんだね・・・彼・・・」
「はい・・・幼い頃から兄弟同然で育ちました」
それからもずっと、彼女は繰り返し繰り返し、彼の熱を下げるために
タオル交換を続けた。
いったいどれくらいの時間が経っただろうか・・・
ただこうして待つ僕にとってはとてつもなく長い時間のようにも感じられたし、
彼女と過ごす時間を何故か短くも感じられていた。
窓の外からうっすらと夜明けの色が差し込み始める頃になると
時折うとうととしていた彼女がいつしか深い眠りに落ちていた。
そっと彼女を覗き見ると・・・
さっきまでまるで無邪気だった彼女の寝顔が、僕の腕の中で憂いを秘めた
大人の女にも見えて、胸が高鳴った。
僕は眠れなかった・・・
体の芯まで冷えるほどの寒さもあったかもしれない・・・
しかしそんな寒さより、僕の肩に落ちた彼女の頭の重みが・・・
僕の右胸にぴったりと寄り添った彼女の細い肩の感触が・・・
僕を睡魔から遠ざけていた・・・
彼女の可憐な寝顔に・・・
吸い込まれそうなほどの不思議な引力を感じていた。
いつしか・・・僕の左手は彼女の細い顎をそっと持ち上げて、
僕の唇は彼女の唇に重ねられていた。
最初はそっと・・・触れただけだった・・・
それでもただ眠り続ける彼女に次第に僕のくちづけはエスカレートしていった。
彼女の少しばかり厚めの・・・柔らかい唇をついばんで・・・
ついには強く吸っていた。
彼女は僕に向かって顎を持ち上げられたまま・・・ひたすら眠ったままだった。
僕は左手を彼女の顎から頬に移動させて・・・彼女の白い頬をそっと支えた。
右手はブランケットの端を握ったまま彼女の肩をしっかり抱いていた。
まるで・・・
僕の全神経が彼女の唇一点に集中しているようだった。
キスなんて・・・挨拶ほどの役割しかないもの・・・
それが・・・
僕の唇が彼女の唇に吸い寄せられたまま離れない・・・
そして・・・ついには・・・
眠ったままの彼女の唇を舌で押し分けて僕は更に深く彼女に進入した。
自分でも気づかないうちに・・・
僕は・・・彼女の唇を・・・
・・・・・・・・・・・・・・・
「誰?・・・」
上の方から聞こえたその声で、僕はやっと我に帰ることができた。
それでも、直ぐには彼女の唇から離れられなかった僕が、その声の方に
振り向くまでには少しの間があった。
当然・・・その声の主が誰であるかは・・・わかりきっていた。
ゆっくりと振り向いた僕を・・・
ベッドの上で既に上体を起こしていたジョルジュと呼ばれていた男が
鋭い眼光で睨みつけていた。
ベットに横たわっている時よりも遥かに整ったように見える顔のその男を
僕は彼女との刹那な時間を邪魔されたとばかりに、睨み返した。
「ん・・・うん・・・」
彼女が隣で目覚めた瞬間、僕は自分の腕に力が入ったのを感じた。
彼女を離したくない想いが、無意識にそうさせていた。
本当ならその目覚めは・・・
彼と僕の睨み合いに終止符を打たせるはずだった。
『ジョルジュ!気がついたの?』
彼女はおもむろに僕の傍らから抜け出ると、梯子を上り、彼の額に手を当てた。
彼女が僕から離れた瞬間・・・僕の心が一瞬うずくのを感じた
何か・・・大事なものを盗られてしまった・・・そんな感覚だった。
『熱下がってるわね・・・良かった・・・心配し・・』
『誰?・・・こいつ・・・』
彼は彼女に額に手を当てられながらも、最初から変わらず鋭い眼光を
僕に向けたまま、彼女の言葉を遮った。
僕も彼を睨んだまま、決して視線を逸らさなかった。
『あ・・この人はね・・私をここへ連れて来てくれたの・・・
悪い人に絡まれてた私を助けてくださったのよ』
『助けて・・・ね・・・』
彼は睨みつけたまま何やら含んだ物言いを僕に浴びせた。
しかし彼としてみれば至極当然のことだったろう。
病に臥せって苦しんだ末、目覚めてみれば、自分の恋人が
見知らぬ男に唇を奪われている場面に出くわした。
≪僕が君だったら・・・殴りかかってるよ≫そう心で呟いて、
僕は左の口角を不敵に上げた。
『あなたと連絡取れなくて、どんなに心配したか・・・
病院に行かなくても大丈夫?』 彼女は心配してそう言った。
『大丈夫だよ・・・風邪引いてただけだ』 彼がやっと、
彼女に穏やかな口調で答えた時、ふたりが交わした親密な眼差しが
僕の胸を疼かせた。
「それじゃ・・・もういいね・・・僕はこれで失礼するよ」
僕は彼らの光景から目を逸らすように立ち上がるとドアの方に向かい
壊れたそれをどけるようにして開けた。
「あ・・・えっ?ちょっと待って・・・」
彼女が帰ろうとする僕を追って慌てて梯子を下りて来た。
「このドア・・・後で修理しといて・・・じゃ・・」
僕はそれにお構い無に、壊れたドアを横に避けた。
『待って!』
彼女の声が僕の背中を追っていたが、僕は部屋を出ると足早に階段を下りた。
何故、そんなに慌てて出て来た?
僕は自分に問いかけていた。
彼に対する後ろめたさ?
いいや・・・二人のハングルのやりとりが気に食わなかった・・・
二人に僕が嫉妬した?・・・
バカな・・・なんで嫉妬なんか・・・
僕の後を彼女が必死で追いかけて来ているのはわかっていたけれど
僕は彼女に振り向かずそのまま無視して突き進んだ。
「 待って!待ってください・・・お名前・・・教えて! 」
彼女は息を切らしながら、僕の背中にそう叫んだ
「僕の名前?・・・知る必要があるの?」
僕は面倒くさそうに彼女に振り向いて答えた。
「必要・・・って・・・・わからないわ!」
「わからないなら・・・知らなくていい。」
「でも・・お礼くらい・・・させてくれても・・・」
「お礼?・・・何の?」
「助けてくれたわ・・私を・・・」
「そんなの・・いらない」
「でも・・・」
「早く戻って!彼が心配する!」 僕はそう言ってアパートを指差した。
「でも・・・本当に?・・・本当にこれで?」
本当にこれで?
「これで?」 ≪何なの≫
「私達・・これで?」
「私達?・・それって何?」
終わりなのかと言いたいの?
終わりだよ・・・
「でも・・・でも!・・・私は・・・」
私は何?・・・
次のブロックで僕は君の視界から消える
それで・・君と僕は・・・終わり・・・
最初から・・・何もなかった・・・
これからも・・・何も・・・ない
何か言いたげな彼女の憂い顔を僕は振り切るように顔を背けた。
「待って!・・・私は・・・私の名前はジニョン!ソ・ジニョン! 」
ソ・ジニョン・・・・
彼女の叫んだ名前を僕は背中で聞いていた。
そしてそのまま後ろ手を無造作に振りながら直ぐのブロックの角を
躊躇なく曲がった。
「 フランク 」 僕はひと言だけそう残した。
彼が消えてしまった角の向こうから、
彼の低く響く声だけが私の耳に届いた・・・
フランク・・・
・・・フランク・・・
創作mirage-儚い夢-1.出会い

この物語は「ホテリアー」のドンヒョクとジニョンがもしも十年前に出逢っていたら・・・
ドンヒョクは仕事としてM&Aを始動させたばかりの頃、年齢は22歳、
ジニョンはホテリアーを目指してNYの大学に留学していた18歳
そんな設定で創作したHotelier side story
ふたりはどの時代に出逢っていても、運命の人を見つけられるだろうか
kurumi☆
-----------------------------------------------

Thema music select &collage by tomtommama
story by kurumi

Thema music select &collage by tomtommama
story by kurumi
むしゃくしゃしていた
仕事のヤマが今日はちょっと外れて、僕は気晴らしに少しばかりの酒をあおった。
そして酔いを覚ますべく、宛ても無く街を歩いていた。
気がついた時にはいつの間にか、ダウンタウンの妖しげな薄暗い路地に
差し掛かっていた。
僕が彼女と初めて出会ったのは、ビルの隙間を抜ける風が頬に冷たい、
そんな初秋の頃だった。
辺りは既に日が落ち、街は淡いシルバーグレーに染まっていた。
まだ6時にもならないというのに、10月ともなると日暮れも早い。
その時、激しく抵抗するような女の甲高い声が僕の耳を劈いた。
その声の位置を探すと、細い路地で数人の男に絡まれている
若い女が僕の視界に入って来た。
しかし、そんな光景はこの辺りでは決して珍しくない。
女の方とて、“嫌だ”と言いながら、面白がっている場合もあったりするものだ。
いつもの僕なら、渇いた感情のまま、冷たく無視して通り過ぎただろう。
ところがどういうわけかその時、僕は立ち止まってしまった。
面倒なことに関わることほどバカらしいことはない。
≪そんなに暇じゃないんだ。≫そう思っていたはずなのに、
僕の足は自分の意に反して彼らの方へと向かっていた。
何故そうしたんだろう。それは・・・
その女が発していた言葉が“ハングル”だったからかもしれない。
僕は≪仕方なく≫というように大きく溜息を吐いて、路地の中へと足を進めた。
「止めろ。」 僕は女にしつこく絡んでいる男の肩に背後から手をかけた。
その瞬間、男が振り向きざまに僕に向かって振りかざした拳を
僕は難なく掌で受け止め、男の腕を後ろ手に捻りねじ伏せた。
男達はよく見ると皆、体は大きいがまだ17・8の子供のような年齢だった。
突然現れた見知らぬ僕に、彼らは次々に牙を剥いて向かって来たが、
ほとほと相手にならない程度のか細い腕力に、僕は正直肩透かしを食った。
結局男達は僕の攻撃に形ばかりの抵抗をし、銘々に罵声を浴びせながら、
そそくさとその場を逃げ去って行った。
そしてその場所に、僕と彼女だけが取り残された。
狭く薄汚いその路地のすえた臭いに僕は眉を顰めながら、視線を向けると、
彼女が細い肩を震わせているのが見て取れた。
しかし僕は慰めの言葉を掛けるでもなく、無言で彼女を見据えていた。
「あの・・・助けてくださって・・・ありがとうございます」
震えていた彼女がやっとのことで、僕に礼を言った。片言の英語だった。
僕は面倒くさそうに「いや・・」と言っただけで、彼女に背を向け
歩き出していた。
「あの!」 それでも彼女は僕の背中に向かって思い切り声を発した。
僕はお義理のように振り向き立ち止まると、投げやりに口を開いた。
「こんなところを女一人で・・・」
「えっ?」
「こんなところを・・・女一人で歩く・・・それは襲ってくださいと
言っているようなものだな・・・君にも十分落ち度がある」
僕は最初早口で言いかけたものの、彼女がまだ英語に慣れていなさそうだと察して
少しそのスピードを落として話した。
それでも彼女は僕の言葉が理解できないのか、首をかしげていた。
「その先の角を・・右に曲がったら・・タクシー乗り場がある
うろうろしてないで、さっさとここを離れることだ」
彼女の存在を正直面倒に思った僕は、最後は早口で言うと、
彼女の前から一時も早く立ち去ろうとした。
『あの!私!友人の家を探してるんです!
別に好きでうろうろしてたわけじゃないわ!』
彼女は突然怒ったような口調で僕に言った。興奮していたらしく、
自分の言葉がハングルになっていることに彼女は気づかないでいるようだった。
「そう。・・・じゃ。」
しかし僕はそのことを指摘するでもなく、敢えて英語で答えると、前へ進んだ。
『あっ・・・あの・・・あの!』 彼女の「あの」だけが急いで僕を追いかけて来た。
「何!」≪立ち止まらなきゃいいものを・・≫僕は立ち止まっていた。
『このまま・・・・・置いていくんですか?・・私を・・』
「どういうこと?」≪置いていく?≫
彼女が発した意味不明の言葉に僕は眉間に皺を寄せ振り向いた。
『うろうろしてたら、襲ってくださいと言っているようなもの、
あなたはそうおっしゃた・・・ここは危ない所なんでしょ?
そんなところに・・・私を置いていくんですか?』
「はっ?」
彼女の理不尽極まりない言い様に、僕は呆れてしまい、言葉を詰まらせた。
≪あのね・・君は今、僕に向かってハングルで話してるんだよ
僕に首をかしげられたって可笑しくないのがわからないの?≫
僕は心の中でそう言い返したが、言葉にはしなかった。
ただ、彼女がまるで「捨てていかないで」と見つめる捨て猫のようなまなざしで
僕に訴えかける必死な様子に呆れながらも、心の中で思わず笑ってしまった。
「何言ってるの?・・・いいかい?それは君の勝手。
君が何の理由で、ここにいようが、いまいが・・
僕には、全く、関係無い!わかった?」
僕はゆっくりと、やはり英語で、彼女の目としっかり視線を合わせ
小さな子供に言い聞かせるように言った。
彼女は大きな瞳を更に大きく見開いて、僕から少しだけ後ずさった。
はなから彼女の勝手な言い分に耳を貸すつもりなど毛頭無かった。
僕はまたそ知らぬ顔を決め込んで速度を速めて歩き出し、家路を急いだ。
しかし
僕の後ろを小走りについて来る彼女の気配が僕の足をまた仕方なしに止めた。
溜息を吐き出しながら、またもや振り向くと彼女も同じように立ち止まって
僕をまっすぐに睨みつけていた。
僕は呆れたようにもう一度これ見よがしに大きな溜息を吐いた。
「・・・いったい・・・何!」
僕が君に・・・
そんな目で睨まれる理由がどこにある?
「ついてくるな。」
彼女の振る舞いに僕は呆れるのを通り越して、少しイライラしてきていた。
『あ・・少し暗くなってきちゃったし・・・私あの・・・
迷っちゃった・・みたいなんです・・道に・・・だから・・・』
彼女は空を指で差しながら、相変わらず堂々とハングルを使い、
僕について来るその理由を正当化するように言った。
「だから!その角にタクシ・・・」 僕はつい怒鳴ってしまった。
≪まだ相手は子供じゃないか≫
僕は指差した手を振り下ろした拍子に自分のジーパンを手でバシンとはじかせた。
彼女はその音にビクリとして顎を引いた。
しかしその直ぐ後にまた、僕に向かって突き進んで来た。
『どうしても!探さなきゃいけないんです!
友人と連絡が取れなくて・・・同級生なんです
同郷で・・・どんな時も連絡くれてたのに・・・3日も・・・
3日も連絡が無くて・・・電話も通じなくて・・・』
≪だから?≫
「だから・・それと、僕と何の関係があるの?
その同級生・・君の!同級生。
その彼の家をこの僕が探して、君をそこへ送って行けとでも?」
僕はバカらしい、と言わんばかりに、それでも彼女に言葉が通じるように
ゆっくりと言った。
彼女は僕のその言葉に、苦笑いのように作り笑顔を向けて僅かに頷いてみせた。
「あのね。よく考えてご覧?僕に、そんな義理がどこにある?それに・・・
君が 誰に狙われようが、襲われようが
僕の知ったことじゃない! ああ、どうぞ?・・・
いたければこの辺でもどこでも・・好きなだけいたらいいさ」
僕が意地悪くそう言うと、彼女は次第にうるうると涙ぐんで見せた。
≪卑怯だぞ≫
『じゃあ、どうしてさっきは助けてくれたんですか?』
彼女は涙を堪えるためか、怒ったような顔になっていた。
≪オイオイ・・≫
「どうかしてたんだろうよ。・・・あのね。・・・僕は本当に。忙しいんだよ。」
彼はそう言い残して、私から逃げるように急ぎ足で立ち去ろうとした。
私はここで彼を見失ったら、きっと見知らぬこの街で途方にくれてしまう
そんな恐怖に慄いて、必死に彼を追いかけた。
本当に必死だった。
「いい加減に!」
僕はまた振り向きざま彼女を怒鳴りつけたものの、彼女の潤んだ瞳と
必死な形相に圧倒されてしまったようで、溜息をつくしかなかった。
「貸して!」
「えっ?」
「住所。書いたの・・彼の。・・・あるんでしょ!」
「あ・・はい!」 彼女は大急ぎで肩から掛けたバックの中をまさぐり、
そこから小さな紙切れを取り出した。
彼は私が差し出したメモを乱暴に取りあげると
さっと目を通して、私にそれを付き返してまた歩き出した
≪えっ?探してくれるんじゃないの?≫
『あの!待って!・・お願いです・・・
あの・・・私、アメリカに来てまだ一ヶ月しか経ってなくて・・・
地理に不案内で・・・英語も片言で・・・あ・・ごめんなさい・・
私・・・今・・・英語・・しゃべってなかった?・・・ハングル・・ずっと?』
≪でも・・彼に・・通じてた?・・≫
私は自分が今まで彼に向かって英語を使って
話してなかったことにやっと気がついた
でも彼はそんな私にずっと・・英語で答えていた?
≪韓国語がわかるの?あ・・今はそんなこと・・・≫
私は今、彼に見放されたらお終いとばかりに
大股で歩く彼の後を必死についていった。
「あの・・・お願いで・・す」
彼が急に立ち止まったので、私は彼の背中にぶつかって
止まるしかなかった。
「ここ・・・」
彼が顎をしゃくって目の前の薄汚れた小さなアパートを
指差した。
「えっ?」
「ここだよ・・・その住所」
彼はちゃんと探してくれていた
「あ・・・ありがとう・・ございます」 彼女は僕に深く頭を下げた
「じゃ・・」
そしてつまらない役目を果たした僕が今度こそはと、その場を立ち去ろうとすると、
僕の体は何かに引っ張られて止まった。
いつの間にか彼女が僕の袖をしっかりと掴んでいたのだった。
「今度は何!」
「あの・・一緒に・・・中へ・・・」 彼女が申し訳無さそうに言った。
「何で!いい加減に・・」
「プリーズ・・・お願いです・・・中がどんなか・・・
もし、彼に何か起こってたら・・・怖い・・・」
彼女が黒く大きな瞳をまたもうるうると潤ませて僕に懇願した。
≪ばかげてる・・・この僕が
何で、こんなことに関わらなきゃならないんだ・・・≫
そう思いながらも何故か彼女の切迫した瞳に縛られでもしたかのように、
僕は従わざる得なかった。
彼女が探している“彼”が住んでいるらしいその建物はかなり古いらしく
薄汚れていた。
入り口を入ると直ぐ二階へと続く階段が見えた。とてもエントランスとは言い難い
狭いスペースで、無論、エレベーターなどあろうはずもない。
≪こういうのをおんぼろというんだな≫
ろくに照明の点検などしていないだろう、薄暗く、細い急な階段を僕と彼女は
一列になってゆっくりと上へと進んだ。
彼女はさっきから、僕の袖を掴み体を硬くしたようにして、緊張を隠さなかった。
彼女のその緊張が僕に伝わって、僕までが知らぬうちに体に力を入れていた。
さっき知り合ったばかりのふたりが、同じ目的地に向かって、壁にピタリと
体を貼り付け、抜き足差し足で昇っていく。≪何とも滑稽な光景だ≫
「袖・・・」 僕は小声で彼女に言った。
「えっ?」 彼女も僕に合わせて小さな声で答えた。
≪袖が≫「伸びる」
「あ・・ごめんなさい・・・」
僕に言われて一度は慌てて離すものの、進み出すといつの間にかまた、
彼女は僕の肘の下で硬そうな拳をふたつ僕の袖につなげていた。
「三階だったよね」
さっきのメモにはそう書いてあったと思った。
「ええ、302」
天井も低い小さなアパートのせいか、三階へは直ぐに着いた。
そしてそのフロアを数歩進むと、目的の部屋も直ぐに見つかった。
「ここだ・・・」
僕が顎をしゃくって302号室を示すと、彼女はごくりと音を立てて息を呑んだ。
「どうしたの?ノックして」 直立不動のまま黙っている彼女に僕は言った。
「え・・ええ・・」
彼女は少し躊躇しながら、手を少し丸めて、その甲で小さくドアをノックした。
一度目のノックで応答が無かったので、彼女は二度目を試みた。
そして二度目のノックの後、彼女はドアにそっと耳を押し当てて、
その向こうの物音を確認するしぐさをした。
しかし何の反応も聞き取れなかったようで、僕に振り返って首を横に振った。
「どうしよう・・・」 彼女はほとほと困り果てたように肩を落とした。
「こんな古いアパート、管理人なんていないと思うよ
彼も留守なのかもしれない・・・諦める?」
僕の彼女への口調が少し柔らかくなっていたことに、自分でも驚いた。
「駄目!諦められない」
≪おいおい・・≫
僕はまた彼女の思いつめたような潤んだ瞳に負けてしまったようだ。
その証拠に次の瞬間、見知らぬアパートの見知らぬ人のドアを足で蹴破っていた。
思った以上の破壊力に、僕は思わず辺りを見渡してみたが誰も現れる気配が無く、
ホッとした。
破られたドアの向こうは廊下よりも薄暗く、最初間取りさえはっきりとしなかったが
かなり狭いことだけは想像に足りた。
何故なら、蹴破ったドアの先端が立て掛かった場所が少し高めに設えたベッド
だということが容易に知り得たからだった。
そのベッドは僕の目線よりちょっと低い位置にあり、その上にあったブランケットの
下に人が横になっているのが、その膨らみから伺い知れた。
「人が死んでる・・・」 僕は神妙な声でそう言った。
≪本当にそう思った≫
僕のその言葉を聞いて、彼女は僕にしがみついて、さっきより更に震えていた。
僕はそのベッドのブランケットの中に恐る恐る手を入れてみた。
「温かい・・・大丈夫・・・死んではいない」
僕がそう言うと、息を呑んでいた彼女の緊張と恐怖が僕の横で少しばかり
解けるのを感じた。
≪とにかく・・・≫
明かりが欲しくて壁のスイッチを見つけて押してみたが無駄だった。
きっと電気を止められたか、故障しているのだろう・・・
僕は取り敢えず窓のカーテンを開けた。
部屋の間取りが外の月明かりで少し浮き上がり、ベッドに寝ている人間の顔が
うっすらと確認できた。
「彼だわ・・・」 彼女は作りつけのベッドに掛かった細い梯子をよじ登り確認した。
「・・・・熱があるみたい・・・」
ベッドの中の男の額に手を当てていた彼女が窓際にいた僕に向かって言った。
僕は彼女と入れ替わりに梯子を上ると、彼の脈を取り、ライターの灯りで眼球を覗いた。
「風邪でも引いて・・・今、眠ってるだけだろう・・・」
僕は彼女に安心するように言った。
僕達が乱暴に侵入して、こうして眼球まで覗かれるという荒行に何の反応も
示さないとなれば、かなりの重症かもしれない。
「少し額を冷やしてあげるといい・・・朝目を覚ましたら
病院に連れて行って・・・」
「あなたは・・・お医者様?」 彼女が突然そう言った。
「医者でなくても、それくらい検討はつく・・・
じゃあ、僕はこれで・・」
「えっ?」 彼女の目と、僕の袖を掴んだ手が≪帰るんですか?≫と聞いた。
「あのね・・・甘えるのもいい加減にして・・・
僕がこんなところまで付き合うこと自体、可笑しいと思わない?
彼を見つけられたんだから、僕はもう用済みでしょ?」
「でも・・・もし、急に彼の具合がひどくなったら・・・私・・・
どうしたら・・・」
「知らないよ・・・そんなこ・・・・」
僕は呆れたような声を出して、今度こそはと彼女を振り切ろうとしていた。
≪また・・・そんな目で見る・・・≫
「わかったよ・・・彼が目が覚めるまで・・・いればいいんだろ?」
僕は決してお人好しな人間ではないはずだった。
「ありがとうございます・・ありがとう・・・ごめんなさい・・・
勝手なお願いだって・・・わかってるんです・・・ごめんなさい・・・」
「もういいよ・・・何かタオルのようなもの探して?・・・
冷やした方がいい・・」 僕はそう言って、彼を指差した。
「あ、はい」 彼女は瞬間、瞳を輝かせた。
そしてさっき僕が蹴破ったドアの向こうに備え付けられた小さなシンクを見つけると
その横に掛けられたハンドタオルを水で濡らして絞り、彼の額に乗せた。
その間、僕はその壊されたドアを元の位置に戻して、そばにあったチェストを
利用してそれを支えた。
今日はかなり冷えていたが部屋の中は暖房器具のひとつも無く、立付けの
悪い窓枠の隙間とさっき壊したドアのせいで、外以上の冷えこみを感じた。
「寒い?」
自分の体を抱くようにして震えている彼女に僕は、わかりきったことを聞いた。
「ええ・・・少し・・・」
「彼が羽織っているもの以外・・・無さそうだね・・・ブランケット・・・」
「大丈夫です」
台所と言っても、お湯を沸かすコンロも無く、温かいものを飲むことも
出来そうになかった。
「何か温かい飲み物、買ってくるよ」
「駄目・・・行かないで・・・」
彼女はまた僕の袖を掴んで哀願するように僕の目を見つめた。
「大丈夫・・・逃げたりはしないよ・・・待ってて・・・」
僕は彼女の頭に掌を置いて、まるで子供を宥めるようにそう言った。
逃げたりはしないよ・・・待ってて・・・
僕はつい彼女にそう言っていた。≪何を馬鹿なことを言ったんだろう・・・≫
この僕があの子に付き合う義理が何処にあるというんだ。
僕は自動販売機の前でジーンズのポケットの中から出したコインを指で弄びながら、
いっそこのまま黙って帰ってしまおうかと考えていた。
それなのに僕は結局、温かいコーヒーを二本買ってしまった。
そして、素手で持つには少し熱過ぎる缶をジャンパーの両のポケットにひとつずつ
入れて、僕は今来た道を足早に引き返していた。
僕が三階までの階段を三段飛ばしで駆け上がると、彼女が見えた。
彼女はドアの外に出て僕を待っていたようで視線の先に僕を見つけるとまるで
迷子の子供が探していた親をやっと見つけたかのように瞳を輝かせ僕に向かって
走って来た。
そしておもむろに僕に抱きついた。
「どうしたの?」
その時僕も、自分の意思とは考えにくい行動を取っていた。
僕は彼女の背中に自分の腕を回し、彼女をしっかりと抱き止めていた。
そしてそれを不思議なことだとは思わなかった。
『帰って来てくれないかと思った・・・』 彼女は僕の腕の中でそう言った。
≪また・・・ハングルになってるよ≫ 僕は心の中でそう思いながら
「逃げないって・・言ったでしょ・・さあ、中に入ろう・・」
彼女を優しく宥めていた。
中に入って彼女は椅子の上からブランケットを手に取り胸に抱えると
僕に向かって初めての笑顔を向けた。
「ロッカーの中にあったの・・・一枚だけだけど・・・」
ものすごい宝物でも見つけて来たかのように、嬉しそうに微笑む彼女が
一瞬愛しく思えて、僕は思わず首を振った。
「あの・・」 彼女が僕の様子に、ブランケットを抱えたまま戸惑っていた。
「良かったね・・・寒いから掛けるといい・・・」
僕はそう言いながら、そのブランケットを肩に掛けてあげようとした。
「いいえ・・・あなたに・・・」 彼女はそう言ってブランケットを僕に押し返した。
「僕に?・・僕はいいよ・・・君こそ、寒いでしょ?」
「私は大丈夫です」 僕は思わず声を立てて笑ってしまった。
いくら寒いからといって、女の子を放って自分だけ暖かい思いをしろと?
「可笑しいですか?」
「あ、いや・・・そうだ。」
僕は彼女からブランケットを受け取ると自分の肩にそれを掛けて、一人掛けのような
小さなソファーに隣に少しスペースを空けて腰を下ろした。
そして僕は自分の右側に無言でブランケットで空洞を作り、彼女に入るように目で
合図した。
彼女は最初躊躇っていたものの、にっこりと笑ってごく自然に僕の腕の中へ、
いや・・暖かそうなブランケットの中に入って来た。
僕はブランケットを二人の前で重ねるように合わせると、その中でさっき買って来た
コーヒー缶をポケットから取り出し彼女の手に握らせた。
「暖かい・・・」 彼女は本当に温かそうにそう言った。
「君・・・おかしな人だね・・・」
「・・・・・?」 彼女は「ん?」というように僕を見上げた。
「僕が君を・・・さっきの男達みたいに襲うとは思わないの?」
「思いません。」 彼女は自信有りげにそう言った。
「どうして・・・そんなに・・」≪初めて会った僕を・・・≫
「信じることができるの?」
「どうして?・・う~ん・・目・・です」
彼女は少し顔を持ち上げて天井を見上げると考えるしぐさをしてそう言った。
「目?」
「あなたの目が澄んでいて・・・とても綺麗だから・・・」 またも彼女は自信たっぷりに
そう言った。
「そんなこと・・・言われたことないや・・・」
「そうですか?」
「一度もね」
「でも・・・私の勘、当たるんですよ」
僕はまた声を立てて笑った。
彼女は首をかしげて、「どうして笑うの?」と僕を可愛く睨んだ。
さっきからどうしてここにいなければいけないのかと悶々としていた僕が
この数時間の間にいつしか彼女とこうしていることに疑問を持たなくなっていた。
≪それは・・・何故だろう・・・≫
それは・・・
僕の横で寒さに少し体を硬くしてうつむいた彼女の長いまつげが・・・
あまりに美しかったからかもしれない。
「そんなに信用されたら・・・何も出来ないね・・・」
僕はそんな冗談を言いながら、自分の心の変化を面白がっていた。
「えっ?」
「いや・・・何でもない・・・」 僕は彼女から視線を逸らした。
一瞬、さっきの自分の言葉が、決して冗談ではなかったことに、
僕自身が気づいてしまった。
僕と彼女との突然の出逢いはこうして始まった・・・
この時
僕達はまだ・・・互いに名前すら・・・
・・・知らなかった・・・
| <前 | [1] ... [31] [32] [33] [34] [35] [36] |