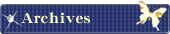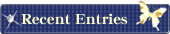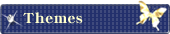創作mirage-儚い夢-24.いじわる

「ねぇジニョン・・・キスしていい?」
僕は後ろから彼女をしっかりと拘束したまま、彼女の耳元に囁いた
「ドンヒョクssi・・・そんなこと・・・聞かないといけないの?」
彼女はまたいつものようにそう言った。
「僕は紳士だから・・・」
「紳士?・・紳士ね~・・・じゃあ、淑女の私は・・・そんな時どう答えれば?」
「んー・・・どうぞ・・って・・・」
「えー・・・そんなの何だか変だわ・・・」
「じゃ・・こうやって・・“いいわ”・・・とか?」 僕は唇を突き出して見せた。
「えー・・・!」
人一倍照れ屋の彼女をからかうのは実に楽しい。
目の前で彼女がみるみる頬を赤く染めていき、一生懸命に僕の言葉を切り返そうとする。
さっき僕を・・・泣かせた罰だよ・・・
ちょっとだけ意地悪させて
「いいから・・・していい?」
僕は照れ隠しにおしゃべりを絶やさない彼女の顎を、クィッと後ろ向きに誘導すると
真顔で彼女の答えを待った。
「いい?」
「だから・・いちいちそんなこと・・聞かないで・・・」
「言ってくれないとできない・・・」
彼女は僕から視線を落として、更にその頬が真っ赤に色づく。
僕はその顎を指で持ち上げて彼女の瞳の中に僕を戻した。
「言って・・・“いいわ”って・・・」
あまりに真剣な僕の眼差しに彼女がやっと観念する。
「い・・いいわ・・・」
震えたようなその返事に僕は薄く微笑んでそっと唇を合わせた。
僕の唇と彼女の唇がゆっくりと触れ合って、互いを確かめるようになまめかしく音を立てた。
次第に濡れゆく彼女の唇を軽く啄ばみながら、彼女の吐息さえ許さないほどの
執拗なくちづけに変えていく。
彼女の右手が僕の胸を押し息苦しさを訴えると、僕の腕が彼女の背中をグイと引き寄せた。
彼女のまだ少し濡れた髪が僕の指に絡んで冷たかった。
僕は唇を離さないまま、彼女を抱き上げそのままベッドへと運んだ。
ふたり同時に倒れ込むように横たわりスプリングを弾ませる・・・
その拍子にふたりの唇が離れて、彼女の吐息が小さく漏れた。
そして僕はまた、ジニョンを真顔で覗き込んでわざと尋ねる。
「抱いてもいい?・・・」
「だ・・駄目って言ったら・・・ど・・どうするの?」
「どうしよう・・・」
「どうしようって・・・」
「どうして欲しい?」
「どうして欲しい・・って・・・」
「あ・・今・・何を想像した?」
「何も・・想像したりなんか・・」
「言ってごらん?・・・」
「・・・・・・」
彼女が少しべそをかいてきた・・・
「フラ・・ンク・・・どう・・して・・・そんなこと・・」
「君のその反応が見たくて・・」
「・・・・・・」
この辺で・・・止めないと、本気で拒絶されそうだね
「ドンヒョクって・・・フランクよりも意地悪な人?・・・」
「そうかも・・・」
僕は彼女がまだつむじを曲げない内に、急いで彼女の首筋に唇を這わせた。
そして・・・ゆっくりと彼女を少女から女へといざなう。
「いじわるして・・・ごめん・・・」
「許せない・・・」
「愛してるから・・許して・・・ジニョン・・・」
愛してる・・・愛してる・・・愛してる・・・愛してる・・・
言葉にするのももどかしいほどに・・・
だから・・・少しばかりの意地悪は大目にみて・・・
僕の・・・君への愛しさが・・・溢れすぎて・・・
君の白く滑らかな肌に零れ落ちていく
そして・・君は・・・
「もう・・・許したでしょ?・・・」
「い・・・」
じ・・・わ・・・る・・・
君に伝えたい僕の愛を、ひとつひとつ君の吐息と絡めながら
いつしか僕が君に埋もれていく・・・
あぁ・・・ジニョン・・・
僕は・・・このまま・・・
君の中に沈んで・・・しまいたい・・・
「やっぱり・・・ベッドから空が見える方がいいな~」
「うん・・・今度用意するときはそうしよう」
「あ・・でも、ここも素敵よ・・・自然がいっぱいで
気持ちいいもの・・・」
「じゃあ、あそこ・・・開けちゃう?」 僕はそう言って天井を指差した。
「ふふ・・」
「明日・・業者に聞いてみるよ」
「・・・・・ドンヒョクssi・・本気なの?
いいわよ、そんなことまでしなくても・・・」
「言っただろ?
僕は君のやりたいことは何でも叶えるって」
「でも・・・」
「ジニョン・・・明日は少しドレスアップして、街へ出掛けないか」
「え?だって明日は・・お仕事・・・」
「夕方までには必ず終わらせる・・・迎えをよこすから
君は準備していて?」
「でも・・・ドレスアップって・・私・・ドレスなんて・・・」
「こっち来て?・・・このクローゼット開けてみて」
僕は彼女のその言葉を待っていたとばかりに、彼女をクローゼットに誘導した。
ジニョンは不思議そうな顔をしながら、バスローブを羽織るとベッドを降りて
僕に近づき、クローゼットの扉を開けた。
そこには事前に用意した数着のドレスやワンピースなどが隙間無く掛けられているはずだ
。
「どうしたの?これ・・・」
「皆、君のものだよ・・・靴もアクセサリーも
下着も用意してある・・・
サイズは・・・多分、合ってるはずだけど・・・」
「下着も?・・・
サイズなんて聞かれたことあったかしら?」
「いいや・・・大体だよ」
そう言いながら僕は両手で輪を作って彼女を抱いている仕草をして見せた。
「ドンヒョク・・・いいえ・・フランクって・・・
いつも女の人にそうやってプレゼントするの?」
彼女は少し口を尖らせて僕を睨みながらそう言った。
僕は当然彼女が喜んでくれるものと思っていた。
「心外だな・・ジニョン・・・女の人に洋服や靴なんてプレゼントしたの初めてだよ
それに、サイズはソフィアが教えてくれた」
「ソフィアさんが?・・彼女にそんなこと聞いたの?」
「何を準備すればいいだろうかって・・・そしたら
着の身着のままだろうから、すべて準備なさい・・って」
「フー」
彼女は呆れ顔を少しオーバーに現して僕を再度睨んだ。
「何?」
「ソフィアさんの部屋・・・あなたのレイアウトでしょ」
「そうだよ・・・」 僕はあっさりと答えた。
「・・・・・・」 ジニョンはそのことが不満だったらしく、僕を更に睨んだ。
「何?」
「・・・・あなたって・・ソフィアさんの言う通りね」
「言う通りって?・・彼女、何を言ったの?」
「女心がまるでわかってない。」
僕を睨みつけた彼女がわざとらしくため息を吐いて、くるりと背を向けると寝室を出て行った。
そしてバスルームに駆け込んだかと思うと、そこからなかなか出て来なかった。
僕は彼女のそんな様子に、愚かにもたじろいでバスルームのドアを叩いた。
「ジニョン!僕、何か悪いことした?
何怒ってるの?出て来いよ!ジニョン!・・・」
「怒ってないわ!シャワー浴びるの!」
投げつけるようなジニョンの声が中から届くと、僕は余計に困惑した。
「じゃあ・・・僕も一緒に・・」
「駄目!」
「ジニョン!?」
僕はジニョンがシャワーを浴びている間、そのドアの前に座り込んで、
彼女が急に怒った理由を尋ねていた。
「ねぇ、ジニョン・・教えてよ・・どうして怒るのさ
洋服を勝手に用意したから?君の趣味に合わなかった?
僕が下着まで用意しちゃったから?
それは僕が買ったんじゃないよ・・業者の人間に頼んだんだ
それとも・・・他に理由が?
ソフィアの部屋のレイアウトがどうのって・・言ってたね
それがどうかしたの?・・・」
「・・・・・・・」
「ねぇ・・・」
「そこどけて!出られない!」
「あ・・ごめん・・・」
僕が慌ててドアから離れると、まだ怒ったままの顔の彼女がやっと中から出てきて、
僕の横をすり抜けた。
僕は、その後を、くっ付きそうなほどにぴったりと付いて歩いた。
「ねぇ・・教えてよ・・・何を怒ってるの?」
僕は彼女の後を追いかけながら、彼女のご機嫌をおろおろと伺っていた。
何で僕がこんなことを?
「何でもないわ」
「何でもなくはないでしょ?・・・十分怒ってる顔だけど」
「・・・・・」
「ジニョン!」
「何でもない!」
彼女が急に立ち止まり僕に振り向くと、決して何でもなくはない表情を僕に向けた。
「改めてわかったわ!あなたって!・・・」
「あなたって?」
「・・・・・・・・・何でもない!」
「それはないだろ?言いかけて止めるのはルール違反だって
いつも君が言ってることだぞ?」
「言いたくないの!」
「言わなきゃわからないことだってあるでしょ?!」
「言ったら、嫌な女になっちゃう!」
「ジニョン!」
僕は彼女の両手首を掴んで、背ける彼女の顔を無理やり振り向かせた。
彼女の目から溢れる大粒の涙が、それまで彼女の行動に少しばかりむっとしていた僕を
一瞬にして萎えさせた。
「ジニョン・・どうして?・・泣くの?・・・
お願い・・・言ってくれ・・・
君にどんなことをしてあげたら喜んでもらえるのか・・・
僕はあんなことしか、思いつかない・・・
好きな人に喜んでもらえることが何なのか、何ひとつ知らなくて・・・
今何故、君が怒るのかがわからない・・・」
僕は本当に困惑してそう言った。
すると不意に彼女が歪めた顔を僕の胸に埋めた。
そして僕に回した両手を僕の背中に食い込ませた。
「・・・・・・嫌な女だわ・・・私・・・あなたが・・・
ソフィアさんを大切な人だと言った・・・
そのことがいつまでもひっかかってる・・・
ソフィアさんは、フランクはこの部屋に入ったことない・・・
そう言った・・・でも、それはきっと私を気遣ってのことよ・・・
わかってるわ・・・でも・・・やっぱり嫌・・・」
「あ・・・」
「あなたとソフィアさんは恋人同士だった・・・
割り込んだのは私の方なのに・・・
彼女は凄く優しくしてくれた・・・それなのに・・・
あなたと彼女のことを考えるといつも胸が苦しくなる・・・」
「ジニョン・・・僕は彼女の部屋に入ったこと無いよ」
「・・・・・」
「確かに彼女の部屋のレイアウトは僕・・・
家具も僕が選んだ・・・今時はね・・・ジニョン・・・
パソコン上でレイアウトも簡単にできるんだよ・・・
彼女に頼まれて僕がコーディネイトした・・・
でも・・玄関先にも行ったことがない・・・本当だ・・・
ソフィアが入れてはくれなかった・・そう言った方が正解かもしれないけど・・・
彼女はそんなことで君に嘘なんかつかないよ
そんなに・・・彼女のことが気になる?
僕が言った言葉が君を傷つけてるの?・・・
ソフィアを大切な人だと言ったこと・・・
でも・・・僕はただ君に嘘をつきたくなかっただけだ
彼女がいなければ、今の僕はなかった・・・
そう言うとまた君を傷つけることになる?・・・
でも・・・その事実を話さないでいることは逆に
君への裏切りのような気がした
僕は君を・・・真直ぐに見つめていたい・・・
君にも偽りの無い本当の僕を見つめていて欲しい・・・
もう僕は・・・君を失えないんだ・・・
誓うよ・・・
これから先・・・どんなことが起ころうと・・・
僕の心は君だけにしか向かわない・・・
だから・・・僕を・・僕の心だけを見て・・・」
彼女は無言のまま、僕に回して作った拳に力を込めた。
「・・・・・・ドンヒョクssi・・・・・・」
「ん?」
「あなたにはきっと・・・女心は一生わからないわ・・・」
「そうなの?」
聞かなかった方が苦しくないこともあるのよ・・・
フランク・・・
「でも・・・いいわ・・・私に話すことは全て本当のこと・・・
それは私だけの・・・ドンヒョクssiの心・・・そうなのね・・・」
ソフィアさんが言ったわ・・・
フランクの心は・・・あなたには重すぎる・・・
でも・・・
それでも・・・私は・・・
あなたの心を背負いたい・・・
「ん・・・」
「ドンヒョクssi・・・私、行きたいところがあるの・・凄くおしゃれして・・・」
「何処?」
「Three Hundred roses・・・」
「Three Hundred roses?・・・ラスベガスの?」
「NYにもできたのよ・・・あの高級レストラン・・・
一度行ってみたかったんだ」
「ああ・・いいよ・・・じゃあ、早速予約入れよう・・
美容室の予約も入れておくよ・・・」
「うん」
「機嫌直してくれた?」
「ごめんなさい・・・」
「じゃあ・・・キスしてい・・」
「だか・・・ぅっ・・」
ごめん、もう・・・
・・・聞かない・・・
創作mirage-儚い夢-23.恋しきもの

「ボス・・・新しい棲みかの住み心地はどうだ・・・」
「ああ・・悪くない・・」
「そうか・・・それは良かった・・・・」
「・・・何の用だ?・・・三日間は電話もしない約束じゃなかったか」
携帯電話の着信音が鳴った時、僕は思わず眉をひそめていた。
案の定、受話器の向こうから聞こえてくるレオの声は、僕の反応を予想したかのように
言葉を濁ごして歯切れが悪かった。
「悪いが明日NYへ戻ってくれないか」
「・・・・・」
「すまない。しかし・・・今度の案件について早い内に
耳に入れておきたいことがある」
「今、話せ。」
「いや・・・直接会って話したい。・・・明日午後1時
いつものところで・・じゃ」
「おい・・」
レオは僕の返事をわざと聞かないというように急いで電話を切った。
最近レオは僕の操縦方法を心得ているように思う時がある。
僕への意見や忠告も、是が非でも通さなければならない時には僕に有無を言わせない。
癪に障ることもあるが、結果としてそれは正解だと言えた。
だからこそ、そのレオが今、僕にNYに戻ることを要求するということは、
それなりに大きな理由があることだと僕も理解せざるえないのだ。
『お仕事なの?』
「ん・・」
ジニョンは濡れた髪をタオルで拭きながらシャワー室から出て来ると
彼女をひとりでここへ置いていくことを考えてうなだれていた僕を気遣うように
優しげに声を掛けた。
『NYへ?』
「ん・・」
『明日?』
「ん・・・ジニョン・・ごめん」
『ケンチャナヨ』
「・・・・・・」
『ケンチャナ・・・フランク・・・私は大丈夫・・・
ここであなたを待ってるわ・・・』
「ジニョン・・・」
ジニョンがさっきから僕に話す言葉がハングルであることにとっくに気付いていたが、
僕は敢えて英語で返していた。
「どうしたの?」
『え?』
「ハングル・・・」
『わかるんでしょ?フランク・・・』
「忘れた・・とっくに・・・」
『嘘ばっかり・・・
私、興奮すると時々英語使わないでハングル使ってたでしょ?
それでも・・あなたとの会話・・不自由したこと無いわ
あなたの答えはいつも英語だったけど・・・」
「フッ・・・」
『私といる時はハングルを使って?・・・フランク・・・』
「どうして?」
『あなたが祖国を忘れないように・・・』
祖国?・・・
「・・・・・・・祖国じゃない。」 僕は強く拒否するように言った。
『祖国よ。』
力強い瞳の彼女を前に僕は思わず下を向いて笑った。
さっき話した僕の身の上話のせい?
それで・・・ハングル・・なの?
『可笑しい?』
「いや・・・可笑しくない・・・」
『フランク・・・その笑い方・・・感じ悪い。』
ジニョンはそう言って、瞳に軽く力を入れて僕を睨んだ。
「フッ・・・きっと・・・そうだな・・・
僕が・・・君に初めて出逢った時・・・
あの場所で足を止めたのは・・・君のそのハングルのせいだった・・・
君と・・・ジョルジュが話すハングルに無性に腹が立っていたのは
君達が羨ましかったから・・・そうなのかもしれない・・・
きっと嫉妬していたんだ・・・君達の交わす・・・懐かしいハングルに・・・
もう二度と使うまいと決めていた・・・
世界中の言語の中で・・・一番嫌いだった・・・
僕は・・・僕という存在を否定した韓国が嫌いだった。」
『・・・・・・・』
「でもそうじゃなかったんだ、きっと・・・一番・・・恋しい国だった・・・
一番耳に優しい原語だった・・・
君の話すハングルがどれだけ僕の心に沁みたのか・・・
きっと、君には想像もできないよ・・・
だって・・・僕自身・・・今・・初めて気がついたんだから・・・」
そう言って僕は彼女に向かって微笑んだ。
『フランク・・・』
「僕は素直じゃないね・・・」
『そうね・・・あなたは素直じゃないわ・・・』
『ミアネ・・・ジニョンssi・・・』
『フラ・・ンク・・・?』
『ドンヒョク・・・』
『え?』
『シン・ドンヒョク・・・僕の韓国名・・・それが・・・
僕の本当の名前・・・“ドンヒョク”・・・言ってみて・・・』
僕は彼女の瞳を真直ぐに見つめて『ドンヒョク』という名をハングルでゆっくりと発音した。
『ドン・・ヒョク・・・・・ドンヒョク・・ssi・・・
あぁ・・何だか・・・素敵な響きだわ・・・ドンヒョクssi・・って・・・』
彼女は僕のその名前を輝くように音にした。
たった今まで、心の奥底に封印され続けた僕の幼い日の心の拠り所が
まるで・・・暗闇の中から・・・ジニョンという光に導き出されていくようだった。
そうなんだ
女神のような彼女の微笑みに僕は完全に降伏していた。
『ジニョン・・・おいで・・・』
僕は彼女の手を取ると力強く引き寄せて自分の膝の上におろした。
そして彼女の肩に掛かったタオルで彼女の髪を包み込み、思い切り力を込めて
乱暴にその髪を拭き始めた。
『痛いわ!フラン・・・ドンヒョク!痛い!』
『黙って!急いで乾かさないと、風邪引くだろ?』
『でも、痛いわ!もう少し、優しくして!・・ドンヒョクssi!・・・』
『駄目!』
駄目だよ・・・今は駄目・・・
お願いだから今はこのまま僕に背を向けていて・・・
せめて・・・
僕達の会話は今を境に英語からハングルに変わり、彼女が僕を呼ぶ名は「ドンヒョク」と
なっていくのだろうか。
シン・ドンヒョク・・・
11年もの間、僕は誰にもその名で呼ばれたことが無い・・・
「あなたは今日からフランク・・・」
そう言われたあの日から・・・抵抗する術も知らなくて・・・
ただ・・・
・・・心で叫んでいた・・・
僕はフランクなんかじゃない・・・ドンヒョクだと・・・
それがいつの頃からか・・・
僕自身も拒絶してきた父がつけたドンヒョクという名・・・
その僕の名が、今・・・愛する人の声で蘇った
ジニョン・・・お願い・・・もっと・・・
もっと呼んで・・・僕の名を・・・君の声で呼んで・・・
もっと・・・もっと・・・ジニョン・・・
しばらくすると・・・
さっきまで抵抗していた彼女が突然大人しくなって
僕がするままに身をまかせ、そしてゆっくりと僕にもたれかかった。
きっとそれは・・・
僕はそのまま彼女を受け止めるように優しく、力強く抱きしめると、
彼女の背中に顔を埋めた。
きっとそれは・・・
僕の涙に気がついたせいだね・・・ジニョン
君が静かに・・・
僕の心が落ち着くのを待っている・・・
君がそっと・・・
君に回した僕の腕を抱いてくれる・・・
言葉のいらない静かな時の流れを・・・
僕は君とふたり・・・
漂う幸せに酔いしれていた・・・
コマウォ・・・
コマウォ・・・ジニョン・・・
創作mirage-儚い夢-22.告白

「星がいっぱい・・・」
「ん・・・」
「綺麗ね~」
「ああ、綺麗だ」
夕食を済ませると僕は、ジニョンを抱いてテラスに置かれたロッキングチェアーの上で
満天の星を見上げていた。
今日一日、食料品や日用品の買い物以外を新しい家の周辺を散策しながら
静かに時間(とき)を過ごした。
彼女とふたりで今夜のメニューを考えながらスーパーのカートを押し、
彼女との約束の釣竿も買って、明日からのふたりの生活を夢見ていた。
他の誰の姿も無く、誰の声も無く、今このときに存在するものは、そよと吹く風の流れに
重なり触れ合う葉の音と、小さくこだまする小鳥の囀りと、そして・・・
僕の・・愛しい・・ジニョン
今までただの一度も味わったことのない、この安らぎのときを僕は決して離すまいと
幾度も幾度も彼女を抱きしめていた。
彼女への、えもいわれぬ愛しさに恐れさえ抱き、神に祈る思いで天空を仰ぎ見る。
都会の空とは比べ物にならないほど輝きを放つ星ぼしが、まるで僕達ふたりを
無条件に祝福しているかのようで心から安堵した。
この僕がそんな感傷に浸たりきることができるのも・・・きっと・・・
この腕の中で無邪気に笑うこの天使のせいに他ならない。
「私ね・・・」
「ん?」
「フランクのアパートで見上げる星空・・・すごく好きだったの・・・
まるで・・・窓枠が額縁みたいで・・・
夜空が一枚の大きな絵のようだったから・・・」
「曇り空で・・真っ暗でも?」 彼女が星空を見たくて僕の部屋に来るという大義名分が、
時折、天空に裏切られていたことを、僕はそう言ってからかった。
「意地悪ね・・・」 彼女はクイと顎を上げて、上目遣いに僕を睨んだ。
「あなたの部屋に行っても・・最初の頃・・・あなたは・・殆ど話しかけてくれなくて・・・
すごく寂しかった・・・ぁ・・確かにね・・・あなたのそばで過ごせてる・・・
それだけでも幸せだったの・・・それは本当よ・・・
星が空一面に輝いている日はいいの・・本当に綺麗で・・幸せな気分に浸れてた・・・
でも・・・曇ってて・・真っ暗な夜空の時は・・
ちょっとだけでもあなたの声が欲しかったりしたわ・・・
あなたってそんな時も・・・すごく厳しい顔をして仕事していて・・・
怖いくらいだったから・・・」
「君が勝手に来てたんだ」
「そうだけど!・・
確かに私が・・勝手に押しかけて来てたけど・・・
ちょっと位相手をしてくれてもいいんじゃない?そう思って・・
あなたのこと、うんと睨んでやったわ・・・」
知っていたよ・・・
「それなのにあなたときたら・・私のそんな気持ちにも気付いてくれなかった」
彼女はそう言いながら・・・今きっと口を尖らせている
「忙しいって・・言ってただろ?」
こんな風に、自分の腕に抱いている彼女をからかうのは実に楽しい。
彼女の抑揚をつけた話し方や甘い声があまりに可愛くて・・・
彼女のそばにいるだけで心が穏やかになっていく、そんな自分を僕は楽しんでさえいた。
「仕事がそんなに大事?・・いつもパソコンをこーんな顔して睨んでて・・・
私のことなんて眼中になかったもの・・・」
彼女は自分の目尻を上に吊り上げながら、僕の顔を真似ているらしかった。
「・・・・・そう見えた?」
「見えた。」
それは君の誤解だよ・・・
「確かに・・・君がいることさえ忘れてた・・・
あー・・きっと、僕は君に少しの興味もなかったのかも」
「え・・・本当に?」
「ん・・本当に・・」
「・・・・・・・・・」
そして僕は僕のからかいに彼女が次第にひしがれて、沈黙し始める頃、
そろそろと自分の本心を打ち明ける。
「嘘。・・・・本当はずっと気にしてた・・・君のこと・・・」
君が夜空を見上げながら瞳を輝かせていたことも・・・
「・・・・・・・・・」
時折僕の方を盗み見て・・・可愛い表情を雲らせていたことも・・・
「眼中になかったら、最初から部屋に入れたりしないだろ?
君の視線が僕に向いてない時・・・僕はしっかり君を見てた・・・」
君がどんなに僕を見ていたか・・・全部・・・知っていた・・・
「ホント?」 人一倍素直な彼女が一瞬にして笑顔を満面に変えた。
「ん・・・」
そうだ、君が言うように・・・僕もたまにはうんと素直になってみよう
「フランクってば・・やっぱり、可愛くないわ」
「ハハハ・・可愛いって・・どういうのを言うの?」
「そんな時、ちゃんと素直な気持ちになってくれてたら
毎日がもっともっと楽しかったのに・・・」
「・・・・ホント・・・そうだね・・・」
本当に・・・もったいないことをした・・そう思うよ
僕は彼女の細い体をぎゅっと強く抱きしめると、ふたりを包んだブランケットの
合わせを深く重ねた。
「寒くない?」
ジニョンは僕の胸の上で頭を左右に振った。
「・・・ねぇ・・・覚えてる?・・・」
「ん?」
「初めて逢った時もあなたが・・・
こうして、私をブランケットに包んで温めてくれた・・・」
「覚えてるさ・・・あの時は君の気迫に僕は君の言うなりだった」
「気迫?」
「そう・・・私を置いていくの!って・・凄い勢いだった。」
「フフ・・・だって、必死だったもの・・・」
「彼の為に?」
「ぁ・・・その時は・・・」
「ジニョン・・・僕を好き?」
僕は自分から聞いておきながら彼女の言葉を遮って、抱きしめていた腕に更に力を込めた。
「好きよ・・・」
「愛してる?」
「愛してるわ・・・・」
彼女は僕の神妙そうな問い掛けに、少し体を僕の方に翻して、怪訝な表情を向けた。
「・・・・・・・」
「・・・・フラ・・ンク?・・・」
「僕はね・・・つい最近まで・・・この世の中に・・・
僕を愛してくれる人なんてひとりもいない・・・そう思って生きていた・・・」
「・・・・どうして?・・・」
「・・・昼間・・僕が何処で生まれたのか・・・そう聞いたよね・・・」
「ええ・・・でも・・・話したくなければ・・」
「東海・・・」
「東海?・・・韓国の?」
「ん・・・」
「ぁ・・・だから・・・ハングル・・・」
「10歳の時・・・母が死んで・・僕は孤児院に預けられたんだ・・・
最初のうちはね・・・父が直ぐに迎えに来る・・そう思ってた
母が亡くなって・・きっと忙しくて・・それで僕は家に帰れない・・
それだけのことなんだって・・・
いつ父が迎えに来てくれるのか・・・・指折り数えてた・・・
窓から孤児院の門を、来る日も来る日も覗いてた・・・
でも・・父はとうとう現れなかった・・・
その内諦めて・・・僕は窓のそばにも立たなくなった・・
そうしている内にアメリカへの養子縁組の話が持ち上がって・・・
僕の知らない間に大人たちの間で話は進められていた
父はね・・・結局・・・
僕がアメリカに発つまで会いには来なかったよ
僕に合わせる顔がなかったのか・・・
それとももう・・僕のことなんてどうでも良かったのか・・
本当のことは何ひとつわからなかった
だけどその頃には僕にとって、そんなこと・・もうどうでも良くなっていた
父からどんな弁明があったところで・・・
父は僕を捨てた・・・
そのことに変わりなかったから・・・
何が何だかわからないまま飛行機に乗せられて・・海を渡った・・・
そして突然・・“この人たちが今日からお前のお父さんとお母さん”・・・
そう言われて紹介された人たちは・・・話す言葉すら違ってた・・・
もちろん・・孤児院を出る前に話は聞かされてたよ・・・
養父母となる人たちがアメリカ人であることや・・・
彼らには実子はいないけど・・
僕の他に、他国からも養子を迎えてること・・・
敬虔なカトリック信者で・・・ボランティア精神に溢れていること・・・
でも、10歳の子供が何処まで理解できたと思う?
それでも・・・
変わってしまった環境の中で僕は自分の生きる術を懸命に探した
僕の生きる場所はここだけなんだと自分に言い聞かせた
そして僕は・・・フランク・シンという人間に生まれ変わった・・」
「フランク・シン・・・それがあなたの・・・」
僕は彼女の言葉に頷きながら先を続けた。
「養子先ではね・・僕は凄く賢くて行儀のいい子・・・そう言われてた・・・
言葉も直ぐに慣れて、半年もしない内に会話に不自由は無かった
養父母は本当に優しい人たちだったし・・・そこで出会った義兄弟とも上手くやってた
でも・・何かが違ったんだ
本当は我侭も不満も言いたかったし・・・
周りの子供達が親に甘えている姿を見ると本当に羨ましかった・・・
“フランク・・・あなたは私達の自慢の子供よ”
養母にそう言われて心をくすぐられるようだった
でもその反面・・そのことが凄く重く僕にのしかかっていた
成績が良くて・・・行儀が良くて・・・大人の言うことを良く聞く・・・だから・・
ここに置いてもらえてるんじゃないか・・・
本気でそう思って、僕は正直かなり無理してた・・・
この居場所を無くしたら、もう何も無くなる・・そう思ったから・・・
ある時僕は・・自分が精神のバランスを崩してることに気がついた
養父母たちの言葉も素直に受け入れられず
屈折して物事を捉えるようになって・・・いい子を演じることに疲れて・・・
ことごとく彼らに反発した
周りの何もかもが嫌になっていったんだ・・・いつしか僕は・・・
“この家から逃げ出したい”そう思うようになってた・・・
それが13の時だ・・・
どうしてもひとりになりたくて・・・
養父母に頼んで全寮制の学校に入れてもらって・・・
それからというもの・・・
僕は必死に勉強して・・・早く独り立ちしようと考えた
早く大人になりたかった
自分だけの力で世の中を渡って・・・お金を稼いで・・・
地位と名誉を我が物にして・・・成功したら
僕を捨てた実の親を見返してやる・・・そう思ってた・・・
たった13の子供が本気でそう思ってた・・・
笑ってしまうよ
遠く離れたこの地で生まれ変わるはずだったのに・・・
新しい僕に・・・フランクに・・・なるはずだったのに・・・
結局最後に僕の中に宿っていたのは・・・
どうでもいい・・・そう思っていたはずの・・父への恨みだけだった・・・」
「・・・・・・・・」
ジニョンは僕の淡々とした告白をただ静かに聞いていた。
「僕は人間が嫌いだ・・・だから・・・人を信じたことなんて一度もない・・・
人を愛したことも・・・一度もない。・・・愛を・・・信じたこともない。
今までは・・・そうだった・・・
そんな僕が・・・どういうわけか或る人を・・・愛してしまった・・・
最初は信じられなかったんだ・・・
僕自身・・・僕の心が信じられなかった・・・
でもどうしようもないほど・・・その人を・・・愛してる・・・」
「・・・・・・・」
「胸が締め付けられるくらいに・・・君を・・・愛してる・・
そのことに嘘はない・・・君は・・・こんな僕を・・・信じられる?」
「・・・・・・・・」
彼女は僕の問いかけに答えずただうつむいていた。
「・・・・信じられない?」
「・・・・・・・・」
そっと指で持ち上げた彼女の顎が涙で濡れていた。
僕はただ静かに涙を流しながら僕を見上げる彼女の瞳に息を呑んだ。
「・・・・どうして・・・君が泣くの?」
「ごめんなさい・・・何も・・知らなくて・・何も教えてくれないって・・
私・・・さっき・・あなたのこと・・責めた・・・」
彼女はそう言いながら僕の膝の上を降りるとそのまま僕の前にひざまずいて
僕の手に頬ずりをした後、僕の手の甲に涙混じりの唇をそっと落とした。
「・・・・・・」
そして彼女は顔を上げて、彼女のキスをただ黙って受けていた僕と真直ぐに向き合った。
「でも・・・愛してくれる人が誰もいないなんて・・・どうして、そんなこと思うの?
そんなの・・・悲しすぎる・・・私はあなたを愛してる
私だけじゃない・・・
ソフィアさんだって・・・あなたを心から愛してる・・・
あなたの亡くなったお母様だって・・あなたを愛してたはず・・
お父様だって・・・きっと、ご事情があったはず・・・」
「ジニョン・・・そんなこと・・・もうどうでもいいことだよ」
「フランク・・・」
「僕は・・君がいてくれればそれでいい・・・
そうやっていつも・・愛してると・・・言ってくれる君が・・・」
「だめ・・・」
「・・・・・・」
「嫌よ・・・フランク・・・
あなたが・・・そんな悲しい心のままに生きるのは嫌・・・」
「・・・・・・」
「親に愛されない子供なんて・・・この世にはいない・・・
絶対に存在しない・・・私はそう信じてる・・・」
彼女の瞳から尚もとめどなく涙が零れ落ちていた。
僕の手を強く握り締めながら、視線を決して逸らさない彼女の瞳の中に、
僕は神々しい優しさと強さを見つけて圧倒されていた。
ジニョン・・・君という人は・・・
人に裏切られて育っては来なかった
だからそんなにも人間をも信じられるんだね・・・
ジニョン?・・世の中にはね・・・
君が想像もつかない人間だって存在するんだよ・・・
でも・・・可笑しいんだ・・・
君のその紛いの無い綺麗な瞳を見つめていると・・・
僕の心が吸い込まれるように君の無垢な心に埋もれていく
そうかもしれないと・・・
こんな僕でも・・・本当は母に愛されて・・・
父にも・・・愛されて・・・
この世に存在したと・・・
・・・信じてみたくなるよ・・・
創作mirage-儚い夢-21.ふたりだけなら

僕たちは二人でキッチンに向かい、蛇口を捻ったり、コンロを操作したりして
まず使い勝手をチェックして楽しんだ。
それから、引き出しという引き出しを開けてみて、何が何処に入っているのかも
一応確認してみたりした。
そうしてここが僕達“ふたりの家だ”ということを噛み締みしめた。
ちょっとした食材や日用品は業者に委託して、準備してもらっていた。
「ジニョン・・・冷蔵庫開けてみて?何が入ってる?」
「ちょっと待って?・・・卵でしょ・・ベーコンやハム・・・
バターとジャムと・・・レタス・・セロリ・・それから・・」
「あーじゃあ・・・卵とバター、ベーコン出して・・・スクランブルエッグにしよう・・・
それからセロリとレタスも出して?
パンもあるみたいだし・・・朝はそれで十分でしょ」
僕はシンク下の引き出しからフライパンやボールを出しながら言った。
「は~い」
僕が次にコーヒーの豆を挽いていると、ジニョンがどう見ても不慣れな手つきで
卵を割ろうとしている様子が視界に入った。
「・・・何してるの?」 僕はわかっていながらそう聞いた。
「卵割ってるの」 彼女は明るくそう答えた。
どう見ても、器用とは思えない彼女の手つきに、僕は溜息をこれ見よがしに吐いた。
「・・・君・・・料理やったことある?」
ジニョンは照れ笑いを浮かべながら、堂々と大きく首を横に振った。
「ジニョン・・・コーヒーの続き・・・頼むよ」
僕は彼女に手招きをして、貴重な卵が無事なうちにクッキングの主導権を僕が
握ることに決めた。
そのことを期待していたと言わんばかりに、彼女は満面の笑みで頭を大きく縦に振った。
僕は再度溜息を吐きながら彼女とすれ違いざま、彼女が僕に向けた小さな掌に
ハイタッチをして、バトンを受け取った。
彼女は僕に屈託の無い笑みを送りながら、とても慣れた手つきでコーヒーを淹れる。
≪そう・・そっちなら、安心して任せられる≫
そんな彼女の姿に自分の頬が緩んでいくのを僕は実感していた。
傍らにいる人をこんなにも柔らかな気持ちで見つめている自分が、信じられなかった。
これが君の言う・・・“幸せ”・・・なんだね・・・
ジニョン・・・
僕はスクランブルエッグを手際よく作り、パンとコーヒーを添えてふたつのトレイに用意した。
「ジニョン・・・用意できたよ・・・?」
ふと辺りを見渡すと、さっきまでそばにいたはずの彼女が見当たらなかった。
僕は慌てて彼女の名を叫んだ。
「 ジニョン?ジニョン! 」 部屋中探しても彼女の姿が見えなかった。
「 ジニョン! 」 自分の声が緊張に包まれていると感じた。その時・・・
「 フランク!こっちよ・・」 彼女の大きな声が外から聞こえた。
声のする方に慌てて赴くと、ジニョンは湖畔に面したテラスのテーブルや椅子を
綺麗に拭いているところだった。
「 ジニョン! 」 彼女の姿を見つけてホッと胸をなでおろした僕の様子に、
彼女はきょとんとした表情を僕に向け、首を傾げた。
「フランク、ここで食べましょ?きっと気持ちいいわ」 ジニョンはにっこりと笑ってそう言った。
「あ・・ああ・・・」 さっき僕が抱いた不安を彼女に悟られまいと、咄嗟に平静を装った。
「どうしたの?」
「いや・・・何でもない・・・」 僕は急いで彼女に背中を向けると、彼女の姿が
ちょっと見えなかっただけで慌てふためいた自分をもごまかした。
僕はキッチンに戻って、さっき用意したふたつのトレイをテラスへと運んだ。
昨日ここに着いた時にはめっきり夜が更けていて、見ることができなかった全貌を、
こうして明るくなって改めて眺めると、白いカントリーハウス風の建物が周りの樹木と
湖畔とのコントラストを描いていて、絶妙な美しさを誇っていた。
そして、湖畔の水面を走ってきたかのような心地よい風がジニョンの笑顔と
コラボレーションして、僕の心に言いようの無い安らぎをもたらす。
今までにこんなにも・・・愛しい朝を迎えたことがあっただろうか・・・
僕の奥深くに眠っていた何かが呼び覚まされる妙な感覚が、間違いなくあった。
君という存在が、僕の中の危険な闘争心の刃をも仕舞わせてしまいそうになる。
このまま君と・・・こうして暮らせたら・・・
「フランク?」
「ん?」
僕は彼女の呼ぶ声を聞き逃してしまうほど、彼女との幸せの中に浸っていたようだった。
「ヤ~ネ・・・真面目な顔しちゃって・・・」
「そう?何?」
「今日はお仕事はないの?って聞いたの・・・」
「ああ・・・うん・・・仕事ね・・・休み。」
「ホント?」
僕は深く頷いた。
先日の案件を終了させた後、3日間の休暇をレオに宣言してきた。
レオも次の案件までに休養も必要だろうと、その間は電話はしないと約束をした。
「じゃあ・・今日は何して遊ぶ?」
「遊ぶ?・・・はは・・・遊ぶんだね・・・」
「可笑しい?」
「いや・・・」
そう言いながらも、僕は声を立てて愉快に笑っていた。
「何だか感じ悪い・・フランク・・・」 彼女が口を尖らせて僕を睨んだ。
「ごめん・・・ 」 僕は更に可笑しくなってお腹をかかえていた。
それはきっと彼女には理解できなかっただろう・・・
君の“遊ぶ?”という言い方が
何故だか僕の遠い記憶にあったものを
懐かしく思い起こさせたような気がしていた
そんなこと言っても・・・
僕の過去を何ひとつ知らない君にはまだ・・・
理解できないね・・・
「ね・・フランク・・・さっき言ってた、ボート・・・あるの?」
「ああ・・あるはずだよ・・・ほら・・あそこに見える・・・」
僕は前方に見える小さな桟橋に繋がれた小ぶりの白いボートを指差した。
「ホントだ・・・あれ・・使ってもいいの?」
「ここにあるものはみんな、自由にしていいんだ」
「じゃあ、後で乗せてね」
「いいよ」
朝食の後、僕達は改めて部屋の中を見て歩き、椅子やテーブルを動かして
好みのレイアウトに変更したり、他に必要なものは無いかを確認したりして、
ふたりで戯れながら、うららかな時を過ごした。
昼には、さっき彼女と約束したボートにランチ用に作ったサンドウィッチを持って乗り込み
穏やかな水辺に漂ってみた。
「フランク・・・凄く綺麗ね・・・
私こういうの・・・生まれて初めて・・・」
「僕も初めてだよ・・・生まれたのは海の近くだったけど・・・
こういうところはなかったな・・・」
僕は思いがけず、自分の生まれた地を話題にしてしまい、自分でハッとした。
「海の近く?・・・フランクは何処で生まれたの?」 当然、ジニョンはそう聞いた。
「あ・・・ジニョン・・・見てごらん・・・魚がいる」
何故・・・ごまかす?・・・
「わぁ・・・本当だ・・・ね、フランク・・・今日、買い物行ったら、釣竿買って?」
「釣竿?」
「そう・・・魚釣るの・・・美味しそうでしょ?」
「そうか・・・お前たち・・・
食いしん坊のジニョンに食べられる運命なんだね・・・」
僕はボートの上から水面に向かって神妙を装い、魚達に呟いてみせた。
「フランク!そんな言い方ないわ!」
ジニョンの拳が僕目掛けて飛んで来ると、僕はわざとボートを揺らして見せた。
案の定、バランスを崩した彼女は、拳よりも先に頭から僕の胸に飛び込んで来た。
そして僕はしてやったりと、彼女をしっかりと抱き取った。
「もう!」 彼女は用意していた拳で柔らかく僕の胸を叩いた。
「ところでジニョン・・・釣った魚は誰がさばくの?」
彼女は甘えたように見上げて僕を指差した。
「やっぱりね・・・」
僕は彼女の首に片腕を回して引き寄せ、軽く締め上げた。
彼女は僕のその腕にしがみつきながら可愛く弾けるように笑っていた。
本当に幸せだった・・・
「ジニョン・・・おいで・・・」
「ん?・・・」 僕はボートに寝そべって彼女に隣に横になるよう促した。
「見てごらん・・NYのアパートより広く空を仰げる・・・」
「本当だ・・・」
「綺麗だね・・・」
「ええ・・・とっても・・・透けるように青い・・・・・・・・・」
そう言ったまま彼女の言葉が止まってしまったことに、僕は怪訝な顔を彼女に向けた。
「どうかしたの?」
「ううん・・・何となく・・・
この空は何処までも続いてるんだろうなって・・・」
「何処までも?」
「ええ・・・何処までも・・・だって・・空はひとつだもの・・・
この同じ空の下で・・・私の愛する人たちが
生活をしてるわ・・・父や・・・母や・・・あなただって・・・そうでしょ?」
「・・・・・・・」
「心配してる・・・かな・・・」
彼女のぽつりと言った言葉が僕の胸をチクリと刺した。
僕が起き上がり彼女を見下ろすと、彼女は小さく笑いながら寂しそうな瞳を僕に向けた。
「後悔してるの?・・・」
「・・・・・・・」
彼女はそれには何も答えず、僕の後から起き上がると、さっきまでの自分の弱さを
振り払うかのように首を横に振り、微笑みで寂しさを隠したようだった。
「ジニョン・・・もう少し待って・・・
僕が君のご両親に自信を持って会えるまで」
「自信?フランクは十分立派な人じゃない・・・」
「立派?何処が?僕の何処が立派なんだ!
君は僕の・・・何を知ってる?」
僕は思わず、自分を卑下するかのような言葉を吐きながら、彼女に厳しいまなざしを向けた。
そして直ぐに、そんな自分を省みて思わず視線を伏せた。
「何も知らないわ・・・だって、フランク・・何も教えてくれないもの・・・
あなたのファミリーネームも・・あなたの生まれたところも・・・
あなたのご家族のことも・・あなたのお仕事のことも・・・
私は何も知らないもの・・・でも・・でも・・
ソフィアさんは知ってるんでしょ?
あなたのお仕事が凄く大変なことも知ってたわ
彼女は私よりも・・・うんとあなたのこと知ってる・・・」
彼女ははらはらと涙を頬に伝わらせながら、僕を悲しそうに睨んだ。
「ごめん・・・そんなつもりで言ったんじゃない・・・
お願い・・・泣かないで・・・」
彼女の涙を見るのが辛くて、うつむき加減の彼女の額に自分の額を押し当て目を閉じた。
それでも・・・彼女の頬を伝う涙の音が僕の心に切なく伝わってくる。
「・・・・・・」
「ごめん・・・」
話さなければならないことは沢山ある・・・
僕がどういう人間なのか・・・
君が沢山の愛情を受けて育ったことと
真逆な人生を送ってきた僕・・・
君はそれを知っても・・・
僕を変わらず愛してくれるだろうか・・・
僕が歩く道を・・・
君は僕に寄り添い一緒に・・・歩いてくれるだろうか・・・
そうだね・・・
君と僕とは生きた世界が違う
君には僕以外に愛する家族が存在することを
僕は受け入れなければならない・・・
それでも・・・ごめん、僕は思ってしまう
この世の中に・・・君とふたりだけなら・・・
ここにいるとつい・・・そんな絵空事を望んでしまう・・・
ただ愛してる・・・それだけでは・・・
駄目なんだね・・・
・・・どんなにいいだろう・・・
君に隠したこの想いを・・・僕は目を閉じ・・また封じ込めた・・・
どんなに・・・いいだろう
この世の中に・・・
君と・・・
・・・ふたりだけなら・・・
創作mirage-儚い夢-20.さざなみ

「そろそろ・・・こっちを向いてもらってもいい?」
「・・・・・・」
「キスしたい・・・」
僕が彼女の耳元でそう囁くと、彼女は不意に振り返り僕の首に飛びつくなり
僕の唇に自分の唇を強く押し当てた。
彼女の突然の行為に驚いた僕はその瞬間、不覚にも彼女から手を離してしまったけれど
急いでもう一度彼女を抱きしめ直すと、先を越されてしまった甘いくちづけの主導を
今度は僕が握った。
確かめ合うかのような甘美で執拗なくちづけが
息を付かせることさえ許さない愛撫の繰り返しが
逢いたかった激しい思いを互いへ訴えると
恋人達は逢えなかった時間を取り戻していく
その狂おしいほどの自分の感情をなだめた後で僕はやっと、彼女を解放した。
そして潤んだ眼差しで見上げる彼女の髪を撫でながら、その濡れた唇に誘われて、
また、何度も何度も小さいキスを繰り返えした。
逢いたかった・・・ジニョン・・・
触れたかった・・・ジニョン・・・
呼びたかった・・・
「ジニョン・・・・・・・・
ねぇ・・本当のことを言ってごらん・・寂しかっただろ?」
僕は彼女を抱きしめたまま、彼女の髪を愛しげに梳きながらそう言った。
「いいえ・・少しも・・・」
「本当に?」
「・・・言わない。・・・悔しいから・・・」
彼女は僕の背中に回した両手で僕の服を握り締めながら口を小さく尖らせた。
「悔しいから?・・・それって・・寂しかったって
言ってることじゃない」
「・・・・・・・」
「いいから素直に言ってごらん?・・・寂しかったって・・・」
「・・・・・・・言わない。」
「強情だな」
「あなたこそ・・・
どうして、そんなにしつこく言わせたがるの?」
「寂しかったから。」 僕は即座にそう答えた。
「・・・・」
「僕が寂しかったから・・・
君の“寂しかった”をいっぱい聞きたい」
「フランク・・」
「ん?」
「・・・・・寂しかった・・・すごく寂しかった・・・
死ぬほど寂しかった・・・
寂しくて寂しくて・・・いつもベッドの中で泣いてた・・・
あなたの・・・声が聞きたくて・・・
寝る前に目を閉じて、あなたの“愛してる”を思い出してた
逢いたくて・・逢いたくて・・・こうして・・・
あなたの顔を・・・この目を・・・この唇を・・・思い出してた・・・」
そう言いながら彼女は目を閉じて僕の顔に細い指を這わせた。
「・・・・・・」
「・・・・・・」
僕は彼女の瞳を熱く見つめながら、僕の顔に触れた彼女の細い指先一本一本に
丁寧にキスをした。
そして僕達は、しばらくの間言葉もないまま、ただ強く抱きしめ合っていた。
「・・・行こうか・・・」
「え?・・・」
「このままこうしていても・・・いいけどね・・・
もっと他のことをしたくなった・・・」
彼女を見つめた僕の瞳の中にその意味を見つけた彼女が頬を赤く染めた。
僕はそんな彼女を愛しく思いながら手を取ると、ソフィアの部屋とは反対の方角へと進んだ。
「待って・・・行くって?・・・ソフィアさんが・・・」
「いいんだ」
「いいって・・・ビネガー待ってる・・」
「待ってないよ・・・」
「・・・・・?」
「ソフィアがそうしろと言ったんだ」
《迎えに来ないで・・・フランク・・・》
「・・・・・でも・・・何処に行くの?」
「僕たちの家・・・」
「・・・・・?」
「いいから・・・おいで・・・」
僕は握ったジニョンの手を更に強く握り締めると、道路の向こうに止めてあった車に急いだ。
迎えに来ないで・・・フランク
ジニョンさんと過ごしたこの三日間は意外とシンプルだったわフランク。
本当はね
彼女のこと・・・もっと憎らしく思うのかと思ってた
でも・・・何故か彼女と一緒にいると・・・
穏やかな気持ちになっていく自分に驚いたわ
不思議な子ね・・・あの子・・・
フランク・・・
あなたも苦しんだのね・・・
でももう戻りましょう
私達にこんなのは似合わない
私はいつもの私に・・・
あなたもいつものあなたに・・・
ひとつだけ・・・
戻れないことはあるけれど・・・
それでも・・・あなたを失うよりは・・・
絶えられそうな気がする・・・
あなたの辛そうな目は・・・
いつまで経っても・・・苦手なのよ・・・私・・・
ルルルーー♪
「ハロー・・・」
「ソフィア?」
「リチャード?・・・何してるの?」
「何してるって?・・・」
「だって、あなた・・今頃はNYで・・」
「ああ・・コンサートのこと?あれは・・・
ある女に断られた時点で、既に消滅・・・」
「消滅?」
「破って捨てたってこと・・・」
「まあ、もったいないことするのね・・・あれプラチナ・チケット・・・よ」
「僕にとってはその女と行けなければゴミ同然・・・」
「・・・・・・」
「どう?」
「どう?って?」
「少しは感動した?」
「・・・・あなたって・・・変な人・・・」
「それは褒め言葉と取ってもいい?・・・」
「・・・リチャード・・・ところで・・ご用は何?」
「ああ、僕の声を聞きたいんじゃないかと思って」
「フフ・・・何の冗談?・・」
「・・・聞きたかっただろ?」
「リチャード・・」
「実際思ってなかった?ああ、そういえば今日はまだ・・・
彼の声を聞いてなかったなって・・ね」
「・・・・・・」
「毎日聞いていた声が聞こえないと・・・妙な気分になる・・・」
「リチャード・・・」
「だから僕は・・・こうして君に毎日電話してる・・・」
「・・・強引な人は好きじゃないわ・・・」
「食事でもどう?・・・迎えに行く・・・」
「・・・悪いけど・・・切るわ」
「・・・会いたい・・・」
「ごめんなさい・・・じゃあ・・・」
「・・・・・」
ピンポーン♪
・・・・・強引な人は嫌いだと言ったでしょ?
でもまだ・・・電話・・・切ってないね・・・
僕はレオに頼んでNY郊外に人里離れた小さな家を探してもらった。
『どうして、家なんかを?』
理由がないといけないか?
『いや・・・しかしボス・・これから俺達は嫌でも忙しくなる
そうなると殆どホテル住まいが多くなるぞ』
・・・・・・
『ま、いい・・・ご希望の物件当たってみるさ・・・』
「この辺のはずなんだ・・・」
「暗いのね・・・まるで森の中みたい」
「家の周りに灯りを灯してくれることになってるんだけど・・・
あ・・あった・・・あそこだ・・・」
「何だか怖いわ」
「大丈夫・・・僕が付いてる」
「ええ・・・」
レオが用意してくれた家は白いカントリーハウスだった。
それはジニョンが表現した通り森のような樹木に覆われていた。
見渡す限り隣家と思しき建物ひとつ見当たらず、闇の夜に浮かんで見えるのは
白っぽい小さな家とそれを照らすひとつの灯りと妖しげな朧月だけだった。
玄関を入ると、右手にしゃれたダイニングキッチン、左手にはソファーやテーブル、
キャビネットが白い布で覆われたまま僕たちを出迎えた。
そしてその奥に白い壁で半分仕切られただけのベッドルームが見える
大きなワンルームタイプの間取りになっていた。
「気に入った?」
「え?・・・」
「気に入らないの?」
「そんなことないわ・・・素敵なお家」
「ここが僕たちの新しい家・・・さあ・・布を外そう・・・」
「え?・・ええ・・・」
僕はふたりの新しい生活の幕開けに白布を大きな音を立てて勢いよく取り除いた。
中からは小ぶりながらもセンスのいい家具が現れ僕は満足だった。
しかし、僕の後に続いて外した布を片付けるジニョンの、少し元気の無い様子が
気になってしかたなかった。
「 ジニョン! 」 僕は彼女に不意にクッションを投げつけてふざけて見せた。
彼女は一瞬驚いてそれを受け損なってしまったけれど、直ぐに僕の行動に反応して、
僕以上の攻撃を仕掛けてきた。
いつもの明るい・・子供みたいなジニョン・・・
それなのに彼女の不安げな憂い顔が僕の心にさざなみを立てる。
ジニョン・・・何がそんなに不安なんだい?・・・
僕との生活が?・・・
韓国のご両親のことが心配なんだね
ジョルジュというあいつのことも・・・
ジニョン・・・僕は・・・君の
その手を掴んで来てしまったこと・・決して後悔はしていない・・・
でも・・・君のその・・・
瞳の中の憂いを僕はどう受け止めればいいんだろう
ジニョン・・・
どうか僕に・・・君のくったくのない笑顔だけをくれないか・・・
僕たちはその夜、いつの間にかベッドに倒れ込むように眠ってしまった。
僕はこの数日ろくに寝ていなかったこともあって珍しく熟睡していた。
薄く射し込んだ光彩に揺り起こされて目覚めると、ジニョンは僕に体を添わたまま
まだ深い眠りの中だった。
しばらくの間、彼女の寝顔を見つめながら、僕は昨日までのことを思い起こしていた。
自分達に降りかかった現実と・・・
まだ見えないふたりの未来・・・
今までは僕に想像できないものなど存在しなかった
それなのに・・・彼女との未来が見えてこない・・・
ただはっきりしていることは・・・
僕がもう彼女を失えない・・・
そのことだけだ・・・
僕はその自分の決心だけを信じて生きようと思った・・・
彼女さえそばにいてくれれば・・・何もいらない・・・
そして僕は彼女の額にそっとキスをしてベッドから起き上がると、窓辺に向かい、
朝日が薄く差し込むカーテンを開けて、まばゆいばかりの光をジニョンの眠るベッドに採り込んだ。
「ジニョン!起きて!ジニョン!」
「んっ?・・・ん・・・」
「来てごらん・・・湖だ・・・朝日が反射して綺麗だよ」
僕の誘いにまだ眠気まなこの彼女がベッドを降りて窓辺に近づいた。
「うわー本当ね・・・凄く綺麗!」
昨夜の彼女の不安げな顔が、湖畔に映る朝焼けを前に輝きを取り戻したように見えた。
「ジニョン・・・朝食を作ろう・・・」
「材料は?」
「少しは用意してもらってる・・・あとで買い物にも行こう
足りないもの、調べないといけないね・・・」
「ええ」
僕に向けた彼女の笑顔はいつもの明るいジニョンだった。
どうしたんだろう・・・僕は・・・昨日から
何故か彼女の笑顔を探しては、その都度胸をなでおろしている
「ジニョン・・・これから・・・
ふたりで色んなことをしよう・・・」
「色んなこと?」
「ああ・・・ふたりで映画を観たり・・・
ミュージカルを観たり・・・
素敵なレストランで食事をするのもいい・・・
あの湖畔にボートを浮かべるのもいいね・・・
とにかく・・・
君がやりたいことは何でも言ってごらん?
君の言うことなら、何でも叶えてあげる
ふたりで沢山のことを経験して・・・君と・・・
幸せを描いていきたい・・・」
「ええ・・・」
僕はジニョンの背中を自分の胸に抱いて窓辺に少し体を預けた。
しかし、湖畔に向けたままの彼女の表情を僕は覗かなかった。
胸の中のざわめきが彼女の心の奥深くを僕に覗かせなかった。
それでも、水面にきらめく神秘な光華が僕の心を少しだけ慰めてくれていた。
フランク・・・大丈夫だ・・・
彼女はきっと・・・
・・・お前の元で笑ってくれる・・・
| <前 | [1] ... [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ... [36] |