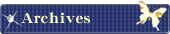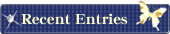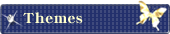passion-28.証

collage & music by tomtommama
story by kurumi
翌朝ジョギングから戻ると、部屋の前にジェニーが立っていた。
彼女の目が、ジニョンから事情を聞いてそこに来たことを物語っていた。
「・・・・・朝ごはんは・・・食べた?」
「ええ・・朝ごはんはちゃんと食べないと、
仕事にならないからって、テジュンssiが・・・」
「これから仕事?いつもこんなに早いの?」
フランクはジェニーの口から出たハン・テジュンの名前を一度は無視した。
「厨房で認めてもらえるまで、みんなより30分早く出て
30分遅く帰りなさいって・・テジュンssiが・・・」
「テジュンssiが・・・そんなことを?」
フランクは妹ドンヒにとって、ハン・テジュンという男が
いかに重い存在であるのか認めざる得なかった。
「ええ、テジュンssiは私に色んなことを教えてくれます」
「そう・・・」
「私昔・・・とても人に言えない生活してたんです」
「苦労したんだね」
「忘れました・・・でもテジュンssiがいつも親身になってくれたから・・・
生きてこられたんだと思います・・」
「・・・・」
「・・・慰めてくれたり・・叱ってくれたり・・
命がけで助けてくれたこともありました・・」
「そう・・・」 フランクは視線を下げて静かに呟いた。
「今・・こうして大好きな料理の仕事をさせてもらえるのも
みんな・・テジュンssiのお陰です」
「料理が好きなの?」
「ええ」
「・・・・・・」
「あ・・でも・・・本当のお兄さんが・・・成功してくれていて・・
良かったです・・・本当に・・・」
「・・・・・・」
「・・・・いい人だったら・・・もっと良かったけど・・・」
フランクは俯きがちにそう言ったジェニーの言葉を聞いて、
寂しそうに苦笑した。
「あの・・もう行かないと・・仕事の時間なので・・」
ジエニーがそう言いながら立ち上がろうとした時、フランクは言った。
「・・・・両親のことを知りたいかい?」
「生きているんですか?」
生まれて初めて対面した肉親を前に居心地の悪さから、できるだけ早く
その場を立ち去ろうと構えていた彼女が目を輝かせ、再度腰を下ろした。
「ああ・・父親は・・・。
母親は君を生んで一年後に亡くなったけど」
「もう誰も生きていないのかと・・」
「君が会いたいなら・・・」
「会いたい!」 フランクの問いかけにジェニーは即座に答えた。
フランクはジェニーの悲痛なほどの眼差しに、心を乱されていた。
もう二度と会わないと、あの日自分が突き放してきた父親に、
会いたいと望む妹が今目の前にいる。
≪僕達を捨てていった人なんだよ
それでも・・・そんなに会いたいの?≫
「会わせて下さい」
「ああ・・わかった・・」 ≪君がそんなに望むなら≫
フランクはまたも寂しげに視線を落とし、溜息をついた。
「いよいよ明日ね・・お父様・・来て下さること承諾下さって・・
本当に良かった・・」 ジニョンは本当に嬉しそうにそう言った。
「ん・・」 しかしフランクは気乗りしない思いを露に俯いた。
フランクはレオに頼んで東海まで父親を迎えに行ってもらったものの
フランクの要請を一度は父が≪自分にはその資格が無い≫と、
頑なに拒んだと聞いた。
フランクは正直、“それならそれでもいい”と思った。
彼自身は父という存在をとうに棄てていたからだ。
しかし結果的に父はレオに説き伏せられ、明日彼に連れられ
やってくることになった。
「嬉しくないの?」
「どうしてあの子はあんなにも、あの人に会いたがるんだろう」
「どうしてって?」
「あの人があの子にどんな仕打ちをしたのか・・
恨んで当然なのに・・」 フランクは不服そうに眉を顰めた。
「ジェニーね・・・二歳の時アメリカに渡ってからずっと・・
養子先で幸せに暮らしていたらしいわ
七歳の時まで、自分がその家の本当の子供だって
信じて疑わなかったらしいの・・・
学校に通うようになって、友達に言われるまで・・」
ジニョンは今日はこの話をフランクにしようと、サファイアを訪れていた。
「パパとママと肌の色が違うねって・・」
今まで自分の生い立ちについて多くを語ろうとしなかったジェニーが、
ジニョンに自ら語り始めたのはきっと、彼女を通して兄フランクに
伝えたかったのだとジニョンは察していた。
「・・・・」
「養父母達は、本当のことを話す機会を作ろうとしていたらしいわ
きっと実の親のことも話して聞かせる用意があったんだと思う
でも、ジェニーがそのことに触れないようにしていたって・・
その頃は本当の両親に会いたい、なんて思わなかった・・
今の幸せを失いたくない、ただそう思ってたって・・」
「・・・・」
「あなたがあの子をどうして捜さなかったのか・・後悔してること・・
伝えたの私・・・そしたらあの子、こう言ったわ・・
“私は自分のルーツを知る機会を・・自分から捨てたんだ”って・・」
「・・・幸せに暮らしていたんだね」
フランクはホッと安堵したかのように溜息をついた。
「ええ・・十三の年までは・・」
「十三?」
「その年に養父母が交通事故でふたりとも亡くなって・・・
車の衝突事故だったらしいわ」
「・・・・・!」
「あの子も一緒だったらしいの・・その事故の時・・
三人とも後部座席にいて・・
ご両親があの子を両側から抱きしめて守って下さった
それであの子は辛うじて助かったの・・・」
「・・・・・」
「養父母には親御さんもご兄弟もいらしたけど
縁もゆかりも無いジェニーを引き取ろうという人は
ひとりもいなかった・・・
それで結局あの子は家族が通っていた教会の牧師さんの元に・・」
「・・・・・」
「そこで親に捨てられた多くの子供達と遭遇して
自分がそういう子供達と同じだったって・・改めてわかって・・・
やりきれない思いだったって・・
血の繋がらない育ての親は命がけで自分を守ってくれた・・
でも・・本当の親は自分を捨てたんだって・・・
その頃かららしいわ・・あの子が荒れ始めたのは・・」
「・・・・・」 フランクはジニョンから顔を背けたまま
彼女の話を無言で聞きながら、溢れ出る涙を堪えることができなかった。
「フラン・・ク?」
彼の胸に言いようのない悔しさが込み上げて仕方なかった。
「どうして・・・その時・・」
「・・・・」
「どうしてその時に・・・
僕が・・あの子と・・出会わなかったんだろう」
「フランク・・・」
「捜すべきだったんだ・・・僕は捜すべきだった
その頃の僕なら・・できたはずなのに・・
あの子を捜すことも・・守ることも・・できたはずなのに・・
僕はそうしなかった・・・」
「自分を責めないで・・お願い・・フランク・・」
フランクは依然としてジニョンから顔を背けたままだった。
頬を止め処なく伝う涙を彼女に見られたくはなかった。
「それなのに・・・」 フランクは苦しい呼吸を懸命に整えながら続けた。
「えっ?・・」
「それなのに・・どうしてあの子は・・・あんな親に会いたがる?
恨んだはずだろ?・・恨んで当然なんだ
本当の親は・・あの人は・・あの子を守らなかったんだから・・」
「・・・・・・・・あの子・・ここに来る前にもね・・
死ぬ程危ない目に遭ってるの
テジュンssiが命懸けで助けたのよ・・」
「・・・・」
「そこから彼女を逃げ出させるためにテジュンssiも
住んでいた場所を離れたの・・
その時、彼女が彼に言ったそうよ・・
“本当の家族に会いたい”って・・
“韓国に連れて行って欲しい”って・・
何でもするから・・今度困らせるようなことをしたら
今度こそ放り出してくれていいからって、頼んだの・・
きっと・・死ぬような思いをして・・・
潜在していた家族への思いが蘇ったんじゃないかしら・・
私は・・・そう思うわ・・」
「・・・・・」
フランクは変わらず、ジニョンの話しを顔を逸らしたまま聞いていた。
「それに遅いことなんてない・・・
あなた達はこうして出会ったんだもの・・
ねぇ、フランク・・思わない?・・・・」
ジニョンはフランクが自分の方を向くのを待った。
フランクはひとつだけ深呼吸をするとやっと、ジニョンに視線を戻した。
「私は思うの・・・今だからこそ
あなた達を神様が会わせて下さったって・・
今のあなただからこそ
あの子の想いをわかってあげられるんじゃない?
それに・・こんな偶然・・あるわけないじゃない・・
だってほら・・私とジェニーが今一緒に暮らしてるのよ
あなたにとって妹なら・・私にとってもそうでしょ?
あの子・・私のこと“オンニ”って慕ってくれてるのよ
そうよ・・これって運命なのよ・・
だから・・遅いことないの・・それに・・
あの子は本当に肉親に会いたがってたの
あなたは今・・あの子の一番の望みを叶えてあげている
そうでしょ?」
「・・・ジニョン・・・」
ジニョンが身振り手振りを交えて、懸命に彼を慰めている姿に
フランクは思わず噴出して笑った。
「何が・・可笑しいのよ」 ジニョンは口を尖らせてフランクを見上げた。
「ハハ・・・ごめん・・・
だって君の顔があまりに真剣だから・・」
フランクは少し大げさにお腹を抱える仕草で笑って見せた。
「フランク!・・笑い過ぎ・・」
しかし彼女にはわかっていた。
フランクは今、妹ジェニーを思って張り裂けそうな程の後悔に
懸命に耐えているのだと。
翌朝、サファイアの前で待つフランクの前に、ジニョンに連れられた
ジェニーが照れくさそうに現れた。
フランクは遠い日に妹の身に起きていた悲しい出来事を思いながら
彼女を愛おしそうに見つめた。
白いブラウスに、同じく白い長めのスカートをはいた妹を
まるで労わるように。
≪あの子ね・・足に傷があるの・・事故の時の・・・
右足の膝下に・・残ってるの
だからいつも長いパンツしかはかないの
でも明日は・・おしゃれさせるわ・・・≫
そしてフランクは誓っていた。
≪もうこれからは決して・・・
お前を不幸にはしない・・・≫
ジェニーはほんの数日前に兄となった男を前に、心が複雑に
揺れ動いていた。
自分にとって、心の兄はテジュン以外になかった。
今更、彼以外に本当に心を許せる兄などできるはずはない。
ジェニーはそう思っていた。
そのテジュンがこう言った。
≪あいつがどんな奴だろうとお前と血の繋がった兄貴なんだ・・・
会いたくてたまらなかった本当の家族に会えたんだ・・
お前は素直に喜べ・・≫
彼のその言葉に、ジェニーは黙って頷いた。
テジュンの言うことに間違いなどあるはずがなかったから・・・。
でも・・・その兄は・・・
≪大切なホテルの敵・・テジュンssiの敵≫
そして・・・
≪ジニョンオンニを・・テジュンssiから奪った人≫
しかし目の前で自分を温かな眼差しで見つめるフランクに
ジェニーは心を囚われていた。
それでも・・・ ≪私の・・・オッパ・・・≫
「行きましょう」
ジニョンが目の前のまだぎこちない兄妹を温かい眼差しでいざなった。
「ああ」 フランクは昔よく繋いでいた小さかった手を思いながら
ジェニーに手を差し伸べた。
ジェニーは戸惑いながらも、差し出されたその手に包まれた。
それは彼女にとって、初めての肉親の手だった。
≪大きな手・・≫
彼女は自分の胸が何かに圧迫される恐怖に震えながら
それでも何故か心地良い温もりをその手から感じ取っていた。
ダイアモンドヴィラの一室が、テジュンの心遣いによって、
ジェニーと父との再会の場所となっていた。
レオに連れられソウルホテルへと案内されて来たその父は
馴染めないテーブルの前で落ち着かない様子だった。
フランクとジェニーがジニョンに案内されて中へ入ると、
父はすぐさま椅子から立ち上がった。
テジュンやジニョン達は長い時を経て巡り合った家族の為に
静かに席を外した。
対面を果たした三人は、互いから少しだけ視線を逸らしていた。
家族と呼ぶには、余りに長い年月をそれぞれに過ごし過ぎていて
その緊張を破るのに少しの勇気が必要だった。
「お父さんだ・・・挨拶を・・・」
フランクはジェニーに向かって静かにそう言った。
≪君を捨てた男だよ、ドンヒ・・
さあ、好きなだけなじるといい
君にはその権利がある≫
するとジェニーは緊張の面持ちのまま前に進み出て、初めて見る父に
ホテルの仲間達に教わった韓国式の正式な挨拶を捧げた。
父は自分が捨ててしまった娘の、心を込めた挨拶を目の当たりにすると、
込み上げるものに堪えきれなくなったのか、思わず彼女に駆け寄り
ひざまずく彼女を泣きながら立たせると自分の犯した罪を詫びた。
「会いたかった・・・死ぬほど会いたかった」
ジェニーは父の腕の中で子供のように泣きじゃくっていた。
≪何を言うんだ、ドンヒ・・
そんなこと言うんじゃない!≫
そして彼女は止めることのできない嗚咽の中で
「生きていてくれてありがとう」と父に繰り返した。
生きていてくれてありがとう
彼女のその言葉の重みを、フランクは心の奥で噛み締め、目を閉じた。
その言葉を口にする妹が恨めしかった。
いいや本当は羨ましかったのかもしれない。
しかし・・・
≪僕は・・・言えない≫
涙ながらに抱きあう父と妹の姿は、フランクにとって余りに衝撃だった。
僕は21年もの間、この父を恨んで・・
憎んで・・そして捨てた
しかし僕にとってのたったひとりの存在の証は・・・
ドンヒは・・・あの人をあんなにも求めている
フランクは居たたまれなかった。
気が付くと、ふたりから目を背け、きびすを返しドアを開けていた。
ドアの外にはジニョンがいた。
しかしフランクは、心配そうに彼を伺う彼女からさえも目を逸らし
逃げるようにその場から立ち去った。
ジニョンがフランクの後を追いかけると、彼は漢江に向かって
静かに佇んでいた。
彼女は少しの間黙って、彼のその広い背中を見つめていた。
彼がまるで景色の中に溶けてしまいそうなほど、儚く見えた。
彼女は堪えきれず駆け寄ると、彼の背中を後ろからそっと抱きしめた。
「ドン・・ヒョクssi・・・」
ジニョンはフランクをそう呼んだ。
「ドンヒョク・・・お願い・・・
・・・泣かないで・・・」・・・
passion-27.絆

collage & music by tomtommama
story by kurumi
その半年前から養護施設に預けられていたドンヒは あの別れの朝、最後にひと目だけどうしても会いたくて あの時あの子を抱きしめて泣いてしまったのは・・・ あの時僕らはとても長いこと・・・声を上げて泣いていた でも・・・僕にはその後の記憶がない ≪あの頃僕が大人だったなら・・・≫何度思ったか知れなかった 「こうしてここから眺める景色は実に爽快だね」
「ジェニー?」
≪ジニョンさんと一緒に住んでいるジェニーです≫
・・・あの子が・・・
「何てことだ・・・」
「どうした?ボス・・」
「ジェニー・・・ドンヒ・・・」 フランクは不思議な巡り合せに驚きながら
胸を突き上げてくる熱いものを秘かに堪えていた。
「この子も・・・リストに?」
フランクは次に用意していたリストラ対象者リストを指してそう言った。
「ああ・・次のリストには上がっている」
レオが手に持った書類を指ではじいて答えた。
「・・・・・」
「フランク・・これは既にソウルホテル側にも渡してあるものだ
今更この中から、たったひとりを外すわけには・・
それがお前の妹とあっちゃ、尚更だな・・」
「わかってる」
「しかし・・・どうする・・」
「期限はいつだった?」
「ひと月後だ・・・そろそろ各人にホテル顧問弁護士から
告知されることになってる」
フランクは前回の急襲的なリストラのやり方に対して、
ソウルホテル側から強い抗議を受けていた。
そしてジニョンの父ソ・ヨンスから、今後のリストラは飽くまでも
正攻法で決着をつけることを進言され、フランクも承諾した。
もともと前回は、ホテル側に大きなショックを与えることが目的であり、
その目的が達せられた今となっては、フランクにとっても
ホテルへのそれ以上の攻撃は無意味でもあった。
結果、ヨンスの要求通り今後のリストラは彼によって個人への事前告知、
そして必要に応じて各人のその後の求職相談にも乗ることを
条件とし、進めることとなった。
それにしても皮肉なことだ。
フランクがホテル経営監査人としての立場で動いているとはいえ、
今や、フランク・シンという男はホテルに勤める人間にとって
脅威とされている男である。
そしてその男フランクが突きつける銃の先には妹ドンヒがいた。
その日の昼下がり、フランクはバックヤードのドアをそっと押した。
そのドアの向こう側では、裏で働く人々が行き交い、忙しく動いていた。
まるで表舞台とは別の時間が早回しに存在しているようだった。
そこを何かを捜し求めながらゆっくりと進む場違いな男とすれ違う度に、
人々は怪訝な表情を露にしていた。
「ジェニー!何やってるんだ!
早くじゃがいもとたまねぎ持って来い!」
厨房の奥から聞こえてきた怒号に、フランクは胸が騒いだ。
「はい!」
快活な声と共に厨房から飛び出して来たひとりの女の子と、
フランクは出会いがしらにぶつかった。
「きゃっ・・ごめんなさい!」
「失礼・・」
彼女はぶつかった男が、ホテルの、そしてテジュンの敵であることに
瞬時に表情を強ばらせ、彼を睨み付けながらその横を通り過ぎた。
彼は、彼女が食料庫に入り、そこから玉ねぎの箱を抱えて出て来る行動を
胸が潰れるような思いでずっと目で追っていた。
その時転びそうになった彼女を、思わず助けしようと彼の腕が伸びたが
冷たく彼女に撥ねつけられた。
彼女の持つ箱から転げ落ちた玉ねぎを彼が拾い上げ彼女に差し出すと
彼女はそれを彼の手から乱暴に奪い取った。
「ここはお偉い方がいらっしゃるところではありませんよ!
たとえ理事であっても、ここへの出入りは料理長の許可を得て
白衣を着なければ入れないんです
それともまたリストラする人間を探してるんですか?」
彼女は彼に対して、敵意をむき出しに突っかかってきた。
「あ・・いや・・」
情けないことにこの時彼は、彼女への言葉が何ひとつ浮かばなかった。
何かに突かれたかのように、胸が痛く、苦しかった。
「何もご用が無いなら、邪魔しないで下さい!」
ドンヒはそう言い捨てて、プイと顔を背けた。
フランクにとって、ドンヒに突き放されたことはショックではなかった。
ただ微かに記憶に残る母の面影を彼女の中に見つけて、
胸が震えるほど熱く、動揺する自分に衝撃を受けていた。
この韓国を出てアメリカに渡ったあの日・・・
僕はまだ11歳の誕生日を迎えていなかった
既に僕の存在も忘れかけていた
あの子がいる施設にひとりで行った
目の前に現れた小さくてあどけないドンヒに
僕は思わず彼女の手に頬ずりをして泣いた
そして僕は次第に愛しさが込み上げて、
思わず彼女を強く抱きしめてしまった
ドンヒは突然の僕の行為にびっくりしたみたいに
まるで火がついたように泣き叫んだ
母さんはとっくに死んで・・・父さんは僕を捨てた
そしてたったひとり僕に残されたはずのあの子は
既に僕の存在すらも忘れかけていた
あの時の僕の思いは今も覚えている
あの子のあどけない顔を覗きながら僕はこう思っていた
≪この子が僕を忘れてしまったら・・・
僕という存在はいったいどこにあったんだろう
どこへ消えてしまうんだろう・・≫と・・・
そして今、ジェニー・アダムスとして生きるこの子には
現実に僕の存在など、心の隅にすらない・・・
その恐怖に震えていたのかもしれない・・・
それともただ・・・
あの子の温もりを失いたくなかっただけなのかもしれない
例えあの子と僕の涙の理由は違っていても
あの時は確かに僕達ふたりは繋がっていたんだ・・・
その後どうやってドンヒの手を離したのか・・・
その記憶がまったく無い・・・
時が過ぎ・・・故郷が恋しくて涙する度に思い出していたのは
その時のドンヒの大きな泣き声とあの子の甘い匂いだった
≪そうしたら決して君の手を離しはしなかったのに・・≫
フランクは漢江を挟んだ向かい側の高台から流れる光の糸を
愛しそうに眺めながら言った。
「ええ」 ジニョンもまた彼と同じ景色に視線を向け、頬を緩めた。
三十分ほど前、フランクからの電話を受け、彼女は彼の為に
ダイアモンドヴィラのエントランス前に椅子をふたつ並べ待っていた。
「どうぞ・・・掛けて」
ジニョンは目の前の椅子を示して、フランクに言った。
「ああ・・ありがとう・・・でもいいの?ここでこうして
僕と過ごしても・・・」 フランクは首をかしげるようにして微笑んだ。
「私・・・今は勤務中じゃないの」 ジニョンは悪戯っぽい笑顔で答えた。
「そう・・」 彼は彼女に穏やかな視線を送ると、椅子に腰を下ろし、
目の前の美しい景色にまた視線を移した。
そして清々しく深呼吸するように胸を逸らした。
ジニョンもまた椅子に腰を下ろすと、彼の横顔を愛しげに見つめた。
「どうして・・・話してくれなかったの?妹さんがいたなんて・・・」
十年前、フランクはジニョンに自分の生い立ちを語っていた。
しかしその時、彼の口から妹の存在は語られなかった。
「んー・・・どうしてだろう・・・
心の何処かで・・僕の中に彼女を置き去りにしたという
罪悪感があったのかもしれない」
フランクはゆっくりと語り始めたが、その瞳には寂しさが漂っていた。
「あなたが置き去りにしたんじゃないわ」
ジニョンはすかさずそう言った。
「思い出したところでどうする?そう思っていた・・・
忘れようとしたんだ・・・韓国での全てを・・・
あの子の存在をも・・・」
「・・・・」
「それなのに・・・
あの子を見てると、喉に何かが閊えたみたいに苦しかった
あの子の苦労や不幸な出来事全てが
自分の責任のような気に・・・」
フランクは込み上げる涙を堪えるかのように、宙を仰いだ。
「あなたのせいじゃない」 ジニョンは努めて静かにそう言った。
本当は叫びたかった。
≪苦しまないで≫ そう言って彼を抱きしめたかった。
でも今は、彼はきっとそうして欲しくはないのだと思った。
「そんなに真剣に慰めないで・・ジニョン・・・」
そう言ったフランクに、ジニョンは泣き顔のような笑顔を向けた。
≪そうなのね・・・今は・・・
こうしてあなたを見つめていればいいのね・・・フランク≫
「ああ・・・」 フランクはジニョンの心の声にそう答えた。
ジニョンは一瞬少し驚いた顔をして、直ぐに満面の笑顔を彼に送った。
「でも・・・あなたの妹さんが・・・ジェニーだったなんて・・・」
「さっき、厨房に行ってみたんだ」
「そう」
「でも睨まれた」 フランクは寂しげに苦笑した。
「ふふ・・あなたは今、ホテルの敵だから」
「その前にも彼女には会ったことがある」
「そうなの?・・いつ?」
「二週間くらい前・・君のアパートの前で・・・
その時も彼女にきつく睨まれた」 フランクはまた苦笑した。
「・・・・・」
「ジニョンオンニにはテジュンさんという恋人がいますって
あなたはジニョンさんを心配しないでって・・」
「あ・・ジェニー・・テジュン信者だから」
「信者?」
「ええ・・テジュンssiの言うことには間違いはないと
思ってるの・・あの子・・」
「信用があるんだね・・彼・・」
「アメリカで彼女が十代の頃から彼が世話をしていたのよ」
「アメリカで?」
「彼女を面倒見ていた牧師さんが亡くなって、
テジュンssiが後を引き受けたらしいわ」
「そう・・・そうだったのか・・・」
「彼が彼女をここへ連れて来たの」
「・・・・・・」
「・・・・フランク?」
ジニョンは遠くに視線を置いたまま沈黙したフランクに問いかけた。
「同じアメリカに住んでいたのに・・・どうして出会ったのが・・・
僕じゃなくて、彼だったんだろう・・・」
視線はそのままにポツリとそう言ったフランクに、ジニョンは
掛ける言葉を見つけられなくて、しばらく彼の横顔を見つめていた。
「・・・・・」
「あ・・ごめん・・・」
「ううん・・・」
「・・・彼に感謝しないといけないね」
「・・・そうね」
「彼女・・・」
「えっ?」
「僕に会いたくないかもしれない」
「そんなことないわ・・あの子が韓国に来た理由は
もしかしたら、本当の家族に会えるかもって・・
そう思っていたのよ
きっと本当のことがわかったら喜ぶ・・」
「僕は・・・本当の家族だろうか・・・」
「弱気なのね・・・あなたらしくないわ」≪いいえ、あなたらしい・・・≫
「彼女に・・・ジェニーには私から言って欲しい?」
「ああ・・そうしてくれると助かる」
「しょうがないわね、本当に・・・弱虫なんだから・・」
そう言ったジニョンの目はとても優しかった。
「ああ・・弱虫なんだ・・・
君がいないと・・・何も出来ない」 そう言ってフランクは
寂しさを残したままの熱いまなざしでジニョンを見つめた。
「冷酷なハンターはまた何処かへ消えたの?」
「ふっ・・・それを言われると胸が痛い」
「でも・・・」
「ん?・・・」
「弱虫で・・いいわ・・・」 ジニョンは悪戯っぽい眼差しでそう言った。
「私の前では・・・弱虫でいい」
フランクは「フッ・・」と小さく笑いながらジニョンから顔を逸らせると、
直ぐに彼女に視線を戻して、優しく睨んだ。
そしてふたりはしばらく言葉を交わすことなく、ただそこに佇んだ。
彼女は彼の心を癒すように優しくその眼差しを見つめ続け・・・
彼は彼女に、もろく崩れてしまいそうな心を素直に委ねていた。
ジニョンはフランクと別れた後、ジェニーを探して厨房に向かった。
「ジェニーは?」
「たった今あがったよ」 料理長が大きな声を張り上げた。
「そう、ありがとう!」 ジニョンはすぐさまきびすを返した。
「おい!・・・何なんだ?いったい・・忙しい奴だな・・」
料理長の声がジニョンの背中を追いかけたが彼女は既に走って消えていた。
今度は更衣室へと向かった。「ジェニー知らない?」
「ジェニーなら、たった今・・」とスタッフに出口を指差され、
ジニョンは従業員通用口へとまたも走った。
家に帰れば彼女に会えるのはわかっている。
でも・・・急いで伝えたかった。一刻も早く知らせてあげたかった。
≪ジェニーの為・・いいえ、フランクの為に・・・≫
ジニョンが呼吸を小刻みに乱しながら通用口を走って出ると、
スロープの先にジェニーの影をやっと見つけた。
「ジェニー!待って!」
ジェニーはジニョンの大きな声に驚き振り向いた。
「オンニ・・・どうしたの?」
ジニョンは更に走ると、やっとのこと、ジェニーを捕まえることができた。
しかし彼女は走り過ぎた為に、呼吸を整えるのに少々時間が掛かった。
その間、ジニョンはジェニーの腕をしっかりと掴んで離さなかった。
ジェニーはそんなジニョンを不思議そうに見つめていた。
「オンニ・・・いったい・・どうしたの?」
「ハァハァ・・待って・・ハァハァ・・ちょっと苦しい・・
あなたの・・・」
「ん?」
「あなたの・・お兄さんが・・・みつかった」
「・・・・・・!」
翌朝フランクがジョギングから部屋に戻ると、ジェニーが
部屋の前に立っていた。
彼女の目が、ジニョンから事情を聞いてそこに来たことを
素直に物語っていた。
フランクは軽く息を整えながら、彼女へ掛けるべき言葉を探した。
・・・「・・・・・朝ごはんは?」・・・
passion-26.おそれ

collage & music by tomtommama
story by kurumi
「今夜は泊まって行ってくれる?」
フランクはジニョンの唇に唇を軽く重ねたままそう言った。
「・・ここに?」 ジニョンは驚いて、少し身を引くと目を丸くした。
「そう・・・ずっと僕と一緒にいて・・・」
フランクはすがるような目でジニョンを見つめた。
「フランク?」
ジニョンは困った顔をして首をかしげ、俯いた。
「ね・・・」 フランクは彼女を下から覗き込んだ。
「それは・・・できないわ」
「どうして?」
「どうしてって・・・」
「人の目が怖いかい?」
「・・・・あなたこそ・・・」
「ん?・・」
「あなたこそ・・・何がそんなに怖いの?」
ジニョンはそう言いながら、フランクの頬を細い指でそっと撫でた。
「僕が?・・」
「ええ・・・」
「どうして・・・そう思うの?」
フランクは頬に触れた彼女の手を取って、自分の唇に持って行くと
その手に優しくくちづけた。
「何だか・・・そう見える・・」
「フッ・・・そうかもしれない・・・僕は・・
きっと怖がっている・・・
君が僕のそばにいなかった長い年月は
僕にとってひどいものだった・・・
もうあんな世界に戻るのは嫌だ・・・」
「戻らないわ」
「本当に?」
「ええ・・私も・・二度と嫌よ・・
あなたがいない世界なんて・・いや・・」
「そうだね・・・戻らない・・・決して・・
でも僕は臆病者になってしまったのかもしれない
こうして君を・・・自分の手元に置いておかないと
不安でしょうがないんだから・・・」
「不安?」
「ああ・・すごく・・・」
「さっきまでの強引なあなたは何処へ行ったの?」
「さあ・・・どこかへ消えてしまったようだ」
「ふふ・・あなたが臆病者だなんて、誰が信じるかしら」
「ね・・いいでしょ?」
フランクはジニョンの耳の厚く柔らかい部分を甘く噛みながら囁き続けた。
「ねぇフランク・・・私も・・・あなたとずっと一緒にいたい・・・
でも・・今は・・・」
「・・・・・」
彼は無言のまま、唇を彼女の喉に這わせながら真直ぐ下りていった。
「フラン・・ク・・・」
彼女が嗜めるように呼んだ彼の名は、溜息に混じって聞こえた。
「・・・ジニョ・・ン・・」 彼は彼女から少しの間も唇を離さなかった。
「はっ・・・フ・・ラ・・・」「お願い・・今夜は・・ここにいて・・・」
「・・ン・・ク・・・・」
「ね・・いて・・」
「・・・だ・・め・・」 ジニョンの抵抗は甘い吐息に消えた。
「許さないと・・言ったら?・・・」
フランク・・・あなたは・・・
非情で冷酷な人だと恐れられている
でも本当は・・・そうじゃないわ・・・
私は知っている・・・
強さと・・・弱さを・・・
いつも背中合わせに抱いている
私の・・・フランク・・・
こうしてあなたの心を撫でていると・・・
私はいつも・・・
寂しい瞳をしたあなたに出会ってしまう
そんなあなたを見るたびに
私の方がずっとあなたを離したくなくなるの・・・
私の方がずっと・・・あなたと一緒にいたくなるの・・・
でも今はだめよ・・・それは・・・
あなたも・・・わかってるでしょ?
ジニョンはまだ薄暗い明け方近くにフランクのベッドを下りた。
まさか明るくなってから、この部屋を出るわけにはいかない。
彼女は、急いで身支度を済ませ、まだ眠っていたフランクの頬に
そっとくちづけると部屋を出た。
≪ずっとそばにいて・・・≫
フランクはジニョンを抱きながら、何度も繰り返していた。
そのフランクの声がジニョンの脳裏からいつまでも消えなかった。
ジニョンはそんなフランクがあまりに愛しくて、何度も何度も
サファイアを振り返りながら、坂を下りた。
フランクはジニョンがこの部屋を出て行く音を確認すると、
閉じていた目を静かに開けた。
「・・・うらぎりもの・・・」 そしてそう呟いてフッと笑みを浮かべた。
フランクはわかっていた。
≪これ以上、自分の思いを無理強いしたら、
ホテルとの板ばさみに彼女はひどく苦しむことになる≫
信じてくれる・・・
今はそれだけで・・・良かったはずなのに・・・
君を手にしてしまったら・・・
もっともっと・・・欲しくなってしまう・・・
本当に僕の元にあるのかが不安で・・・
また君がいつかこの手から零れ落ちそうな気がして・・・
片時も離れていたくない・・・
そうだよ・・・
君の言うとおりだ・・・
僕は怖くて・・・仕方がない・・・
君を抱いていないと・・・
何もかもが怖くて仕方がない・・・
フランクの改革は結果的にはソウルホテルを救うことになる。
ジニョンはそう信じると決めた。
しかしフランクが何を考えているのか、何をしようとしているのか・・・
ジニョンにはまだ本当のところをわかってはいなかった。
テジュンがこの状況を乗り切ろうと懸命になっていることにも
現実にリストラなどの処遇により厳しい境遇にある仲間達のことも
考える度にひどく苦しかった。
「君は黙って見ていなさい」 フランクはジニョンにそう言った。
「心配しないで」 彼女の杞憂を慮ってフランクは更にそう言った。
ジニョンはフランクの声に黙って頷いた。
彼の言葉、全てを信じると誓いながら。
「ジニョン・・」
「パパ・・」
フロントにいたジニョンにヨンスが笑顔を向けながら近づいてきた。
「まだ仕事は終わらないのかな?」
「いいえ・・今終わるところよ」
「少し話を・・・いいかい?」
「え・・ええ」
父もまた、リストラの対象となった人々のために、再就職の斡旋など
自分の出来うることに懸命に挑んでいた。
ジニョンはフランクと敵対する立場にある父に対しても、
申し訳ない思いでいっぱいだった。
ジニョンは父を屋上へと誘った。
「ここが話に聞いていたお前の憩いの場所かい?」
「ええ・・一度パパにも見せてあげようと思ってたの」
「このホテルとの付き合いは長いが、ここは初めてだな」
「ふふ、本当はここ立ち入り禁止よ
だから他の人はめったに上ってこないわ・・
私の場所なのよ」 ジニョンはヨンスに満面の笑顔を向けた。
「元気そうだね、ジニョン・・」
ヨンスは彼女のその笑顔に向けて、嬉しそうに言った。
「ええ・・何んとか」
「何んとか?」 ヨンスはジニョンの顔を下から覗きこんだ。
「な~に?・・・ふふ・・そうね、と・て・も・・」
「そうだろ?何だか、吹っ切れたような顔をしている」
ヨンスはそう言いながら、深呼吸するように空を仰いだ。
「ええ・・そうかも」 ジニョンも同じように深呼吸をして空を仰いだ。
「・・・フランクは元気か?」
ヨンスは漢江に視線を移して、正面を見据えたまま切り出した。
「えっ?」
「私がこんな質問をするのは以外かい?」
「・・・・あ・・いいえ・・・」
当然、自分とフランクのことは父の耳にも入っているだろうと思っていた。
しかしジニョンはまだ父に話すことはできないと思っていた。
「彼を信じてるんだね」 ヨンスの言い方はとても穏やかで
決してジニョンを非難しているのではないことがよくわかった。
「・・・・ええ」 ジニョンは素直にそう答えた。
「そうか」
「ごめんなさい」
「どうして謝るんだ?」
「どうしてって・・」
「謝るんじゃない。ジニョン・・・それは彼に対して失礼だろ?」
「・・・・・」
「ジニョン・・・もうお前は一人前の大人だ
あの頃・・・お前はまだ子供で・・・
私はただ・・神から授かったお前に
どうしても幸せな人生を送って欲しくて・・・
彼から引き離してしまった・・・
お前の幸せは彼の元には無いと信じて疑わなかったんだ
それが、結果的に神に逆らうことになるとは・・・
思いもしなかったよ・・・」
ヨンスは今までの自分の後悔を懺悔するかのように切々と話した。
「・・・・・」
「許しておくれ、ジニョン」 ヨンスはそう言って、ジニョンの頭を撫でた。
「パ・・パ・・」
「私がお前達ふたりの時間を奪ったことに変わりはないが
お前達は自分達の力で・・・自分達の意思で
お前達の時間を手繰り寄せたんだね」
ヨンスはしみじみとそう言った。
「許してくれるの?」
「“彼は必ず私を迎えに来る”・・・
NYから戻ったお前は来る日も来る日もそう言い続けた・・
覚えているかい?」
「ええ・・」
「その頃、そんなお前を見るのが私は辛かった
自分が犯してしまった罪を認めることが怖かったんだ・・・
だから苦しんでいたお前に目を瞑ってしまっていた」
「いいえ・・パパだけのせいじゃないわ・・・
私ね・・・フランクをすごく愛してる・・・
怖いくらいに・・愛してる
彼がここへ来て・・それがよくわかったの・・・
だから今すごく後悔してるの・・・私はどうして・・
待つことしかしなかったんだろうって・・」
「ジニョン・・・」
「だから・・・パパのせいじゃないわ・・・
私のせい・・・そして・・彼のせい・・
私達ふたりのせいなの・・・
そのせいで私達・・今でも苦しんでるの・・・」
「・・・・・」
「でも安心して?パパ・・もう大丈夫だから・・私達・・・」
そう言ってジニョンはヨンスに微笑んだ。
「そうか・・・大丈夫か・・・」 ヨンスもまたジニョンに微笑を返した。
「彼を・・信じてくれる?」
「彼がしていることは、今までのソウルホテルの有り方を
根底から覆すようなものだ
果たしてそれが吉と出るのか・・・今はわからない」
「・・・・・」
「しかし・・・私は信じたい・・・」
「・・・・・」
ジニョンはヨンスの言葉を聞きながら胸を詰まらせていた。
「彼がここに現れた時・・彼が何をしにここへ来たのか
直ぐにわかったよ・・・きっと・・
彼を待っていたのは・・お前だけじゃなかったんだ」
「パパ・・・」
「ジニョン・・・」
「え?」 ジニョンは零れそうになる涙を指で拭いながら父を見上げた。
「もう少し後でいい・・・
彼に・・・伝えてくれないか・・・」
「・・・・・」
「今度は君と酒を飲みたいと・・・」 ヨンスはそう言って笑顔を向けた。
「ええ・・伝えるわ・・パパ・・・もう少し・・後で・・」
そう言いながらジニョンはヨンスの腕にしっかりとしがみついた。
それから二日後のことだった。
「ボス・・・見つかったぞ」
「ん?」
たった今しがたサファイアに届けられた書類は、
フランクの妹ドンヒの消息を知らせるものだった。
「何処に?」 フランクは緊張した面持ちでレオを見た。
「ソウルだ」
「ソウル?」
「連絡先がある」
レオのその言葉に、フランクは瞬間的に受話器を持ち上げ、
レオに向かって顎をしゃくった。
その連絡先にあった番号は驚いたことにソウルホテルの厨房だった。
フランクは思わず、用件も告げずその受話器を置いた。
「レオ・・ソウルホテル従業員名簿を・・
厨房で働く人員にアメリカ名は?」
「ひとりだけいる・・・ジェニファー・S・アダムス・・」
「ジェニファー・・・ジェニー?」
≪ジニョンオンニのことは心配しないで!≫
≪ジニョンさんと一緒に住んでいるジェニーと言います≫
・・・あの子が・・・ドンヒ?・・・
|
|
passion-25.途

collage & music by tomtommama
story by kurumi
例えそうでなかったとしたら・・・
奪い取るしかない・・・
攻撃的にも思えたフランクの言葉がジニョンには不思議と優しく心に響いていた。
フランクの唇が彼女の唇を噛みながら彼女を愛しむように音を立てた。
互いの唇から漏れる甘い吐息がひとつになると、まるで心までもが交じり合い、
抱きあう錯覚を覚えた。
きっととっくにふたりの心は重りあっていた
きっととっくに・・・ふたりは信じあっていた
互いの瞳の奥にその事実を見出すだけで
重ねた唇の熱がふたりの心を繋ぐだけで・・・
ふたりのすべてが救われるようだった
そしてふたりは心の中で互いに向かって叫んでいた。
あなたを・・・誰よりも・・・
何よりも・・・
愛している・・・と・・・
「僕を・・・信じるね」
「ええ・・・」
「僕がここへ何をしに来たのか・・・誰の為に来たのか・・・」
「わかってるわ」
「君の立場が今以上に悪くなるかもしれない・・・
今以上に辛い思いをするかもしれない・・・でも・・・
ほんの少しの間だ・・・だから・・・耐えられるね」
「ええ・・・大丈夫」
フランクはジニョンの頭を優しく撫でて、声には出さず≪いい子だ≫と口を動かし微笑んだ。
ジニョンは彼が昔よくしてくれたその仕草に、口を尖らせてみせて「もう子供じゃないのよ」と笑った。
フランクとジニョンはふたり並んでカサブランカを後にした。
ジニョンはもう、仲間達にもフランクとの関係を隠そうとはしなかった。
案の定ふたりを追う仲間達の目は決して温かいものではなかった。
≪私は大丈夫≫
ジニョンはフランクを見上げて、瞳の奥でそう語りかけた。
フランクは彼女の肩を強く抱き寄せて、それに答えた。
ソウルホテルの夜は、神々しいほどに輝いていた。
ジニョンはダイヤモンドヴィラの眩しいばかりのライティングに視線を送りながら、
その裏側に思いを馳せて心を曇らせた。
「それじゃ・・・今日はもう遅いから帰るわ」
ジニョンがフランクに向かってそう言った瞬間、フランクは彼女の手首をグイと掴んだ。
「な・・フランク・・何?」
彼はジニョンの手を掴んだまま、サファイアの方角を目指して無言で坂を上がって行った。
「フランク!」
ジニョンは大またで歩くフランクについて行くために小走りにならざる得なかった。
その間、彼は彼女の手を決して離さず、自分の斜め後ろで文句を並べ立てる彼女の顔を
覗くこともなく、真直ぐ前だけを見て突き進むように歩いた。
そしてフランクは、サファイアの自分の部屋の前に着くなり、大きく息をひとつ吐いた。
ジニョンは胸を押さえ、苦しそうに小刻みに呼吸を繰り返しながら彼への不満を繋げようとした。
「フ・・フラン・・ク・・もう・・」
しかしフランクは彼女のその声など聞こえないかのように、構わずそのまま部屋のドアを開けた。
部屋に入りメインルームのドアを開けると寛ぐレオの姿がそこにあった。
「ボス・・遅かったな・・・あ・・」
レオは振り向いた瞬間、フランクの横で困惑を絵にかいたような
ジニョンの姿を見て、言葉を詰まらせた。
「レオ・・お前、今夜は何処かに用があるんだったよな」
フランクはレオに向かって表情も変えず突然そう言った。
「用?・・いやそんなものは・・・」
レオがそう言いかけた時もフランクの顔は無表情だったが、レオはフランクの意図を
瞬間に汲み取った。
「あ、ああ・・そうだった・・・
俺は今夜は用があって・・そうだ・・帰らないんだった」
そしてレオはたった今思い出したというように、そう言いながら、自分の部屋へと急いだ。
「ボ~ス・・俺は明日の昼頃。帰ってくるんだったよな」
ほんの少しして部屋から上着を持って出て来たレオがそう言って、
彼のそばをわざとらしく横切った。
「・・・・・」
フランクは変わらず無表情のまま、彼のその言葉にも返事をせず、
彼が部屋を出るのを待った。
「何のつもり?」 ジニョンは怪訝そうにフランクの顔を覗いた。
「こっちへ来て」
フランクはその間ずっと離していなかったジニョンの手をしっかり握り直して
彼女を自分の寝室へと導いた。
「駄目よ」 ジニョンは思わず彼の手から逃れようと腕を引いた。
「どうして?」 しかしフランクは決してその手を離さなかった。
「だって・・だめ・・」 ジニョンはそう言って下を向いた。
「ジニョン・・僕を見なさい。」 フランクの拒絶を許さないような
強い言葉にジニョンは困惑を抱いたまま顔を上げた。「・・・・・」
「ホテルでお客様との個人的な時間は過ごせません・・
そう言いたいの?」
「・・・・・」
「なら聞く。・・今君は職務中?」
「違・・う・・けど・・・」
「ここの従業員は個人的にここへ宿泊することはないの?」
「・・・あ・・るけど・・」
「だったら・・君は今一個人・・そして僕の恋人だ。」
「そう・・だけど・・」
「君は僕を信じると言った・・」
「でも・・それとこれとは違う。」 有無を言わせないように畳み掛けるフランクの言い様に、
ジニョンは何んとか応戦しようと顎を上げた。
「何が違う?」
「無茶言わないで」
「何が無茶?この僕が。・・君を抱きたいと思うことが?」
「フランク・・」
「僕は・・君が欲しい。」
フランクはジニョンの目を真直ぐに見つめて自分の想いを率直に告げた。
「でも・・・ここではいや」 ジニョンは彼のその目を頑なに拒んだ。
「ここでなきゃ駄目だ。」 彼は引かなかった。
「どうして?」 彼女も引かなかった。
「どうしても。」
フランクは彼女の迷いを払拭するかのように突然彼女をきつく抱きしめた。
「・・・フ・・ランク・・」
彼は彼女の耳元で、「ここでなきゃ駄目だ・・・」と繰り返し囁いた。
そしていつの間にか薄紅色に変わった彼女の柔らかい耳を唇で噛んで
誘うようにくちづけを繰り返した。
強引な言葉とは裏腹に、フランクのその行為は繊細で優しかった。
「・・・だめ・・よ・・・だ・・め・・・」 ジニョンはまだ足掻いていた。
しかし、いつの間にか甘い吐息と化した彼女の声からは拒絶の色は消えていた。
ジニョン・・・
君は今までも・・・これからも・・・ソウルホテルを離すことはできない
それなら・・・僕は・・・
そのホテルごと君を愛するしか・・・ないだろ?
君は僕のすることを信じると決めたんだ
だったら・・・
その覚悟を・・・見せて・・・
テジュンは「21世紀ヴィジョン」への出資者を手当たり次第に探した。
ソウルホテルの主要株主はもちろんのこと、面識のある有識者、
韓国内外大企業の経営者、思い当たる所にはなりふり構わず願い出た。
しかし、その結果は散々なものだった。
ヨンスの言うように、今ソウルホテルは多大な負債を抱えている。
≪そんな状況下で、いったい誰がお金を出すだろう≫
テジュンの胸の奥に、諦めの雫が滴り落ちかけていた。
そんな時、一本の電話を受け取った。
「ヒョン・・・元気ですか?」
「ジョルジュ?」
それはソウルホテル長男イ・ジョルジュからのものだった。
「ええ・・お久しぶりです」
「お前!・・」
ジョルジュがソウルを再び離れて7年が経過しようとしていた。
その間彼は一度も韓国の地を踏んではいなかった。
「ヒョン、ご無沙汰して申し訳ありませんでした・・」
テジュンがソウルホテルで働くようになった頃、彼はまだ高校生だった。
その頃からホテルのふたりの息子達はテジュンを兄と慕っていた。
「まったくだ。」 テジュンは突き放したようにそう言った。
しかし彼のその言葉には温かさが滲み出ていた。
「父の葬儀の時は大事な仕事で拘束されていて・・・
申し訳なく思っています」
「ああ、わかってるよ・・聞いている・・しかし、社長が寂しがってらっしゃるぞ。
ホテルも今大変だしな」
「ええ、でもホテルにはあなたがいる」
「俺は・・・」
「ん?」
「俺は・・・何の役にも立たんさ」 テジュンは少し寂しそうに言った。
「そんなことはない・・・ソウルホテルはあなたじゃないと駄目だよ・・
父さんがいつもそう言っていた」
「俺じゃなきゃ駄目なことなんて、あるのか?」
テジュンは珍しく弱気になっていた。
「何言ってるの?ヒョン・・・
あなたがいつも父さんや母さんを助けてくれていたんでしょ?
あなたが・・・ジニョンを励ましてくれてたんでしょ?
あなたがヨンジェを立ち直らせてくれた
僕は・・・あなたに沢山の恩を感じてるんだ」
「恩?・・そんなもの感じる必要はない・・
それよりジョルジュ・・帰って来ないのか」
「いや、そこはもう僕の場所じゃない
ホテルはあなたが・・・そしてホテルをいつの日か・・
その時が来たらヨンジェに・・・」
「お前・・・やっぱりその為に?」
「えっ?・・」
「ヨンジェの為に・・・」
「そんなことはないよ・・・
僕はジニョンに振られて逃げ出しただけ・・・」
「そうか?」
「でも、ホテルのことは・・・ホテルはやはり実の息子が継ぐべきだ。
ヨンジェが継ぐべき・・・・そう思ってる」
ジョルジュはその昔、子供に恵まれなかったチェ社長夫妻が、養子縁組をした子供で
その5年後に生まれたヨンジェはその事実を知らされていなかった。
その為に、ヨンジェはジョルジュがホテルを捨てて行ったと思い込み、彼に対して
複雑な思いを募らせていた。
「ジョルジュ・・・」
「それはそうとジニョンは・・・元気?」
「ああ・・元気だ」 ≪色々あるがな≫
「そう・・・ヒョン・・・ごめんね」
≪きっとフランク・シンの存在はあなたを苦しめているんだろうね≫
ジョルジュは心の中でそう呟いた。
「ん?・・何をお前が謝るんだ?」
「いや・・・何でもない」
≪ごめん・・・でもジニョンには・・彼だけなんだ・・・
フランク・シン・・・彼だけなんだ・・・≫
ジョルジュはジニョンの幸せを望んでいた。そして彼女の幸せには、フランクが必要なのだと
信じていた。
「ところで急に何だ?・・もしかして社長の・・」≪病気のことを?≫
「母さんがどうかしたの?」
「あ・・いや・・」
社長から病気のことはジョルジュに伝えるな、と口止めされたことを
思わず言い掛けてしまいテジュンは慌てて口を噤んだ。
「今日僕が電話したのはビジネスなんです」
この時、ジョルジュは母親の病気のことはまったく知らなかった。
「ビジネス?」
「ええ・・今僕がお世話になっている方が・・」
「・・・お前、今何処に?」
「今僕はNYパーキンコーポレーションにいます」
「パーキン・・?」
「ええ・・・それでね、ヒョン、実は頼みがあります」
「あなたって・・・」
ベッドにうつ伏せたまま、ジニョンはフランクの顔を見ることなく
シーツの中に潜ったようにモゴモゴと口を開いた。
「何?」 フランクは彼女のその背中に唇を落として聞いた。
「あなたって・・・きらい。」
「そう・・・」
「本当よ!・・あなたって・・本当に嫌い!」
ジニョンは勢い良くフランクに振り返って睨んだ。
「でも・・・そうは言ってなかった、さっき・・」
「その勝ち誇った顔・・もっと嫌い!」
「この顔は・・生まれつきだ」 フランクは満面の笑みを彼女に向けた。
ジニョンの顔は頬を膨らませて彼を睨んだままだった。
フランクは微笑みながら彼女の大きく膨れた頬を自分の唇で押して潰すと
彼女の背中にもう一度腕を回した。 「ごめん・・・」
「・・・・・・!」
ジニョンは彼の唇で潰されたその頬が次第に緩むのを感じていた。
「もっと謝らなきゃ駄目?」
フランクが彼女から少しだけ離れて、彼女の顔を覗きこむように言った。
彼女は彼のその顔を見て、思わず吹き出したように笑うと、彼の背中に腕を回し、優しく撫でた。
そして安心しきったような笑みを浮かべながら彼の胸に頬を埋めた。
ジニョン・・・いいかい?
これから僕達はふたりで歩くんだ
ふたりで・・・信じた途を・・・
そうしたらきっと
明るい光へと辿り着くことができる
さっきふたりで眺めたあの眩いホテルの輝きを
本物の輝きにするために・・・
君があの輝きを心から愛しめるように・・・
心から誇れるように・・・
そして僕は・・・僕の手に残るのは君だけでいい・・・
君がそばにいてくれる・・・
それだけでいい
本当だよ・・・
たとえ・・・多くの何かを失おうとも・・・
僕は何ひとつ悔いは無い・・・
それが僕のただひとつの途だから・・・
君が・・・僕の・・・
・・・途だから・・・
passion-24.神との賭け

collage & music by tomtommama
story by kurumi
リストラ戦争が勃発したと、バックヤードの隅々までもが大騒ぎとなった。
リストに載った者と逃れた者との間で只ならぬ確執も生まれていた。
しかし、今回は運よく逃れたとしても、これから先第二弾第三弾と
続くのではないかという強迫観念は残る者の気持ちをも萎縮させていた。
またフランクの打ち出した改革案は、人員のリストラだけに留まらず
様々な経費の削減案が盛り込まれていた。
減給はもちろんのこと、働く母親達への育児補助・厚生施設など
フランクが無駄と考えるものは容赦なく廃止された。
また仕入れ先の洗い直しなどにも力を入れ、一部の幹部との癒着で
繋がっていた業者は即刻出入り禁止とした。
「総支配人、リストラは無いとおっしゃったじゃないですか
私達はこれから・・・どうすれば・・・」
その声は怒りを通り越した、哀れなほどの悲嘆だった。
「小さな子供を抱えて、仕事はできません・・・
でも仕事をしないと育ててはいけないんです」
テジュンは言葉に詰まって、ただ項垂れた。
そして彼は自分に許可無く張り出されたリストを乱暴に剥ぎ取ると
それを握り締めて、フランクの元へと走った。
テジュンが部屋の主であるフランクに許可も無く押し入った時
フランクは書類に目を通していた視線を少し上げただけで
彼の登場を予測していたかのように、驚きすら見せなかった。
「どういうつもりです!」
テジュンはその紙切れをフランクのデスクに叩きつけ声を張り上げた。
「どういうとは?」
フランクは全く動じる様子も見せず、書類に目を通している姿勢のまま
片方の眉だけを上げ平然と答えた。
「勝手なまねを・・あなたにそんな権利など・・」
「言いがかりもいいところだな・・・
私はあなたの代わりに決断して差し上げたと思っている
むしろ感謝して欲しいくらいだ。」
「頼んだ覚えは無い。」
「お人よしのあなたには時間をいくら差し上げても
出来そうにないと判断したんです」
フランクはわざとらしく溜息を混ぜて、手の中の書類をばさりと
デスクの上に放した。
「あなたには!この人達の何もわかっていない・・
彼らがどれほど、ホテルに貢献したかも
どれほどの愛情を持っているかもわからずに
どうしてこんなことができるんだ!」
「言ったはずです。
従業員の人となりなど、私は一分の興味も無い。」
「彼らの力無しではソウルホテルはなかった。」
「今は違う。」
「もっと他に・・・方法があるはずだ。」
「言ってもらおう・・何ができる?」
「・・・・・」
「結局何もできない。
ふっ・・吠えるだけなら誰でもできるんです」
「人を軽く見ていたら、ホテルはお終いだ」
「人の代わりなど、いくらもいる。」
「あなたには!・・・きっと。
女の代わりもいるんでしょうね」
フランクとテジュンは睨み合ったまま、しばし微動だにしなかった。
ジニョンのことに触れられる時だけが、フランクを一瞬人間に戻す。
そのことにフランク自身もとっくに気がついていた。
しかし、今は人間ではいられない。
「・・・ここでは仕事の話だけにしていただきましょうか」
「これがあなたの仕事ですか」
テジュンはフランクを見下ろすように言った。
「ええ」 フランクはまったく動じない、というように彼を見上げた。
「尽くしてくれた彼らは、ホテルの宝なんです」
「ふっ・・そんなことだから・・」 フランクは鼻で笑って見せた。
「私は人の心を忘れるようになったら・・
それこそホテリアーとして失格だと思ってます
もしもそうなったら、私は間違いなく、この仕事を辞める。」
「なるほど・・それは殊勝なお考えだ・・・
だが、あなたがお辞めになったところで私は痛くもかゆくも無い
そうですね・・あなたが辞めるなら、
これからリストラを被る誰かが救われるかもしれない・・
きっとその誰かが喜ぶでしょう」
フランクの言葉は氷のように冷たかった。
「・・・・・」
「言っておきますが・・・
それを破り捨てたところで、決定は変わらない。」
フランクはさっきテジュンが投げつけた紙の残骸を目で指して
そう言った。
「社長は承知しない。」
「ふっ・・おもしろい・・
では今すぐ社長にホテルが現在どういう状況に
陥っているか、確認してくるといい」
フランクは不適な笑みを浮かべながら、テジュンを睨みあげた。
「・・・・・」
「社長はきっとこの書類に判を押しますよ」
そう言って、さっきテジュンが破り捨てたリストラリストが
正式なものと化している書類の束を、フランクは翳して見せた。
「あなたという人は・・・」
「これ以上あなたと話すことはない。
あなたも同意見でしょうが・・・
虫が好かない顔は長く見ていたくはない。
消えてもらいましょうか・・ここから・・今直ぐに。」
フランクはテジュンに向かって放った厳しい目を決して崩さなかった。
まるでソウルホテルそのものをクリーニングするかのように
フランクは隅から隅までを見直し、改善策を打ち立てていった。
その容赦の無い改革に、あがる悲鳴さえフランクは耳を貸さなかった。
そして全てはシン・ドンヒョクの言う通りだった。
今や、ソウルホテルに残された道は、彼が立てた計画に沿う
そのことが最良の策と、あらゆる現実が物語っていた。
ドンスク社長は決断を迫られていた。
ヨンスもあらゆる手を使って、リストラの波を穏やかにできないものか
画策してみたが、ホテルは到底彼の手に負えない程の窮地を迎えていた。
「ドンスクssi・・・申し訳ない・・・
彼の言う通り、人員整理は止む得まい・・・
ただ、これ以上はその波を広げないよう手を尽くそう
それに、ドンスクssi・・・あなたももうお分かりでしょう?
今のままではホテルは立ち行かない」
「ええ・・・でも・・・
私・・・主人に顔向けができません・・・
あんなに人を大切にして来た人ですもの・・・
私・・・彼のところに行った時、このことをどういう風に
報告すればいいんでしょう」
ドンスクはそう言って、涙を流した。
ヨンスは、そんな彼女を前に、深く溜息を付くしかなかった。
そんな中、テジュンは必死にあがいていた。
このまま手をこまねいているわけにはいかなかった。
まず、ソウルホテルとして生き残るために今何が足りないのか
シン・ドンヒョクの考えを覆す手立ては本当に無いものなのか
あらゆる方向から思考を重ね、シン・ドンヒョクに提案書を出した。
しかし、シン・ドンヒョクの反応は冷たいものだった。
「絵に描いた餅ということわざをご存知かな?
こういうのを・・ゴミというんです」
フランクはテジュンの前にその書類を無下に放り投げた。
同席していたジニョンの目が落胆と怒りに満ちていたが
フランクはテジュンを通して、彼女をも冷たく睨み付けた。
それでもテジュンは諦めなかった。
そして寝る間も惜しんで自分の計画書に何度も熟考を重ねることで
次第に強い自信が沸き出る自分を感じ始めた。
次の朝、テジュンの姿は社長とヨンスの前にあった。
彼はふたりの前で背筋を伸ばした。
「お願いがあります」
テジュンはドンスクとヨンスに真剣な眼差しを向け強い決意を語り始めた。
「私に・・・21世紀ヴィジョンを遂行させてください」
「21世紀ヴィジョン?・・三年前、君が計画していた・・
あれか?」
「ええ・・あの計画をもう一度」
「しかし・・それには多くの資金が必要だぞ」
ヨンスは今でさえ多額の負債を抱えている状況で、
それはかなり難しいことだと考えていた。
「はい・・わかっています・・・その為に多くの出資者を
募らなければなりません・・でもやってみる価値はあります・・
是非、やらせてください」
「テジュンssi・・・自信はあるの?」
「はい・・・あります」
「でも・・・今は・・・」
「このままでは、次のリストラ犠牲者を出してしまいます
今、ホテルそのものが快活に起動する何かが必要なんです」
「その何かがこれなのか?」
「はい」
テジュンの返事は力強かった。
テジュンの目は切羽詰っているこの状況の中で、キラキラと輝いていた。
ヨンスは彼のその姿を見て、フランクが望んでいるものはきっと
こういうことなのだろうと、思っていた。
現実は酷なものだった。
100名もの仲間達が苦境の波にさらわれていった。
日毎にひとり消えふたり消え、残された者の心にも影を落とした。
繰り返し続くフランクとテジュンの争いが胸を締め付け、
ジニョンは深く打ちひしがれていた。
≪私には・・・どうすることもできないの?・・・
フランク・・・どうしても、こうしなきゃならないの?≫
スンジョンが深く肩を落としているジニョンを哀れんで、
何んとか励まそうと、カサブランカに誘った。
「ジニョン・・歌おう」
「歌うって・・そんな気分じゃないわ」
「だから歌うのよ」 スンジョンは譲らなかった。
カサブランカの二階に設けられたカラオケ室の中で、
ふたりは意識して楽しげな曲を数曲歌った。
≪嫌なことを忘れて・・・いいえ、忘れられるわけが無い≫
突然、ジニョンが声を詰まらせ曲の途中で歌うのを止めた。
「ごめんなさい・・・ごめんなさい・・・
みんなを苦しめて・・・ごめんなさい・・・」
「ジニョン・・・」
「みんなを苦しめているあの人を・・・私は愛してるの・・・
私は・・・あの人だけを・・・愛してるの・・・
私・・・いったいどうしたら・・・どうしたらいいの?先輩・・・」
ジニョンはマイクを持った手で溢れ出る涙を拭った。
そんなジニョンの姿にスンジョンは掛ける言葉が見つけられなくて
ただ一緒になって泣いていた。
結局心を紛らわすことなどできないまま、ふたりは帰ろうと階段を下りた。
その時、フランクはいつものようにカウンターで寛いでいた。
スンジョンが先に彼に気がついて、ジニョンの背中を指で突いて
「先に帰るわね」と後ろ手に手を振り立ち去った。
ジニョンは少し困惑したように彼を見て、二階へと戻った。
そして彼女は二階の手摺りに手を掛けて、螺旋階段の方へ
視線を向けていた。
少しして彼女の期待通りに黒い影がその螺旋階段を上ってくるのが見えた。
その影は次第に姿を現して、静かにジニョンの元へと歩み寄った。
「君が待っている場所に・・・
こうして僕は一歩ずつ近づいている」
「あなたが辿り着く場所に、私はきっといないわ」
「いるさ・・必ず。」
「もしも・・・いたとしたら・・・
あなただけじゃなくて・・・私も地獄に落ちるわね」
「君となら・・・落ちてもいいよ」
「本当に・・・罰が当たるわ・・・」
「罰?・・・とっくに覚悟してる」
「フランク・・・」
「今日・・教会に行って来たんだ・・・」
「・・・・・」
「神に祈って来た・・・
どんな罰でも受ける・・・その代わり・・・
君だけはこの手に残してくれと・・・」フランクは淡々と続けた。
「それが叶うなら・・・
この魂を差し出してもいい・・・そう言って来た」
そう言い終った時の彼の薄い笑みは余りに寂しげだった。
「私を賭けたの?神様と」
「ああ・・そうだ。」
「私は・・・神の手を取るかもよ」
「いいや・・・君は僕の手を取るよ・・・
・・・もしも・・・そうでなかったとしたら・・・」
「そうでなかったとしたら?」
「・・・奪い取るしかない。」
彼のその言葉は狂おしいばかりに攻撃的だった。
しかしそれとは逆に、その目は寂しげな翳りを漂わせたままだった。
ジニョンはフランクの言葉を、心を震わせながら聞いていた。
“あなたが愛しくてたまらない”心の奥で叫ぶ自分の声が胸を突き上げると
涙が込み上げて仕方なかった。
そしてジニョンは自分の心のなすがまま彼にゆっくりと近づいて、
少し背伸びをすると彼の首に腕を回し、無言で彼を抱きしめた。
「ああ・・・フランク・・・」
ジニョンは溜息を吐くように彼の名を呟いて、彼の肩に頬を乗せた。
「少しだけ・・・こうしていてもいい?」
「少しだけ?・・」 フランクは小さく笑った。
「昔から・・あなたの肩にこうするのが好きだったの・・・
こうしているとね・・・すごく・・落ち着くことができて・・・
気持ちが良くて・・・」
「僕も・・・こうして君を抱いていると、気持ちがいい」
「このまま・・・周りのこと・・何もかも忘れてしまえたら・・・
ふたりだけの世界で生きられたら・・・」
「忘れる?それはできないでしょ?・・・
それにもう僕もそんなことはできない・・・君の為に・・・」
「私の為・・・」
「そう・・・全て君の為だ・・・」
「・・・・私はどうしたらいいの?」
「ただこうしていればいい・・・ただ僕を・・
信じていればいい・・・」
「・・・・・・」
彼女はその後、言葉を繋げないまま、ただ彼を抱きしめていた。
彼もまた、自分の全霊を掛けて自分の腕の中に戻った彼女を
強く抱きしめた。
幾ばくかの時を互いに抱きあい、互いの温もりを確かめ合った後
フランクはそっと彼女の肩に手を置き、彼女を自分から少しだけ離した。
そして彼女に向き合い、彼女をしばらく愛しげに見つめた後
彼女の頬を両手でそっと挟み、くちづけた。
それは昨日の奪うような激しいものではなく、まるで労わるような
優しいくちづけだった。
互いの唇から漏れる吐息がひとつになると、まるで心までもが
交じり合い、抱きあう錯覚を覚えた。
彼のくちづけが、“愛してる”と泣いているようだった。
そうでなかったとしたら・・・
・・・奪い取るしかない・・・
彼はそう言った・・・
そして彼女はわかっていた
彼はその言葉通りに・・・彼女を・・・
とうの昔に・・・神から・・・
・・・奪い取っていたと・・・
| <前 | [1] ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... [36] | 次> |