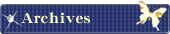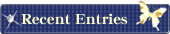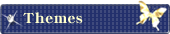passion-8.赤い道標

collage & music by tomtommama
story by kurumi
あなたを・・・許したわけじゃないわ・・・
以来ジニョンはサファイアヴィラに顔を出してくれなくなった。
フランクが用事を頼んでも、代わりの人間がそれに対応した。
彼もまた、それに対して敢えて苦情を申し立てはしなかった。
≪待つよ・・・ジニョン・・・≫
「ボス・・・探していた人が見つかったぞ」
一枚の紙を手に、レオが神妙な顔付きで近づいて来た。
「ん?」
手渡されたその紙には少し草臥れた男の写真が写っていた。
「仕事はどうする?」
「・・・・キャンセルしてくれ」
フランクはこの日が来るのを待っていた
この人に会う日を・・・いいや・・・
21年前、自分を捨てた男の成れの果てを
見定めるその日を・・・
フランクはレオの運転で車を走らせ、東海を訪れた。
21年ぶりに足を踏み入れたその町は、何もかもフランクの記憶の奥深くに
仕舞い込まれ、捨て去られたかのように・・・
≪僕の胸にたったひとつの感傷も蘇らせてはくれなかった≫
この小さな町でその男が住むアパートを探すのは
簡単なことだったがそこに辿り着く前に、フランクは既に
ここへ来たことを後悔していた。
アパートを訪ねると男は留守だった。
「どうする?ボス・・・またの機会にするか」
「いや、もういい」
フランクは彼が留守だったことにホッとしていた。
「おい・・そう言うな・・せっかく見つかったんだ・・・
な、食事でもしていかないか」
フランクが直ぐにもここから去ろうとしていることを察したレオは、
慌ててアパート近くの食堂を指差した。
「こんな場所で?」
「まあ、いいじゃないか」
レオは気が乗らないフランクの背中を押しやって、食堂の扉を開けた。
「おばさん、食事を頼む」
レオが声を掛けると、暖簾の奥から五十絡みの女が出て来て
客用の愛想を振り撒いた。
「あら、お客さん、いらっしゃい!刺身はどうだい?
鍋はサービスするよ」
「それを頼む」
「酒はいいのかい?」
「ああ、酒はいい・・車なんでな・・」
レオがそう言いながら、フランクを見て“お前は?”と目で
問いかけ、フランクは首を横に振ってそれに答えた。
小さくうらぶれたその店は閑散としていて、客はフランク達だけだった。
「この店はどれくらい前からやってるんだい?」
レオが店主に聞いた。
「そうだね、20年位になるかね・・どうしてだい?お客さん・・」
「いや・・そこのアパートに住んでるシンのおじさん知ってるだろ?」
「あんた達・・まさか借金取りかい?」
「いや、違う違う、昔の知り合いなんだ」
「そうかい・・・知ってるよ、うちにも良く来る・・
実は迷惑なんだけどね」
「オンマ・・そんなこと言わないで」
暖簾の奥から二十歳位の娘が、会釈をしながらやって来ると、
フランクのテーブルに料理を並べながら、母親を嗜めた。
「何言ってんだい・・お前が甘やかすから、
いつも来るんじゃないか」
「おじさんは可哀想な人よ・・」
「可哀想なもんかい!いつも呑んだくれて、
お前が悪いんだよ
ただ飯食わしたりするもんだから、調子に乗ってるんだ、あの親父」
「そんなこと言うもんじゃないわ・・オンマ・・
それにおじさんは小さい頃から私を可愛がってくれたわ」
「そりゃあ、捨てちまった娘のことを思い出してるのさ」
「娘?」
フランクが鋭い目を店主に向けると、彼女はビクリと体を堅くした。
「あ・・そういやあ、シンのおじさんには息子がいただろ?」
レオがとっさに取り繕うように店主に言った。
「息子もとっくにアメリカに養子に出しちまったんだよ、
まったく、ギャンブルに狂って、呑んだくれて・・
自分の子供を売っちまったんだ・・
ろくな生き方をしてないね!あの男は」
「オンマ!止めてったら」 娘は母の腕を引いた。
「娘さんも養子に出したのかい?」 レオは再度訊ねた。
「ああ、二歳にもならないうちにね」
店主の歯に絹着せぬ言い様が全てを真実だと物語っていて、
フランクは俯いたまま言いようのない怒りに体を震わせていた。
その時急に外が騒がしくなったかと思うと、ひとりの男が店に駆け込んで来た。
「大変だ!警察を呼んでくれ!」
「どうしたんだい?」 店主が言った。
「シンのおじさんが・・家の前でやくざに絡まれてる」
男はひどく慌てていた。
その時、その言葉を聞くや否や、フランクが店を飛び出した。
フランクがその場所に走って向かうと、さっき訪ねたアパートの前で数人の
見るからに素性がわかる男達が、ひとりの老人に殴る蹴るの暴力を振るっていた。
フランクは駆けつけて瞬時に男達の腕を掴み、無言で彼らに立ち回った。
そして男達は彼によって簡単に地面に叩きつけられた。
「何しやがる!
俺達はこいつに金を返してもらいに来ただけだぞ!」
「金?」
「ああ!こいつが借金を返さねえんだよ!」
「いくらだ」 フランクは男の腕を後ろ手にひねり上げたまま言った。
「1万ウォン」
「1万?」
フランクは彼らを睨みつけた後、後から追いかけて来たレオに向かって
顎をしゃくった。
レオは財布から金を数枚出すと、その男にくれてやりながら、
「もう二度とシンに近づくな。」と凄みを利かせた。
男達は過分に渡された紙幣に対して、急にぺこぺこと頭を垂れながら、
その場から逃げるように立ち去った。
老人は殴られたからなのか、酔っていたからなのか、地面に座り込んだまま、
正体を失っていた。
突然フランクはその老人の襟元を掴むと、乱暴に彼をその場に立たせた。
「1万?たったの1万?・・そんなはした金のために・・・
あんたは・・あんたはいったい何をやってるんだ!」
フランクは言いようの無い怒りがふつふつと沸いてくる自分と戦っていた。
≪あの男達と同じように・・・
この男を死ぬほど打ちのめすことができたなら・・・≫
「離せー、俺を誰だと思ってるんだ。俺にはなー金持ちの息子がいるんだぞ~
金なんか、いつだって返してやるよ~」
老人が突然、フランクの腕を払って、喚き散らした。
「息子なんていないだろ?本当にもう、何やってんだか・・
ほら!しっかりしなよ」
「おじさん・・しっかりして・・大丈夫?」
老人の両脇に、さっきの店の親子が駆けつけていた。
「うるさい!息子はいるんだよ!俺の息子はな!アメリカで成功して、
金持ちになってんだ・・」
「そうかいそうかい」
店主が聞き飽きたという顔でそう言った。老人は尚も続けた。
「俺がそうしてやったんだよ・・
俺があいつらがちゃんと食べて、ちゃんと勉強できるようにな・・
俺が手放してやったんだ~
あいつを幸せにしたのは俺なんだぞ~」
「幸せ?」 フランクが小さく呟いた。
「・・・・・」 老人はフランクの声に、怪訝な顔をして、無言のまま彼を見上げた。
「あんたに・・・何がわかる・・・」 フランクはまたも呟いた。
そして老人の胸倉を再度激しく掴んで言葉をぶつけた。
「あんたに何がわかる!
自分を捨てた親を一生恨み続けることしかできない子供の気持ちが!
どんなに断ち切ろうとしても、断ち切ることも出来なくて。
死に物狂いで勉強して、仕事で成功しても・・
余るほどのお金を手にしても!
いつまでも拘って拘って・・誰にも心が開けない!
幸せなんて一度も!たったの一度も感じたことがない!
そんな情けない気持ちが!あんたにわかるのか!」
フランクは今にも泣いてしまいそうな自分を怒りで堪えた。
老人はフランクの叫びに一気に酔いを醒ましたかのように目の前の若い男を見た。
そして、男のその瞳の中に、彼の子供の時の姿を見つけて、目を大きく見開いた。
「お・・お前は・・・」
「あなたが・・・どんな生き方をしているのか・・・
一度見てみたかった・・・」
そしてフランクは心の涙をごくりと飲み込んで、言葉を繋げた。
「これで本当に終わりです。もう二度と・・・
会うことはないでしょう。」
フランクは止め処ない怒りを胸深くに押し込めて、努めて淡々と言い放つと
老人の胸倉からその手を乱暴に離した。
そして、自分の内ポケットから、白い封筒を出し、老人の胸に押しやるように
叩きつけた。
その封筒は呆然と立ち尽くす老人の胸から滑り落ちて、地面にひらりと舞い落ちた。
それからフランクは、傍にいた店の娘の方に向き直って、彼女に一枚の小切手を
差し出した。
「食事の支払いです・・・それから・・・色々とありがとう」
フランクは厳しい顔も厳しい声も変えられぬまま、娘にそう言った。
娘は少したじろいだが、彼から手に押し込まれた一枚の紙を黙って受け取って、
それを見た。
食事の代金にしては余りに高額だった。
「あの・・」と娘が声を出した時には既に、フランクは車へ戻り、
レオに向かって怒鳴っていた。「車を出せ!」
「待ってくれ・・話を聞いてくれ」
老人はやっと我に帰って、フランクの後を追った。
レオは無言で運転席に戻ったが、しばしエンジンを掛けるのを躊躇っていた。
「いいから!出せ!」
フランクは、車のドアで老人との間を遮断すると、前だけを見据えて再度怒鳴った。
レオは、仕方なくエンジンを掛けた。
「待ってくれ・・話を・・話を・・」
走り出した車に老人は追いすがったが、フランクは決して、老人を振り返らなかった。
「ね、凄いお金だよ・・億だよ・・億!」
さっきの封筒を拾った店主が慌てて、老人に駆け寄った。
老人は差し出されたその封筒を、言葉にできない悲しみと
自分自身への怒りに任せて、宙に放り投げた。
フランクは締め付けられる胸の奥で≪これで終わりだ≫と繰り返していた。
しかし、自分のその言葉に打ちのめされたように、予期せぬ涙が頬を伝った。
≪泣いてなんかいない≫
更にそう自分に言いきかせて、その涙を信じようとしなかった。
それなのに、それが自分の意に反して止め処なく流れると口の中に入り、
その苦さを教える。
フランクはとうとう、眼鏡を外し、手でその涙を押さえ、
堪えきれない嗚咽を我慢するのを止めた。
フランクが落ち着くのを待ってレオが声を掛けた。
「もう一度戻るか」
「どうして」
「・・・そうしたいんじゃないかと思ってな」
「余計なことを言うな」
「お前が成功したこと・・・親父さん、知っていたな」
「・・・・」
「親父さん、あんな風に言ってたがな、
本当に喜んでいたそうだ・・お前の成功を・・」
「どうしてお前がそんなことを?」
フランクは怪訝な目でレオを見た。
「おふくろさんの墓に寄るか?」
「いや・・今日はいい」
≪こんな自分を母には見せられない・・・≫フランクはそう思った。
「毎月な・・・墓に花が添えられるそうだ」
「・・・?」
「若い女の人が来ていると、さっきの店の娘が言ってた」
「娘?・・お前、初めてじゃなかったのか」
≪そう言えば、あの娘はレオを見て会釈したようだった≫
「ああ・・お前を連れてくる前に一度訪ねた・・・
時々親父さんと墓参りに行くんだそうだ、あの娘・・
それで何度か綺麗な花を見かけて・・誰がこんなことをって
親父さんと一緒に待ってたんだそうだ
親父さんはな、最初・・もしかしたら、お前か・・娘か・・・
そう思っていたらしい・・・」
「ドンヒじゃなかったのか?」
「違ったそうだ・・・」
「誰だったんだ?」
「誰だろうな」
レオの言い方は決して知らない、とは言ってなかった。
「わかってるんだろ?」 フランクもまた同じだった。
「・・・・お前にも・・・もう・・わかるだろ?」
「・・・・・・」
赤い灯台の前を通ると、急に懐かしさが込み上げて、フランクはレオに
停車を促がした。
ここは幼い頃、父に連れられてよく魚釣りに来ていた・・・
その時の父はとても優しくて、餌をつけて僕に竿を握らせた
≪いいか、ドンヒョク・・しっかり握ってるんだぞ・・
魚がえさに食いつくのをこうやってな・・
静かに待つんだ・・≫
≪父さん!引っ張られるよ!≫
≪よ~し、そのまま踏ん張って竿を上げてみろ
上手いぞ~その調子だ≫
フランクは突然走馬灯のように浮かんだ父の笑顔を思いながら、
フゥと大きく溜息をついた。
「どうして今頃・・・あの人の笑顔なんか・・・
思い出すんだろう・・・」
そう呟いてフランクは寂しく笑った。
あの人を許せない僕と・・・
君から許されない僕・・・
どちらも・・・罪深い・・・
そうだろ?・・・ジニョン・・・
そしてフランクはポケットから携帯電話を出すと、メールを打った。
受信ソ・ジニョンssi・・・
・・・配信シン・ドンヒョク・・・
|
|
passion-7.空

collage & music by tomtommama
story by kurumi
「ソ支配人」
フロントの前で見かけたジニョンにフランクが声を掛けた時、
彼女は見るからに顔面蒼白だった。
「何かあったのか?・・」
彼は慌てて彼女に駆け寄ると、思わずその腕を掴んでいた。
ジニョンは他のスタッフの自分達を見る視線が気になり、
急いで彼から離れた。
「あ、いいえお客様・・ご心配には及びません・・
それより何か急ぎのご用でしょうか・・・」
ジニョンは努めて平静を装ったが、周りのスタッフの様子からも
只ならぬ問題が起こっていることは事実のようだった。
「いや・・いい・・」
フランクは彼女の邪魔にならないようその場から少し離れたものの
彼の神経はソ・ジニョンに向かって研ぎ澄まされた。
「ソ支配人・・何処にも見つかりません」
「外には出ていないはずよ・・もっと探して」
「ソ支配人!」
そこへひとりの男が血相を変えやって来たかと思うと、
ジニョンを激しく怒鳴った。
「あれほど頼んだのに・・どうしてくれるんだ!」
「申し訳ございません・・」 ジニョンは男に深く頭を下げていた。
男が怒りをぶつけながら、勢い余って彼女の腕を掴んだ瞬間
フランクはとっさにふたりに駆け寄ってその男の腕をねじ伏せ、一喝した。
「彼女に何をする」
「何だ!あんたは・・」 男は一旦フランクから逃れて、彼に身構えた。
「申し訳ございません・・・・お客様・・こちらへ・・」
ジニョンは慌てて、今にもその男を殴らんばかりのフランクを
急いでその場から引き離し、フロントの袖に彼を連れて行った。
「フランク、余計なことは止めて!・・
事情もわからないのに乱暴するなんて・・
あのお客様には私に怒る権利があるの
あなたには関係ないことだわ」
ジニョンは小声ではあるが、強い口調で彼を嗜めた。
「しかし・・あいつ・・君を・・」
「私は仕事中なのよ・・フランク・・
あの方のお子様がお部屋からいなくなってしまって・・
あの方がお出掛けの間、お世話を頼まれていたの
私の責任なの!」
「子供?」
「ええ・・長期滞在中の女の子・・
この前あなたも私と一緒のところ見かけたでしょ?」
「・・・・ああ・・」
フランクは先日エレベーター前で見かけた女の子を思い出した。
「だからと言って・・」
フランクはまたカウンターに視線を移して男を睨んだ。
「止めて・・お願い」 ジニョンはフランクに懇願するように言った。
その時、フロントには総支配人のハン・テジュンが現れ、その客を宥め、
スタッフ総動員で娘を探していることと、警察にも連絡を取ったことなど
卒のない対応をしていた。
「・・今はどうかお部屋に・・お客様。」
ジニョンはフランクに釘を刺すような視線を残して、フロントに戻り
総支配人と共にその客の男に再度頭を下げた。
フランクはその光景に思わず目を背けていた。
ジニョンの窮地を救うのが自分ではなく、別の男だという事実に。
そして彼はそれ以上は係らずその場を離れ、彼女が言うように
自分の部屋へときびすを返した。
彼がサファイアヴィラに近づくと、玄関の前に子供を連れた
若い女性の姿が見えた。≪あれは・・・≫
フランクは彼女に向かって声を掛けた。
「ユンヒssi」 その女性はキム会長の娘、ユンヒだった。
彼女は今実家を出て、このホテルに滞在していると聞いていた。
そしてその横で彼女に手を引かれているのは、今本館で探している
その女の子に違いなかった。
ユンヒはフランクに振り向いて、会釈をした。
その女の子はというと、彼に対して可愛くないほどに仏頂面だった。
「どちらへ?」 フランクはユンヒに行った。
「今、お訪ねしようかと」
「僕の部屋へ?」
「ええ・・・」
「この子は・・・君の隠し子?」 フランクはわざと真顔でそう言った。
「ふふ・・そんな真面目なお顔して・・・私が10歳の時に生んだ子ですと
言った方がいいですか?」 ユンヒは返した。
「君でも冗談を言うんですね」
フランクはユンヒに対して初めて素直な笑顔を向けた。
「・・・・・」
「どうしたの?」
フランクはユンヒが驚いたような顔で彼を見つめていたので訊ねた。
「初めて笑ってもらったかも・・あなたに・・」
「そうかな」
「そうです」
≪確かに彼女と会う時はいつも、僕の方こそ仏頂面だったかもしれない≫
フランクは思い出したように笑って、ユンヒの笑顔と向き合った。
「ところで、その子はたった今・・支配人達が血相を変えて探して・・」
フランクがそう言いかけた瞬間、その女の子がユンヒの後ろに
素早く隠れた。
「えっ?そうなの?スジナ・・ホテルの人に話して来たんじゃ・・」
「嘘をついたのかい?お姉さんに・・」
フランクは少し身を屈めて、その子に言った。
「困ったわ・・じゃ、帰らなきゃ・・」
「いやよ!・・わたし帰らない!」
スジンはユンヒにしがみついて離れようとしなかった。
「僕の部屋へはどうして?」
「ええ・・実は・・・」 ユンヒは女の子を見下ろしながら言いかけた。
彼女の様子から少し混み入った話のようだったので、フランクは
「中で話そう・・フロントには安心するように電話を入れておけばいい」
そう言って、彼女達を部屋の中へ招き入れた。
「わぁ~・・この前来た時と同じお空・・」
部屋に入ると、スジンはさっきまでの仏頂面から一変して
子供らしい声を立ててはしゃいだ。
≪空?≫
「ソ支配人を・・」 フランクはフロントに電話を入れた。
『ソ支配人は只今、手が離せませんので・・』
「とにかく、何を置いても部屋へ来なさい、今直ぐに。そう伝えて。」
フランクは文切り調に言って、スジンのことには触れず受話器を置いた。
「いいんですか?」
フランクの電話の内容を聞いて、ユンヒは不安な眼差しを彼に向けた。
「君達の話を聞く間位はいいでしょう・・・さあ、聞かせてくれるかな?」
フランクはスジンの視線まで身を屈めて言った。
「お父さん・・君を探していたよ」
「お父さんなんて、きらい!」 スジンは目にいっぱい涙を溜めていた。
フランクは事の次第を訊ねようと、ユンヒに視線を移した。
「この子、父親の仕事に付いて、今ホテル暮らしなんだそうです
つい最近お母さんを病気で亡くしたばかりだそうですが
父親はこの子の面倒を見ながら、仕事をしているのだとか・・・
そのせいで彼女はいつもひとりぼっちで・・・」
ユンヒはそう言いながら、スジンを悲しそうに見つめた。
きっと自分に置き換えて彼女を見ているのだろうと、フランクは思った。
「それで・・どうしてこの部屋に?」
「ええ・・彼女の母親が健在中に何度かこのホテルに
泊まったことがあって・・・
そんな時はいつもこのお部屋だったそうなんです・・
この子にとって思い出の部屋なんですって・・・
この子・・ソウルホテルに泊まると聞いてこの部屋に泊まれると思って
喜んでいたそうなのですが・・・」
「先客があったわけだ」
「ええ・・・それに、ここは離れになっているので
子供ひとりでは置いていけないと、本館を選んだのだと
父親が言っていたそうです
この子とは何度かロビーで会ったことがあって、
よくおしゃべりしていたんです
そしたらさっきひとりでこっちに向かっているこの子を見かけて・・・
聞いたら、今日もお父さんがお仕事中でひとりだって・・
話を聞いて、私がつい、知っている人がこの部屋に泊まっていると・・・
ごめんなさい・・・勝手に・・・ご迷惑でしたよね・・・」
「いいや・・・そんなことはないよ」 フランクは優しげに言った。
「本当に?」 ユンヒはホッとしたように微笑んだ。
「少し、ここで遊んでいくといい」 フランクはスジンの顔を覗いて言った。
「いいの?」
「ああ・・もう少しで怖いお姉さんが迎えに来るから・・
それまでならね」
「うん!おじさん・・ベランダに出てもいい?
あそこからお母さんとお空見てたんだ~~」
スジンは潤んだ瞳はそのままにフランクに向かって無邪気に笑った。
「旅行に来ても、お母さん体が弱くて、このお部屋から
あまり外へは出られなかったんですって」
ユンヒがそっと教えてくれた。
≪だから・・空なのか≫
10分ほどしてジニョンが呼び鈴も鳴らさず部屋に駆け込んで来た。
以外に早かったことにフランクは驚いた。
ジニョンは部屋へ入るなり、スジンを見つけて腰が抜けたように
座り込んだ。
そして次の瞬間、慌ててスジンに駆け寄り、彼女の腕を掴むと
彼女を強く抱きしめた。「スジナ!・・心配したでしょ!もう!」
それだけ言うと、ジニョンは大きな瞳から涙をぽろぽろと零した。
そして小さく呟いた。「・・・良かった・・・何もなくて・・・」
スジンはそんなジニョンの姿に彼女の真意を汲んだのか
同じように泣きながら「ごめんなさい」と繰り返した。
「母親の匂いを見つけたかったのよ・・・」
ユンヒがフランクの傍らでポツリと言った。
「母親の匂い?」 フランクはユンヒを見た。
「お母さんがいなくなってしまったことはわかってる・・・
父親が仕事で忙しいのもわかってる・・・
でも・・・自分の家ではないホテルに置いておかれて
ひとりぼっちで・・・寂しくて・・・
そんな時、この部屋を思い出したんだわ・・・
お母さんの匂いが欲しくて・・・
そして無意識にこの部屋に向かって歩いていたのよ
決して・・・お父さんが嫌いなわけじゃ・・・ないの・・・」
そう言ったユンヒの表情は寂しげだった。
フランクにはユンヒのその言葉がスジンのことではなく、
自分自身のことを言っているように聞こえた。
ジニョンがフロントに連絡した後、少しだけスジンが部屋で
寛ぐ時間を待って一緒に部屋を出て行った。
「それじゃ、私も・・・失礼します・・・」 ユンヒが言った。
「ああ・・お茶も出さなかったね」
「ふふ・・今度は出していただけますか?」
「そうしよう」
「・・・・ありがとうございました」
「礼を言われることしてないけど」
「いいえ・・・あの子の心を受け入れて下さった」
「・・・・・」
「子供にはわかるんです」
「君も子供なのかな?」
「あなたにあんな風に優しくされるなら・・・
子供でもいいかも・・・」
「僕はそんなに優しくないですか?」
「ええ・・・凄く怖いです」
「はは・・・」
ユンヒはフランクを今までにない柔らかい眼差しで見つめていた。
≪母さんの匂い・・・か・・・≫
フランクはユンヒが言った言葉を振り返っていた。
母の匂いなど・・・とうに忘れてしまった
しかし・・・僕も探していたような気がする
あの子くらいの時はまだ、母さんと一緒にいて・・・
丁度ドンヒが生まれて・・・
母さんを独り占めできなくなって・・・
そうだ・・・
母さんに抱かれているドンヒにやきもち妬いてた
フランクはその時の自分の感情を遠い記憶の箱から引き出して
寂しく笑った
遠くこの国を離れた後も・・・
死んでしまったとわかっている母さんが恋しかった
母さんの匂いが・・・恋しかった・・・
フランクはベランダの椅子に腰掛けてそこから空を仰いだ
≪このお空をお母さんと一緒に見てたの≫
僕が・・・母さんと一緒に見上げた空は・・・
・・・どんな色をしていただろう・・・
一時間ほどして、今度は呼び鈴を鳴らしてジニョンが現れた。
「先程は・・・ありがとうございました」
そして彼女は支配人然としてフランクに頭を下げた。
「何も伝えなかったのに、良くわかったね・・あの子がいると」
「あなたが、私のあの状況を知っていたのに、
“何を置いても来い”なんて・・・
あの子と関係がなければ言うはずないもの・・・」
「僕は我侭な客なんでしょ?」
「ええ・・我侭で・・困ったお客様だわ・・・
本当のことを言ってくだされば、ここに来るまでの時間
ドキドキしなくて済んだのに・・・意地悪だわ」
ジニョンは微笑みながら彼を睨んだ。
「君への意地悪は得意だから」
「ふふ・・・そうだったわね・・・」
「・・・・・」 「・・・・・」
ほんの少しの間ふたりは互いの心に寄り添うように見詰め合っていた。
しかし、ジニョンはそれを振り切るように、彼の心から離れた。
「あ・・・あの・・・あの子の父親に説明しました・・
彼女がどうしてここへ来たがったのか・・・
お客様が・・・
あの子の父親があなたにお礼を申し上げて欲しいと」
「礼なら僕じゃなくて・・・」
「彼女?・・・ユンヒさんでしたっけ?・・・
パールヴィラにお泊りのお客様・・・」
「ああ」
「知り合い?・・ですか?」
「んー・・・見合い相手」
「え?」 ジニョンは一瞬顔を強ばらせた。
「・・・・・・・気になる?」 フランクはジニョンの顔を覗いて言った。
「い・・いいえ・・・」
「それは残念。」
「・・・・・」
「嘘だよ・・見合いなんてしてない」
フランクは言葉を交わしながら、少しずつ彼女に近づいていた。
「何も・・聞いてないわ・・私・・」
ジニョンは近づいてくる彼に戸惑いながら、一歩ずつ後ろへ下がった。
「その目が聞いてる」
「わかったように言わないでって・・言ったでしょ?」
「そうだったね・・・」
「あなたが・・誰と付き合おうと・・・」
「関係ない?・・・」
「・・・・ええ。」
後ずさりしていたジニョンがとうとう、背中を壁にぶつけて止まった。
ふたりの距離はフランクが緩く差し伸べた手が簡単に彼女に届くほどだった。
彼が彼女の結い上げた髪のほつれ毛を人差し指で受けて彼女の耳に
そっと掛けてあげると、彼女はピクリと体を堅くして声を漏らした。「あ・・・」
「我を忘れて、あの子を探し回っていたんだね」
「お・・可笑しい?」
ジニョンは俯きながら慌てたように自分で髪を整えるような仕草をした。
「いいや・・・綺麗だ・・・」
「・・・・・」 「・・・・・」
フランクは彼女を見つめたまま、心のままに自分の唇を彼女に近づけた。
彼女は金縛りにあったようにただ彼を見つめたままだった。
「あ・・あなたを・・・許したわけじゃ・・ないわ・・・」
それが彼女の精一杯の拒絶の言葉だった。
「わかってる・・・」
ふたりの唇がもう直ぐで触れそうになったその時、それは音を立てた。
彼女の右手に握られた無線機から、ハン・テジュンの声が轟いた。
『ソ支配人・・応答して下さい』
「・・・・・」「・・・・・」 ふたりは互いの唇の熱を間近に感じたまま
息を呑んで一瞬固まった。
「・・・ふっ・・・彼、君がここにいることを知ってるね」
フランクは仕方なく彼女から離れて、抑揚なく言った。
「そ・・そんなこと・・」
「・・・出れば?」
フランクは不機嫌そうに言った。
「・・・・・・・・はい・・ソ・ジニョン・・」
ジニョンは一度小さく深呼吸をして無線に応答した。
『至急フロントへ』 ハン・テジュンの言葉は短かった。
「了解しました」
「ほらね」
「何が?」
「どこにいるのか聞かなかった」
「・・・・・」
「帰るの?」
「仕事中ですので」 彼女はそれだけを言って、ごくりと息を飲み込んだ。
「じゃあ、終わったらここへ戻って来てくれる?」
フランクは請うように彼女を見たが彼女は少し間を置いて首を横に振った。
「・・・・・いいえ。」
ジニョンはその時にはもう、さっきまでの夢見心地の様子は微塵もなく
憎らしいほどに毅然としていた。
フランクはただ寂しげに笑うと俯き、小さく呟いた。
・・・「・・・わかった・・・」・・・
|
|
passion-6.執着

collage & music by tomtommama
story by kurumi
ジニョンはしばらく、その場で動くことができず、呆然としていた。 ≪外ではもう会わない≫ フランクにそう宣言した。 「ソ支配人に頼みたいことがあるのですが」 フランクとジニョンの昔の関係を知らないホテルの人間達の間では、 しかし彼の彼女への執着は諦めを知らなかった。 水温チェックの為にプールを訪れていたジニョンを見つけたフランクが、 「そうかしら」 ジニョンは呆れた顔をして、ツンと横を向いた。 「あっ疑ってるね?君が水温チェックに来るなんて情報、 「ふふ」 フランクの言い様にジニョンは思わず笑ってしまった。 「そうやって笑っている方が可愛い」 フランクも笑顔だった。
「悪かったわね・・いつもは可愛くできなくて・・」 「・・・・・・・困るわ・・本当に・・噂が広まって・・」 「僕が行くところに君が来てるのかもしれない」 「・・・・・!」 ジニョンは彼を横目に睨んで見せた。 「冗談だよ・・・ごめん・・・ ジニョンは彼のこれまでの行動に呆れ果てながらも 「誤解じゃない」 フランクは彼女の目を射るように見つめて言った。 「困るの」 「僕は困らない」 「・・・・・」 ジニョンはフーと溜息を吐いた 「NYに行かないか」 「・・・・・」 「あの家に・・・」 「えっ?・・だって・・」≪あの家はもう売られたはず≫ 「レイモンドが、戻してくれた」 「レイ・・・」 「駄目よ・・行けないわ」 「どうして?」 「どう・・し・・キャー」 フランクは先に水上へと浮上し、周りを見渡したが、 「まだ、泳げなかったのかい?」 「ごほっ・・ごほっ・・おお・・きな・・お世話・・」 ジニョンがやっと落ち着きを取り戻して、状況を把握すると、 「あ・・あの・・離して・・・」 ジニョンは彼の腕の中でもがきながら言った。 「・・・・・・離すの?」 彼の声が彼女の耳の直ぐそばで聞こえた。 「離して・・ください」 彼女は混乱していた。 「ここで?」 そこはどうもジニョンの足では届かない深さのようだった。 「あ・・・離さないで」 彼女は彼の首に回した手に力を込めた。 「いいよ・・離さない」 「もう少しこのまま・・」 「フランク!」 「わかったよ・・」 プールサイドに辿り着いて、フランクはまず自分が上がり、 ジニョンがプールサイドに上がった時、騒ぎを聞きつけて 「従業員がご迷惑をお掛けしましたようで・・ テジュンはフランクに向かって、穏やかさを装ってそう言った。 「いいえ」 フランクも静かに答えた。 「ソ支配人・・・着替えに行きなさい」 テジュンはフランクに一礼した後、ジニョンの腕を取り、 フランクはふたりの後姿を見送った後、 「失礼ね」 「どうしてあんなことに?」 「つまずいて落ちちゃったの」 「奴も?」 「奴って・・お客様よ」 「お客様も?」 テジュンは嫌味ったらしく誇張して言った。 「彼は助けようとして・・私を」 「そうか」 「それだけのことよ」 「そうだろうな」 「じゃ」 ジニョンは女子更衣室へと消えて行った。 フランクは全速力で二往復泳いだ後にやっとプールサイドに上がった。 さっきこの手に・・・この胸に抱きしめたジニョンの感触が あの時・・・
「駄目・・・」
「どうして?」
「できない」
「僕を許せないから?」
「・・・・・・」
「待ってる・・・」
本当は今、そのドアを開けて、≪彼を追いかければ≫
何もかも上手く行くのかもしれない。≪でも・・・≫
ジニョンは10年前、自分を黙って置きざりにしたフランクへのわだかまりを
自分の心からどうしても拭い去ることができなかった。
≪必ず迎えに来てくれる、そう信じていたのに・・・待ってた私を、
ずっとずっとひとりにしたくせに・・・
あなたなんかに“待ってる”なんて言って欲しくない≫
急に奥の部屋の明かりが点いてジニョンは驚いた。
居間を覗くと、ジェニーとテジュンがソファーに腰掛け座っていた。
テーブルには蝋燭を立てたデコレーションケーキが置かれ
ふたりが誰を待っていたのか、想像するのは容易かった。
「あ・・・」
ジェニーが睨みつけるような顔をジニョンに向けていた。
「あ・・すまん・・・驚かせたな
ジェニーがお前の誕生日を祝おうと準備してくれていたんだ。
それで俺も呼ばれて・・その・・待ってた
玄関で・・あー・・音がしたんで・・その・・・
ジェニーが驚かそうと・・電気消して・・
悪気じゃなかったんだ・・許せ・・・」
たった今しがたの、フランクと自分とのやりとりを目撃していた事実を、
テジュンの言葉のよどみが証明していた。
「・・・・・」
「誕生祝いって雰囲気でもないな・・じゃあ、俺は帰るよ」
テジュンが罰の悪そうな顔をして、立ち上がった。
「あ・・待って、テジュンssi」
ジニョンは逃げるように玄関を出て行ったテジュンを追いかけた。
「待って・・・」
エントランスの出口でジニョンはやっとテジュンに追いついた。
「言い訳はいらない」 テジュンはジニョンを振り向かないまま言った。
「言い訳はしないわ」
「言い訳・・しろよ」
テジュンがくるりと振り向いて、ジニョンを情けないような表情で見つめた。
「どっちよ」 ジニョンは呆れたように彼を見て言った。
「するだろう・・普通」
「言い訳して欲しいの?」
「いや・・」
「あの人は・・」
「いや・・いい」
「言い訳しろって言ったじゃない」
「誕生日おめでとう・・・」 そう言って、テジュンが小さな包みを出した。
「何?」
「いいから・・受け取れ・・」
そう言った後にテジュンの目にジニョンの首にネックレスが見えた。
「プレゼントか」
「あ・・ええ」
「高そうだな」
「ええ・・でも、外すわ・・・」
ジニョンはテジュンからのプレゼントの箱からネックレスを取り出しながら
そう言った。
「こっちの方が私に合ってそう」
「安物って意味か」
「ええ」
「悪かったな」
ふたりは何も言わず照れくさそうに笑った。
そして、テジュンは「やっぱり帰るよ」とジニョンに手を振った。
ジニョンは複雑な笑顔のまま彼を見送った。
彼もまたそれを聞き入れたかのように思われた。
しかし、その後もフランクの積極的な行動は止まらなかった。
ホテル内のレストラン、カクテルバーなど彼はあらゆる場所に
頻繁に姿を現し、ジニョンと遭遇する機会を狙った。
ハウスキーパー達との朝礼の場所に顔を覗かせることもしばしばで
そんな時も彼は明らかにジニョンに向かって満面の笑みを向けた。
ジニョンは他の従業員達の手前、彼を嗜めるしかなかった。
「こんなところで何をなさってるんですか?」
「ジョギングの途中です」
「お客様、申し訳ございませんが
ここは走るところではありません」
「クールダウン中だよ・・走ってはいない」
そう言って彼はわざと空を仰いでジニョンの視線を避けた。
「・・・・・!」
従業員を介してジニョンをカサブランカに呼びつけたこともあった。
「お客様・・・お呼びでございますか?」
「もう仕事は終わりでしょ?一緒にいかがです?支配人」
「御用は何でしょう」
「用・・・んー・・・」
「御用が無いのでしたら・・・」
「逢いたかった」
「・・・・・!」
「それだけでは駄目?」
「・・・・・・」
「だって、外では逢えないのでしょう?」
そう言って、フロントに電話を掛けてくることもしばしばだった。
「ソ支配人は只今手が離せませんので、代わりのものが・・」
「いや結構。・・・それともソ支配人はふたりいるのですか?」
フランクはホテル従業員に対しても露骨だった。
ひとりの客が、ソ・ジニョンという従業員に入れ込んで、
言い寄っているという噂が駆け巡っていた。
そしてジニョンもまた、プレゼントされた300本の薔薇に逆上せ上がり
ホテリアーの品位を失墜しているという噂を実しやかに広める者もいた。
ジニョンは意を決してフランクの部屋に向かった。
「御用は何でしょう・・ソ支配人」
フランクは彼女の表情にその真意を読んで、敢えて白々しく言った。
「フランク・・」
「僕はお客様じゃないの?」
「私にいったいどうしろと言うの?」
「どうしろって?」
「私はここで仕事をしているのよ・・生活をしているの
あなた、私の生活を乱して面白がってるとしか思えない」
「それは心外だな」
「お願いだから・・」
「・・・・・」
「お願いだから・・・私を放っておいて」
「・・・・・」
彼女の言葉に無言のまま視線を落とした彼を見て、ジニョンは
少し言い過ぎたかと、それ以上彼を責め立てることができなかった。
「キャッ!」
そうっと彼女の方に近づき、水面からプールサイドへと飛び上がって
彼女を驚かせた。
「あー驚いた」 ジニョンはその場にしゃがみこんで胸に手を当てた。
「ごめん・・驚かせるつもりはなかった」
「何をなさってるんですか?」
フランクは水からさっと出て、タオルを取った。
「・・・・・見てわからない?」 そう言ってフランクは自分の格好を目で示した。
「・・・・・」 ジニョンは彼の素肌に赤面して俯いた。
「最初に言っておくけど・・待ち伏せたわけじゃないよ」
どうやって掴むの?僕はもう1500は泳いでる」
「怒っている顔も好きだけど」
でも、ホテルの外で会えないなら
仕方ないでしょ?・・しかし・・
ホテルには色んな遊び場があって良かった」
それが彼が自分と会うために懸命に努力している結果だと思うと
心をくすぐられないわけではなかった。
しかし、それはホテリアーとして決して好ましいこととは言えない。
「誤解を受けるわ」 ジニョンは少し後ずさりしながら言った。
ジニョンは、レイモンドの顔を思い浮かべて懐かしそうに彼の名を口にした。
「レイとは親交が?」
「ああ・・・彼の仕事を請け負っている」
「そう」
「行こう・・・一緒に」
ジニョンはフランクの目の力に圧倒されて、更に後ずさりしていた。
突然ジニョンがプールサイドに躓いて、バランスを崩し、
フランクが慌てて駆け寄り彼女の体を抱えるのと同時に
ふたりの体は宙を舞い、プールの水面へとダイブした。
ジニョンの姿がなく、一瞬慌てた。
しかし直ぐに水中でもがいているジニョンの姿を見つけて
ホッとしながら、彼女を救い上げた。
彼女は水を飲んだようで、咳き込んで、少々パニックを起こしていた。
その後、フランクの声が聞こえなくなった。
自分がしっかりとフランクにしがみついていて、彼は自分の体を
黙ったまま強く抱きしめていることがわかった。
彼はその言葉が自分の本心だと彼女にわからせるように想いを込めて
彼女を更に強く抱きしめた。
「・・・・・」 「・・・・・」
「あの・・プールサイドへ連れて行って」
フランクはジニョンの体を包み込んだまま動かなかった
ジニョンは我に帰ると、この状態から早く脱しなければ、と思った。
フランクはやっとジニョンの言うことを聞いてくれ、彼女を抱いて動き出した。
ジニョンに手を差し伸べた。
ジニョンは少し躊躇って、それでも彼の手を取った。
テジュンがそこへ現れた。
申し訳ございませんでした・・お客様」
頭の先からずぶぬれのジニョンを見てテジュンは事務的に言った。
「あ・・はい」
ジニョンもまた、自分を取り繕うように、きびすを返した。
プールサイドを出て行った。
濡れたジニョンを拭こうと手に取っていたタオルを乱暴にイスに放ると、
再度勢い良くプールの中へとダイブして消えた。
「まるで濡れネズミだな」
テジュンはひとつ溜息をついた。
誕生日の一件以来、ジニョンとの進展は特になかった。
真面目な話をしようとすると、冗談で交わされる。
その間、サファイアの客、シン・ドンヒョクという男が、
ジニョンに近づいていることを、ホテルの仲間の口から聞かされた。
ジニョンがあいつとの関係を話そうとしたあの日、思わず、
聞かない選択をしてしまった。
気にならないわけじゃなかった。
≪しかし・・・聞いたところで、どうする・・・≫
ジニョンさえ、自分の元にいてくれるなら、あいつのことなど
気になるわけじゃない。
ただ、一時はあの男を拒絶しているように見えたジニョンがこの所、
彼に対する態度を軟化させたように思えて、胸が騒いだ。
そしておもむろにイスに腰掛けると、まぶたを閉じ体を横たえた。
いつまでも消えてくれなかった。
プールの中で、言葉も無く彼女を抱いていたのは・・・
声を掛けてしまったら・・・
現実に戻ってしまったら・・・
この腕の中から彼女が消えてしまいそうな・・・
そんな気がしたからだ
本当は・・・
離したくなかった・・・本当に・・・
・・・離したくなかった・・・
|
|
passion-5.薔薇の決意

collage & music by tomtommama
story by kurumi
フランクはいつもの朝と同じように、ロードワークで汗を流していた。
こうして風に吹かれていると≪しばし心の騒ぎに休息をくれる≫
フランクは決意していた。
もう一度、彼女を取り戻すことを。
それが彼女が望まないことだとしても、もう自分の心に嘘はつけない。
昨夜自分自身が起こした事実に正直になると決めた。
ジニョンは今朝もまた、アラームが鳴る前に目覚めた。
フランクが目の前に現れてからというもの、いつもそうだった。
でも今朝はいつもとまた違っていた。
昨夜はなかなか寝付けなくて、さっき眠ったばかりだと思ったのに
気がつくと東には既に朝日が昇っていた。
≪離さない≫
フランクのあの声が何度も何度も繰り返しジニョンの胸に響いていた。
≪あれはどういうこと?あなたは何のつもりで、あんなことを?≫
ジニョンは、フランクの理解しがたい行動に対して、
困惑と憤りとそしてあろうことか甘い疼きを感じている自分の心に
苛立っていた。
ジニョンがホテルに出勤すると、オフィスに人だかりができていた。
「どうしたの?何かあったの?」
ジニョンが尋ねると、その人だかりが一斉にジニョンに振り返って
彼女は一瞬後ずさりした。
「ジニョン!」 スンジョンがその輪の中から飛び出て来て、
ジニョンの鼻先に自分の鼻先をつけんばかりに近づいた。
「な・・何ですか・・・先輩・・」 ジニョンは更に後ろへ下がるしかなかった。
「あなた、花屋の御曹司とでもお付き合い始めたの?」
スジョンが一大事でも起きたかのように目を見開いて、そう言った。
「えっ?」≪何のこと?≫
「これ」
彼女が差した指の先に、今までに決して目にしたことがないような、
それは大きな花束がジニョンの机を占領していた。
「まあ・・すごい・・・」
花束のあまりの美しさと豪華さにジニョンの笑顔が花開いた。
「薔薇の花!」 スンジョンは腕組して言った。
「見ればわかるわ」 ジニョンはさらりと答えた。
「300本だって!」 スンジョンの声が次第に強くなってい
た。
周りの空気を察したジニョンが自分を指差して“私に?”と目で尋ねた。
スンジョンは口を尖らせながら黙って頷いた。
「いったい・・誰が・・こんな」 ジニョンはちょっと困ったように苦笑しながら、
中に差し込まれたカードを抜き取った。
それはフランクからだった。ジニョンは目を閉じて溜息をついた。
「あ・・これね・・お礼にって、お客様が・・」
ジニョンは自分の反応をそばでじっと待っていたスンジョンに
弁解するように言った。
「お客様?何で、お客様がこんなことを?
これって、行き過ぎじゃない?
あなた、いったい、お客様に何してあげたのよ!
あ・・まさか・・・・・・」 スンジョンはよからぬことに想像を巡らせ
ジニョンを疑いの眼差しで見た。
「スンジョン先輩!まさかって・・って、何よ!」
ジニョンは急いで、フランクの部屋に電話を入れたが、あいにく彼は留守だった。
しかし、行き過ぎた贈り物をこのままにしておくわけにはいかないと、彼女は
ホテルの中にいるという彼を必死に探した。
「ここにいらしたんですね」
フランクはホテル内に常設されているビリヤード場にいた。
「よくわかりましたね、ここが」
フランクはナインボールに興じながら、ジニョンに柔らかい視線を送った。
「お客様がホテルにいらっしゃる間は、どちらにいらしても把握できます
・・・ホテリアーですから。」 ジニョンは少し自慢げに言った。
「ほう・・それは感心だ」
フランクは笈の先にチョークを塗りつけながら言った。
「それで・・あの・・お花・・」
≪早く本題を・・≫そう思ってジニョンは切り出した。
「ああ、届きましたか?ルームサービス」
「あんなことをされては困ります、お客様。」
「どうして?昨日のお礼です、そう書いてあったでしょう?
受け取って下さい、遠慮なさらずに」
フランクはさらりと答えた。
「オフィスの人間が驚きます」
≪ここで引き下がるわけにはいかない≫ジニョンはフランクを見据えた。
「それじゃあ、今度からご自宅に届けましょう」
「あの!そうではなくて・・・
私はお客様から、プレゼントを頂く理由がありません
・・だから・・」
「だから?」 フランクはジニョンとの会話の間も笈の動きを止めなかった。
「だから・・・あんなことはなさらないで頂きたいんです」
「んー・・・僕はそうしたい。・・・優秀なホテリアーは
客の望みは聞いてくれるんじゃなかったかな」
フランクがそう言っている間に、彼が放った笈の先は俊敏にボールに当たり、
そのボールがまた別のボールを潔い音ではじかせた。
「でも」
「でも?」
「わからないわ」
ジニョンのその言葉を聞いて、フランクは初めて手を休めて、笈を自分の前に立てた。
「わからない?・・何がわからない?
あの花が何の花なのか?それとも・・・
僕が単なる客なのか・・君の男なのか?」
「嫌な言い方。」 ジニョンは彼を睨みつけるように言った。
この時既にジニョンは、ホテリアーとしての仮面を脱ぎ捨て、遠い昔
フランクを知るジニョンとして、その彼を睨みつけていた。
フランクは彼女のそんな変化に気がついて、俯き口元だけで笑った。
≪ジニョンだ・・・≫
「嫌な言い方・・・結構。
しかし僕は戻りたい・・・君の男に。」
「何言ってるの?ふざけないで!」
「ふざけてなどいない」
「そんなに面白いの?私をからかって・・
わかってるわ、あなたは!・・・・」
「あなたは・・・何?」
「あなたは・・・昔自分を好きだった女が
他の男に心を動かされているのを見て
気分が悪くなったのよ・・そうよ
あなた、自分のプライドが許さなかったんだわ」
「君は他の男に心など動いていない」
「どういうこと?」
「僕を愛している」 フランクは彼女を見据えたまま、力強くそう言った。
「はっ・・何言ってるの?・・ふざけないで!」
ジニョンは怒りでカーと熱くなる自分を感じていた。
これ以上ここにいると、自分がとんでもないことを言いそうな気がして、
急いでその場を離れようとした。
「ソ・ジニョン!」
ジニョンはフランクのその声に驚いてぴたりと足を止めた。
フランクは持っていた笈を床に立てたまま、ジニョンを見据えていた。
「どうして韓国へ来たのか・・・そう聞いたね」
「・・・そんなことどうでもいいわ。」
「君に逢いに来た」
「・・・うそつき。」
「うそじゃない・・」
「信じないわ!」
「君も・・・僕を待っていた」
「勝手なこと言わないで!」 ジニョンは彼に激しく言葉を投げつけた。
そして、逃げるようにその部屋を出て行った。
フランクはわかっていた。こんなやり方に彼女が酷く怒ることも。
しかし彼は敢えてそうした。
今、彼女に怒って欲しかったから。
自分に対する怒りを思い切りぶつけて欲しかったから。
だから彼は、強引に彼女に向かって行くと決めたのだった。
≪ジニョン・・・もっと怒れ・・・
もっと・・・僕にその怒りをぶつけるんだ≫
彼女が心の奥深くに彼に対する怒りを押し込めている以上、
≪彼女を取り戻すことなどできない≫
フランクはそう思っていた。
「何言ってるの!何言ってるの!・・
ふざけないで!、私はあなたなんか・・・
あなたなんか!待ってない、愛してない!」
ジニョンは屋上に上がり、漢江に向かって怒鳴り散らした。
しかし、怒鳴った瞬間に虚脱していく自分の体を支えられなくて、
彼女はその場にしゃがみこんでしまった。
≪愛してなんか・・・ない・・あなたなんか・・・
あなたなんか・・・あなた・・なんか・・・≫
夜勤明けの次の朝、ジニョンは鳴り響く電話の音で眠りを妨げられた。
「はい・・ソ・ジニョン・・・」 電話の主はフランクだった。
ジニョンは慌てて飛び起きて、電話の向こうの声が言うままにベランダから下を覗くと、
携帯電話を耳に当てたフランクが上を見上げて、こちらを伺っていた。
「どうして携帯の電源を切ってるの?」
「あなたが何度も電話してくるからでしょ!」
あの薔薇の事件があってからというもの、フランクはことあるごとにジニョンを追い
挙句にはホテル内のみならず、彼女の携帯にまで電話をよこすようになっていた。
「しかし苦労したよ・・自宅の電話番号調べるの・・」
フランクはジニョンが迷惑だと言っている言葉を全く無視していた。
「・・・・・!」
その直後、玄関のベルが鳴り、デパートの配達人が持ちきれないほどの
届け物を抱えて部屋に入って来た。それがすべて、フランクの仕業だとわかって、
ジニョンは頭を抱えた。
しばらくして、ジニョンが両手いっぱいに箱と袋を抱えて、エントランスを出て来た。
「どうして?」フランクは不満そうに言った。
「あなたこそ・・どうしてこんなことを?」
「今日、君の誕生日だから」
「えっ?・・」
ジニョンは自分の誕生日のことなどすっかり忘れていた。
「今まで君の誕生日、祝ったことがなかったから・・・
10年分のお祝い・・・」
そう言って、フランクは満面の笑みをジニョンに向けた。
「とにかく・・あなたに祝っていただく義理はないわ・・
これはお返しします」
「返されても困るよ・・僕が持ってても仕方ないし」
「でも、受け取れないわ・・お店に返してください」
ジニョンは決して引き下がらなかった。
「わかったよ・・・その代わり、食事は一緒に行ってくれる?
もう・・予約してあるんだ」
「・・・・・・・」
ジニョンは呆れて怒った顔のまま、それでも溜息混じりに頷いた。
フランクが予約していたのは、最近韓国にできた
“three
handredroses”だった。
「覚えてる?」
「ええ・・あ・・だから・・・」
「そう・・300本の薔薇・・」
「・・・・・」
「君がどうしても行きたいって、あの時そう言った・・・
あの頃僕はちょっとばかり稼いだ全財産を叩いて
家を買ったばかりで余りお金を持ってなかった。
だから君にも余りおしゃれをさせて上げられなくて・・・」
「そんなの必要なかったわ」
「あの頃もそう言っていた・・・」
「・・・・・」
「でも今はどんな贅沢もさせてあげられる」
「だから?」
「だから・・・」
「あの時も・・・今も!私はそんなこと
ひとつも望んでいなかったし・・・望んでいない」
「わかってる」
「わかってないわ・・・
高い物を贈ればいいってことないの
私が欲しかったのは・・・」
「欲しかったのは?・・・」
フランクはその先の言葉が聞きたい、というように、彼女の目をみつめた。
「・・・・わ・・私は。・・・
韓国に戻ってから、自分の望みを叶えるために
必死になって勉強して、今、小さい頃の夢を叶えたの。」
「君の夢は僕だったはずだ」
「そうじゃなくしたのはあなたでしょ!」
つい声が大きくなってしまって、ジニョンは周りを気にして、左右を見た。
「もう一度、君の夢になりたい」
フランクはジニョンのその怒りに決して怯まなかった。
「無理よ。」 ジニョンは今度は静かに、無表情に言った。
「どうして」
「フランク・・・」
ジニョンは呆れたような溜息と一緒にその名前を口にした。
「やっと名前を呼んでくれたね」
それでもフランクはそのことを素直に喜んだ。
「・・・・・・」 彼の輝くような笑顔と対照的に彼女は黙り込んだ。
「待ってたんだ・・・君が僕の名前を呼んでくれるのを」
「いったいどうしたって言うの?急に・・・おかしいわ
あなた、ホテルに初めて来た時も・・あんなに落ち着いて
私とだって、ホテルの客と従業員として
冷静に対応してくれていたじゃない
だから私も、ホテリアーとして精一杯あなたに・・
可笑しいわ・・急にこんなこと・・・」
「気持ちを抑えられなくなった・・それじゃ、答えにならない?」
「この前会ったでしょ?彼なの・・・
私の方からプロポーズした人って・・
彼も・・受け入れてくれてる・・・私達、婚約してるの」
「君は“違う”と言った」 フランクは冷ややかな表情でそう言った。
「言ってないわ」
「言った。・・・それが君の本心だ」
「わかったように言わないで!」
小声を意識しながらもジニョンの語調は強かった。
「わかってる。」
「何が?私の何をわかってるの?」
ジニョンの瞳が堪えた涙で潤むのを見て、
フランクは自分も胸を詰まらせているのを実感していた。
「止めましょう・・・こんなところで・・・
これ以上話しても・・・帰るわ」
ジニョンは席を立ちかけて言った。
「ごめん・・気分を悪くしたなら謝る・・・
でも帰らないで・・・少しでいい・・・
君の誕生日に・・・もう少し、ここにいて・・」
ジニョンは動揺を抑えるように胸に手を宛がって、小さく深呼吸をした。
「いいわ・・・でも、もうホテルの外では逢ったりしない。」
ジニョンは、それが自分の本心と、断固とした口調で彼を見た。
「・・・外で会うことは望まない・・しばらくの間。」
フランクは、今のこの場に彼女を留めて置くために、そう言った。
「しばらくじゃないわ・・プレゼントももう止めて・・」
「わかった・・・ルームサービスももう止めよう・・・
その代わり・・・」
そう言いながらドンヒョクはジニョンの後ろに回った。
「その代わり・・・これだけは受け取って」
フランクはジニョンの首にネックレスを掛けた。
「困るわ・・こんな高そうなもの」
「やっぱり似合ってる・・・」 そう言いながらフランクは目を細めた。
「高いんでしょ?」
「領収書見せる?」
そう言ったフランクの笑顔が昔と少しも変わらなくて、ジニョンは
胸を締め付けられるように動揺した。
「・・・いつだって強引・・・」 ジニョンは怒りの表情を崩さなかった。
それでもいつしか自分の声が柔らかくなっているのを、彼女は感じた。
≪いつもそうだった・・・
喧嘩をして、私がどんなに怒っても、
いつの間にかフランクのペースに巻き込まれて
いつの間にか・・私は気持ちを落ち着かせている・・・
でも・・・昔とは違うのよ、フランク・・・
もう私は、昔のような子供じゃないの≫
「誕生日・・・おめでとう」 フランクはグラスを差し出した。
彼が差し出したグラスに、ジニョンは自分のグラスをそっと添えて、
泣き笑いのような顔で答えた。「ありがとう・・・」
レストランを後にして、フランクはまたジニョンが固辞するのも聞かず
強引に彼女をアパートまで送った。
「ありがとう・・・君の誕生日を一緒に過ごさせてくれて」
「・・・あ・・ありがとうございます・・それじゃ・・」
ジニョンが車を出ようとすると、フランクは急いで車を降りて
助手席へ回り、ドアを開けて彼女の手を取った。
「部屋の前まで送らせて」 フランクのその言葉に、ジニョンは
返事こそしなかったが、瞳は拒んではいなかった。
フランクは彼女の後を付いて、階段を上り始め、彼女の横に並んだ。
ジニョンは自分が可笑しかった。
フランクと、まるでまた新たな出逢いをしているような錯覚を
覚えている自分を見ていた。
「あ・・ありがとう・・ここなの・・それじゃ」
「こんな時・・・お茶でもって誘わない?」
「フランク!・・調子に乗らないで」
「ごめん」
それでも少し動揺してしまったジニョンがバックから取り出そうとした鍵を
落としてしまい、同時に拾おうとしたふたりの指が触れ合った。
「あ・・」
フランクはジニョンににっこり微笑んで、その鍵を拾うと、
彼女の部屋のドアを自分が開けてあげた。
「さあ・・入って?・・・」 そして、彼女に入るように促がした。
「え・・ええ・・」
部屋に入ろうとしたジニョンが、後ろに聞こえた音に振り返ると
フランクが鍵の束を彼女の目の前で揺らしてからかうように笑っていた。
そして、手を差し出したジニョンの掌にそっとその鍵を落とすと
それまで鍵を握っていたフランクの手が、ジニョンの掌を被って
彼女の手首を掴むと、彼は真剣な面持ちで彼女を見つめながら
ジニョンと共に部屋へと入った。
彼の自分を見つめる眼差しに圧倒されて、彼女はまるで
金縛りにでもあったようだった。
彼の手が自分の髪に触れる優しさを忘れてはいない
彼の唇が自分の唇に触れる柔らかさを忘れてはいない
そうよ・・・いつも恋しくて・・・恋しくて・・・待っていた
≪でも・・・≫ 裏切られた悲しみは、もっと忘れてはいない
ジニョンは自分に近づく彼の唇の前で俯き顔を伏せ、拒絶した。
「駄目・・・」
「どうして?」
「できない。」
「僕を許せないから?」
「・・・・・・」
「・・・待ってる・・・」
「・・・・・・」
「おやすみ・・・」
待っている・・・
君が僕に心ゆくまで怒りをぶつけてくれるまで・・・
その怒りが涙となって・・・
綺麗に洗い流され・・・
君が・・・僕に戻るまで・・・
passion-4.支配

collage & music by tomtommama
story by kurumi
ジニョンはあの後、電車を二本見送った。
もしかしたら・・・あの階段を下りてあの人が追って来るかもしれない
≪違う・・私はそんなこと考えてはいない・・・≫
彼女は懸命に否定しながら、三本目の電車に駆けこんだ。
≪何を・・・してるの?私ったら・・・馬鹿みたい・・・≫
フランクもまたあの時、階段の上で彼女を待っていた。
彼は無意識の内に銜えた煙草が短くなる経過を
伏せた睫毛の下で追っていた。
そしてもう一度だけ階段の下に視線を送ると今度こそ諦めをつけて
今しがた彼女と歩いて来た道をゆっくりと引き返した。
フランクは部屋に戻ると、さっきジニョンと歩いたたった数分の距離を
何度も思い返しながら、眠りに付いた。
しかしその浅い眠りの中にも彼女は現れた。
≪ジニョン!≫
フランクは彼女の名を叫ぶ自分の声で目が覚めた。
そしてそれからもずっと、彼女はフランクを解放してくれなかった。
≪逢いたい・・・≫
一度逢ってしまうと、次に逢うまでがこんなにも遠いものなんだろうか・・・
彼女への想いが膨れ上がって、仕事に要する思考さえも妨げた。
「ボス、エリックから・・」
「レオ・・悪いが、後にしてくれないか」
仕事が何も手に付かなくなっていたフランクはその日のランチを
ルームサービスではなく、ホテル内のレストランで摂っていた。
もちろん少しでもジニョンに出逢う機会を作るためだった。
そして部屋に戻ろうとした時やっとジニョンの姿に辿り着いた。
小さな子供を伴い、エレベーターを待っていた彼女に彼は
呆れるほどの喜びを抑えて、落ち着き払ったように声を掛けた。
「誰かな?」 フランクは彼女が連れた小さな女の子に向かって尋ねた。
「あ・・お客様です」 ジニョンは彼の予期せぬ登場に驚いた顔を隠さず
それでも冷静を取り繕って答えた。
「そう・・・ところで今日は仕事は何時に終わりますか」
「4時に退社です」
「ではその後に観光案内をお願いできますか?」
「あ、いえ・・今日はその後に予定が・・
総支配人の歓迎会なんです」
「それは何時から?」
「8時です」
「それまでには帰れます・・では、4時10分にロビーで」
フランクは彼女に有無を言わさぬ言葉を置いて
彼女の顔を振り返ることなく立ち去った。
「あのおじさん、お姉さんのこと、好きなのね」
「・・・・どうして?」
「だってわかるもの・・顔にそう書いてある」
「おませね」
ジニョンは溜息をついた。
≪どうしてそんなに勝手なの?
あなたにはできるだけ逢いたくないのよ・・・≫
フランクの後姿がエントランスから消えるのを、
彼女は恨めしそうに見送った。
ジニョンは更衣室の自分のロッカーの前で着替えもせずに座り込んでいた。
フランクがこのホテルに滞在するようになって、当然お客様としての彼には
ホテリアーとしての最善を尽くすつもりでいたし、しているという自負もあった。
≪でも・・・≫ 彼女はこうして必要以上に、彼と接することで、
自分の心が掻き乱されることに恐怖にも似た憤りを覚えていた。
≪このまま約束をすっぽかしてしまおうかな≫
心でそう思いながらも、ジニョンはいつの間にか着替えを済ませると、
従業員通用口ではなく、フランクの待つロビーへと向かっていた。
≪彼女は来るだろうか≫ 強引なまでの誘いを掛けながらも、
フランクの中にその不安がなかったわけじゃない。
しかし、そうせずにはいられなかった。
離れていたこの10年もの月日さえ≪僕の中に君が消えることはなかった≫
それを確認するためにここに来たのかもしれない、とフランクは思った。
「お待たせしました」
そう言いながら、ジニョンが小走りにフランクへ向かっていた。
≪この腕の中へ飛び込んで来てくれる≫ フランクのそんな錯覚を
直ぐに打ち消すように、ジニョンは彼の前でぴたりと足を止めた。
「いえ、僕も今来たばかりです・・・行きましょう」
フランクは彼女の先を歩いて、自分の強引な態度に彼女が
顔をしかめていることには気づかない振りをしていた。
ジニョンは、さっきまでの困惑を吹っ切ったように、明るい様子で、
フランクの観光案内に努めた
幾つかの観光スポットを幾分急ぎ足で巡って、最後に訪れたのは
韓国の観光には欠かせない宗廟だった。
アメリカでは見ることができない壮大な歴史がそこにあった。
その佇まいは、フランクの心を簡単に時空を飛び超えさせてくれた
何千年もの時の流れの中で、自分達のこの10年の月日など
ひとつの点ほどもない短さだと思い知ると、こうして思い悩むことが
虚しくもあった。
フランクはジニョンにもらった綿菓子を、手に持て余しながら、
ひとり思い巡らせていた。
「ごめんなさい・・甘いものはお好きじゃなかったですね」
「あ・・いや・・・」
「知り合いにも甘いものが苦手な人がいるんです。
でも、彼は何故かチョコレートは好きなの。
しかも高級なチョコでないといけないんですけどね。
だからバレンタインに贈るのも大変で・・」
「バレンタインか・・・僕はもらったことなかったな」
フランクはポツリとそう言った。
「えっ?」
ジニョンはフランクを不思議そうに見上げたが
彼が自分達のことを言っているのだと直ぐに気がついた。
「ああ・・だって、その日はもう私、韓国に戻っていたから」
ジニョンは簡単にそしてさらりと言ってのけた。
「・・・・そうだった」 フランクも単調に答えた。
「私、凄く好きな人ができて・・・彼に告白したんです
三年前のバレンタインの日に・・・」
「・・・・・」 フランクは黙って聞いていた。
「それって・・・悪いことじゃないですよね」
ジニョンは急に立ち止まって、彼を睨みつけるようにして言った。
ふたりは向かい合って、しばらく無言で互いの瞳の奥を覗いていた。
少し間があって彼はやっと口を開いた。 「・・・ああ」
フランクは彼女から視線を逸らさず、表情すら変えずに答えた。
「良かった」 ジニョンもまた、抑揚の無い声で言った。
「そろそろ時間ですね・・・お送りします」
その場に居たたまれなくなっていたのはフランクの方だった。
彼は彼女の自分を突き放すような言葉のひと言ひと言に、
意図も簡単に打ちのめされた。
テジュンの歓迎会の時間が押し迫っていたが
帰り道は渋滞に遭遇し、車は身動きが取れないままだった
「これじゃあ、どうしようもないな・・・
諦めて食事でもしていきませんか」
「えっ・・・ええ」
ふたりは車を降りると、通り道で見かけたバーガーショップの前に立った。
「いいかな・・ここで・・・」
「ええ・・大好きだから」 ジニョンは満面の笑顔で答えた。
≪知ってるよ・・・だから寄ったんだ≫
ジニョンの屈託のない食べっぷりを見ているだけで、
フランクは心の中で昔の自分達を探し出すことが出来た。
それだけで彼は互いの間に蠢く何かから逃れることが出来た。
「食べないんですか?」
ジニョンは食べ物に手を付けず、自分を見つめ続けるフランクに
怪訝な視線を向けた。
「あ・・ええ、良かったら食べて?」
「私、そんなに食いしん坊じゃないわ」
「そう?」
「大人になったのよ」
「そうだね・・・綺麗になった」 フランクは感慨深げにそう言った。
「ありがとうございます・・・そう言った方が素直かしら」
彼女はそう言って微笑んだ。
フランクはただ無言で微笑を返した。
「・・・・・どうして・・・」 ≪私を置いて行ったの?≫
そう言い掛けてジニョンは言葉を呑んだ。
「えっ?」
「いえ、どうして、韓国へ?」
「・・・・・」
「あ・・ごめんなさい、お仕事だって、言ってらっしゃいましたね」
「違う」
「えっ?」
「そう言ったら?」 フランクはジニョンを切なげに見つめていた。
ジニョンは自分で尋ねておきながら、自分の期待する答えが
そこにあるような錯覚に囚われて、彼の視線から急いで逃れた。
「あ・・雨・・」
「ホントだ」
「そろそろ帰らないと」
「そうだね」
雨脚は激しくなるばかりだった。
フランクは ≪もう少し雨宿りをしていかないか≫と言いたい自分を
強く押し留めていた。
その代わりに、自分のコートを脱いで彼女をその中に包み込んだ。
ジニョンは彼の行動に一瞬驚きを見せたが、小さく笑って、
彼の差し出した布の傘を無下に拒むことはしなかった。
車までの短い距離、彼女の香りがフランクの胸を震えるほどに
ときめかせていた。
「遅くなってしまって・・・申し訳なかったね・・・
結局・・歓迎会、間に合わなかった」
「大丈夫です・・後で謝りますから」
ジニョンのアパートに着いて、彼女を離さなければならない時間が
徐々に近づくに連れて、フランクは酷く動揺している自分に気が付いた。
しかしその感情を言葉で表すことができないもどかしさがあった。
フランクは諦めたように車を降りて助手席に回り込むと、
さっきと同じようにコートを彼女に差しかけた。
ジニョンもまた、彼のその行動を素直に受け入れた。
ふたりで雨の中を走っていた時、ジニョンが突然足を止めた。
フランクが彼女の視線を追うと、傘を差した男がこちらを凝視して
立っていた。ハン・テジュンだった。
「あ・・・」 ジニョンは思わず声を漏らして、困惑を顔に浮かべた。
「テジュンssi・・・ごめんなさい、歓迎会、間に合わなくて・・
車が・・渋滞して・・その・・」
ジニョンは自分を弁明するべく一方的に言葉を繋げていた。
テジュンは無言だった。
そしてジニョンは当然のようにフランクのコートから抜け出て、
テジュンの元に足を進めようとした。
その時だった。
フランクはとっさにジニョンの腕を強く掴んだ。
そして彼はその鋭い視線をテジュンに向けていた。
ふたりが掛けていたフランクのコートは既に地面に落ち、
フランクもジニョンもそしてそのコートも雨に酷く打たれていた。
「離して・・」 ジニョンは驚いてフランクを見た。
「離さない」
その時のフランクはジニョンに向かって、たった今まで装っていた
客のベールを脱いでしまっていた。
「どうして・・」 ジニョンの瞳に怒りの色が浮かんだ
「どうして?」 フランクの目も怒っていた。
しかし、何に対して怒っているのか、彼自身にもわからなかった。
ただ怒りが込められたふたりの瞳は絡み合ったまま
しばらく離れなかった。
「離してください」 そこにテジュンが透かさず言葉を挟んだ。
「あなたには関係ない!」
フランクはジニョンの腕を掴んだまま、テジュンを睨みつけた。
「関係ないのはあなたではありませんか?彼女は私の婚約者です」
テジュンはフランクに向かってきっぱりと言い放った。
「えっ?・・あ・・違う」
ジニョンはテジュンの言葉に驚き、とっさにフランクを見てそれを否定した。
しかし彼女は直ぐに我に帰って、そのフランクへの視線を
また厳しいものに変えた。
「離して!」
フランクはジニョンの激高した声に、やっと自分を正気に戻すと、
強く掴んでいた彼女の腕からゆっくりと自分の手を離した。
テジュンはジニョンをフランクから奪い取るように自分の傘に迎え入れ、
彼女の肩を抱いて、走ってアパートの中へ消えていった。
フランクはその場に立ち尽くしていた。
雨に打たれたまま、そしてたった今、衝動的に起こしてしまった自分の行動の
自分自身への弁明を懸命に探していた。
≪今僕は何をしたんだ?≫
「サファイアの客だな」 アパートの階段を上りながらテジュンが言った。
「ええ」 ジニョンはテジュンの先を小走りに上がりながら答えた。
「どうして」
「観光案内を頼まれたの」
「観光案内?」
「ええ!・・・それより私!あなたといつ婚約したの?」
「お前が俺にプロポーズした時だ」
「はっ・・あの後、何も言わないで私のそばを離れたくせに」
「あの時はそうせざる得なかった」
「そうしなきゃいけなかった?そう!」
「・・・しかし・・俺は戻って来た」
「勝手なのね」
「お前が連れ戻しに来たんだ」
「ホテルの為よ」
「それだけじゃなかっただろ?」
「帰って!」
ジニョンは部屋の鍵を開けると、テジュンを残してドアの中へと消えた。
「おい!ジニョン!」
ジニョンは後ろ手にドアの鍵を閉めて、さっき起こったすべてのことを
急いで自分から遠ざけた ≪みんな・・・勝手なことばかり・・・≫
「オンニ?今テジュンssiの声がしたけど、
一緒だった?さっき、私送って来てもらったの」
同居しているジェニーが部屋の奥からジニョンに声を掛けた。
「え・・ううん、一緒じゃないわ」
「どうしたの?オンニ・・ずぶ濡れじゃない・・
オンニ、震えてる」
ジェニーがジニョンの体に触れると、ジニョンはびくりと体を堅くした。
「大丈夫・・雨に濡れちゃって、寒かったの」
「あ・・タオルを・・」
とジェニーはバスルームに向かったがジニョンは彼女を呼び止めた。
「ジェニー・・ありがとう、大丈夫よ、
このままシャワー浴びるから」
ジニョンはシャワーのコックを回して、熱い水を頭から浴びながら、
左の二の腕をさすっていた。
彼女の白い腕に太い筋状の線が赤く残っていた。
さっきフランクに強く掴まれた時にできた痕だった。
≪離さない≫
この水が体を濡らすよりも深くさっきの彼の声が胸に沁みていた。
≪うそつき・・・離したくせに≫ 涙が込み上げてきた。
しかしジニョンは自分が泣いているとは信じたくなかった。
フランクの為に、泣いたりはしない、泣くはずがない。
≪そうよ・・・これは涙じゃないの≫
≪あいつ・・・≫ テジュンは今上ってきた階段をひとり下りながら、
さっき目の前で起こっていたジニョンとあの客との様子に
ふたりのただならない関係を見ていた。
≪やはり、知り合いだったのか≫
≪私の婚約者だ≫
自分が彼らの前で宣言してしまったことには後悔は無い。
今までジニョンに対して、はっきりとした態度を取れなかったのは、
自分自身の置かれた立場ではジニョンに対して責任が取れるか
不安だったからだ。
今もまだ、総支配人としての立場に就いたものの、これからが
正念場ということは理解している。
だから正直、彼女への告白はもう少し時間を置いてからと考えていた。
しかし、あの男を前にして、テジュンの中に何故かが目覚めた
“急がなければ”と、心が騒いだ。
≪あの男のことは知っていた・・・ソウルホテル総支配人、ハン・テジュン≫
ホテルの経営者も彼らふたりが結婚することを望んでいることも
≪知っている。理性ではわかっていた。
ジニョンにとってそれが幸せなのかもしれないということも≫
それでもフランクは彼女の姿を追わずにいられなかった。
彼女の、時に見せる変わらぬ仕草に浮かれずにはいられなかった。
そしてあの時、あの男に向かうジニョンの・・・
彼女の手を掴まずにはいられなかった。
≪離さない≫
自分が思わず口にしていた言葉が脳裏から消えてくれなかった。
そして、その時のジニョンの驚きと怒りの目も。
≪いったい・・・どうするつもりだったんだ≫
フランクは思い切り力を込めて彼女の腕を掴んでしまった自分の手を
呆然と見つめながら、自分でもどうしようもないほどの彼女への
思慕を認めざる得なかった。
≪ジニョン・・・ジニョン・・・ジニョン・・・≫
ソウルへ来てからずっと彼女が頭の中を支配して、
開放してくれなかった。
逢うたびに・・・この想いは膨れ上がる
逢うたびに・・・また逢いたくなる・・・
逢うたびに・・・逢うたびに・・・君を・・・
・・・離したくない・・・
知らず知らず自分の頬を幾重もの涙が伝って落ちるのを
口に届いた苦い味で確認した。
ジニョン・・・もう駄目だ・・・
「もう・・・
・・・耐えられない」・・・
|
|
| <前 | [1] ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... [36] | 次> |